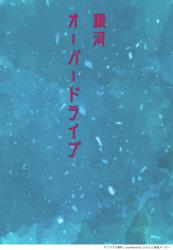年が明けて数日が経ち、学校が始まった。
相変わらず、授業はつまらないが、一つだけ変わったことがあった。それは私に信じることのできる友達ができたことだ。
私が一人で次の授業の準備をしていると真希ちゃんがやってきた。彼女と会うのは年末以来だった。
「倉持さんとはどうなったの?」
「仲良くなれたよ。その節はありがとう」
「良いの、このくらい。由香里ちゃんの顔、前よりも明るくなったと思うよ」
「ええ、そうかな?」
「そうだよ、絶対」
この時の彼女の笑顔が私の目に今でも焼き付いている。
「良かった。由香里ちゃんが楽しそうで」
「えっ?」
「ううん、何でもないよ。じゃあ、次の授業の始まるから戻るね!」
「う、うん」
私はうまく返事をすることができなかった。思えば、真希ちゃんは私に幸せでいて欲しかったのかもしれない。
私と咲は学校ではあまり喋ったり一緒に行動するのは控えようと事前に決めた。それは友美やその周りの人を刺激しないためであったし、咲が学校ではうまく喋れないということだったからだ。
そんな事もあって、この日の私は教室で一人昼ご飯を食べようとしていた。咲の方も違う場所に行ったみたいで教室にはいなかった。すると、同じ部活の渡さんが私も座席までやって来た。彼女は気まずそうにひそひそ声で話しかけてきた。
「由香里ちゃん、友美から逃げて。由香里ちゃんが倉持さんと仲良くしているところを見た人がいた。それで、友美が怒っちゃったの。カンカンよ。すぐに距離を置いた方がいい」
「どうして、そんな事私に言うの」
「あなたに幸せでいて欲しいから」
すると、私さんの肩を誰かが叩いた。
彼女が振り向くとそこには友美がいた。彼女の顔はとても怖かった。友美は私に囁いた。
「倉持と仲良くなったみたいじゃない。私はそれを許さない。だから、放課後どこか空いている教室で二人で話をしましょう」
彼女は渡さんの肩をまた叩いた。
「あなた、何でここにいるの? まさか私のことを警告しにきたんじゃないよね」
渡さんの顔が強張っていた。
「大丈夫よ。これで何も咎めるつもりはないから。だって、私は寛大だもの」
私はこんな事をしている友美の一体どこが寛大なのだと思った。それでも、彼女と話をしなければならない気がした。
「わかった。後で話をしよう」
「そうこなくちゃ」
友美の手が私の肩に触れた。
「じゃあ、放課後」
彼女は私の肩から手を離すと、いつも通りの表情に戻って教室の出入り口の方へと去って行った。
放課後、私はチャットで咲に事情を話してから、友美と会った。彼女もまた一人きりだった。
「では、行きましょう」
私たちは誰もいない教室を見つけ、そこへと入った。日はすでに傾き始めている。
「話って何?」
最初に喋ったのは私の方だった。
「何って、あなた、最近倉持咲と一緒に遊んだんでしょ? 私が聞きたいことはそれだけ」
「聞いてどうするつもり」
「もちろん、あなたの悪い噂を流して苦しめてやる」
「そんな物、私にはないけど」
「まあ、そこはなんとかでっち上げてあげる」
友美の心は壊れていた。何もないところから根も歯もない噂を流して人を傷つけようとしている。なぜ、彼女はそこまでするのだろうか。私は彼女が咲に抱く感情は狂っているように思えた。この時、私は少し後退りをしてしまった。
「あら、怖いの?」
怖くなかったといえば嘘になる。それでも私は友美と咲の関係を修復するため、それと咲のナイフを取り返すために友美と真正面から向き合うことにした。
「ねえ、友美。咲のナイフを持っているでしょ。あれ、彼女に返してあげたら?」
「絶対にやだ」
この時の友美の言葉には彼女が固い意志を持っているように感じた。
「どうして?」
「あんなやつ死んでほしい」
「そんなこと言わないでよ」
「私はね自分の手であいつを殺してやりたいんだよ!」
彼女の声が果てしない空に響き渡る。その言葉は虚無と悪意に満ちていた。
「なんで、私ばかりこうなんだ! 本当の友達なんて誰もいないし、親だって私のことなんか構ってくれない! だからあの笑顔が憎たらしい! いかにも愛されて育ったようなあの笑顔が!」
この瞬間、私は友美の中の果てしなく満たされることのない欲望の正体を垣間見た。いや、欲望と言い表すのは失礼だったかもしれない。彼女は本来満たされているべきものが満たされていないのだ。
「友美、あなたを心配してくれる人は本当にいないの?」
「いるよ! でも、いないって思ってた方が私は楽なの!」
「そんな……」
「だから本気で心配してくれたあいつが憎いんだ。許せないんだ!」
私には彼女の理屈がわからなかった。いや、わかりたくなかった。これを理解したら私は決して、決して超えてはならない一線を超えてしまうような気がした。
そう考えている間に、彼女はポケットに忍ばせていたナイフを取り出した。それはクリスマスパーティーで咲が落とした物だった。刃が私の方に向けられる。
「実はね、前々からあんたを見てると虫唾が走るの。いっつもいっつもヘラヘラして相手を煽ててさ。もう我慢の限界よ。死ね!」
彼女は私の方に向かって走る。ナイフを振り上げて私の顔めがけて振り下ろした。私は慌てて左の前腕でガードした。その刹那、私の左前腕に恐ろしいほどの痛みが襲った。その場で倒れ込む。
「あああ!!」
ナイフで切られたのだ。慌てて右手で左前腕を抑える。少し生温い液体が右の掌についた。抑えた所を見ると、そこには血が出ていた。それなりの量の血が地面にも付いた。
「もっと痛ぶってあげる。今度はそうね、目ね」
そう言って彼女はまたナイフを振り上げた。だが、
「何事だ!」
私の叫び声を聞いたのか、先生らしき人の声が聞こえた。それに加えて、何人もの人が階段を駆け上がる音が聞こえてきた。
「ああ、そんな……」
友美は自分のしたことの重さをようやく理解したようだった。ナイフで人を殺そうとしたのだ。それに耐えきれなくなったのか、彼女は倒れ込んだままの私の顔を蹴った。
「この! お前のせいだ!」
そう言い残して、彼女はナイフを持ったまま教室を出て行った。その顔にはやはり狂気があった。これ以降、私は友美の生きている姿を見ることは無かった。
彼女が教室を出てから程なくして、数人の先生たちが入ってきた。先生の一人が慌てて電気をつけた。私の血で床が濡れていた。
「おい、佐野、大丈夫か!」
担任の先生が側までやってきた。私の意識は少しずつ途切れていた。
「友美……」
そこから、私の意識は一時間ほど途切れてしまった。意識が戻ってから聞いたことだが手を切られたことの心理的ショックと失血が原因だったらしい。
保健室で休んでいると担任の先生がやってきた。
「具合はどうだ?」
「落ち着きました」
「それは良かった。で、一体何があったんだ?」
「……石崎さんと話していたら、突然向こうがナイフを出してきて斬りつけてきたんです。それで腕で庇ったらこんなことに」
私は包帯の巻かれた左腕を見つめた。切られたあたりが痛い。
「それで、石崎さんは?」
「どこかに行ってしまった。刃物を持ったまま逃げているから街中大騒ぎだ。もう先生たちで探すのはやめて、警察の人たちが彼女を探している……」
「そんな……」
「まさか、彼女がこんな事をするなんて……」
私は保健室の外を見た。すでに夜になっていて、学校の正門前は話を聞きつけたであろうマスコミの人たちでごった返していた。正門から帰るのは難しくなってしまったので、私は裏からこっそりと家に帰った。家に帰るとお母さんとお父さんが心配そうな顔をして待っていた。
「良かった、無事で良かった!」
お母さんは私をきつく抱きしめた。それに続いてお父さんも私のことを抱きしめた。
私は思わず泣いた。自分の不甲斐なさや友美への恐怖で泣いた。泣いていることが自然なことなのかおかしなことなのか、この狂ってしまった日常の中で私はわからなくなってしまった。
友美のことはまだ取り返しがつく段階にあるとこの街の誰もが思っていた。元通りではないかもしれないが、それでもそれなりに戻すことができると信じていた。それは私もそうだし、咲も、真希ちゃんも、その他の全員もそう願っていた。そう願っていたのに。
相変わらず、授業はつまらないが、一つだけ変わったことがあった。それは私に信じることのできる友達ができたことだ。
私が一人で次の授業の準備をしていると真希ちゃんがやってきた。彼女と会うのは年末以来だった。
「倉持さんとはどうなったの?」
「仲良くなれたよ。その節はありがとう」
「良いの、このくらい。由香里ちゃんの顔、前よりも明るくなったと思うよ」
「ええ、そうかな?」
「そうだよ、絶対」
この時の彼女の笑顔が私の目に今でも焼き付いている。
「良かった。由香里ちゃんが楽しそうで」
「えっ?」
「ううん、何でもないよ。じゃあ、次の授業の始まるから戻るね!」
「う、うん」
私はうまく返事をすることができなかった。思えば、真希ちゃんは私に幸せでいて欲しかったのかもしれない。
私と咲は学校ではあまり喋ったり一緒に行動するのは控えようと事前に決めた。それは友美やその周りの人を刺激しないためであったし、咲が学校ではうまく喋れないということだったからだ。
そんな事もあって、この日の私は教室で一人昼ご飯を食べようとしていた。咲の方も違う場所に行ったみたいで教室にはいなかった。すると、同じ部活の渡さんが私も座席までやって来た。彼女は気まずそうにひそひそ声で話しかけてきた。
「由香里ちゃん、友美から逃げて。由香里ちゃんが倉持さんと仲良くしているところを見た人がいた。それで、友美が怒っちゃったの。カンカンよ。すぐに距離を置いた方がいい」
「どうして、そんな事私に言うの」
「あなたに幸せでいて欲しいから」
すると、私さんの肩を誰かが叩いた。
彼女が振り向くとそこには友美がいた。彼女の顔はとても怖かった。友美は私に囁いた。
「倉持と仲良くなったみたいじゃない。私はそれを許さない。だから、放課後どこか空いている教室で二人で話をしましょう」
彼女は渡さんの肩をまた叩いた。
「あなた、何でここにいるの? まさか私のことを警告しにきたんじゃないよね」
渡さんの顔が強張っていた。
「大丈夫よ。これで何も咎めるつもりはないから。だって、私は寛大だもの」
私はこんな事をしている友美の一体どこが寛大なのだと思った。それでも、彼女と話をしなければならない気がした。
「わかった。後で話をしよう」
「そうこなくちゃ」
友美の手が私の肩に触れた。
「じゃあ、放課後」
彼女は私の肩から手を離すと、いつも通りの表情に戻って教室の出入り口の方へと去って行った。
放課後、私はチャットで咲に事情を話してから、友美と会った。彼女もまた一人きりだった。
「では、行きましょう」
私たちは誰もいない教室を見つけ、そこへと入った。日はすでに傾き始めている。
「話って何?」
最初に喋ったのは私の方だった。
「何って、あなた、最近倉持咲と一緒に遊んだんでしょ? 私が聞きたいことはそれだけ」
「聞いてどうするつもり」
「もちろん、あなたの悪い噂を流して苦しめてやる」
「そんな物、私にはないけど」
「まあ、そこはなんとかでっち上げてあげる」
友美の心は壊れていた。何もないところから根も歯もない噂を流して人を傷つけようとしている。なぜ、彼女はそこまでするのだろうか。私は彼女が咲に抱く感情は狂っているように思えた。この時、私は少し後退りをしてしまった。
「あら、怖いの?」
怖くなかったといえば嘘になる。それでも私は友美と咲の関係を修復するため、それと咲のナイフを取り返すために友美と真正面から向き合うことにした。
「ねえ、友美。咲のナイフを持っているでしょ。あれ、彼女に返してあげたら?」
「絶対にやだ」
この時の友美の言葉には彼女が固い意志を持っているように感じた。
「どうして?」
「あんなやつ死んでほしい」
「そんなこと言わないでよ」
「私はね自分の手であいつを殺してやりたいんだよ!」
彼女の声が果てしない空に響き渡る。その言葉は虚無と悪意に満ちていた。
「なんで、私ばかりこうなんだ! 本当の友達なんて誰もいないし、親だって私のことなんか構ってくれない! だからあの笑顔が憎たらしい! いかにも愛されて育ったようなあの笑顔が!」
この瞬間、私は友美の中の果てしなく満たされることのない欲望の正体を垣間見た。いや、欲望と言い表すのは失礼だったかもしれない。彼女は本来満たされているべきものが満たされていないのだ。
「友美、あなたを心配してくれる人は本当にいないの?」
「いるよ! でも、いないって思ってた方が私は楽なの!」
「そんな……」
「だから本気で心配してくれたあいつが憎いんだ。許せないんだ!」
私には彼女の理屈がわからなかった。いや、わかりたくなかった。これを理解したら私は決して、決して超えてはならない一線を超えてしまうような気がした。
そう考えている間に、彼女はポケットに忍ばせていたナイフを取り出した。それはクリスマスパーティーで咲が落とした物だった。刃が私の方に向けられる。
「実はね、前々からあんたを見てると虫唾が走るの。いっつもいっつもヘラヘラして相手を煽ててさ。もう我慢の限界よ。死ね!」
彼女は私の方に向かって走る。ナイフを振り上げて私の顔めがけて振り下ろした。私は慌てて左の前腕でガードした。その刹那、私の左前腕に恐ろしいほどの痛みが襲った。その場で倒れ込む。
「あああ!!」
ナイフで切られたのだ。慌てて右手で左前腕を抑える。少し生温い液体が右の掌についた。抑えた所を見ると、そこには血が出ていた。それなりの量の血が地面にも付いた。
「もっと痛ぶってあげる。今度はそうね、目ね」
そう言って彼女はまたナイフを振り上げた。だが、
「何事だ!」
私の叫び声を聞いたのか、先生らしき人の声が聞こえた。それに加えて、何人もの人が階段を駆け上がる音が聞こえてきた。
「ああ、そんな……」
友美は自分のしたことの重さをようやく理解したようだった。ナイフで人を殺そうとしたのだ。それに耐えきれなくなったのか、彼女は倒れ込んだままの私の顔を蹴った。
「この! お前のせいだ!」
そう言い残して、彼女はナイフを持ったまま教室を出て行った。その顔にはやはり狂気があった。これ以降、私は友美の生きている姿を見ることは無かった。
彼女が教室を出てから程なくして、数人の先生たちが入ってきた。先生の一人が慌てて電気をつけた。私の血で床が濡れていた。
「おい、佐野、大丈夫か!」
担任の先生が側までやってきた。私の意識は少しずつ途切れていた。
「友美……」
そこから、私の意識は一時間ほど途切れてしまった。意識が戻ってから聞いたことだが手を切られたことの心理的ショックと失血が原因だったらしい。
保健室で休んでいると担任の先生がやってきた。
「具合はどうだ?」
「落ち着きました」
「それは良かった。で、一体何があったんだ?」
「……石崎さんと話していたら、突然向こうがナイフを出してきて斬りつけてきたんです。それで腕で庇ったらこんなことに」
私は包帯の巻かれた左腕を見つめた。切られたあたりが痛い。
「それで、石崎さんは?」
「どこかに行ってしまった。刃物を持ったまま逃げているから街中大騒ぎだ。もう先生たちで探すのはやめて、警察の人たちが彼女を探している……」
「そんな……」
「まさか、彼女がこんな事をするなんて……」
私は保健室の外を見た。すでに夜になっていて、学校の正門前は話を聞きつけたであろうマスコミの人たちでごった返していた。正門から帰るのは難しくなってしまったので、私は裏からこっそりと家に帰った。家に帰るとお母さんとお父さんが心配そうな顔をして待っていた。
「良かった、無事で良かった!」
お母さんは私をきつく抱きしめた。それに続いてお父さんも私のことを抱きしめた。
私は思わず泣いた。自分の不甲斐なさや友美への恐怖で泣いた。泣いていることが自然なことなのかおかしなことなのか、この狂ってしまった日常の中で私はわからなくなってしまった。
友美のことはまだ取り返しがつく段階にあるとこの街の誰もが思っていた。元通りではないかもしれないが、それでもそれなりに戻すことができると信じていた。それは私もそうだし、咲も、真希ちゃんも、その他の全員もそう願っていた。そう願っていたのに。