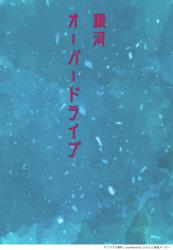咲の家に戻ると、心配そうな顔をして彼女の母と佐伯くんが待っていた。
「大丈夫なの?」
「大丈夫。さっきはごめんなさい」
咲は母に向かって謝った。
「大丈夫なら良いけど、二人とも随分とびしょ濡れね。咲、佐野さんに服を貸してあげなさい」
「うん」
「じゃあ、二人とも着替えてらっしゃい」
私は咲の服を借りてそれに着替えた。上下黒づくめで、サイズが少し合わなかったが着られたので問題はなかった。
着替え終わると、ちょうど咲の方も着替え終わっていた。昼間の時とあまり変わらない服装だった。
「そういう服装が好きなの?」
「そうね。あまりこだわってはいないけれどこういう服装が好きなの」
「そうなんだ」
「由香里のその服装、似合ってる」
「えっ、本当に?」
「本当」
私は驚いた。黒尽くめの服が似合うとは思っていなかったからだ。リビングに戻ると、彼女の母や佐伯くんからも似合っていると評されたので、本当に似合っているようだった。
咲が部屋に戻ると、佐伯くんが近づいてきた。
「ねえ、咲ちゃんのことを考えてくれてありがとう」
彼は少し恥ずかしそうに深くお辞儀をした。
「さっきまで喧嘩腰だったの急にどうしたんですか?」
「ここを飛び出してから、あなたはちゃんと戻ってきた。それはつまり佐野さんが咲ちゃんと仲良くやっていけるだろうって、さっき思った」
彼は頭を掻きながら複雑そうな表情を浮かべた。
時刻は夕方の五時となって、空はもう暗かった。私が家に帰ることにすると咲は私の家の近くまで一緒に歩きたいと言った。彼女が私よりも先に外に出て待ってくれた。私が咲の家を出ようとすると、彼女の母が肩を叩いた。私が振り向くと彼女は昼間に見た時よりも顔が明るかった。
「どうか、咲のことをよろしくね」
私は特に深くも考えず、
「はい」
とだけ返した。
暗がりの道を進みながら私と咲は話し続けた。内容は他愛もないことだった。好きなアーティストのこと、本のこと。この頃の私にはそういう他愛もないことを話せる友達がいなかったし、話してもどこか場違いな感覚があったのだけれど、なぜだか咲とだけはそういう会話を平気ですることができた。これは私にとって久しぶりの感覚だった。
会話や群れの中に潜む駆け引きとかを気にすることなく、彼女とは話すことができた。
この時、私は初めて彼女の笑顔を見た。彼女の笑顔には何か大きな力があるように感じた。彼女が本来は愛されて育った良い人なのだと理解した。
歩いていると、彼女が何かを思い出したかのように足を止めた。
「そういえば、私のナイフがどこに行ったか知ってる? どこかで失くしたみたい」
私は友美の家での事を思い出した。咲のナイフは今、友美が持っている。
「そのナイフなら今、友美が持っていると思う。一昨日、咲が友美の家からいなくなった後で見つけたけど、友美に取られちゃった……」
「……そう」
「あれ、大事な物なんでしょ?」
「そう。あれを持っていると落ち着くの」
「そうなんだ。ごめん……」
「ナイフはまたどこかで買えば良いから、大丈夫だよ。あとさ、提案なんだけど、良いかな?」
「良いよ」
「今度遊びに行かない? せっかく友達になれそうだから」
私にとってこれは意外な展開だった。まさか彼女の方から誘われるなんてと思った。それと嬉しかった。
「うん、良いよ。いつが良いかな?」
「じゃあ、連絡先を教えて。後でチャットで決めよう」
「そうだね」
私たちはそれぞれスマホを取り出して連絡先を交換した。
「よろしくね」
こう言った時の彼女の笑顔には曇り一つなかった。
「こちらこそ、よろしく」
咲と別れて家に入るとお母さんが私の格好を見てあれこれ聞いてきた。彼女に殴られたとは言えなかったので転んで川に落ちたと言った。すると、お母さんは少し微笑んだ。
「でも、良かった。なんか友達ができたみたいで」
「えっ」
「まあ、仲良くしなね」
お母さんにはお見通しだったらしかった。私にはそれなりの付き合いである友達は何人もいたが、どこか求めている人とは違うような気がしていた。もちろん、その人たちのことも大事ではあるのだけど、これほどまでに大事にしようと思ったのは、咲が初めてだった。
ご飯を食べた後で私は咲と連絡を取って、年が明けてからまた会うことにした。私はその日がとても楽しみに思えた。大晦日と正月、それから三が日にも楽しいことは沢山あったが、やはり私は咲と会う日のことが楽しみだった。
年が明けて一月四日の朝。私は街の中心にある商業ビルの前で、咲のことを待っていた。到着してから五分くらい経ったところで、彼女がやってきた。相変わらず黒い格好だった。
「ごめん、待たせた?」
「いや、全然大丈夫だよ」
「じゃあ、行こうか」
私たちはまずは映画を観ることにした。観たのは年末に公開されたばかりの話題のファンタジー映画だった。何年も続いているシリーズもので、内容はよくわからなかったが咲と一緒に観たということに意味があった。
「どうだった?」
劇場を出ると咲から感想を聞かれた。私は正直に思ったことを伝えた。
「そうだね。内容はよくわからなかったけど、あなたと観れて楽しかったよ」
この時、彼女は私の言葉を聞いてどう思ったのだろうか。彼女の本心は今となってはもうわからないのだが、この時の彼女はとても笑顔だった。
それから私たちは買い物をすることにした。しばらく店を探していると咲がアクセサリーが欲しいと言って一緒に安いアクセサリーショップに行った。
店に入るなり彼女はネックレスの置いてある方へと向かい、品定めを始めた。
「どれが良いかな」
「私も見るよ」
私も一緒にネックレスを眺めた。とても綺麗な物が多くて、どれが良いのか悩んだ。目移りする中で、一際輝いて見える物が一つあった。
「ねえ、これ良くない?」
私はそれを手に取った。それはオレンジ色をした小さな石が一つ嵌めらているネックレスだった。この時の私はこのネックレスは咲にピッタリなように感じられた。彼女はネックレスをまじまじと見つめた。
「うん、これで良いかも」
咲は早速そのネックレスを買った。値段はそれなりだったらしいが、彼女はとても気に入ったようだった。
アクセサリーショップを出た頃には時刻は昼前になっていたので、私たちはご飯を食べることにした。十分くらい探して近くで見つけた美味しそうなイタリアンに入って席を確保した。メニューを決めるのに二人揃って少し悩んでしまったが、その時間すらも私は楽しいと感じていた。
注文した料理が届くと、私たちは無言で食べた。それがお互いにとって心地が良かったのだ。食べ終えてお店を出ると、咲が喜びを噛み締めるように呟いていたのが聞こえた。
「楽しい」
彼女には心からの友達がこれまでいなかったのだ。いたとしても裏切られてしまったのだろう。だからこそ、言動やナイフで自分のことをずっと守ってきたのだ。心がこれ以上壊れないように。私は改めて、友美のことを考え直した。彼女はどうしてあれ程までに咲のことを妬んでいるのだろうか。そこにはきっと理由があるはずで、それを解せば、二人は仲直りができるのではないかと思った。だが後になって思い返せば、その考えが間違っていたのだ。悲しいことだが、友美を救おうとするべきではなかった。この時の私はあんな事になるなど思っていなかった。
昼ご飯を食べた後、また少し買い物をしたところで、今日は解散することにした。
「じゃあ、次は学校で会おう」
この時の咲は少し寂しそうだった。
「そうだね。じゃあ、学校で」
「待って、その前に」
「何?」
「一緒に写真を撮らない? 撮ってなかったから」
「そういえば、そうだね。撮ろう!」
私たちはそれぞれのスマホを取り出して、ツーショットの自撮り写真を撮った。実は私にとってツーショットの自撮りを撮ることは初めてだった。普段はなかなかする気になれないのだけど、彼女とだけは撮ってもいいかなと思えた。
「顔が入らない」
「もう少し左に行けば入ると思う」
お互い、自撮りには慣れていなかったので手探りでベストショットを探した。ちょうど良いかなというところで私たちはカメラのシャッターを切った。
「良いのが撮れたと思う。ありがとう!」
撮れた写真はとても良かった。私と咲の笑顔が眩しいくらいに写っていた。
「じゃあ、また学校で!」
「じゃあね!」
私たちはそれぞれの帰路に着いた。その直後、私は彼女から借りた服を返し忘れたことに気がついた。だが、まあ今度返せば良いかくらいに考えて、そのまま家に帰ることにした。悲しいことは刻一刻と迫っていた。
「大丈夫なの?」
「大丈夫。さっきはごめんなさい」
咲は母に向かって謝った。
「大丈夫なら良いけど、二人とも随分とびしょ濡れね。咲、佐野さんに服を貸してあげなさい」
「うん」
「じゃあ、二人とも着替えてらっしゃい」
私は咲の服を借りてそれに着替えた。上下黒づくめで、サイズが少し合わなかったが着られたので問題はなかった。
着替え終わると、ちょうど咲の方も着替え終わっていた。昼間の時とあまり変わらない服装だった。
「そういう服装が好きなの?」
「そうね。あまりこだわってはいないけれどこういう服装が好きなの」
「そうなんだ」
「由香里のその服装、似合ってる」
「えっ、本当に?」
「本当」
私は驚いた。黒尽くめの服が似合うとは思っていなかったからだ。リビングに戻ると、彼女の母や佐伯くんからも似合っていると評されたので、本当に似合っているようだった。
咲が部屋に戻ると、佐伯くんが近づいてきた。
「ねえ、咲ちゃんのことを考えてくれてありがとう」
彼は少し恥ずかしそうに深くお辞儀をした。
「さっきまで喧嘩腰だったの急にどうしたんですか?」
「ここを飛び出してから、あなたはちゃんと戻ってきた。それはつまり佐野さんが咲ちゃんと仲良くやっていけるだろうって、さっき思った」
彼は頭を掻きながら複雑そうな表情を浮かべた。
時刻は夕方の五時となって、空はもう暗かった。私が家に帰ることにすると咲は私の家の近くまで一緒に歩きたいと言った。彼女が私よりも先に外に出て待ってくれた。私が咲の家を出ようとすると、彼女の母が肩を叩いた。私が振り向くと彼女は昼間に見た時よりも顔が明るかった。
「どうか、咲のことをよろしくね」
私は特に深くも考えず、
「はい」
とだけ返した。
暗がりの道を進みながら私と咲は話し続けた。内容は他愛もないことだった。好きなアーティストのこと、本のこと。この頃の私にはそういう他愛もないことを話せる友達がいなかったし、話してもどこか場違いな感覚があったのだけれど、なぜだか咲とだけはそういう会話を平気ですることができた。これは私にとって久しぶりの感覚だった。
会話や群れの中に潜む駆け引きとかを気にすることなく、彼女とは話すことができた。
この時、私は初めて彼女の笑顔を見た。彼女の笑顔には何か大きな力があるように感じた。彼女が本来は愛されて育った良い人なのだと理解した。
歩いていると、彼女が何かを思い出したかのように足を止めた。
「そういえば、私のナイフがどこに行ったか知ってる? どこかで失くしたみたい」
私は友美の家での事を思い出した。咲のナイフは今、友美が持っている。
「そのナイフなら今、友美が持っていると思う。一昨日、咲が友美の家からいなくなった後で見つけたけど、友美に取られちゃった……」
「……そう」
「あれ、大事な物なんでしょ?」
「そう。あれを持っていると落ち着くの」
「そうなんだ。ごめん……」
「ナイフはまたどこかで買えば良いから、大丈夫だよ。あとさ、提案なんだけど、良いかな?」
「良いよ」
「今度遊びに行かない? せっかく友達になれそうだから」
私にとってこれは意外な展開だった。まさか彼女の方から誘われるなんてと思った。それと嬉しかった。
「うん、良いよ。いつが良いかな?」
「じゃあ、連絡先を教えて。後でチャットで決めよう」
「そうだね」
私たちはそれぞれスマホを取り出して連絡先を交換した。
「よろしくね」
こう言った時の彼女の笑顔には曇り一つなかった。
「こちらこそ、よろしく」
咲と別れて家に入るとお母さんが私の格好を見てあれこれ聞いてきた。彼女に殴られたとは言えなかったので転んで川に落ちたと言った。すると、お母さんは少し微笑んだ。
「でも、良かった。なんか友達ができたみたいで」
「えっ」
「まあ、仲良くしなね」
お母さんにはお見通しだったらしかった。私にはそれなりの付き合いである友達は何人もいたが、どこか求めている人とは違うような気がしていた。もちろん、その人たちのことも大事ではあるのだけど、これほどまでに大事にしようと思ったのは、咲が初めてだった。
ご飯を食べた後で私は咲と連絡を取って、年が明けてからまた会うことにした。私はその日がとても楽しみに思えた。大晦日と正月、それから三が日にも楽しいことは沢山あったが、やはり私は咲と会う日のことが楽しみだった。
年が明けて一月四日の朝。私は街の中心にある商業ビルの前で、咲のことを待っていた。到着してから五分くらい経ったところで、彼女がやってきた。相変わらず黒い格好だった。
「ごめん、待たせた?」
「いや、全然大丈夫だよ」
「じゃあ、行こうか」
私たちはまずは映画を観ることにした。観たのは年末に公開されたばかりの話題のファンタジー映画だった。何年も続いているシリーズもので、内容はよくわからなかったが咲と一緒に観たということに意味があった。
「どうだった?」
劇場を出ると咲から感想を聞かれた。私は正直に思ったことを伝えた。
「そうだね。内容はよくわからなかったけど、あなたと観れて楽しかったよ」
この時、彼女は私の言葉を聞いてどう思ったのだろうか。彼女の本心は今となってはもうわからないのだが、この時の彼女はとても笑顔だった。
それから私たちは買い物をすることにした。しばらく店を探していると咲がアクセサリーが欲しいと言って一緒に安いアクセサリーショップに行った。
店に入るなり彼女はネックレスの置いてある方へと向かい、品定めを始めた。
「どれが良いかな」
「私も見るよ」
私も一緒にネックレスを眺めた。とても綺麗な物が多くて、どれが良いのか悩んだ。目移りする中で、一際輝いて見える物が一つあった。
「ねえ、これ良くない?」
私はそれを手に取った。それはオレンジ色をした小さな石が一つ嵌めらているネックレスだった。この時の私はこのネックレスは咲にピッタリなように感じられた。彼女はネックレスをまじまじと見つめた。
「うん、これで良いかも」
咲は早速そのネックレスを買った。値段はそれなりだったらしいが、彼女はとても気に入ったようだった。
アクセサリーショップを出た頃には時刻は昼前になっていたので、私たちはご飯を食べることにした。十分くらい探して近くで見つけた美味しそうなイタリアンに入って席を確保した。メニューを決めるのに二人揃って少し悩んでしまったが、その時間すらも私は楽しいと感じていた。
注文した料理が届くと、私たちは無言で食べた。それがお互いにとって心地が良かったのだ。食べ終えてお店を出ると、咲が喜びを噛み締めるように呟いていたのが聞こえた。
「楽しい」
彼女には心からの友達がこれまでいなかったのだ。いたとしても裏切られてしまったのだろう。だからこそ、言動やナイフで自分のことをずっと守ってきたのだ。心がこれ以上壊れないように。私は改めて、友美のことを考え直した。彼女はどうしてあれ程までに咲のことを妬んでいるのだろうか。そこにはきっと理由があるはずで、それを解せば、二人は仲直りができるのではないかと思った。だが後になって思い返せば、その考えが間違っていたのだ。悲しいことだが、友美を救おうとするべきではなかった。この時の私はあんな事になるなど思っていなかった。
昼ご飯を食べた後、また少し買い物をしたところで、今日は解散することにした。
「じゃあ、次は学校で会おう」
この時の咲は少し寂しそうだった。
「そうだね。じゃあ、学校で」
「待って、その前に」
「何?」
「一緒に写真を撮らない? 撮ってなかったから」
「そういえば、そうだね。撮ろう!」
私たちはそれぞれのスマホを取り出して、ツーショットの自撮り写真を撮った。実は私にとってツーショットの自撮りを撮ることは初めてだった。普段はなかなかする気になれないのだけど、彼女とだけは撮ってもいいかなと思えた。
「顔が入らない」
「もう少し左に行けば入ると思う」
お互い、自撮りには慣れていなかったので手探りでベストショットを探した。ちょうど良いかなというところで私たちはカメラのシャッターを切った。
「良いのが撮れたと思う。ありがとう!」
撮れた写真はとても良かった。私と咲の笑顔が眩しいくらいに写っていた。
「じゃあ、また学校で!」
「じゃあね!」
私たちはそれぞれの帰路に着いた。その直後、私は彼女から借りた服を返し忘れたことに気がついた。だが、まあ今度返せば良いかくらいに考えて、そのまま家に帰ることにした。悲しいことは刻一刻と迫っていた。