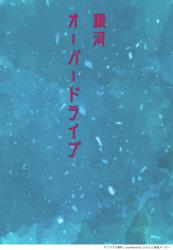散らかったままの玄関で、私は天井を眺め続けた。何もない虚空だ。それはまるで、今の私たちの心をそのまま表したようなものだった。
「はあ……」
ため息を吐いてみる。何も起こらない。ふと、足元を見つめてみても何もない。あるのは、割れた花瓶の破片や、落ちたままの額縁の類だけのように見えた。外から入ってくる夕日が私や破片たちを照らし出した。
すると、光に当たって、銀色に光る物に気がついた。私は思わずそれを手に取る。
「これは……」
それは、掌くらいの大きさの折り畳み式のナイフだった。興味本位で刃先を出してみる。刃が夕日に照らされて輝いている。これが、かりんさんの言っていた、倉持さんのナイフなのだとすぐにわかった。おそらく、さっきの喧嘩で倉持さんが落として気がつかなかったのだろう。友美はみんなのところへと行ったままだ。
もし、彼女がこのナイフを見つけたら、何をするのだろうか? 私は、理屈は無いはずなのに少し怖くなった。このナイフは直接、倉持さんに渡すべきだと思った。だから、それを刃先を畳んでポケットに隠そうとした、その時だった。
「ねえ、それは何?」
後ろを振り返ると、そこには友美が立っていた。
「な、何でもないよ」
思わず、右手に持ったナイフを背中に隠した。しかし、友美はわたしの右手を何も言わずに掴んだ。
「やめて!」
彼女は私の叫びをものともせず、私からナイフを取りあげた。彼女に握られた右手が痛かった。それから友美は、謝ることも無く、廊下を歩き始め、階段を登っていった。私は何も言うことができず、ただ立ち尽くした。
友美と倉持さんの喧嘩から三十分ほどが経って、私は荷物を持って、友美の家を出た。その時、彼女の家からやけに冷たい空気が、私の心に流れ込んできた。それは友美が持つ負の感情がそう感じさせているのか、それとも、石崎家全体が持つ空気なのかは判別はつかなかった。
あの後、改めて、かりんさんに聞くと、友美の両親は共働きで、あまり家にいることは少なく、今では、彼女のことを置いて、海外にいるとのことだった。彼女の家族が家に居ないことと、彼女の言動にどういう関係性があるのかは、わからない。だけど、それは誰か、あるいは友美自身が何とか乗り越えなくてはいけないことのような気がした。
帰り道、自転車を漕いでいるとイルミネーションが目に入ってきた。カラフルに点滅する大きなクリスマスツリー、袋を担いだサンタクロースの格好をしたおじさん、それに群がる子供たち。その時、私は、世間はクリスマスだったことを思い出した。思い出したけれど、それを喜べる気にもなれなかった。
思わず、自転車にブレーキをかける。何も考えずにぼーっとしてみたら、案外それだけで、気持ちが落ち着いた。
空はすっかり暗くて、星がところどころ見えている。この時の私の気持ちもこんな感じだったのだろうか。後になって考えてみたが、この頃の私の気持ちはぐちゃぐちゃになっていて、今でも上手に表現ができないでいる。
この後、私はお母さんのためにチキンを買ってから家へと戻った。
家で私が買ったチキンを食べていると、またしてもお母さんが「何かあったでしょ」と聞いてきた。「なにも、ないよ……」と私が返すと、心配そうな顔で話をやめた。そこまでは、いいのだが、私にとって意外だったのは、この後、お父さんがいつも以上に早く帰ってきたのである。
「ただいま」
疲れ切った調子でそう言ったお父さんを見て、私は驚いた。
「ねえ、どうしたの? いつもより早く帰ってきちゃって……」
「あ、ええとな、今日はクリスマスだし、せめて今日くらいは早く帰ろうかと思ってな。あ、あとこれだ。これを由香里に渡したかったんだ」
弱々しい声と共にお父さんは小包を差し出した。
「何これ?」
「クリスマスプレゼント」
私は、どうにも苦しい気持ちになって、それを受け取るなりすぐに部屋へと直行した。
「おい、由香里?」
「由香里?」
お母さんとお父さんの声が聞こえたが、それに答える気にもなれず、自分の部屋のドアを閉じた。いつのまにか息が苦しくなっていたが、この時の私はこうすることを選んだのだ。
プレゼントを傍に置いて、ベットの上に飛び込む。気持ちはぐちゃぐちゃ。かと言って、気持ちを落ち着ける手段はない。
「どうして、こうなるかな…… 」
自分の中に在るピラミッドが崩れはじめている。
みんなが必死に立てたピラミッドは、いずれ意味が無くなって取り崩されてゆくのだろうけど、私の中のそれは倉持さんという突如現れた存在に壊されようとしている。一方で、私自身は、変われずにいる。さっき、二人が喧嘩をした時、止めに入れていたらよかったのにと、この時思った。気がつくと眠りについていた。
目が覚めた時には真夜中の二時だった。開ききってない目で辺りを見回す。
「変な時間に起きちゃったな……」
眠気がとれていく。フラフラしながら立ち上がって少しストレッチをする。目を向けると傍に置いたままだったお父さんからのプレゼントがあった。
せっかく貰った物だから、開けないのももったいなかったので、包みを開ける。中には小さなオルゴールが入っていた。木でできていて、全体に温もりが感じられた。ゼンマイを回して、音を鳴らしてみる。流れてきたのは優しい曲だった。私にはこれがなんの曲かはわからなかったが、一瞬で好きになれた。この時、思わず自分が笑顔になれたことに気がついた。それから、誰に向かってでもなく、つぶやいてみる。
「ありがとう、お父さん」
いつか、この言葉をちゃんと言おう。そう思った。
それから、友美や倉持さんのことを考えてみた。二人が仲直りすることはできるのだろうか? しばらく考えてもこの状況を乗り越える手段は見つからなかった。
「考えても、仕方ないのか……」
私は一つの賭けに出ることにした。ただ、今すぐはどうにもできないので、私はまた眠りについた。
気がついたら、夜も更けて朝になっていた。
リビングに出るとお母さんが、いつも通りにテレビを見ていた。
「おはよう……、その、昨日はごめん」
昨日のことを謝る。昨晩は二人を心配させてしまった。本当にごめんなさい。
「良いのよ。気にしてないからさ。あと、お父さんも同じだから、心配しないでね」
お母さんの返事は意外なものだった。嬉しくなる。
朝食を済ませてから、私は頼れそうな人を探した。少し考えて真希ちゃんなら頼りになりそうな気がしたので連絡を入れた。すると、すぐに彼女から返信があり、昼過ぎから会うことになったので、私は時間が来るまで家で待った。
時間が来たので、待ち合わせの場所で数分ほど待っていると、真希ちゃんが現れた。私服姿の彼女がこちらまで駆けてくる。私の前まで来ると彼女は申し訳なさそうに聞いてきた。
「ごめん、待たせた?」
「全然」
「それなら良かった」
私と真希ちゃんは早速、近くの座れるベンチを見つけて座り込んだ。それからこの日の本題を話し始めた。
「今日、来てもらったのはさ、倉持さんと友美のことなんだ」
「うん。それで?」
「二人に仲直りしてもらいたいから、どうしたら良いか一緒に考えてくれない?」
「わかった。かなり難しいと思うけど、由香里ちゃんがそうしたいなら手伝うよ」
「ありがとう!」
私は真希ちゃんに向かって手を合わせた。
私と真希ちゃんはどうしたら二人を仲直りさせることができるのかを考え始めた。だけど、仲直りできそうな手立ては簡単には見つからなかった。
「どうしよう、出ない」
近くの自販機で買った温かいお茶を飲む。真希ちゃんもさっき買った温かい紅茶を一口飲んでからため息をついた。
「あの二人を隔てる壁は思った以上に大きそうね」
真希ちゃんが言った。私は二人を仲直りさせるための方法を書いたメモを眺めながら彼女の言葉にうなづいた。
「でも、由香里ちゃんがここまで人のことを考えてるの初めて見た」
「え、そう?」
「そうだよ」
彼女の言葉に私はハッとした。たしかに、これ程以上に他人のことを考えていたことが無かった。
私はただ、クラスの中にあるヒエラルキーのことや、自分を守ることしか考えていなかった。だけど、今はこうして、真希ちゃんと一緒に友美と倉持さんのことを考えている。私は、倉持さんが現れたことで何かが変わったのかもしれない。そう思えた。
「ねえ、何も浮かばないならまずは本人らに話を聞いてみたらどうかな?」
しばらく考えた結果、真希ちゃんはそう提案してくれた。たしかに、まずはそこからだと思った。
「そうだね。でも、倉持さんにどう話を聞いたら良いかわからないし、そもそも連絡先や家も知らないよ」
「大丈夫、倉持さんの家なら知ってる人がいるから、その人に聞けば良いと思う」
「本当! じゃあ、その人に連絡をとってもらって良いかな?」
それから彼女はすぐに連絡をとってくれた。私は次の日にその人と会うことになった。こうして、私の戦いが始まった。
「はあ……」
ため息を吐いてみる。何も起こらない。ふと、足元を見つめてみても何もない。あるのは、割れた花瓶の破片や、落ちたままの額縁の類だけのように見えた。外から入ってくる夕日が私や破片たちを照らし出した。
すると、光に当たって、銀色に光る物に気がついた。私は思わずそれを手に取る。
「これは……」
それは、掌くらいの大きさの折り畳み式のナイフだった。興味本位で刃先を出してみる。刃が夕日に照らされて輝いている。これが、かりんさんの言っていた、倉持さんのナイフなのだとすぐにわかった。おそらく、さっきの喧嘩で倉持さんが落として気がつかなかったのだろう。友美はみんなのところへと行ったままだ。
もし、彼女がこのナイフを見つけたら、何をするのだろうか? 私は、理屈は無いはずなのに少し怖くなった。このナイフは直接、倉持さんに渡すべきだと思った。だから、それを刃先を畳んでポケットに隠そうとした、その時だった。
「ねえ、それは何?」
後ろを振り返ると、そこには友美が立っていた。
「な、何でもないよ」
思わず、右手に持ったナイフを背中に隠した。しかし、友美はわたしの右手を何も言わずに掴んだ。
「やめて!」
彼女は私の叫びをものともせず、私からナイフを取りあげた。彼女に握られた右手が痛かった。それから友美は、謝ることも無く、廊下を歩き始め、階段を登っていった。私は何も言うことができず、ただ立ち尽くした。
友美と倉持さんの喧嘩から三十分ほどが経って、私は荷物を持って、友美の家を出た。その時、彼女の家からやけに冷たい空気が、私の心に流れ込んできた。それは友美が持つ負の感情がそう感じさせているのか、それとも、石崎家全体が持つ空気なのかは判別はつかなかった。
あの後、改めて、かりんさんに聞くと、友美の両親は共働きで、あまり家にいることは少なく、今では、彼女のことを置いて、海外にいるとのことだった。彼女の家族が家に居ないことと、彼女の言動にどういう関係性があるのかは、わからない。だけど、それは誰か、あるいは友美自身が何とか乗り越えなくてはいけないことのような気がした。
帰り道、自転車を漕いでいるとイルミネーションが目に入ってきた。カラフルに点滅する大きなクリスマスツリー、袋を担いだサンタクロースの格好をしたおじさん、それに群がる子供たち。その時、私は、世間はクリスマスだったことを思い出した。思い出したけれど、それを喜べる気にもなれなかった。
思わず、自転車にブレーキをかける。何も考えずにぼーっとしてみたら、案外それだけで、気持ちが落ち着いた。
空はすっかり暗くて、星がところどころ見えている。この時の私の気持ちもこんな感じだったのだろうか。後になって考えてみたが、この頃の私の気持ちはぐちゃぐちゃになっていて、今でも上手に表現ができないでいる。
この後、私はお母さんのためにチキンを買ってから家へと戻った。
家で私が買ったチキンを食べていると、またしてもお母さんが「何かあったでしょ」と聞いてきた。「なにも、ないよ……」と私が返すと、心配そうな顔で話をやめた。そこまでは、いいのだが、私にとって意外だったのは、この後、お父さんがいつも以上に早く帰ってきたのである。
「ただいま」
疲れ切った調子でそう言ったお父さんを見て、私は驚いた。
「ねえ、どうしたの? いつもより早く帰ってきちゃって……」
「あ、ええとな、今日はクリスマスだし、せめて今日くらいは早く帰ろうかと思ってな。あ、あとこれだ。これを由香里に渡したかったんだ」
弱々しい声と共にお父さんは小包を差し出した。
「何これ?」
「クリスマスプレゼント」
私は、どうにも苦しい気持ちになって、それを受け取るなりすぐに部屋へと直行した。
「おい、由香里?」
「由香里?」
お母さんとお父さんの声が聞こえたが、それに答える気にもなれず、自分の部屋のドアを閉じた。いつのまにか息が苦しくなっていたが、この時の私はこうすることを選んだのだ。
プレゼントを傍に置いて、ベットの上に飛び込む。気持ちはぐちゃぐちゃ。かと言って、気持ちを落ち着ける手段はない。
「どうして、こうなるかな…… 」
自分の中に在るピラミッドが崩れはじめている。
みんなが必死に立てたピラミッドは、いずれ意味が無くなって取り崩されてゆくのだろうけど、私の中のそれは倉持さんという突如現れた存在に壊されようとしている。一方で、私自身は、変われずにいる。さっき、二人が喧嘩をした時、止めに入れていたらよかったのにと、この時思った。気がつくと眠りについていた。
目が覚めた時には真夜中の二時だった。開ききってない目で辺りを見回す。
「変な時間に起きちゃったな……」
眠気がとれていく。フラフラしながら立ち上がって少しストレッチをする。目を向けると傍に置いたままだったお父さんからのプレゼントがあった。
せっかく貰った物だから、開けないのももったいなかったので、包みを開ける。中には小さなオルゴールが入っていた。木でできていて、全体に温もりが感じられた。ゼンマイを回して、音を鳴らしてみる。流れてきたのは優しい曲だった。私にはこれがなんの曲かはわからなかったが、一瞬で好きになれた。この時、思わず自分が笑顔になれたことに気がついた。それから、誰に向かってでもなく、つぶやいてみる。
「ありがとう、お父さん」
いつか、この言葉をちゃんと言おう。そう思った。
それから、友美や倉持さんのことを考えてみた。二人が仲直りすることはできるのだろうか? しばらく考えてもこの状況を乗り越える手段は見つからなかった。
「考えても、仕方ないのか……」
私は一つの賭けに出ることにした。ただ、今すぐはどうにもできないので、私はまた眠りについた。
気がついたら、夜も更けて朝になっていた。
リビングに出るとお母さんが、いつも通りにテレビを見ていた。
「おはよう……、その、昨日はごめん」
昨日のことを謝る。昨晩は二人を心配させてしまった。本当にごめんなさい。
「良いのよ。気にしてないからさ。あと、お父さんも同じだから、心配しないでね」
お母さんの返事は意外なものだった。嬉しくなる。
朝食を済ませてから、私は頼れそうな人を探した。少し考えて真希ちゃんなら頼りになりそうな気がしたので連絡を入れた。すると、すぐに彼女から返信があり、昼過ぎから会うことになったので、私は時間が来るまで家で待った。
時間が来たので、待ち合わせの場所で数分ほど待っていると、真希ちゃんが現れた。私服姿の彼女がこちらまで駆けてくる。私の前まで来ると彼女は申し訳なさそうに聞いてきた。
「ごめん、待たせた?」
「全然」
「それなら良かった」
私と真希ちゃんは早速、近くの座れるベンチを見つけて座り込んだ。それからこの日の本題を話し始めた。
「今日、来てもらったのはさ、倉持さんと友美のことなんだ」
「うん。それで?」
「二人に仲直りしてもらいたいから、どうしたら良いか一緒に考えてくれない?」
「わかった。かなり難しいと思うけど、由香里ちゃんがそうしたいなら手伝うよ」
「ありがとう!」
私は真希ちゃんに向かって手を合わせた。
私と真希ちゃんはどうしたら二人を仲直りさせることができるのかを考え始めた。だけど、仲直りできそうな手立ては簡単には見つからなかった。
「どうしよう、出ない」
近くの自販機で買った温かいお茶を飲む。真希ちゃんもさっき買った温かい紅茶を一口飲んでからため息をついた。
「あの二人を隔てる壁は思った以上に大きそうね」
真希ちゃんが言った。私は二人を仲直りさせるための方法を書いたメモを眺めながら彼女の言葉にうなづいた。
「でも、由香里ちゃんがここまで人のことを考えてるの初めて見た」
「え、そう?」
「そうだよ」
彼女の言葉に私はハッとした。たしかに、これ程以上に他人のことを考えていたことが無かった。
私はただ、クラスの中にあるヒエラルキーのことや、自分を守ることしか考えていなかった。だけど、今はこうして、真希ちゃんと一緒に友美と倉持さんのことを考えている。私は、倉持さんが現れたことで何かが変わったのかもしれない。そう思えた。
「ねえ、何も浮かばないならまずは本人らに話を聞いてみたらどうかな?」
しばらく考えた結果、真希ちゃんはそう提案してくれた。たしかに、まずはそこからだと思った。
「そうだね。でも、倉持さんにどう話を聞いたら良いかわからないし、そもそも連絡先や家も知らないよ」
「大丈夫、倉持さんの家なら知ってる人がいるから、その人に聞けば良いと思う」
「本当! じゃあ、その人に連絡をとってもらって良いかな?」
それから彼女はすぐに連絡をとってくれた。私は次の日にその人と会うことになった。こうして、私の戦いが始まった。