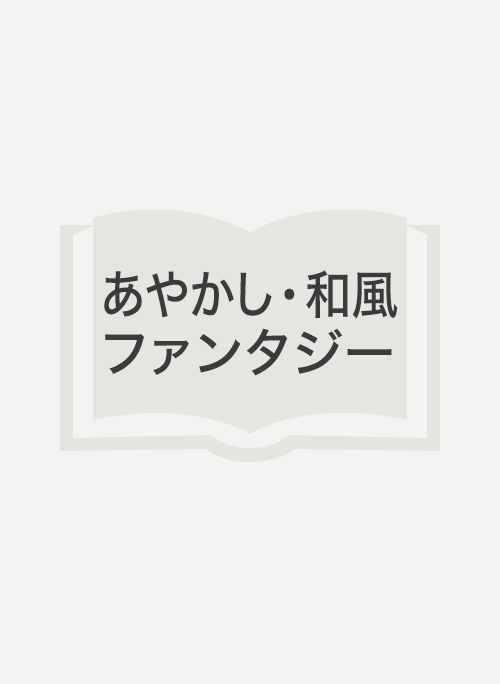花は眩しさを感じゆっくりと瞳を開けると真っ白な空間に自分の身体がふわりと浮かんでいることに気がついた。
それを囲むように過去の出来事が目に見えて分かるように流れている。
花が生まれた時の様子から現在まで事細かに見えるようになっていた。
(これは……)
周囲を見渡すと流れている出来事の中に美藤家で虐げられている自分の姿が目に入った。
花が貧血で蹌踉けてしまい姉の未都の着物にお茶を零して激怒されている時だ。
怒鳴り声も耳に届くが花は不思議と恐怖心を覚えなかった。
塞ぎ込みたくなるほど辛い経験だったはずなのに自分でも驚くほど今は大丈夫だった。
流れてくる出来事の中に燈夜が映ってその理由が分かった。
「私、強くなったんだ……」
あの日、生きることを諦めていた自分に手を差し伸べてくれた。
無能だから、薄桜色の髪だからといって燈夜は軽蔑なんてしなかった。
真綿のように包み込んで愛してくれた。
次第に自分も惹かれて彼と幸せな未来を歩みたいと望んだ。
その願いを叶えたいと燈夜と過ごすうちに自然と心が強くなったのだ。
虐げられた辛い経験もきっと忘れてはいけないのだと思う。
きっとそれが今後の人生の糧となってさらに自分を強くしてくれる。
大切な人達の笑顔を思い浮かべながら花は再び瞳を閉じた。
長い夢を見ていたような気がする。
次に瞳を開けると視界がぼやけており少しずつはっきりと見えてきた。
「花……!」
名前を呼ぶ声が聞こえ頭を動かすと燈夜が心配そうに顔を覗き込んでいる。
「燈夜様……」
恋い慕う彼に会えた、自分は死んではいなかったのだと分かり安堵した。
起き上がろうとするが頭痛と倦怠感で身体がほとんど動かなかった。
「まだ顔色が良くない。起き上がらなくていいよ」
優しく手で制止され花は言葉に甘えて小さく頷いた。
「失礼します、燈夜様」
千代子が二人の様子を見に襖を開けて入ってきた。
目を覚ましている花を見るたび口元を手で抑え驚愕の声をあげる。
「花様……!目を覚まされたのですね!私、お医者様を呼んできます!」
「ああ、頼む」
燈夜がそう言うと千代子は小走りでその場をあとにした。
再び部屋に二人きりになると花は燈夜にあの帝都の反乱について尋ねた。
「燈夜様、あの後どうなったのですか?」
異形の大量発生、負傷した軍人達、母親とはぐれた女の子……。
自分は意識を失ってしまったので何も知らない。
気になることが多すぎて燈夜の言葉を今か今かと待ってしまう。
そんな気持ちが表情にも出ていたのか燈夜は落ち着かせるように花の頭を撫でながら話してくれた。
帝都に発生した異形は全て討伐され戦いで負傷した軍人達も適切な治療を受け現在は回復に向かっているようだ。
花が助けた女の子もあれからすぐに母親と再会できたそうで娘を守ってくれて感謝してもしきれないと言っていたそうだ。
燈夜の言葉に不安だった種が取り除かれていく。
しかしまだ聞きたいことがあるのに強い頭痛を感じ顔を歪めると燈夜は俯いた。
「花、本当にすまない」
「え……?どうして燈夜様が謝られるのですか?」
謝るのは母親の透緒子に異形が反応するほどの不の感情の原因をつくってしまった自分なのに何故助けてくれた燈夜が謝るのか分からなかった。
燈夜は悔しそうに握っていた掌を震わせており初めて見る表情に花は胸が苦しくなった。
「千代子から花が突然いなくなったと連絡を受けすぐに美藤家の仕業だろうと察した。ある程度釘を刺しておけば斎園寺家の当主の婚約者を誘拐することはないだろうと甘い考えをもってしまっていたんだ。そんな俺のせいで花を傷つけて怖い思いをさせた。すまない」
頭を下げる燈夜。
そんな彼を見て花は倦怠感が残る身体を必死に起き上がらせ優しく抱きしめた。
「花?」
花の突然の行動に燈夜は目を丸くしている。
泣いているとき、前を見られないとき、今まで燈夜にどれだけ支えられたか。
今度は自分が彼を支える番なんだと回した腕に力を込める。
「燈夜様のせいなんかじゃないです。またこうして傍にいられる、それだけで十分なんです。だから自分を責めたりしないで……」
一つ一つの言葉を丁寧に紡ぐ。
自分から男性を抱きしめるなんて以前の花には考えられなかった。
不思議と恥ずかしさはない。
息をのむ音が聞こえると花の背中にも手が回される。
さらにぴったりと身体が密着し二人の距離が無くなった。
「ありがとう。花」
耳元で呟かれたその言葉は少し震えており、花は自然と回した腕にさらに力を込めた。
燈夜は普段、弱音を吐かない。
人々の上に立つ存在として相応しい強く堂々とした当主でいようとしていたのが花には分かった。
弱い一面を見せてはいけないと気持ちを抑え込んでいたのだろう。
燈夜が自分に甘えてくれているようで嬉しかった。
無能で役立たずだと言われ続けていたがやっと自分が人の、愛する人の支えになれたのだと。
燈夜の温もりを感じていると襖の外から声がかかる。
「花様、燈夜様。お医者様が到着なされたのですが入ってもよろしいですか?」
「……!は、はい!どうぞ!」
千代子の声に花は自分が大胆な行動をしていたと、はっと我に返り慌てて燈夜から離れる。
燈夜はきょとんとした顔をしており抱き合っているのを見られても全く気にしなさそうだった。
花はこんな状況を人に見られたら恥ずかしさでどうにかなってしまいそうだ。
入ってきた千代子は花を見るたび慌てふためく。
「花様、お顔が真っ赤ですよ!?もしかして熱が……」
「い、いえ!大丈夫です!」
顔を両方の掌で隠し否定する花を燈夜は愛おしそうに瞳を細め見つめていた。
花は医者から数日間の絶対安静が必要だと診断された。
一日休めば十分だと楽観的に考えていた花はまさかそこまで自分の身体が危機的状況であることに驚いていた。
診療が終わり医者が帰ると千代子は家事を行うため部屋をあとにした。
布団に再び横になると燈夜が優しく頭を撫でてくれる。
「眠るまで傍にいるから安心しなさい」
「はい……。でも燈夜様もあまり眠れていないのでは?顔色があまりよろしくないような……」
燈夜は目が覚めたときから陶器のように白く美しい肌が普段よりさらに白く、青い。
きっと自分のことを心配してずっと看病してくれたのだろうと花は察した。
優しい燈夜ならそうするとすぐに分かったが、あの戦いのあとにろくに休まずに看病をしていたとするともう身体は限界のはず。
このままではいつか倒れてしまうと心配になり口を開いた。
「私のことは気にしなくていいですから燈夜様も休んでください」
「……それじゃあ」
燈夜は手を顎に添え何かを思案しているかと思えば突然、花が使っている布団をぺらりと捲る。
「えっ!?と、燈夜様!?」
燈夜は何食わぬ顔で布団に入り花の横で寝ようとする。
一緒に寝ようと誘ったわけではないのだが何か勘違いをさせてしまっただろうかと慌ててしまう。
そんな花を見て燈夜はくすりと笑うとそっと布団から出た。
「冗談だ。今日はやめておくよ。花の心の準備ができたらそのときは……ね?」
色香漂う瞳で見つめられ花の胸が高鳴る。
花は早鐘を打つ鼓動のせいでなかなか寝付くことができなかったのだった。
それを囲むように過去の出来事が目に見えて分かるように流れている。
花が生まれた時の様子から現在まで事細かに見えるようになっていた。
(これは……)
周囲を見渡すと流れている出来事の中に美藤家で虐げられている自分の姿が目に入った。
花が貧血で蹌踉けてしまい姉の未都の着物にお茶を零して激怒されている時だ。
怒鳴り声も耳に届くが花は不思議と恐怖心を覚えなかった。
塞ぎ込みたくなるほど辛い経験だったはずなのに自分でも驚くほど今は大丈夫だった。
流れてくる出来事の中に燈夜が映ってその理由が分かった。
「私、強くなったんだ……」
あの日、生きることを諦めていた自分に手を差し伸べてくれた。
無能だから、薄桜色の髪だからといって燈夜は軽蔑なんてしなかった。
真綿のように包み込んで愛してくれた。
次第に自分も惹かれて彼と幸せな未来を歩みたいと望んだ。
その願いを叶えたいと燈夜と過ごすうちに自然と心が強くなったのだ。
虐げられた辛い経験もきっと忘れてはいけないのだと思う。
きっとそれが今後の人生の糧となってさらに自分を強くしてくれる。
大切な人達の笑顔を思い浮かべながら花は再び瞳を閉じた。
長い夢を見ていたような気がする。
次に瞳を開けると視界がぼやけており少しずつはっきりと見えてきた。
「花……!」
名前を呼ぶ声が聞こえ頭を動かすと燈夜が心配そうに顔を覗き込んでいる。
「燈夜様……」
恋い慕う彼に会えた、自分は死んではいなかったのだと分かり安堵した。
起き上がろうとするが頭痛と倦怠感で身体がほとんど動かなかった。
「まだ顔色が良くない。起き上がらなくていいよ」
優しく手で制止され花は言葉に甘えて小さく頷いた。
「失礼します、燈夜様」
千代子が二人の様子を見に襖を開けて入ってきた。
目を覚ましている花を見るたび口元を手で抑え驚愕の声をあげる。
「花様……!目を覚まされたのですね!私、お医者様を呼んできます!」
「ああ、頼む」
燈夜がそう言うと千代子は小走りでその場をあとにした。
再び部屋に二人きりになると花は燈夜にあの帝都の反乱について尋ねた。
「燈夜様、あの後どうなったのですか?」
異形の大量発生、負傷した軍人達、母親とはぐれた女の子……。
自分は意識を失ってしまったので何も知らない。
気になることが多すぎて燈夜の言葉を今か今かと待ってしまう。
そんな気持ちが表情にも出ていたのか燈夜は落ち着かせるように花の頭を撫でながら話してくれた。
帝都に発生した異形は全て討伐され戦いで負傷した軍人達も適切な治療を受け現在は回復に向かっているようだ。
花が助けた女の子もあれからすぐに母親と再会できたそうで娘を守ってくれて感謝してもしきれないと言っていたそうだ。
燈夜の言葉に不安だった種が取り除かれていく。
しかしまだ聞きたいことがあるのに強い頭痛を感じ顔を歪めると燈夜は俯いた。
「花、本当にすまない」
「え……?どうして燈夜様が謝られるのですか?」
謝るのは母親の透緒子に異形が反応するほどの不の感情の原因をつくってしまった自分なのに何故助けてくれた燈夜が謝るのか分からなかった。
燈夜は悔しそうに握っていた掌を震わせており初めて見る表情に花は胸が苦しくなった。
「千代子から花が突然いなくなったと連絡を受けすぐに美藤家の仕業だろうと察した。ある程度釘を刺しておけば斎園寺家の当主の婚約者を誘拐することはないだろうと甘い考えをもってしまっていたんだ。そんな俺のせいで花を傷つけて怖い思いをさせた。すまない」
頭を下げる燈夜。
そんな彼を見て花は倦怠感が残る身体を必死に起き上がらせ優しく抱きしめた。
「花?」
花の突然の行動に燈夜は目を丸くしている。
泣いているとき、前を見られないとき、今まで燈夜にどれだけ支えられたか。
今度は自分が彼を支える番なんだと回した腕に力を込める。
「燈夜様のせいなんかじゃないです。またこうして傍にいられる、それだけで十分なんです。だから自分を責めたりしないで……」
一つ一つの言葉を丁寧に紡ぐ。
自分から男性を抱きしめるなんて以前の花には考えられなかった。
不思議と恥ずかしさはない。
息をのむ音が聞こえると花の背中にも手が回される。
さらにぴったりと身体が密着し二人の距離が無くなった。
「ありがとう。花」
耳元で呟かれたその言葉は少し震えており、花は自然と回した腕にさらに力を込めた。
燈夜は普段、弱音を吐かない。
人々の上に立つ存在として相応しい強く堂々とした当主でいようとしていたのが花には分かった。
弱い一面を見せてはいけないと気持ちを抑え込んでいたのだろう。
燈夜が自分に甘えてくれているようで嬉しかった。
無能で役立たずだと言われ続けていたがやっと自分が人の、愛する人の支えになれたのだと。
燈夜の温もりを感じていると襖の外から声がかかる。
「花様、燈夜様。お医者様が到着なされたのですが入ってもよろしいですか?」
「……!は、はい!どうぞ!」
千代子の声に花は自分が大胆な行動をしていたと、はっと我に返り慌てて燈夜から離れる。
燈夜はきょとんとした顔をしており抱き合っているのを見られても全く気にしなさそうだった。
花はこんな状況を人に見られたら恥ずかしさでどうにかなってしまいそうだ。
入ってきた千代子は花を見るたび慌てふためく。
「花様、お顔が真っ赤ですよ!?もしかして熱が……」
「い、いえ!大丈夫です!」
顔を両方の掌で隠し否定する花を燈夜は愛おしそうに瞳を細め見つめていた。
花は医者から数日間の絶対安静が必要だと診断された。
一日休めば十分だと楽観的に考えていた花はまさかそこまで自分の身体が危機的状況であることに驚いていた。
診療が終わり医者が帰ると千代子は家事を行うため部屋をあとにした。
布団に再び横になると燈夜が優しく頭を撫でてくれる。
「眠るまで傍にいるから安心しなさい」
「はい……。でも燈夜様もあまり眠れていないのでは?顔色があまりよろしくないような……」
燈夜は目が覚めたときから陶器のように白く美しい肌が普段よりさらに白く、青い。
きっと自分のことを心配してずっと看病してくれたのだろうと花は察した。
優しい燈夜ならそうするとすぐに分かったが、あの戦いのあとにろくに休まずに看病をしていたとするともう身体は限界のはず。
このままではいつか倒れてしまうと心配になり口を開いた。
「私のことは気にしなくていいですから燈夜様も休んでください」
「……それじゃあ」
燈夜は手を顎に添え何かを思案しているかと思えば突然、花が使っている布団をぺらりと捲る。
「えっ!?と、燈夜様!?」
燈夜は何食わぬ顔で布団に入り花の横で寝ようとする。
一緒に寝ようと誘ったわけではないのだが何か勘違いをさせてしまっただろうかと慌ててしまう。
そんな花を見て燈夜はくすりと笑うとそっと布団から出た。
「冗談だ。今日はやめておくよ。花の心の準備ができたらそのときは……ね?」
色香漂う瞳で見つめられ花の胸が高鳴る。
花は早鐘を打つ鼓動のせいでなかなか寝付くことができなかったのだった。