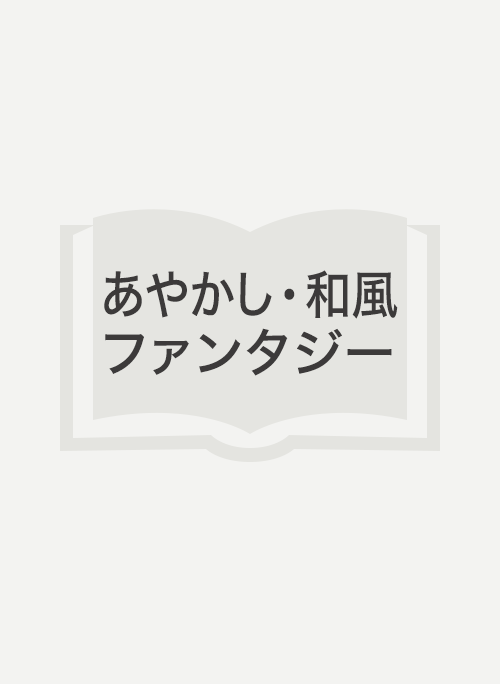「花、大丈夫か?」
「は、はい……」
燈夜とお世話係の千代子が布団に入って寝ている花を心配そうに見ている。
花は昨日から高熱で寝込んでいた。
先程、医者が屋敷に来て診察してもらったが疲労からくる熱で暫くの安静が必要と言われた。
美藤家で働いている頃よりかなり休みを貰っているのに体調を崩してしまっている自分が情けなくなる。
「もっと早く俺が花の体調に気が付けば良かった。すまない」
「私も花様に家事を頼ってしまったところがありますわ。申し訳ありません」
二人の謝罪に花は重い頭をゆっくりと横に振る。
「そんな……。家事は私がやりたくてやっていたことですし、熱を出したのは自分の責任です。私の方こそお二人にご迷惑をおかけしてしまって……」
謝ろうとした花の頭を燈夜が優しく撫でた。
「迷惑じゃない。花にはいつも助けられている」
燈夜の言葉に同意するように千代子が頷く。
「ええ。今はゆっくり休まれて下さい。私は粥を作って参りますね」
「ありがとうございます……」
千代子は微笑むと部屋から出て行った。
二人きりになり燈夜は花の額に乗せてあった濡らした手拭いを触る。
少し温くなってきたのを確認すると一旦取り、近くに置いてある桶に入れる。
燈夜は氷雪の異能を使い、桶の中の水を冷やす。
手拭いを絞り再び花の額に置く。
ひんやりとした冷たさが熱くなった顔に伝わって気持ちが良い。
「粥を食べたら薬を飲むんだよ」
「はい……」
穏やかな声が熱で重い頭でもスッと入ってくる。
虐げられていた頃は今のように体調が悪くても休むことは出来ず働き詰めだった。
温かい布団に入って粥を食べ薬を飲む。
世の中の人にとってそんな当たり前のことが出来なかった。
しかし今はそうしなさいと勧めてくれる人達がいる。それが花には奇跡のように喜ばしく感じる。
暫くすると千代子が粥を運んできた。
花は燈夜に助けてもらいながらゆっくりと起き上がる。
粥を受け取ると再び千代子は部屋から出て行った。
きっと恋仲の二人を邪魔したくないのだろう。
千代子の計らいに燈夜は気づいていた。
花は匙で粥を掬おうとするが熱のせいで少しの目眩を感じる。
ぼうっとしている花に気づき燈夜は匙を持っている花の手に自分の手を重ねる。
「私が食べさせよう」
「え……!?い、いや大丈夫ですよ……!」
食事を食べさせられるのは記憶にあるかぎり誰にもしてもらったことは無い。
たとえ婚約者の立場でもそれは恥ずかしいと想像するだけで照れてしまった。
気合いを入れて粥を食べようとした花の手から匙が無くなる。
不思議に思い顔を上げるとその匙は燈夜の手の中にあった。
「と、燈夜様……!?」
戸惑っていると燈夜は器から匙で粥を一口分掬い、花の口の前にもってくる。
「ほら、口を開けなさい」
匙を持ちながら優しく微笑む燈夜を見て断ろうとしていた花の気持ちが揺らぐ。
ここまでしてもらっているのにその善意を無駄にすることは出来ないと照れる感情を必死に抑え口を開けた。そっと口の中に粥が入る。
(あ、美味しい……)
もぐもぐと食べる花を見て燈夜は愛おしそうに目を細め、再び粥を掬うのだった。
あまり食欲が無かった花だったが燈夜のおかげか、不思議と食べることができ千代子が片付けた器は空になっていた。
薬も飲み、再び布団に入る。
食後と薬を飲んだからか眠気が襲う。
うとうととしている花を見て燈夜は優しく頭を撫でる。
「眠りにつくまで傍にいるから安心しなさい」
「ありがとうございます……」
身体は辛かったが隣に恋い慕う燈夜がいる。
苦しさの中に少しの余裕が出来て花はゆっくりと瞼を閉じた。
僅かに眩しさを感じ目を開け気がつくと花は花畑が広がる見知らぬ地に立っていた。
(あれ……?ここは……)
色とりどりの花が広がり美しい光景だが何故自分がここにいるのか一抹の不安を覚える。
辺りに視線を向けると少し離れた場所に桜の木が一本あることに気がついた。
どれくらいの年数が経っているのだろう。
とても立派で美しく心を奪われる。
その神々しくも感じる桜の木の下に白い着物を着た一人の男性が立っていた。
顔ははっきり見えないが体格からして男性であることが分かる。
(誰だろう?燈夜様……?…ううん、違う)
燈夜ではないのなら誰なのだろう。
記憶を辿ってみるがあのような男性と会ったことはないような気がする。
じっと見ているとその男性は口を開いた。
「花」
(え?私のことを知ってる……?)
自分と会ったことがあるのか問おうとして口を開くが声が出ないことに気づいた。
どんなに頑張っても喉が詰まるような感覚がして思っていることが言葉として発することが出来ない。
初めての感覚に頭が混乱してしまう。
せめて目線で訴えることが出来ないかとじっと男性を見つめる。
「花、ーー」
(え?)
最後の言葉の部分が聞き取れず戸惑った瞬間、突如として花びらが視界を覆う。
もう少し近づいてその顔をしっかり見たいのに足も動かない。
手を伸ばすが大量の花びらで完全に塞がれそこで辺りが暗闇に包まれた。
「っ……!」
ハッと目が覚めると見慣れた天井が視界に入る。
襖の隙間から橙色の光が差し込んでおり夕刻なのだと分かった。
起き上がりながら先程の光景は夢だったのだと胸を撫で下ろし乱れた呼吸を整えていると涙が流れていることに気づいた。
(あれ、私泣いている……?どうして……)
不思議に思いながら頬を伝う涙を拭おうとすると様子を見に来た燈夜が襖を開けた。
涙を流している花を見て目を見開いている。
「花、どうした……!どこか痛むか?」
珍しく焦りを滲ませ花の傍に寄る燈夜。
そうでは無いと伝える為にすぐに首を横に振る。
「違うんです。夢を見て……」
「夢?」
花は夢の内容を全て燈夜に話した。
話が終わると燈夜は何か考えるそぶりを見せる。
「白色の着物……」
「燈夜様?」
何か思い当たる節があるのか疑問に思い、花は首を傾げる。
「もしかすると夢に出てきた男性は花の実の父、美藤貴之ではないか?」
「お父様……!?」
美藤家の前当主、美藤貴之は花が幼い頃に病気で亡くなった。
しかも姉の未都の異能である記憶の消去により花には幼少期の記憶が無かった。
顔も分からなかったが会合や宴に度々参加している燈夜なら知っていても可笑しくはない。
「俺が幼い頃、両親に連れられて異能家系が集まる場に行ったことがある。そこに花の父親も白色の着物を来て参加していた」
しかし花が見たのは夢であることから本当に同一人物かは分からないと燈夜は言った。
仮に夢に出てきたのが貴之だとしたら何故姿を見せたのか分からなかった。
実の母親である透緒子にも『異端の子』と呼ばれ愛されなかった花。
では貴之はどうだったのだろうと考えたこともあった。
記憶にも無く人にも聞いたことが無い。
きっと貴之も無能で薄桜色の髪をもつ娘なんか好きにならないと勝手に思っていた。
愛される資格が自分には無いから。
「花が心配で見に来たのではないか?」
燈夜の一言に自然と顔を上げる花。
その一言に前を見ているような希望を感じるような思いが込められている気がする。
しかしどうしても花の心の中には覆い隠すような霞が残っていた。
「父は私を愛していたのでしょうか……」
俯く花に燈夜は自分の手を重ねた。強張った手に温もりが伝わる。
「一度、会合で話を聞いたことがある。自分には可愛い娘がいるのだと。…その名は花」
その言葉に視界が涙で潤むのが分かった。
自分は確かに父親に愛されていたのだと。
諦めていた気持ちに光が差し込む。
涙がぽろぽろと零れ、布団を濡らす。
そんな花を燈夜は優しく抱き締めた。
貴之は花を虐める透緒子と未都を何回も咎めていたが言うことを聞かず困っていたところ病状が悪化し床に伏せてしまったことは花は知らなかったのだった。
「は、はい……」
燈夜とお世話係の千代子が布団に入って寝ている花を心配そうに見ている。
花は昨日から高熱で寝込んでいた。
先程、医者が屋敷に来て診察してもらったが疲労からくる熱で暫くの安静が必要と言われた。
美藤家で働いている頃よりかなり休みを貰っているのに体調を崩してしまっている自分が情けなくなる。
「もっと早く俺が花の体調に気が付けば良かった。すまない」
「私も花様に家事を頼ってしまったところがありますわ。申し訳ありません」
二人の謝罪に花は重い頭をゆっくりと横に振る。
「そんな……。家事は私がやりたくてやっていたことですし、熱を出したのは自分の責任です。私の方こそお二人にご迷惑をおかけしてしまって……」
謝ろうとした花の頭を燈夜が優しく撫でた。
「迷惑じゃない。花にはいつも助けられている」
燈夜の言葉に同意するように千代子が頷く。
「ええ。今はゆっくり休まれて下さい。私は粥を作って参りますね」
「ありがとうございます……」
千代子は微笑むと部屋から出て行った。
二人きりになり燈夜は花の額に乗せてあった濡らした手拭いを触る。
少し温くなってきたのを確認すると一旦取り、近くに置いてある桶に入れる。
燈夜は氷雪の異能を使い、桶の中の水を冷やす。
手拭いを絞り再び花の額に置く。
ひんやりとした冷たさが熱くなった顔に伝わって気持ちが良い。
「粥を食べたら薬を飲むんだよ」
「はい……」
穏やかな声が熱で重い頭でもスッと入ってくる。
虐げられていた頃は今のように体調が悪くても休むことは出来ず働き詰めだった。
温かい布団に入って粥を食べ薬を飲む。
世の中の人にとってそんな当たり前のことが出来なかった。
しかし今はそうしなさいと勧めてくれる人達がいる。それが花には奇跡のように喜ばしく感じる。
暫くすると千代子が粥を運んできた。
花は燈夜に助けてもらいながらゆっくりと起き上がる。
粥を受け取ると再び千代子は部屋から出て行った。
きっと恋仲の二人を邪魔したくないのだろう。
千代子の計らいに燈夜は気づいていた。
花は匙で粥を掬おうとするが熱のせいで少しの目眩を感じる。
ぼうっとしている花に気づき燈夜は匙を持っている花の手に自分の手を重ねる。
「私が食べさせよう」
「え……!?い、いや大丈夫ですよ……!」
食事を食べさせられるのは記憶にあるかぎり誰にもしてもらったことは無い。
たとえ婚約者の立場でもそれは恥ずかしいと想像するだけで照れてしまった。
気合いを入れて粥を食べようとした花の手から匙が無くなる。
不思議に思い顔を上げるとその匙は燈夜の手の中にあった。
「と、燈夜様……!?」
戸惑っていると燈夜は器から匙で粥を一口分掬い、花の口の前にもってくる。
「ほら、口を開けなさい」
匙を持ちながら優しく微笑む燈夜を見て断ろうとしていた花の気持ちが揺らぐ。
ここまでしてもらっているのにその善意を無駄にすることは出来ないと照れる感情を必死に抑え口を開けた。そっと口の中に粥が入る。
(あ、美味しい……)
もぐもぐと食べる花を見て燈夜は愛おしそうに目を細め、再び粥を掬うのだった。
あまり食欲が無かった花だったが燈夜のおかげか、不思議と食べることができ千代子が片付けた器は空になっていた。
薬も飲み、再び布団に入る。
食後と薬を飲んだからか眠気が襲う。
うとうととしている花を見て燈夜は優しく頭を撫でる。
「眠りにつくまで傍にいるから安心しなさい」
「ありがとうございます……」
身体は辛かったが隣に恋い慕う燈夜がいる。
苦しさの中に少しの余裕が出来て花はゆっくりと瞼を閉じた。
僅かに眩しさを感じ目を開け気がつくと花は花畑が広がる見知らぬ地に立っていた。
(あれ……?ここは……)
色とりどりの花が広がり美しい光景だが何故自分がここにいるのか一抹の不安を覚える。
辺りに視線を向けると少し離れた場所に桜の木が一本あることに気がついた。
どれくらいの年数が経っているのだろう。
とても立派で美しく心を奪われる。
その神々しくも感じる桜の木の下に白い着物を着た一人の男性が立っていた。
顔ははっきり見えないが体格からして男性であることが分かる。
(誰だろう?燈夜様……?…ううん、違う)
燈夜ではないのなら誰なのだろう。
記憶を辿ってみるがあのような男性と会ったことはないような気がする。
じっと見ているとその男性は口を開いた。
「花」
(え?私のことを知ってる……?)
自分と会ったことがあるのか問おうとして口を開くが声が出ないことに気づいた。
どんなに頑張っても喉が詰まるような感覚がして思っていることが言葉として発することが出来ない。
初めての感覚に頭が混乱してしまう。
せめて目線で訴えることが出来ないかとじっと男性を見つめる。
「花、ーー」
(え?)
最後の言葉の部分が聞き取れず戸惑った瞬間、突如として花びらが視界を覆う。
もう少し近づいてその顔をしっかり見たいのに足も動かない。
手を伸ばすが大量の花びらで完全に塞がれそこで辺りが暗闇に包まれた。
「っ……!」
ハッと目が覚めると見慣れた天井が視界に入る。
襖の隙間から橙色の光が差し込んでおり夕刻なのだと分かった。
起き上がりながら先程の光景は夢だったのだと胸を撫で下ろし乱れた呼吸を整えていると涙が流れていることに気づいた。
(あれ、私泣いている……?どうして……)
不思議に思いながら頬を伝う涙を拭おうとすると様子を見に来た燈夜が襖を開けた。
涙を流している花を見て目を見開いている。
「花、どうした……!どこか痛むか?」
珍しく焦りを滲ませ花の傍に寄る燈夜。
そうでは無いと伝える為にすぐに首を横に振る。
「違うんです。夢を見て……」
「夢?」
花は夢の内容を全て燈夜に話した。
話が終わると燈夜は何か考えるそぶりを見せる。
「白色の着物……」
「燈夜様?」
何か思い当たる節があるのか疑問に思い、花は首を傾げる。
「もしかすると夢に出てきた男性は花の実の父、美藤貴之ではないか?」
「お父様……!?」
美藤家の前当主、美藤貴之は花が幼い頃に病気で亡くなった。
しかも姉の未都の異能である記憶の消去により花には幼少期の記憶が無かった。
顔も分からなかったが会合や宴に度々参加している燈夜なら知っていても可笑しくはない。
「俺が幼い頃、両親に連れられて異能家系が集まる場に行ったことがある。そこに花の父親も白色の着物を来て参加していた」
しかし花が見たのは夢であることから本当に同一人物かは分からないと燈夜は言った。
仮に夢に出てきたのが貴之だとしたら何故姿を見せたのか分からなかった。
実の母親である透緒子にも『異端の子』と呼ばれ愛されなかった花。
では貴之はどうだったのだろうと考えたこともあった。
記憶にも無く人にも聞いたことが無い。
きっと貴之も無能で薄桜色の髪をもつ娘なんか好きにならないと勝手に思っていた。
愛される資格が自分には無いから。
「花が心配で見に来たのではないか?」
燈夜の一言に自然と顔を上げる花。
その一言に前を見ているような希望を感じるような思いが込められている気がする。
しかしどうしても花の心の中には覆い隠すような霞が残っていた。
「父は私を愛していたのでしょうか……」
俯く花に燈夜は自分の手を重ねた。強張った手に温もりが伝わる。
「一度、会合で話を聞いたことがある。自分には可愛い娘がいるのだと。…その名は花」
その言葉に視界が涙で潤むのが分かった。
自分は確かに父親に愛されていたのだと。
諦めていた気持ちに光が差し込む。
涙がぽろぽろと零れ、布団を濡らす。
そんな花を燈夜は優しく抱き締めた。
貴之は花を虐める透緒子と未都を何回も咎めていたが言うことを聞かず困っていたところ病状が悪化し床に伏せてしまったことは花は知らなかったのだった。