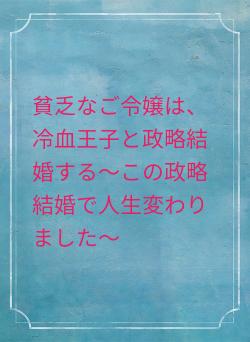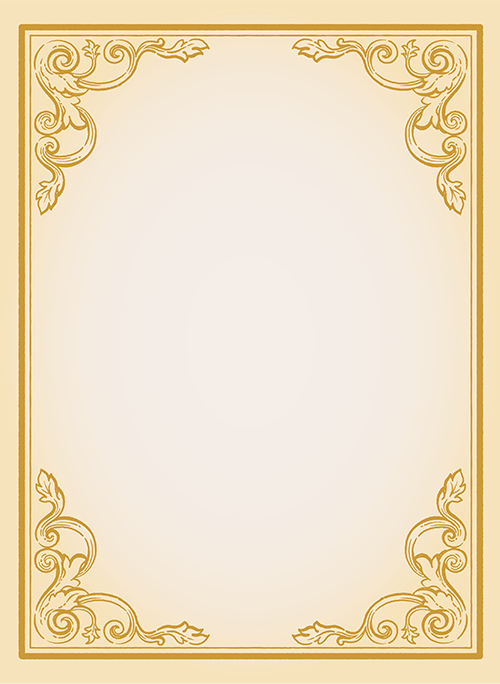「太陽、おはよう」
「おっはよーう!三日月!」
幼馴染の太陽に小さく挨拶すると、太陽は笑顔でそう返してくれた。
中学二年生。夜野三日月。
俺は太陽が大好きだ。理由は、なぜだか太陽の事が輝いて見えるからだ。
俺と違って太陽はいつでも元気いっぱいで、友達も沢山いた。
そんな太陽とは真逆で、俺はずっと落ち着いていて、友達も少ない。
こんな俺と仲良くしてくれるのは、太陽ぐらいだ。
『太陽、なんで俺と仲良くしてくれてるんだ?』
前に、思いきってそう聞いてみた。
すると太陽は、
『私ね、三日月の事が凄く憧れなの。
だから三日月と仲良しでいたいんだ』
太陽は笑顔でそう言っていた。
俺は嬉しかった。
俺を必要としてくれて、俺と一緒に居てくれて。
そんな所も、俺は太陽の良いところだと思った。
だって、俺はこんな事を恥ずかしくて言えないから。
……太陽は、俺にとって人生より大事な物だった。
「おはよ、三日月。それと朝野(あさの)さんも」
学校に着き、教室に入ると俺の親友の雲莉(くもり)が笑顔でそう言った。
「おはよ、雲莉」
「おっはよーう雲莉くーん!」
小さく言う俺を前に、太陽は雲莉に元気にそう言った。
相変わらず太陽は元気だな。
「ふふ、おはよう。ところで、太陽ちゃんって呼んでも、いいかな?」
雲莉は不敵な笑みを浮かべて、太陽にそう問いかける。
「う、うんっ!いいよっ!雲莉くん!」
太陽は少し表情を崩した気がしたが、気のせいか。
そう思って席に座った。
「おっはよーう!三日月!」
幼馴染の太陽に小さく挨拶すると、太陽は笑顔でそう返してくれた。
中学二年生。夜野三日月。
俺は太陽が大好きだ。理由は、なぜだか太陽の事が輝いて見えるからだ。
俺と違って太陽はいつでも元気いっぱいで、友達も沢山いた。
そんな太陽とは真逆で、俺はずっと落ち着いていて、友達も少ない。
こんな俺と仲良くしてくれるのは、太陽ぐらいだ。
『太陽、なんで俺と仲良くしてくれてるんだ?』
前に、思いきってそう聞いてみた。
すると太陽は、
『私ね、三日月の事が凄く憧れなの。
だから三日月と仲良しでいたいんだ』
太陽は笑顔でそう言っていた。
俺は嬉しかった。
俺を必要としてくれて、俺と一緒に居てくれて。
そんな所も、俺は太陽の良いところだと思った。
だって、俺はこんな事を恥ずかしくて言えないから。
……太陽は、俺にとって人生より大事な物だった。
「おはよ、三日月。それと朝野(あさの)さんも」
学校に着き、教室に入ると俺の親友の雲莉(くもり)が笑顔でそう言った。
「おはよ、雲莉」
「おっはよーう雲莉くーん!」
小さく言う俺を前に、太陽は雲莉に元気にそう言った。
相変わらず太陽は元気だな。
「ふふ、おはよう。ところで、太陽ちゃんって呼んでも、いいかな?」
雲莉は不敵な笑みを浮かべて、太陽にそう問いかける。
「う、うんっ!いいよっ!雲莉くん!」
太陽は少し表情を崩した気がしたが、気のせいか。
そう思って席に座った。