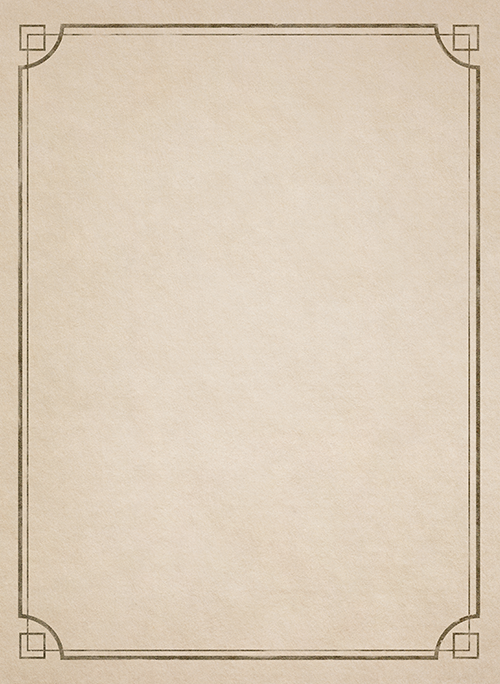彼女は知ったかぶりが得意である。
知ったかぶりと聞けば「プライドの高い奴」とか「嫌な奴」みたいな印象を抱くかもしれない。しかし、彼女は違った。もはや知っているのではないかと思えるほどに完全無欠の知ったかぶりなのだ。だから皆、彼女が知ったかぶりしていることに気が付いていない。たった一人、僕を除いては。
「おはよう。伯井くん」
突然の声の主を確かめるため振り向くと、眠そうに目をこする彼女がいた。学校にいる時の元気溌剌、快晴のような彼女ではなく、小雨が降ったかのようなしっとりと色っぽい少女だった。
「あ、おはよう。眠そうだな」
「はぁ~~、うん。夜更かししちゃってね」
大きく口を開けて欠伸をする。
「そんな夜中まで何してたんだ?」
「なかなか寝れなくてテレビとかケータイ見てたら……。はぁ~~。朝になってた」
「それは災難だな。そんじゃあ、昨日やってた『カバのあくび特集』見たか?」
「ああ、見てないのよ。見たかったんだけどお姉ちゃんがリモコンの主導権を握っていてね」
「そっか、そりゃ残念だなぁ。この感動と冷めやらぬ興奮を共有していたかったのだが」
「カバのあくびに感動興奮なんてあるの?」
少し小バカにしたような口調でつついてくる。
ああ、そりゃごもっともだ。そんなもので誰が感動と興奮を味わうというのだ。そんなもので感動できるほど心が豊かなら戦争なんてとうに無くなっているだろう。そう『カバのあくび特集』なる番組は放送などされていない。そんな番組は存在しない。
彼女は知ったかぶりが、得意である。そのことを皆知らない。ただ僕を除いては。そして、「僕が知っている」ということを彼女は知らない。
最終下校のチャイムが鳴った。
部活で汗水を流した華やかな青春を送る学生どもは「カラオケ行こうぜ」「コンビに寄って行こ」なんてはしゃぎながら思い思いの方向へ散らばって行く。そんな雑踏の奥からひょっこりと現れたのは彼女だった。
「お待たせ」
「いや待ってないよ」
「嘘つき。今日は部活早上がりの日なんでしょ。この時間までいるってことは待ってたってことでしょ」
破顔一笑、この笑顔を見られるなら待っている甲斐があるというものだ。
「さあ、帰ろうか」
「うん」
しばらくの無言が続く。
「わざわざごめんね、いつ友達と帰ってるのに。どうしてもカバのあくびの感動を共有したくてさ」
「ううん、大丈夫。私もカバのあくびの話聞きたいし」
まさか本心で言っているわけでもなかろう。知ったかを隠すための彼女なりの策略か? まあ、僕の前では今さらだが。
「あとさ、ちょっと相談がある」
「なになに?恋バナか?」
ふふっと笑ってみせる。
「なに?本当にそうなの?」
「まあそんなところだな」
「誰よ、誰よ」
「誰でもいいだろ。それより、お前いろんなこと知ってるだろ。アドバイスくれ」
「いいけどちゃんと頼んで」
「めんどくせーやつだな」
「別にいいのよ。伯井くんの恋が実らなくたって。私に関係ないもの」
「わかった、わかったよ。アドバイスをください」
「『お願いします』は?」
「お願いしますぅ」
満足したらしく、にやりと笑って話を進める。
「で、どんな人よ」
「うーん、そうだな。知らないことでも知ってるって言う奴だな」
彼女は少し顔を赤らめて、うつむいた。
そして、少しひきつった笑顔でこう言った。
「そんな嫌な子のどこがいいのよ」と。
知ったかぶりと聞けば「プライドの高い奴」とか「嫌な奴」みたいな印象を抱くかもしれない。しかし、彼女は違った。もはや知っているのではないかと思えるほどに完全無欠の知ったかぶりなのだ。だから皆、彼女が知ったかぶりしていることに気が付いていない。たった一人、僕を除いては。
「おはよう。伯井くん」
突然の声の主を確かめるため振り向くと、眠そうに目をこする彼女がいた。学校にいる時の元気溌剌、快晴のような彼女ではなく、小雨が降ったかのようなしっとりと色っぽい少女だった。
「あ、おはよう。眠そうだな」
「はぁ~~、うん。夜更かししちゃってね」
大きく口を開けて欠伸をする。
「そんな夜中まで何してたんだ?」
「なかなか寝れなくてテレビとかケータイ見てたら……。はぁ~~。朝になってた」
「それは災難だな。そんじゃあ、昨日やってた『カバのあくび特集』見たか?」
「ああ、見てないのよ。見たかったんだけどお姉ちゃんがリモコンの主導権を握っていてね」
「そっか、そりゃ残念だなぁ。この感動と冷めやらぬ興奮を共有していたかったのだが」
「カバのあくびに感動興奮なんてあるの?」
少し小バカにしたような口調でつついてくる。
ああ、そりゃごもっともだ。そんなもので誰が感動と興奮を味わうというのだ。そんなもので感動できるほど心が豊かなら戦争なんてとうに無くなっているだろう。そう『カバのあくび特集』なる番組は放送などされていない。そんな番組は存在しない。
彼女は知ったかぶりが、得意である。そのことを皆知らない。ただ僕を除いては。そして、「僕が知っている」ということを彼女は知らない。
最終下校のチャイムが鳴った。
部活で汗水を流した華やかな青春を送る学生どもは「カラオケ行こうぜ」「コンビに寄って行こ」なんてはしゃぎながら思い思いの方向へ散らばって行く。そんな雑踏の奥からひょっこりと現れたのは彼女だった。
「お待たせ」
「いや待ってないよ」
「嘘つき。今日は部活早上がりの日なんでしょ。この時間までいるってことは待ってたってことでしょ」
破顔一笑、この笑顔を見られるなら待っている甲斐があるというものだ。
「さあ、帰ろうか」
「うん」
しばらくの無言が続く。
「わざわざごめんね、いつ友達と帰ってるのに。どうしてもカバのあくびの感動を共有したくてさ」
「ううん、大丈夫。私もカバのあくびの話聞きたいし」
まさか本心で言っているわけでもなかろう。知ったかを隠すための彼女なりの策略か? まあ、僕の前では今さらだが。
「あとさ、ちょっと相談がある」
「なになに?恋バナか?」
ふふっと笑ってみせる。
「なに?本当にそうなの?」
「まあそんなところだな」
「誰よ、誰よ」
「誰でもいいだろ。それより、お前いろんなこと知ってるだろ。アドバイスくれ」
「いいけどちゃんと頼んで」
「めんどくせーやつだな」
「別にいいのよ。伯井くんの恋が実らなくたって。私に関係ないもの」
「わかった、わかったよ。アドバイスをください」
「『お願いします』は?」
「お願いしますぅ」
満足したらしく、にやりと笑って話を進める。
「で、どんな人よ」
「うーん、そうだな。知らないことでも知ってるって言う奴だな」
彼女は少し顔を赤らめて、うつむいた。
そして、少しひきつった笑顔でこう言った。
「そんな嫌な子のどこがいいのよ」と。