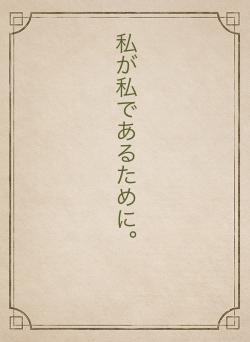昼休み、僕は教室で誰と話すでもなく、一人でまた頬杖をついて外を眺めていた。
夢の高校生活!なんていうのはよく聞くけど、僕はそんな風には思っていない。約百年の人生の中のうち、たった数年の過程、そこまでにしか思っていない。そもそも僕には友達もいないし、勉強も運動も今ひとつだ。唯一才覚があったかもしれない美術だって、あの日、を境に今まで感じていたような楽しさはどこかへ消え、描いていてもどこか苦しい、という感覚だけが残った。
誰といようがどこにいようが変わらない。何をしてても息苦しい。そこに決して光が差すことはない。救いようのないこの感覚はまるで無彩色の黒と同じだ。
ーーあーあ、誰かが変えてくれたらな。
決して自分では変わろうとしない。誰かが来るまで待ってる。そんな自分はやっぱり嫌いだ。
僕は頬杖をつく左手で頬をつねった。
「……」
そうなる事がまるで決まっていたかのように僕は体験入部もせず、美術部に入部届を出した。きっと親も、親戚も、みんなが、僕以外が、そう望んでる。
早速出したその日から活動開始らしい。顧問の先生に「絵が好きなの?」と聞かれ、自分の名前を出すと、やっぱりびっくりされた。だろうな、と思った。
僕は手渡された画用紙の上に特に何も考えずに、対象物だけを見て線を走らせる。いつものように。誰にも失望されぬように。僕の絵として、美術界で天才と呼ばれた少年、目黒那月(めぐろなつき)として。
夢の高校生活!なんていうのはよく聞くけど、僕はそんな風には思っていない。約百年の人生の中のうち、たった数年の過程、そこまでにしか思っていない。そもそも僕には友達もいないし、勉強も運動も今ひとつだ。唯一才覚があったかもしれない美術だって、あの日、を境に今まで感じていたような楽しさはどこかへ消え、描いていてもどこか苦しい、という感覚だけが残った。
誰といようがどこにいようが変わらない。何をしてても息苦しい。そこに決して光が差すことはない。救いようのないこの感覚はまるで無彩色の黒と同じだ。
ーーあーあ、誰かが変えてくれたらな。
決して自分では変わろうとしない。誰かが来るまで待ってる。そんな自分はやっぱり嫌いだ。
僕は頬杖をつく左手で頬をつねった。
「……」
そうなる事がまるで決まっていたかのように僕は体験入部もせず、美術部に入部届を出した。きっと親も、親戚も、みんなが、僕以外が、そう望んでる。
早速出したその日から活動開始らしい。顧問の先生に「絵が好きなの?」と聞かれ、自分の名前を出すと、やっぱりびっくりされた。だろうな、と思った。
僕は手渡された画用紙の上に特に何も考えずに、対象物だけを見て線を走らせる。いつものように。誰にも失望されぬように。僕の絵として、美術界で天才と呼ばれた少年、目黒那月(めぐろなつき)として。