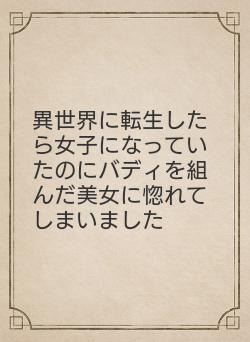「藍沢くん!」
最近、学校に行くと必ず声をかけてくるやつがいる。隣の席の変で、純情で、嫌になるくらいに綺麗なやつ。そんなやつは、ボクの近くにいるべきじゃないのに。
「おはよ、葵ちゃん。ボクのことも楓でいいって言ってるのに」
ボクは、首を傾げながらその女を上目遣いに見る。こうすれば、大概の女はボクに夢中になる。はずなのに、こいつはそうは行かない。
「い、いえ!も、もうちょっと時間が経つまで待ってくれると…う嬉しいかな…なんて…!」
不必要なほどに焦っている。そんなに真に受けなくてもいいのに。こっちだって別にお前に好意があるわけじゃないし。
「で、朝からどうしたの?」
朝から疲れる。ボクの都合通りに動いてくれない女。早く、見限って世界に絶望すればいいのに。
「あ、あの!生物、勉強しませんか??」
彼女は片手をあげて、ボクに申し出る。そうだろうと、思ってたけど。本当にそんなことやるつもりなんだ。
「今?」
優等生は大変ですね。心の中で毒づく。でもそれを決して表に出さずに髪の毛がサラリと揺れる程度に軽く首を傾ける。
「はい!2人とも電車の時間とかあるし…!確実に勉強できる時間にした方がいいと思って」
勉強するのはめんどくさい。でも、反論するのはもっとめんどくさい。だから、ボクは人懐こい笑みを顔に浮かべた。
「じゃあお願いします!」
そう言って、席に座って教科書を広げる。かと言って、やる気は毛頭ない。適当に時間が過ぎるのを待つか。
「で、でも教科書とか使った勉強ってつまらないよね。だから、あのクイズ形式で一旦どのくらいできるのか自分でわかっておくのがいいかなって思って!」
そう言って彼女は、紙切れをポケットから取り出した。何をしようとしてるんだ?ボクは訝しげに彼女を見つめる。
「はい、第1問!」
どうやら勝手に、クイズが始まった。ボクは、答えるなんて一言も言ってないのに。一生懸命紙を読む彼女から視線を外し、窓を見る。
「生物の分類の基本的な単位は?」
「種」
ボクはぽんと、直ぐに答えた。彼女は呆気に取られたように目を見開く。そうだよ、そういう顔に普通なるよな。
「せ、正解…!第2問、ATPのリン酸の結合は?」
「高エネルギーリン酸結合」
またもやボクは直ぐに答える。彼女は今度は薄く躊躇いの声を出した。そうだ、ボクは―。
「正解!第3問、葉緑体に含まれている緑色の色素は?」
「クロロフィル」
答えたボクに、彼女は紙から視線を外す。そして、ボクの目をしっかりと見る。ボクは、曖昧に視線を彷徨わせた。
「もしかして、藍沢くんって生物得意ですか?」
得意、だった。と言うべきだろう。でも、このクラスの中で1位2位を争えるくらいの知識があると思う。
「いやいや、それなら赤点なんか取らないって」
ボクはへらっと笑った。困らせれば、近くからいなくなる。そして、なんの汚れもないその瞳を嫌悪というシミで汚すことができる。
「でも、このくらいの知識があるなら赤点なんて…」
そうだ、ボクは本当は生物のテストで赤点なんか取らない。でも…。
「楓は、生物が得意なのね」
あの声が頭を掠めるから。
「いや、苦手なんだよ。ほんとに」
苦手なんじゃない、嫌いなんだ。思い出したくない記憶が、思い出したくない笑顔が顔を出すから。やりたくないんだ。
「ほんと…ですか…?」
彼女は窺うような目でボクの目を見る。まっすぐ目を見られるのは好きじゃない。特にこいつには何かを見透かされそうだ。
「そ。でも、葵ちゃんが大丈夫そうだなって思うならもう教えてくれなくても大丈夫だよ」
というか、いらない。毎日、生物の教科書を取り出してこの教科と向き合わなければならないなんて辛い。嫌なんだ。
「いや、私は苦手意識とか持って欲しくないから教えるよ!」
眩しいほどの純粋さ。やりたくないのにそれを押し付けようとしてくる傲慢さ。美しさと汚さは紙一重。
「いらない。そんなもん、いらない」
気づけば本心が口に出ていた。今まで学校でこんな自分を出したことはなかったのに。出会った人にこんな態度をとったことはなかったのに。
「生物、嫌い…?」
彼女が首を傾げる。ボクの計算ずくめの首傾げと違って純粋な疑問からくる首傾げ。彼女は全てがボクと違いすぎる。
「嫌い。嫌いなんだよ、全部」
どうでもいいと、思った。こいつひとりに嫌われるくらい。訳の分からない未知な女子に嫌われるくらいどうでもいいと。
「じゃあ!私が藍沢くんの答えられない問題を持ってきたら一緒に勉強する!そうしよ!私が持って来れなかったら勉強する必要はないの。どう?」
嫌だけれど、生物には自信があった。だから、ボクは頷いたのだ。彼女に確実に勝てる自信があったから。
最近、学校に行くと必ず声をかけてくるやつがいる。隣の席の変で、純情で、嫌になるくらいに綺麗なやつ。そんなやつは、ボクの近くにいるべきじゃないのに。
「おはよ、葵ちゃん。ボクのことも楓でいいって言ってるのに」
ボクは、首を傾げながらその女を上目遣いに見る。こうすれば、大概の女はボクに夢中になる。はずなのに、こいつはそうは行かない。
「い、いえ!も、もうちょっと時間が経つまで待ってくれると…う嬉しいかな…なんて…!」
不必要なほどに焦っている。そんなに真に受けなくてもいいのに。こっちだって別にお前に好意があるわけじゃないし。
「で、朝からどうしたの?」
朝から疲れる。ボクの都合通りに動いてくれない女。早く、見限って世界に絶望すればいいのに。
「あ、あの!生物、勉強しませんか??」
彼女は片手をあげて、ボクに申し出る。そうだろうと、思ってたけど。本当にそんなことやるつもりなんだ。
「今?」
優等生は大変ですね。心の中で毒づく。でもそれを決して表に出さずに髪の毛がサラリと揺れる程度に軽く首を傾ける。
「はい!2人とも電車の時間とかあるし…!確実に勉強できる時間にした方がいいと思って」
勉強するのはめんどくさい。でも、反論するのはもっとめんどくさい。だから、ボクは人懐こい笑みを顔に浮かべた。
「じゃあお願いします!」
そう言って、席に座って教科書を広げる。かと言って、やる気は毛頭ない。適当に時間が過ぎるのを待つか。
「で、でも教科書とか使った勉強ってつまらないよね。だから、あのクイズ形式で一旦どのくらいできるのか自分でわかっておくのがいいかなって思って!」
そう言って彼女は、紙切れをポケットから取り出した。何をしようとしてるんだ?ボクは訝しげに彼女を見つめる。
「はい、第1問!」
どうやら勝手に、クイズが始まった。ボクは、答えるなんて一言も言ってないのに。一生懸命紙を読む彼女から視線を外し、窓を見る。
「生物の分類の基本的な単位は?」
「種」
ボクはぽんと、直ぐに答えた。彼女は呆気に取られたように目を見開く。そうだよ、そういう顔に普通なるよな。
「せ、正解…!第2問、ATPのリン酸の結合は?」
「高エネルギーリン酸結合」
またもやボクは直ぐに答える。彼女は今度は薄く躊躇いの声を出した。そうだ、ボクは―。
「正解!第3問、葉緑体に含まれている緑色の色素は?」
「クロロフィル」
答えたボクに、彼女は紙から視線を外す。そして、ボクの目をしっかりと見る。ボクは、曖昧に視線を彷徨わせた。
「もしかして、藍沢くんって生物得意ですか?」
得意、だった。と言うべきだろう。でも、このクラスの中で1位2位を争えるくらいの知識があると思う。
「いやいや、それなら赤点なんか取らないって」
ボクはへらっと笑った。困らせれば、近くからいなくなる。そして、なんの汚れもないその瞳を嫌悪というシミで汚すことができる。
「でも、このくらいの知識があるなら赤点なんて…」
そうだ、ボクは本当は生物のテストで赤点なんか取らない。でも…。
「楓は、生物が得意なのね」
あの声が頭を掠めるから。
「いや、苦手なんだよ。ほんとに」
苦手なんじゃない、嫌いなんだ。思い出したくない記憶が、思い出したくない笑顔が顔を出すから。やりたくないんだ。
「ほんと…ですか…?」
彼女は窺うような目でボクの目を見る。まっすぐ目を見られるのは好きじゃない。特にこいつには何かを見透かされそうだ。
「そ。でも、葵ちゃんが大丈夫そうだなって思うならもう教えてくれなくても大丈夫だよ」
というか、いらない。毎日、生物の教科書を取り出してこの教科と向き合わなければならないなんて辛い。嫌なんだ。
「いや、私は苦手意識とか持って欲しくないから教えるよ!」
眩しいほどの純粋さ。やりたくないのにそれを押し付けようとしてくる傲慢さ。美しさと汚さは紙一重。
「いらない。そんなもん、いらない」
気づけば本心が口に出ていた。今まで学校でこんな自分を出したことはなかったのに。出会った人にこんな態度をとったことはなかったのに。
「生物、嫌い…?」
彼女が首を傾げる。ボクの計算ずくめの首傾げと違って純粋な疑問からくる首傾げ。彼女は全てがボクと違いすぎる。
「嫌い。嫌いなんだよ、全部」
どうでもいいと、思った。こいつひとりに嫌われるくらい。訳の分からない未知な女子に嫌われるくらいどうでもいいと。
「じゃあ!私が藍沢くんの答えられない問題を持ってきたら一緒に勉強する!そうしよ!私が持って来れなかったら勉強する必要はないの。どう?」
嫌だけれど、生物には自信があった。だから、ボクは頷いたのだ。彼女に確実に勝てる自信があったから。