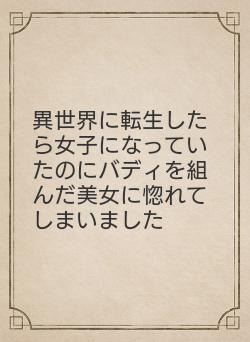「カエデ…、朝だよ…」
ソファの上で目を擦る。目を開けると、女子が目に入る。ああ、あのまま寝たのか。
「はよ、ごめん朝まで」
ボクが謝ると彼女は笑顔で首を振った。そして、立ち上がるとキッチンへ向かう。なにやら冷蔵庫を開けたらしい。
「朝ごはん作るね。そしたら私、1回家帰るから」
すごく面倒見がいい。それもこれもボクのことが好きだからなんだろう。ボクはまだこの子の名前が思い出せない。
「ありがと、顔洗ってくる」
ボクはへらっとした笑みを向けて、立ち上がる。こうしていれば安定するのだ。鎮痛剤があれば、どんな痛みにも耐えられる。
洗面所から戻ると彼女は帰る支度をしていた。学校に行くまでまたひとりだ。早く終わらせて早く学校に行こう。
「じゃあ帰るね。また呼んでよね、カエデ」
そう言って彼女の顔が近づいてくる。ボクは素知らぬ顔をして避けた。何も気づいていない振りをして後ろを振り向く。
「朝ごはん、ありがと」
ボクが笑顔で言うと、彼女は一瞬の硬直のあと笑顔に戻った。そして、カバンを肩にかけると頷く。ボクはヒラヒラと手を振った。
「そうね、カエデってそういう人だった」
そう言って、彼女はボクの家から出ていった。そういう人とはどういう人だろう。朝まで抱きしめあって、体を密着させていたにも関わらずキスはさせずに生殺しのような状態で帰すサイコパスな男だということだろうか。
「これでも優しくしてる方だけど」
そう言って、彼女が作っていった食事を捨てる。こんなものはいらない。好意なんていらない、好意が詰まった好意の塊のような食事なんて食べても気持ち悪いだけだ。
水を飲む。水はいい。飲んでも何も感じない。
「疲れた」
そう吐き捨てて家を出る。喧騒が耳に入る。人を感じる。
なんて、心地いいんだろう。1人は嫌いだ。だって、
「朝ごはんは楓の好きななめこの味噌汁よ」
あの声が聞こえてくるから。
息を吐く。息を吸う。呼吸はいつだって難しい。
「なんでここにいるんだろ」
そう吐き捨てることで、自分の均衡を保つ。そうでもしないと、飲み込まれてしまいそうだ。ものすごく大きな闇に、自分の中に深く根付く気持ちの悪い愛に。
「藍沢くん!」
駆け寄ってくる一人の女子。名前は知らないけど、中学の頃の同級生よりは記憶に新しい。そうだ、高校で同級生の昨日、声をかけたきた女子の片割れ。
「おはよ」
へらっとした笑顔で、女子に手を振る。女子は、嬉しそうに頬を朱色に染めてボクと並んで歩く。手を振っただけなのに、その行為は一緒に登校しようとそういう意味になるんだろうか。
「朝から会えるなんてラッキー!」
ごく自然な流れで、彼女とボクは一緒に登校することになった。ボクにとっても好都合だ。誤魔化しのラジオを止めて、イヤホンを耳から外す。
「大げさだなぁ」
そう言って、いかにも仲がいいように装う。そうしていればいつの間にか、隣にいることが当たり前になっていく。そうして、ボクの鎮痛剤のバリエーションは増えていく。
「あ、そういえば自己紹介してなかったよね!私、ユカ。よろしくね」
名前なんてどうでもいい。名前なんてこの世になければいい。名前があるからボクたちの人間関係はもっと複雑なものになってしまうんだ。
「うん、よろしく。あれ、昨日一緒にいた子は?」
二人で駅のホームに立ちながら横に並ぶ。人混みに紛れて、ボクは有象無象の一つになる。そうして、人に紛れている時間がボクの唯一の安息の時間だ。
「ああ、ナミ?あの子は、徒歩通だから。それに私は二人っきりのほうが嬉しいな」
昨日は、二人で騒ぎながらボクに近づいてきたくせに。友情なんてこんなものだ。これだから、人間なんて信じるもんじゃない。
「そっか、ボクも一緒に登校できて嬉しいよ」
そう言って、微笑みかければ彼女は心底嬉しそうな顔をする。ほら、心を奪うなんて簡単だ。ボクの心は今でもあの人に奪われ続けているけれど。
「あー!おはよ、ユカ、藍沢くん!!二人で登校なんて羨ましいぞ〜!」
昨日のもうひとりの女子がボクたちを見つけて、駆け寄ってくる。それに、ボクと登校した女子が答える。とても申し訳無さそうな、でも本心ではなさそうな困ったような笑顔で。
「そうなの。ナミもいれば楽しいだろうなぁって言ってたんだけどさ〜」
さっきまではいないほうが嬉しいとか言っていたのに。笑顔で、平然と、嘘を吐く。それがたとえ相手を傷つけないための言葉であってもそれは本当にいいことなんだろうか。
「じゃ、また後でね」
気持ち悪くなってきて、一人で教室に入る。朝から、気分が悪い。また、イヤホンを取り出して今度はとりわけ明るいバンドの曲を流した。
「あ!来た!!藍沢くん…!」
席から立ち上がって、ボクを見上げる女子は昨日生徒手帳をボクに届けてくれたあの女子だった。あの、つまらない女子。朝からなんの用だろうか。
「ちょっと…いい?」
そう言って、彼女は教室を出ていこうとする。ボクは、そのまま見送ってしまおうかとも思ったけれど少しの良心が痛んで、彼女の背中を追った。着いたのは、屋上だった。
「屋上なんて来れたんだ」
ボクはそう言いながら、手すりに寄りかかる。人がいなくてなんて寂しい場所だろう。地面を見下ろしながら静寂を噛みしめる。
「う、うん。話をするなら人がいないほうがいいと思って…」
なんの話だろうか。話しづらそうな雰囲気を漂わせて、告白でもするつもりだろうか。昨日、あんな断り方をしておいて?」
「話?」
ボクは、あくまで人好きのする笑顔を崩さないまま、首をかしげた。心のうちは、決して悟られないように。好意的な印象が彼女の中に残るように。
「そう、あの藍沢くん」
言葉を切る、女子。もったいぶらずに早く言え。お前の話にさほど興味はない。ボクの鎮痛剤になるつもりがないならなおさら。
「藍沢くん、生物の点数悪いでしょ…」
彼女はとてつもなく言いづらそうに言った。呼び出して、何を言われるかと思えばこいつ、ボクをバカにするためだけに呼び出したのか?だいたい、なんでボクの生物の点数なんてこいつが知ってるんだ。
「あー、確かに…悪かったかも…?」
ボクはヘラっとした笑顔で、頬をかいた。怒りで満たされそうな心と表情を切り離す。あくまで、穏やかな自分であらなければ鎮痛剤は離れていってしまう。
「あのね、先生が…。勉強、教えてやれって…。でも、点数が悪いなんて話、みんなのいるところでするのも良くないかなって思って来てもらったんだけど…」
ああ、教師に言われたのか。教師に頼まれるということはよほどの優等生なのか?優等生なら昨日の純情ぶった態度も納得できる。
「じゃあ、お願いしようかな」
勉強なんてやる気があるわけがなかった。でも、これを機に隣の席の変で、つまらなくて、優等生な女子をボクの鎮痛剤の一つにできるかもしれない。そんな、不純な動機だった。
「そっか、良かった!断られなくて」
その汚れを知らない笑顔にボクはあまりに不似合いだった。でも、逆に手に入れたくなった。ボクに、好意を抱いて都合のいいように使われてぐちゃぐちゃに汚れてしまえばいい。この世に、きれいなものなんていらないんだ。
ソファの上で目を擦る。目を開けると、女子が目に入る。ああ、あのまま寝たのか。
「はよ、ごめん朝まで」
ボクが謝ると彼女は笑顔で首を振った。そして、立ち上がるとキッチンへ向かう。なにやら冷蔵庫を開けたらしい。
「朝ごはん作るね。そしたら私、1回家帰るから」
すごく面倒見がいい。それもこれもボクのことが好きだからなんだろう。ボクはまだこの子の名前が思い出せない。
「ありがと、顔洗ってくる」
ボクはへらっとした笑みを向けて、立ち上がる。こうしていれば安定するのだ。鎮痛剤があれば、どんな痛みにも耐えられる。
洗面所から戻ると彼女は帰る支度をしていた。学校に行くまでまたひとりだ。早く終わらせて早く学校に行こう。
「じゃあ帰るね。また呼んでよね、カエデ」
そう言って彼女の顔が近づいてくる。ボクは素知らぬ顔をして避けた。何も気づいていない振りをして後ろを振り向く。
「朝ごはん、ありがと」
ボクが笑顔で言うと、彼女は一瞬の硬直のあと笑顔に戻った。そして、カバンを肩にかけると頷く。ボクはヒラヒラと手を振った。
「そうね、カエデってそういう人だった」
そう言って、彼女はボクの家から出ていった。そういう人とはどういう人だろう。朝まで抱きしめあって、体を密着させていたにも関わらずキスはさせずに生殺しのような状態で帰すサイコパスな男だということだろうか。
「これでも優しくしてる方だけど」
そう言って、彼女が作っていった食事を捨てる。こんなものはいらない。好意なんていらない、好意が詰まった好意の塊のような食事なんて食べても気持ち悪いだけだ。
水を飲む。水はいい。飲んでも何も感じない。
「疲れた」
そう吐き捨てて家を出る。喧騒が耳に入る。人を感じる。
なんて、心地いいんだろう。1人は嫌いだ。だって、
「朝ごはんは楓の好きななめこの味噌汁よ」
あの声が聞こえてくるから。
息を吐く。息を吸う。呼吸はいつだって難しい。
「なんでここにいるんだろ」
そう吐き捨てることで、自分の均衡を保つ。そうでもしないと、飲み込まれてしまいそうだ。ものすごく大きな闇に、自分の中に深く根付く気持ちの悪い愛に。
「藍沢くん!」
駆け寄ってくる一人の女子。名前は知らないけど、中学の頃の同級生よりは記憶に新しい。そうだ、高校で同級生の昨日、声をかけたきた女子の片割れ。
「おはよ」
へらっとした笑顔で、女子に手を振る。女子は、嬉しそうに頬を朱色に染めてボクと並んで歩く。手を振っただけなのに、その行為は一緒に登校しようとそういう意味になるんだろうか。
「朝から会えるなんてラッキー!」
ごく自然な流れで、彼女とボクは一緒に登校することになった。ボクにとっても好都合だ。誤魔化しのラジオを止めて、イヤホンを耳から外す。
「大げさだなぁ」
そう言って、いかにも仲がいいように装う。そうしていればいつの間にか、隣にいることが当たり前になっていく。そうして、ボクの鎮痛剤のバリエーションは増えていく。
「あ、そういえば自己紹介してなかったよね!私、ユカ。よろしくね」
名前なんてどうでもいい。名前なんてこの世になければいい。名前があるからボクたちの人間関係はもっと複雑なものになってしまうんだ。
「うん、よろしく。あれ、昨日一緒にいた子は?」
二人で駅のホームに立ちながら横に並ぶ。人混みに紛れて、ボクは有象無象の一つになる。そうして、人に紛れている時間がボクの唯一の安息の時間だ。
「ああ、ナミ?あの子は、徒歩通だから。それに私は二人っきりのほうが嬉しいな」
昨日は、二人で騒ぎながらボクに近づいてきたくせに。友情なんてこんなものだ。これだから、人間なんて信じるもんじゃない。
「そっか、ボクも一緒に登校できて嬉しいよ」
そう言って、微笑みかければ彼女は心底嬉しそうな顔をする。ほら、心を奪うなんて簡単だ。ボクの心は今でもあの人に奪われ続けているけれど。
「あー!おはよ、ユカ、藍沢くん!!二人で登校なんて羨ましいぞ〜!」
昨日のもうひとりの女子がボクたちを見つけて、駆け寄ってくる。それに、ボクと登校した女子が答える。とても申し訳無さそうな、でも本心ではなさそうな困ったような笑顔で。
「そうなの。ナミもいれば楽しいだろうなぁって言ってたんだけどさ〜」
さっきまではいないほうが嬉しいとか言っていたのに。笑顔で、平然と、嘘を吐く。それがたとえ相手を傷つけないための言葉であってもそれは本当にいいことなんだろうか。
「じゃ、また後でね」
気持ち悪くなってきて、一人で教室に入る。朝から、気分が悪い。また、イヤホンを取り出して今度はとりわけ明るいバンドの曲を流した。
「あ!来た!!藍沢くん…!」
席から立ち上がって、ボクを見上げる女子は昨日生徒手帳をボクに届けてくれたあの女子だった。あの、つまらない女子。朝からなんの用だろうか。
「ちょっと…いい?」
そう言って、彼女は教室を出ていこうとする。ボクは、そのまま見送ってしまおうかとも思ったけれど少しの良心が痛んで、彼女の背中を追った。着いたのは、屋上だった。
「屋上なんて来れたんだ」
ボクはそう言いながら、手すりに寄りかかる。人がいなくてなんて寂しい場所だろう。地面を見下ろしながら静寂を噛みしめる。
「う、うん。話をするなら人がいないほうがいいと思って…」
なんの話だろうか。話しづらそうな雰囲気を漂わせて、告白でもするつもりだろうか。昨日、あんな断り方をしておいて?」
「話?」
ボクは、あくまで人好きのする笑顔を崩さないまま、首をかしげた。心のうちは、決して悟られないように。好意的な印象が彼女の中に残るように。
「そう、あの藍沢くん」
言葉を切る、女子。もったいぶらずに早く言え。お前の話にさほど興味はない。ボクの鎮痛剤になるつもりがないならなおさら。
「藍沢くん、生物の点数悪いでしょ…」
彼女はとてつもなく言いづらそうに言った。呼び出して、何を言われるかと思えばこいつ、ボクをバカにするためだけに呼び出したのか?だいたい、なんでボクの生物の点数なんてこいつが知ってるんだ。
「あー、確かに…悪かったかも…?」
ボクはヘラっとした笑顔で、頬をかいた。怒りで満たされそうな心と表情を切り離す。あくまで、穏やかな自分であらなければ鎮痛剤は離れていってしまう。
「あのね、先生が…。勉強、教えてやれって…。でも、点数が悪いなんて話、みんなのいるところでするのも良くないかなって思って来てもらったんだけど…」
ああ、教師に言われたのか。教師に頼まれるということはよほどの優等生なのか?優等生なら昨日の純情ぶった態度も納得できる。
「じゃあ、お願いしようかな」
勉強なんてやる気があるわけがなかった。でも、これを機に隣の席の変で、つまらなくて、優等生な女子をボクの鎮痛剤の一つにできるかもしれない。そんな、不純な動機だった。
「そっか、良かった!断られなくて」
その汚れを知らない笑顔にボクはあまりに不似合いだった。でも、逆に手に入れたくなった。ボクに、好意を抱いて都合のいいように使われてぐちゃぐちゃに汚れてしまえばいい。この世に、きれいなものなんていらないんだ。