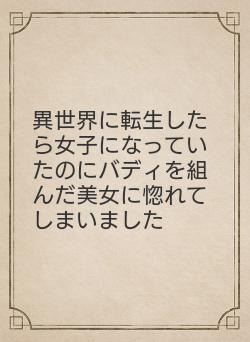少し個性的だからってボクの記憶には残らない。人に興味なんてない。だって、所詮他人じゃないか。たとえ血が繋がっていたとしたって、所詮は自分じゃない他人なんだ。
「ね、ねえねえ、藍沢くん…でいいんだよね?」
1時間授業が終わって、女子の声で話しかけられる。そういえば、誰か来るって言ってったけ?さっき手振ってあげた人達。
「うん、藍沢 楓。楓でいいよ」
女子たちに笑顔を向ける。それだけで女子たちは心を掴まれてくれる。容易いものだ。
「か、楓くん!今年からよろしくね!」
そうそう、こんなふうに軽々しく1年という期間を使う。1年の間に何が起こるかわからないのに。ボクを激しく憎むかもしれないのに。なんて薄っぺらい感情。なんて、上辺だけの言葉たち。
「うん、こちらこそ。声掛けてくれて嬉しいよ」
でも、こうしていれば誰かは来てくれる。決して1人になんてならずに済む。そばに居てくれる誰かがいてくれる。
「か、かっこいい…!」
ボクがはにかめば女子は喜ぶ。ボクが話しかければ女子は楽しむ。ボクがいれば、女子は騒ぎ出す。
「はぁ…」
彼女たちが離れていってまた静寂がボクを包む。ああ、虚しい。1人でいるのは嫌いだ。
放課後を知らせるチャイムが鳴って、生徒たちは騒ぎ出す。ボクはそうそうに支度を終わらせて、教室を出た。今日は、どうやって寂しさを紛らわそうか。
定期券を確認して、電車に乗り込む。イヤホンを耳につけて、静寂を誤魔化す。とにかく独りだと感じるのは辛い。
イヤホンよりも大きな音で、次の駅が知らされる。もう、着いちゃったのか。電車は人に紛れられる。でも、家に帰ったら本当に1人になってしまう。
定期券をかざして、駅を出る。1人でとぼとぼと歩く。イヤホンでできるだけ人が多く出ているラジオとかを流す。人を、感じる。
ああ、もうすぐ家だ。暗くて静かな家だ。1人きりで過ごさなきゃ行けない…家だ。
「おかえり、楓。今日は早かったのね」
あの声が聞こえてくる家だ。
「あ、あの!」
絶望に目の前が暗くなってきて、クラクラしてきた頃。誰かに肩を叩かれた。突然の人の気配に驚きながらも振り向く。そこに居たのは、隣の席の女子だった。あの、ちょっと変な女子。欲しくてたまらなかった人という存在にボクは呼吸の仕方を思い出す。
「ん?」
てか、学校では興味無いみたいな感じでやってたくせに家まで着いてきたのか?ストーカーかよ、やっぱボクのこと好きなんじゃん。やり方、こっわ。
「え、えと、ほんとは電車降りる前に声かけようと思ったんだけど降りていっちゃって…だから、私も降りて駅出る前に声かけようと思ったんだけどイヤホンつけてて聞こえなかったみたいで…。で、追いかけては来たんだけどなんか声かけられなくて…気づいたらこんなところまで…」
ズラズラと言い訳を並べる女子。名前、なんて言ったっけ?ここまで来たんならもう言い訳とかいいからさっさと要件言えよ。でも…人が来てくれて良かった…。
「そっか、ごめんごめん」
内心では感情がごちゃごちゃしているのに顔は爽やかな笑みを浮かべることができる。我ながら怖いと思う。普通の人はもっと下手なはずなのに。
「で、これ!落としたよ!」
でも、彼女の要件はボクが思っていたのとは違った。彼女の手には、手のひらサイズのものが握られていた。ボクは、それに見覚えがある。
「生徒、手帳…」
それはボクの生徒手帳だった。どうやらカバンのサイドポケットに入れていたものが落ちたらしい。これを届けに、わざわざ…?
「落としたら大変だから!それじゃ!」
ボクが恐る恐る受け取ると、彼女はそそくさとボクに背を向ける。え、これだけ…?これが口実な訳じゃなくて?
「待って…!」
ボクは彼女の手を掴んで引き止める。今、彼女を帰してしまったらボクはまた1人になる。そしたらまた、呼吸が出来なくなって真っ暗になって沈んでいく。
「は、はい?」
彼女は驚いた顔で振り返る。ここで、彼女を家に引き込んで、関係を持ってしまえば。新しい鎮痛剤が増える。
「家、寄ってかない?お礼に、飲み物でも!」
最高に人懐こい笑顔で言う。女子はこれでイチコロだ。それなのに、彼女はさささっとボクから遠ざかる。
「え、えと、あの、あんまり、よく知らないし、だ、だから、その、今日は帰ります!もっと仲良くなったら…で、バイバイ!」
そう言って彼女はボクに背を向けて、逃げていった。顔、真っ赤だったし。純情かよ。
「はぁ、つまんな」
ボクは頭をがしがしとかく。イヤホンの音量を上げる。思い通りに行かないと、ムカつく。
「冷めるわぁ」
1人で毒づいてスマホを見る。誰か呼ぼう。そうしてこのムカつきも寂しさも虚無感も消してしまおう。適当な連絡先にメッセージを送る。するとすぐに既読がつく。ああ、都合が良くて気持ちいい。
「カエデ!」
ドアが開いて、入ってくる女子。ああ、そういえばこんなやつだった。容姿すらも忘れていた中学の頃の同級生は嬉しそうに笑った。
「もう、高校入ってから全然連絡くれないんだもん。私のこと忘れちゃったのかと思った!」
頬を膨らませる女子。自分のこと、可愛いと思ってんのかな。ボクは冷めた感情を隠して、笑顔を浮かべる。
「忘れるわけないじゃん。高校に慣れるの手こずって忙しかっただけ」
適当な理由を言う。すると彼女はすぐに笑顔に戻る。この軽い感じが心地いい。
「じゃあ、なんか作ろっか。お腹空いてるで―」
「今は、ここにいて欲しい」
ボクは彼女の腕を引っ張って隣に座らせる。ただ、そばに居てくれるだけでいい。だって、ボクの鎮痛剤でしかないんだから。
「うん、いいよ」
鎮痛剤の肩に顔を埋める。すると、抱きしめて頭を撫でられる。ああ、ほら隣に誰かがいるってなんて居心地がいいんだろう。あんな女のことなんて忘れてしまおう。ボクには、こんなに素晴らしい鎮痛剤があるんだから。
「ね、ねえねえ、藍沢くん…でいいんだよね?」
1時間授業が終わって、女子の声で話しかけられる。そういえば、誰か来るって言ってったけ?さっき手振ってあげた人達。
「うん、藍沢 楓。楓でいいよ」
女子たちに笑顔を向ける。それだけで女子たちは心を掴まれてくれる。容易いものだ。
「か、楓くん!今年からよろしくね!」
そうそう、こんなふうに軽々しく1年という期間を使う。1年の間に何が起こるかわからないのに。ボクを激しく憎むかもしれないのに。なんて薄っぺらい感情。なんて、上辺だけの言葉たち。
「うん、こちらこそ。声掛けてくれて嬉しいよ」
でも、こうしていれば誰かは来てくれる。決して1人になんてならずに済む。そばに居てくれる誰かがいてくれる。
「か、かっこいい…!」
ボクがはにかめば女子は喜ぶ。ボクが話しかければ女子は楽しむ。ボクがいれば、女子は騒ぎ出す。
「はぁ…」
彼女たちが離れていってまた静寂がボクを包む。ああ、虚しい。1人でいるのは嫌いだ。
放課後を知らせるチャイムが鳴って、生徒たちは騒ぎ出す。ボクはそうそうに支度を終わらせて、教室を出た。今日は、どうやって寂しさを紛らわそうか。
定期券を確認して、電車に乗り込む。イヤホンを耳につけて、静寂を誤魔化す。とにかく独りだと感じるのは辛い。
イヤホンよりも大きな音で、次の駅が知らされる。もう、着いちゃったのか。電車は人に紛れられる。でも、家に帰ったら本当に1人になってしまう。
定期券をかざして、駅を出る。1人でとぼとぼと歩く。イヤホンでできるだけ人が多く出ているラジオとかを流す。人を、感じる。
ああ、もうすぐ家だ。暗くて静かな家だ。1人きりで過ごさなきゃ行けない…家だ。
「おかえり、楓。今日は早かったのね」
あの声が聞こえてくる家だ。
「あ、あの!」
絶望に目の前が暗くなってきて、クラクラしてきた頃。誰かに肩を叩かれた。突然の人の気配に驚きながらも振り向く。そこに居たのは、隣の席の女子だった。あの、ちょっと変な女子。欲しくてたまらなかった人という存在にボクは呼吸の仕方を思い出す。
「ん?」
てか、学校では興味無いみたいな感じでやってたくせに家まで着いてきたのか?ストーカーかよ、やっぱボクのこと好きなんじゃん。やり方、こっわ。
「え、えと、ほんとは電車降りる前に声かけようと思ったんだけど降りていっちゃって…だから、私も降りて駅出る前に声かけようと思ったんだけどイヤホンつけてて聞こえなかったみたいで…。で、追いかけては来たんだけどなんか声かけられなくて…気づいたらこんなところまで…」
ズラズラと言い訳を並べる女子。名前、なんて言ったっけ?ここまで来たんならもう言い訳とかいいからさっさと要件言えよ。でも…人が来てくれて良かった…。
「そっか、ごめんごめん」
内心では感情がごちゃごちゃしているのに顔は爽やかな笑みを浮かべることができる。我ながら怖いと思う。普通の人はもっと下手なはずなのに。
「で、これ!落としたよ!」
でも、彼女の要件はボクが思っていたのとは違った。彼女の手には、手のひらサイズのものが握られていた。ボクは、それに見覚えがある。
「生徒、手帳…」
それはボクの生徒手帳だった。どうやらカバンのサイドポケットに入れていたものが落ちたらしい。これを届けに、わざわざ…?
「落としたら大変だから!それじゃ!」
ボクが恐る恐る受け取ると、彼女はそそくさとボクに背を向ける。え、これだけ…?これが口実な訳じゃなくて?
「待って…!」
ボクは彼女の手を掴んで引き止める。今、彼女を帰してしまったらボクはまた1人になる。そしたらまた、呼吸が出来なくなって真っ暗になって沈んでいく。
「は、はい?」
彼女は驚いた顔で振り返る。ここで、彼女を家に引き込んで、関係を持ってしまえば。新しい鎮痛剤が増える。
「家、寄ってかない?お礼に、飲み物でも!」
最高に人懐こい笑顔で言う。女子はこれでイチコロだ。それなのに、彼女はさささっとボクから遠ざかる。
「え、えと、あの、あんまり、よく知らないし、だ、だから、その、今日は帰ります!もっと仲良くなったら…で、バイバイ!」
そう言って彼女はボクに背を向けて、逃げていった。顔、真っ赤だったし。純情かよ。
「はぁ、つまんな」
ボクは頭をがしがしとかく。イヤホンの音量を上げる。思い通りに行かないと、ムカつく。
「冷めるわぁ」
1人で毒づいてスマホを見る。誰か呼ぼう。そうしてこのムカつきも寂しさも虚無感も消してしまおう。適当な連絡先にメッセージを送る。するとすぐに既読がつく。ああ、都合が良くて気持ちいい。
「カエデ!」
ドアが開いて、入ってくる女子。ああ、そういえばこんなやつだった。容姿すらも忘れていた中学の頃の同級生は嬉しそうに笑った。
「もう、高校入ってから全然連絡くれないんだもん。私のこと忘れちゃったのかと思った!」
頬を膨らませる女子。自分のこと、可愛いと思ってんのかな。ボクは冷めた感情を隠して、笑顔を浮かべる。
「忘れるわけないじゃん。高校に慣れるの手こずって忙しかっただけ」
適当な理由を言う。すると彼女はすぐに笑顔に戻る。この軽い感じが心地いい。
「じゃあ、なんか作ろっか。お腹空いてるで―」
「今は、ここにいて欲しい」
ボクは彼女の腕を引っ張って隣に座らせる。ただ、そばに居てくれるだけでいい。だって、ボクの鎮痛剤でしかないんだから。
「うん、いいよ」
鎮痛剤の肩に顔を埋める。すると、抱きしめて頭を撫でられる。ああ、ほら隣に誰かがいるってなんて居心地がいいんだろう。あんな女のことなんて忘れてしまおう。ボクには、こんなに素晴らしい鎮痛剤があるんだから。