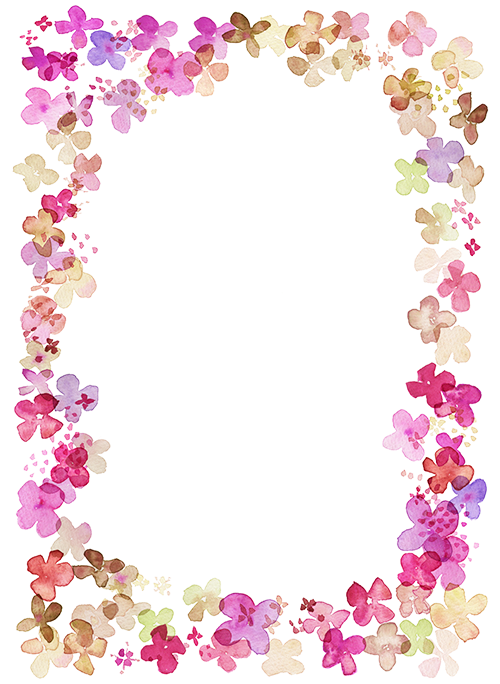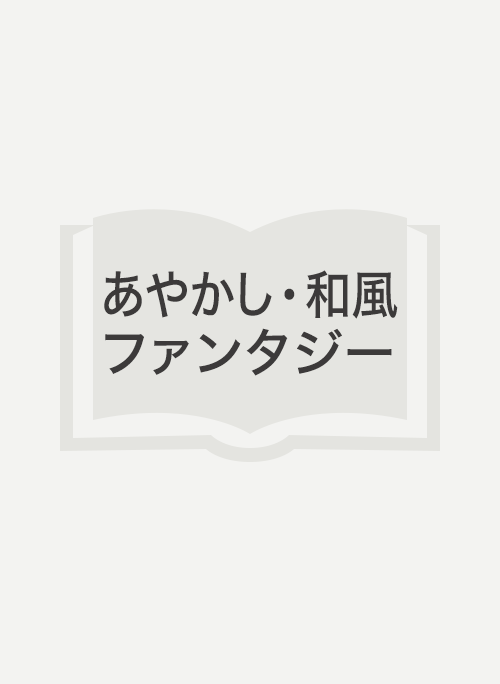「この子が水鏡が選んだ桜河様の花嫁……」
光が満ちる天界にある壮観な屋敷の一室でまるで天女のような美しい女性が水晶に映っている撫子を見ている。
暫く見るとフッと瞳を閉じ、すぐ傍に控えていた使用人に声をかける。
「人間界に行く準備を」
「かしこまりました」
恭しく頭を下げ部屋から出て行く。
水晶に手をかざし映っている撫子を消すと上品な声で一言呟いた。
「桜河様に相応しいのはこの私ですわ」
幼なじみの崇明から求婚をされて数日経った。
求婚をされてすぐにその場を去ったので返事はまだしていない。
撫子の中ではすでに気持ちは決まっていた。
しかしそれを伝えて幼なじみという関係が壊れてしまったらと考えてしまい、崇明と会えていなかった。
あまり長引かせてはいけないと分かっているのにもし今までのように話せなくなったらと怖くなっていた。
暗い顔をしている撫子に桜河は毎日寄り添ってくれた。
撫子が崇明に恋心を抱いてはいないのは知っている。
ただ撫子が優しく繊細であることから、悩みで心が潰されないようにずっと隣にいた。
「撫子、大丈夫か?」
「は、はい。大丈夫です」
考え込んでいたのか桜河の声にハッとし顔を上げ笑いかける。
桜河は心配させないようにと撫子が無理して笑っていることに気がついていた。
目の下には隈があり夜もあまり眠れていないことが分かる。
指でそっと目尻を撫でる。
「眠れていないのだろう。……あの時撫子は返事の言葉を考えていたのに立ち去ってしまってすまなかった」
自分の愛する花嫁が他の男と話しているのが耐えられなかった。
しかもそれは愛の言葉。
伝えている様子を見ていられず、もうそれ以上聞かせないように撫子を抱き寄せ独占欲のまま立ち去った。
桜河の申し訳なさそうに眉を下げる姿に撫子は慌てて首を横に振る。
「そんな、龍神様のせいではありません!気持ちは分かっていたのに怖くなってしまったから……」
俯き膝の上に置いてある手をぎゅっと握り締める。
自分の弱さがずっと嫌いだった。
心の中では分かっているのに一歩踏み出すのが怖かった。
小刻みに震えている撫子を桜河は自分の腕で包み込む。
撫子の耳が桜河の胸に当たりトクントクンと心臓の音が聞こえる。
「優しい撫子が本当の兄のように慕っていた相手だ。自分の気持ちを伝えたところで関係を壊そうとするあいつでは無いはずだ」
その言葉がスッと胸に届く。
少しずつ心の靄が晴れていくような気がした。
崇明は虐げられていた自分をずっと案じてくれた思いやりのある人。
きっと自分の思いを素直に伝えれば分かってくれる。
撫子の中で崇明を信じたいと気持ちに変化が出てきた。
「……私、崇明お兄ちゃんに気持ちを伝えます」
撫子の決意に満ちた目を見て桜河は頷く。
重ねられた手の温かさから勇気をもらえたような気がした。
崇明と会うのは撫子が決意を固めた日から一週間後に決まった。
以前、崇明から携帯番号が書かれた紙を渡されたが鈴代家の自室に仕舞ったままだった。
お世話係である百合乃に清瀬家の会社の番号を調べてもらい連絡をすると受付の女性が出た。
崇明は海外に出張に行っているようで帰国するのは一週間後だと分かった。
代わりに会いたいという旨を伝えてもらい崇明が帰国した日に会う約束になった。
少しの緊張を感じながら一日一日を過ごしていた。
今日は桜河が執務で天界へ向かい不在の為、百合乃と近所を散歩していた。
撫子が外出をする際は桜河か護衛の者が必要だが屋敷の近所の場合は百合乃が付いてくれることもあった。
百合乃は神に仕える一族出身。
神や花嫁を守る為に護身術を心得ており少しの外出ならお世話係の立場であっても一任されていた。
美しさと知識も兼ね備え、しかも護身術まで出来る百合乃に撫子は秘かに憧れていた。
「今日は良い天気ですね、撫子様」
「はい。気持ちが良いです」
雲一つない晴天が広がり時折優しく吹く風が頬を撫でる。
思わず伸びをしたくなるような気持ちよさで緊張していた心が楽になる。
「撫子様……!」
暫く歩いて再び屋敷に着くと帰宅した撫子に気がついた女性の使用人が慌てて出てくる。
駆け寄ってくる姿に何事かと瞳を瞬かせる。
「な、撫子様にお客様です」
「お客様?」
自分にお客様にあたるような人物がいたか考えを巡らせてみるが思い当たる節がない。
幼なじみの崇明は出張中で鈴代家の人間は撫子や桜河の許可が無いと光結町に入れない。
それでは誰なのだろうと首を傾げていると使用人がそれを汲み取ったのか口を開いた。
「花の神の一族、蘭姫様でございます」
「花の……」
名前を聞いても初めて聞く名前でピンとこない。
今までで話に上がったか振り返ってみたが記憶に無かった。
桜河だったら分かるかもしれないが今は不在。
何故自分なのか分からなかったが相手は神の一族。
とにかく会わなければいけないと思い、使用人に案内され蘭姫が待っている客間に向かった。
「こちらでございます」
客間の前に着くと百合乃が心配そうに顔を覗き込む。
「お一人で大丈夫ですか?私もお隣に居りましょうか?」
百合乃の提案に首を横に振る。
「ありがとうございます。でも大丈夫です」
本当は不安だが自分を訪ねてきた客人。
誰かに甘えず一人でしっかりと客人対応くらいしなくてはと気を引き締める。
まだ百合乃は不安げな表情をしていたがそっと一歩下がった。
深呼吸をして口を開く。
「失礼します」
戸を開け部屋に入ると座っていた女性の視線がこちらに向く。
桃色で絹のような美しい髪に長いまつげとぱっちりとした瞳、まるで人形のような容姿に一瞬で目を奪われる。
こんなにも美しい女性に出会ったことが無い。
「貴女様が鈴代撫子様ですね?」
鈴のような綺麗な声にハッと我に返る。
「は、はい……!」
撫子が頷いてから座ると使用人が二人の分のお茶を運んできた。
テーブルの上に置き退出をすると二人きりになる。
お茶を飲む所作でさえも洗練されていて美しい。
湯呑みを静かに置くと蘭姫は撫子に視線を向ける。
「私、花の神である桐斗の妹の蘭姫と申します」
丁寧にお辞儀をされ撫子も慌てて頭を下げる。
「す、鈴代撫子です」
少しだけだが桜河から神達の話は聞いたことがあった。
八百万存在する神達の中で花の神の桐斗は強力な力の持ち主で桜河と共に人間界の繁栄に尽力してきた。
その一族も皆、絶大な力を所有しており天界での地位は高かった。
しかしその桐斗に妹が居ることは知らなかった。
そんな凄い人物が何故自分を訪ねてきたのか不思議に思っていた。
「単刀直入に申しますわ。撫子様、桜河様の花嫁を辞退して下さい」
「……え?」
一瞬何て言われたのか分からなかった。
蘭姫の真剣さにも怒りにも感じるような瞳が撫子を射貫く。
「もう一度申します。花嫁を辞退して下さいませ」
「ど、どうしてですか?」
聞き間違いなどでは無かった。
上品でお淑やかな姿から想像出来ない衝撃的な言葉を言われ驚いてしまう。
まさか辞退しろだなんて言われると思わず突発的に理由を聞いてみてしまった。
「調べさせていただきましたが貴女様は元は庶民的な家庭の出身だそうですね。教養も無い貴女様に桜河様の妻としての務めが果たせるとでも?」
蘭姫の言葉に何も反論出来なかった。
撫子の両親は名家出身だが駆け落ちをした為、亡くなるまでは特別裕福な暮らしでは無かった。
鈴代家の養子になってからも使用人同様の扱いを受けていたので令嬢としての教養は何も身に付いていない。
黙っている撫子を変わらず冷たい瞳で見つめている。
「私は桜河様の婚約者だったのです」
「こん、やく、しゃ……?」
その言葉に撫子は体が固まってしまった。
桜河に婚約者が存在していたことは聞いたことが無かったから。
思考が停止しそうになりながらも必死に頭を回転させる。
撫子はふと一つのある疑問が浮かんだ。
神達は水鏡を使用して自分の花嫁を決めるのに何故婚約者が必要なのか。
撫子の考えを見透かしたのか質問する前に蘭姫が口を開いた。
「水鏡の儀式の際、ごく稀にですが花嫁が映し出されないことがあります。その場合は神の一族の女性と結婚をするのです」
すぐに分かった。
もし自分が映し出されなかったら桜河は蘭姫と結婚をしていたのだと。
きっと彼女は桜河に想いを寄せていたのだろう。
それなのに教養も無い娘が龍神の花嫁に選ばれたことに怒りを抱いているのが表情から伝わってきた。
何と言って良いか分からなかった。
桜河も使用人達も優しくて今の暮らしは幸せだ。
最初は戸惑ったが少しずつ周囲が許してくれるのならここにいたいと願うようになった。
しかしそんな自分を花嫁として桜河の隣に居ることを良しとしない人物もいると知り現実を突きつけられる。
神の花嫁となれば社交界に赴く機会も当然あるだろう。
そんな華やかな場で龍神の花嫁として恥ずかしくないような振る舞いが出来るのか分からない。
周りから見れば一目で蘭姫が花嫁に相応しいと言うはずだ。
「神と花嫁の間に生まれる世継ぎは霊力が非常に高い。確かにそれも繁栄の為に重要なことであるのは承知しております。しかし私も一族に誇れるほど高い霊力を持っております。私が桜河様との世継ぎを産んでも十分貢献出来ますわ」
次々と放たれる言葉に刺があるが蘭姫の言うことは正しかった。
自分の甘さを痛感し異論も反論も出来なかった。
「撫子様は桜河様を好いているのですか?花嫁としての覚悟がお見受け出来ませんが」
「私は……」
桜河と共に過ごして自分の胸の中に新たに芽生えてくる気持ちに戸惑っていた。
自分に優しく笑いかけ触れてくれる桜河に胸は高まるがそれが恋なのか異性だからなのか恋愛経験が無い撫子は分からなかった。
黙る撫子に蘭姫は小さく溜息を吐き立ち上がった。
「私はもうお暇致します。辞退の件、お考え下さいね」
戸を開け客間を出て行く。
様々な思いが頭を巡り撫子は暫くその場から動けずにいたのだった。
光が満ちる天界にある壮観な屋敷の一室でまるで天女のような美しい女性が水晶に映っている撫子を見ている。
暫く見るとフッと瞳を閉じ、すぐ傍に控えていた使用人に声をかける。
「人間界に行く準備を」
「かしこまりました」
恭しく頭を下げ部屋から出て行く。
水晶に手をかざし映っている撫子を消すと上品な声で一言呟いた。
「桜河様に相応しいのはこの私ですわ」
幼なじみの崇明から求婚をされて数日経った。
求婚をされてすぐにその場を去ったので返事はまだしていない。
撫子の中ではすでに気持ちは決まっていた。
しかしそれを伝えて幼なじみという関係が壊れてしまったらと考えてしまい、崇明と会えていなかった。
あまり長引かせてはいけないと分かっているのにもし今までのように話せなくなったらと怖くなっていた。
暗い顔をしている撫子に桜河は毎日寄り添ってくれた。
撫子が崇明に恋心を抱いてはいないのは知っている。
ただ撫子が優しく繊細であることから、悩みで心が潰されないようにずっと隣にいた。
「撫子、大丈夫か?」
「は、はい。大丈夫です」
考え込んでいたのか桜河の声にハッとし顔を上げ笑いかける。
桜河は心配させないようにと撫子が無理して笑っていることに気がついていた。
目の下には隈があり夜もあまり眠れていないことが分かる。
指でそっと目尻を撫でる。
「眠れていないのだろう。……あの時撫子は返事の言葉を考えていたのに立ち去ってしまってすまなかった」
自分の愛する花嫁が他の男と話しているのが耐えられなかった。
しかもそれは愛の言葉。
伝えている様子を見ていられず、もうそれ以上聞かせないように撫子を抱き寄せ独占欲のまま立ち去った。
桜河の申し訳なさそうに眉を下げる姿に撫子は慌てて首を横に振る。
「そんな、龍神様のせいではありません!気持ちは分かっていたのに怖くなってしまったから……」
俯き膝の上に置いてある手をぎゅっと握り締める。
自分の弱さがずっと嫌いだった。
心の中では分かっているのに一歩踏み出すのが怖かった。
小刻みに震えている撫子を桜河は自分の腕で包み込む。
撫子の耳が桜河の胸に当たりトクントクンと心臓の音が聞こえる。
「優しい撫子が本当の兄のように慕っていた相手だ。自分の気持ちを伝えたところで関係を壊そうとするあいつでは無いはずだ」
その言葉がスッと胸に届く。
少しずつ心の靄が晴れていくような気がした。
崇明は虐げられていた自分をずっと案じてくれた思いやりのある人。
きっと自分の思いを素直に伝えれば分かってくれる。
撫子の中で崇明を信じたいと気持ちに変化が出てきた。
「……私、崇明お兄ちゃんに気持ちを伝えます」
撫子の決意に満ちた目を見て桜河は頷く。
重ねられた手の温かさから勇気をもらえたような気がした。
崇明と会うのは撫子が決意を固めた日から一週間後に決まった。
以前、崇明から携帯番号が書かれた紙を渡されたが鈴代家の自室に仕舞ったままだった。
お世話係である百合乃に清瀬家の会社の番号を調べてもらい連絡をすると受付の女性が出た。
崇明は海外に出張に行っているようで帰国するのは一週間後だと分かった。
代わりに会いたいという旨を伝えてもらい崇明が帰国した日に会う約束になった。
少しの緊張を感じながら一日一日を過ごしていた。
今日は桜河が執務で天界へ向かい不在の為、百合乃と近所を散歩していた。
撫子が外出をする際は桜河か護衛の者が必要だが屋敷の近所の場合は百合乃が付いてくれることもあった。
百合乃は神に仕える一族出身。
神や花嫁を守る為に護身術を心得ており少しの外出ならお世話係の立場であっても一任されていた。
美しさと知識も兼ね備え、しかも護身術まで出来る百合乃に撫子は秘かに憧れていた。
「今日は良い天気ですね、撫子様」
「はい。気持ちが良いです」
雲一つない晴天が広がり時折優しく吹く風が頬を撫でる。
思わず伸びをしたくなるような気持ちよさで緊張していた心が楽になる。
「撫子様……!」
暫く歩いて再び屋敷に着くと帰宅した撫子に気がついた女性の使用人が慌てて出てくる。
駆け寄ってくる姿に何事かと瞳を瞬かせる。
「な、撫子様にお客様です」
「お客様?」
自分にお客様にあたるような人物がいたか考えを巡らせてみるが思い当たる節がない。
幼なじみの崇明は出張中で鈴代家の人間は撫子や桜河の許可が無いと光結町に入れない。
それでは誰なのだろうと首を傾げていると使用人がそれを汲み取ったのか口を開いた。
「花の神の一族、蘭姫様でございます」
「花の……」
名前を聞いても初めて聞く名前でピンとこない。
今までで話に上がったか振り返ってみたが記憶に無かった。
桜河だったら分かるかもしれないが今は不在。
何故自分なのか分からなかったが相手は神の一族。
とにかく会わなければいけないと思い、使用人に案内され蘭姫が待っている客間に向かった。
「こちらでございます」
客間の前に着くと百合乃が心配そうに顔を覗き込む。
「お一人で大丈夫ですか?私もお隣に居りましょうか?」
百合乃の提案に首を横に振る。
「ありがとうございます。でも大丈夫です」
本当は不安だが自分を訪ねてきた客人。
誰かに甘えず一人でしっかりと客人対応くらいしなくてはと気を引き締める。
まだ百合乃は不安げな表情をしていたがそっと一歩下がった。
深呼吸をして口を開く。
「失礼します」
戸を開け部屋に入ると座っていた女性の視線がこちらに向く。
桃色で絹のような美しい髪に長いまつげとぱっちりとした瞳、まるで人形のような容姿に一瞬で目を奪われる。
こんなにも美しい女性に出会ったことが無い。
「貴女様が鈴代撫子様ですね?」
鈴のような綺麗な声にハッと我に返る。
「は、はい……!」
撫子が頷いてから座ると使用人が二人の分のお茶を運んできた。
テーブルの上に置き退出をすると二人きりになる。
お茶を飲む所作でさえも洗練されていて美しい。
湯呑みを静かに置くと蘭姫は撫子に視線を向ける。
「私、花の神である桐斗の妹の蘭姫と申します」
丁寧にお辞儀をされ撫子も慌てて頭を下げる。
「す、鈴代撫子です」
少しだけだが桜河から神達の話は聞いたことがあった。
八百万存在する神達の中で花の神の桐斗は強力な力の持ち主で桜河と共に人間界の繁栄に尽力してきた。
その一族も皆、絶大な力を所有しており天界での地位は高かった。
しかしその桐斗に妹が居ることは知らなかった。
そんな凄い人物が何故自分を訪ねてきたのか不思議に思っていた。
「単刀直入に申しますわ。撫子様、桜河様の花嫁を辞退して下さい」
「……え?」
一瞬何て言われたのか分からなかった。
蘭姫の真剣さにも怒りにも感じるような瞳が撫子を射貫く。
「もう一度申します。花嫁を辞退して下さいませ」
「ど、どうしてですか?」
聞き間違いなどでは無かった。
上品でお淑やかな姿から想像出来ない衝撃的な言葉を言われ驚いてしまう。
まさか辞退しろだなんて言われると思わず突発的に理由を聞いてみてしまった。
「調べさせていただきましたが貴女様は元は庶民的な家庭の出身だそうですね。教養も無い貴女様に桜河様の妻としての務めが果たせるとでも?」
蘭姫の言葉に何も反論出来なかった。
撫子の両親は名家出身だが駆け落ちをした為、亡くなるまでは特別裕福な暮らしでは無かった。
鈴代家の養子になってからも使用人同様の扱いを受けていたので令嬢としての教養は何も身に付いていない。
黙っている撫子を変わらず冷たい瞳で見つめている。
「私は桜河様の婚約者だったのです」
「こん、やく、しゃ……?」
その言葉に撫子は体が固まってしまった。
桜河に婚約者が存在していたことは聞いたことが無かったから。
思考が停止しそうになりながらも必死に頭を回転させる。
撫子はふと一つのある疑問が浮かんだ。
神達は水鏡を使用して自分の花嫁を決めるのに何故婚約者が必要なのか。
撫子の考えを見透かしたのか質問する前に蘭姫が口を開いた。
「水鏡の儀式の際、ごく稀にですが花嫁が映し出されないことがあります。その場合は神の一族の女性と結婚をするのです」
すぐに分かった。
もし自分が映し出されなかったら桜河は蘭姫と結婚をしていたのだと。
きっと彼女は桜河に想いを寄せていたのだろう。
それなのに教養も無い娘が龍神の花嫁に選ばれたことに怒りを抱いているのが表情から伝わってきた。
何と言って良いか分からなかった。
桜河も使用人達も優しくて今の暮らしは幸せだ。
最初は戸惑ったが少しずつ周囲が許してくれるのならここにいたいと願うようになった。
しかしそんな自分を花嫁として桜河の隣に居ることを良しとしない人物もいると知り現実を突きつけられる。
神の花嫁となれば社交界に赴く機会も当然あるだろう。
そんな華やかな場で龍神の花嫁として恥ずかしくないような振る舞いが出来るのか分からない。
周りから見れば一目で蘭姫が花嫁に相応しいと言うはずだ。
「神と花嫁の間に生まれる世継ぎは霊力が非常に高い。確かにそれも繁栄の為に重要なことであるのは承知しております。しかし私も一族に誇れるほど高い霊力を持っております。私が桜河様との世継ぎを産んでも十分貢献出来ますわ」
次々と放たれる言葉に刺があるが蘭姫の言うことは正しかった。
自分の甘さを痛感し異論も反論も出来なかった。
「撫子様は桜河様を好いているのですか?花嫁としての覚悟がお見受け出来ませんが」
「私は……」
桜河と共に過ごして自分の胸の中に新たに芽生えてくる気持ちに戸惑っていた。
自分に優しく笑いかけ触れてくれる桜河に胸は高まるがそれが恋なのか異性だからなのか恋愛経験が無い撫子は分からなかった。
黙る撫子に蘭姫は小さく溜息を吐き立ち上がった。
「私はもうお暇致します。辞退の件、お考え下さいね」
戸を開け客間を出て行く。
様々な思いが頭を巡り撫子は暫くその場から動けずにいたのだった。