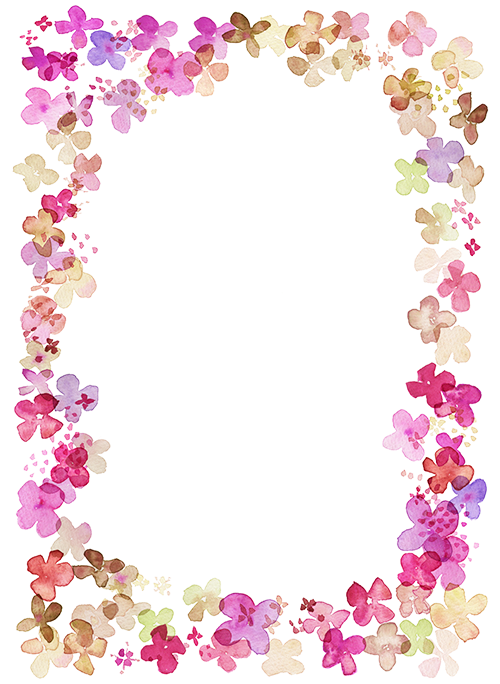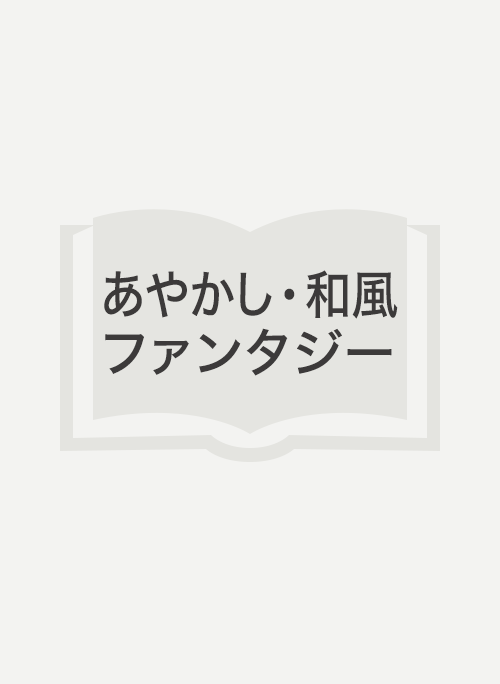どれくらい泣いただろう。
まだ頭の中では過去の辛い出来事が波のように押し寄せてくる。
もう足掻くのは辞めた。
きっとこれは忘れてはいけない戒めという意味なのだろう。
婚約者を奪われ悲しみに暮れる玲子の気持ちも分かる。
その悲しみ、恨みを娘である自分にぶつけて晴らしたいのだ。
撫子は涙も涸れ果て悪夢に身を任せた。
「……」
「撫子……」
唸り続けていた撫子がぱたりとそれを止め、一瞬安堵したが熱は下がらず顔色も悪い。
撫子が倒れてから桜河は寝ずに寄り添い、気づけば太陽が昇り始めていた。
「失礼いたします」
額に乗せている濡れた手拭いの交換をしに来た百合乃は部屋に入ると眠り続ける撫子をそっと見る。
「撫子様、大丈夫でしょうか…」
手際良く手拭いを取り替えながらも声は少し震えていた。
仕える主が倒れても冷静になって動けと教えられてきた百合乃は動揺する姿は見せなかったが目を覚まさない撫子を見て抑えていてもやはり心配する気持ちが勝っているのだろう。
それは他の使用人とて同じ。
『何か出来ることはありますか』
『よろしければ治癒の神の霊力が込められた御守りをどうぞ』
撫子は皆に愛されているのだと改めて実感した。
神に仕える使用人は水鏡に映し出された花嫁にも忠誠を誓うが、それ以上に撫子の陽だまりのような優しさに彼女を好きになっていたのだ。
「俺や百合乃達の思いはきっと撫子に伝わる」
「……!そうですね」
少しだけ笑顔が戻った百合乃は手拭いの交換を終えると部屋を出て行った。
部屋に再び静寂が訪れる。
桜河は撫子の小さい手を握りながら愛しい花嫁への想いをゆっくり口にした。
「水鏡の儀で初めて映し出された撫子を見てとても愛らしい女性だと思った。そんな君を腕の中に閉じ込められたときは嬉しかったが……。でも最初は撫子を戸惑わせてしまった……。すまない」
時折悪夢で苦しそうに顔を歪める撫子。
桜河は体に障らぬよう小さな声で続けた。
「あの夜、撫子が俺のことを好きだと言ってくれたとき幸福で心が満ち溢れた。もしこの生活を拒絶してしまったらと俺は心のどこかで怯えていたのだろう」
龍神として強い存在でいなければいけない。
この霊力で人間界を守護する、それが使命だ。
しかし執務に没頭して知らぬうちに周囲を怖がらせてしまった。
「でも撫子の優しさに触れて俺は変われた」
『桜河様』
その春の日差しのような柔らかい声が氷で凍てつく心を解かした。
もう一度その声を聞きたい。
いや一度ではなくこれから先も。
花のような笑顔、頬を林檎のように染める照れた顔……。
コロコロと変わる表情全てが大切な宝物だ。
「撫子。悪夢から覚めて俺に会いに来て」
撫子は暗闇で蹲りながら頭に流れ込んでくる悪夢をずっと見ていた。
どんな非道なことをされてもこれで玲子の恨みが少しでも晴れてくれればそれで良かった。
(ここにずっといれば許される……?)
この戒めを受け入れようとそっと瞳を閉じたとき。
『撫子』
誰もいるはずがない暗闇に声が聞こえた。
顔を上げると亡くなったはずの両親が少し離れた場所に立っている。
「お父さん……!お母さん……!」
会いたいと願っていた二人に駆け寄ろうと立ち上がり踏み出そうとした。
しかし足が鉛のように重くなり前に進んでくれない。
「え……!?」
必死に動かそうとするがびくともせず初めての感覚に動揺してしまう。
早く両親の元に行きたいのに一寸も動かない。
「撫子、ごめんね」
父の声にパッと顔を上げると悲しそうな顔をしていた。
それは母も同じで今にも泣きそうな表情に胸が痛んだ。
「撫子が辛い思いをしているのは私達のせいよ」
「俺達の問題に巻き込んでしまって……。撫子だけは守りたかった」
「お父さん、お母さん……」
こんな両親を見るのは初めてで傍に寄って『私は大丈夫だよ』と言いたいのに足が動かない。
そんな撫子を見て両親は首を横に振った。
「撫子、まだこちらに来ては駄目よ」
「で、でも!」
ずっと会いたかった両親がすぐそこにいるのに駆け寄ることさえ出来ない体に焦りが募る。
「大切な人がいるのだろう?」
父がすっと撫子の後ろの方角を指差す。
振り返ると小さな光が見えた。
先ほどまでは辺り一帯、漆黒に包まれていたのに突如現れた光に目を見開く。
『撫子。悪夢から覚めて俺に会いに来て』
耳に届く大切な人の声。
聞いた瞬間、胸が震えた。
(そうだ、私のことを待ってる人がいる)
ここではなく、光が降り注ぐ陽だまりの場所に行きたい。
両親に向き直り真っ直ぐ見据える。
「お父さん、お母さん……。私やっぱり戻るね」
二人は頷くとゆっくりと姿が薄れてやがて消えていった。
撫子は頬に流れた涙を拭うと光に向かって歩き出した。
重たい瞼を開けると見慣れた茶色の木目の天井が視界に入った。
「撫子……!」
首を横に動かすと桜河が心配そうに撫子の顔を覗き込んでいた。
夢の中で聞こえた声の主に会えた安堵からか瞳が潤むのが分かった。
「お……うが……様の声……聞こえ……ましたよ」
途切れ途切れの言葉。
目尻に涙を溜めて話す撫子に桜河はそっと頬に手を添える。
「そうか……。本当に良かった」
桜河は微笑んでいたが触れる手は少し震えていてかなり心配してくれていたのだと分かった。
風邪のせいか喉が痛み、声があまり出ない代わりに感謝の気持ちを込めて桜河の手に頬を擦り寄せた。
桜河の息を呑む音が聞こえゆっくりと顔が近づく。
こうしてまた触れ合えることができるのは奇跡なのだと思いながら撫子はそっと瞳を閉じその瞬間を待つのだった。
まだ頭の中では過去の辛い出来事が波のように押し寄せてくる。
もう足掻くのは辞めた。
きっとこれは忘れてはいけない戒めという意味なのだろう。
婚約者を奪われ悲しみに暮れる玲子の気持ちも分かる。
その悲しみ、恨みを娘である自分にぶつけて晴らしたいのだ。
撫子は涙も涸れ果て悪夢に身を任せた。
「……」
「撫子……」
唸り続けていた撫子がぱたりとそれを止め、一瞬安堵したが熱は下がらず顔色も悪い。
撫子が倒れてから桜河は寝ずに寄り添い、気づけば太陽が昇り始めていた。
「失礼いたします」
額に乗せている濡れた手拭いの交換をしに来た百合乃は部屋に入ると眠り続ける撫子をそっと見る。
「撫子様、大丈夫でしょうか…」
手際良く手拭いを取り替えながらも声は少し震えていた。
仕える主が倒れても冷静になって動けと教えられてきた百合乃は動揺する姿は見せなかったが目を覚まさない撫子を見て抑えていてもやはり心配する気持ちが勝っているのだろう。
それは他の使用人とて同じ。
『何か出来ることはありますか』
『よろしければ治癒の神の霊力が込められた御守りをどうぞ』
撫子は皆に愛されているのだと改めて実感した。
神に仕える使用人は水鏡に映し出された花嫁にも忠誠を誓うが、それ以上に撫子の陽だまりのような優しさに彼女を好きになっていたのだ。
「俺や百合乃達の思いはきっと撫子に伝わる」
「……!そうですね」
少しだけ笑顔が戻った百合乃は手拭いの交換を終えると部屋を出て行った。
部屋に再び静寂が訪れる。
桜河は撫子の小さい手を握りながら愛しい花嫁への想いをゆっくり口にした。
「水鏡の儀で初めて映し出された撫子を見てとても愛らしい女性だと思った。そんな君を腕の中に閉じ込められたときは嬉しかったが……。でも最初は撫子を戸惑わせてしまった……。すまない」
時折悪夢で苦しそうに顔を歪める撫子。
桜河は体に障らぬよう小さな声で続けた。
「あの夜、撫子が俺のことを好きだと言ってくれたとき幸福で心が満ち溢れた。もしこの生活を拒絶してしまったらと俺は心のどこかで怯えていたのだろう」
龍神として強い存在でいなければいけない。
この霊力で人間界を守護する、それが使命だ。
しかし執務に没頭して知らぬうちに周囲を怖がらせてしまった。
「でも撫子の優しさに触れて俺は変われた」
『桜河様』
その春の日差しのような柔らかい声が氷で凍てつく心を解かした。
もう一度その声を聞きたい。
いや一度ではなくこれから先も。
花のような笑顔、頬を林檎のように染める照れた顔……。
コロコロと変わる表情全てが大切な宝物だ。
「撫子。悪夢から覚めて俺に会いに来て」
撫子は暗闇で蹲りながら頭に流れ込んでくる悪夢をずっと見ていた。
どんな非道なことをされてもこれで玲子の恨みが少しでも晴れてくれればそれで良かった。
(ここにずっといれば許される……?)
この戒めを受け入れようとそっと瞳を閉じたとき。
『撫子』
誰もいるはずがない暗闇に声が聞こえた。
顔を上げると亡くなったはずの両親が少し離れた場所に立っている。
「お父さん……!お母さん……!」
会いたいと願っていた二人に駆け寄ろうと立ち上がり踏み出そうとした。
しかし足が鉛のように重くなり前に進んでくれない。
「え……!?」
必死に動かそうとするがびくともせず初めての感覚に動揺してしまう。
早く両親の元に行きたいのに一寸も動かない。
「撫子、ごめんね」
父の声にパッと顔を上げると悲しそうな顔をしていた。
それは母も同じで今にも泣きそうな表情に胸が痛んだ。
「撫子が辛い思いをしているのは私達のせいよ」
「俺達の問題に巻き込んでしまって……。撫子だけは守りたかった」
「お父さん、お母さん……」
こんな両親を見るのは初めてで傍に寄って『私は大丈夫だよ』と言いたいのに足が動かない。
そんな撫子を見て両親は首を横に振った。
「撫子、まだこちらに来ては駄目よ」
「で、でも!」
ずっと会いたかった両親がすぐそこにいるのに駆け寄ることさえ出来ない体に焦りが募る。
「大切な人がいるのだろう?」
父がすっと撫子の後ろの方角を指差す。
振り返ると小さな光が見えた。
先ほどまでは辺り一帯、漆黒に包まれていたのに突如現れた光に目を見開く。
『撫子。悪夢から覚めて俺に会いに来て』
耳に届く大切な人の声。
聞いた瞬間、胸が震えた。
(そうだ、私のことを待ってる人がいる)
ここではなく、光が降り注ぐ陽だまりの場所に行きたい。
両親に向き直り真っ直ぐ見据える。
「お父さん、お母さん……。私やっぱり戻るね」
二人は頷くとゆっくりと姿が薄れてやがて消えていった。
撫子は頬に流れた涙を拭うと光に向かって歩き出した。
重たい瞼を開けると見慣れた茶色の木目の天井が視界に入った。
「撫子……!」
首を横に動かすと桜河が心配そうに撫子の顔を覗き込んでいた。
夢の中で聞こえた声の主に会えた安堵からか瞳が潤むのが分かった。
「お……うが……様の声……聞こえ……ましたよ」
途切れ途切れの言葉。
目尻に涙を溜めて話す撫子に桜河はそっと頬に手を添える。
「そうか……。本当に良かった」
桜河は微笑んでいたが触れる手は少し震えていてかなり心配してくれていたのだと分かった。
風邪のせいか喉が痛み、声があまり出ない代わりに感謝の気持ちを込めて桜河の手に頬を擦り寄せた。
桜河の息を呑む音が聞こえゆっくりと顔が近づく。
こうしてまた触れ合えることができるのは奇跡なのだと思いながら撫子はそっと瞳を閉じその瞬間を待つのだった。