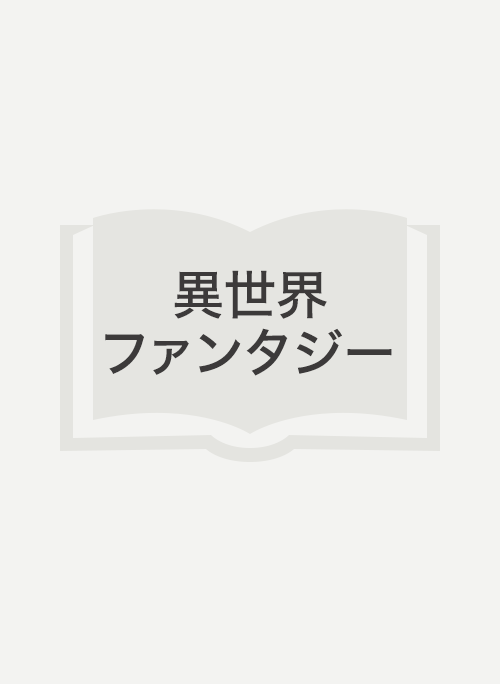前回のあらすじ
無事大嘴鶏と子供を救助した二人。
しかし冒険屋たちの様子がおかしくて……。
「おい、その天狗を連れて行くなら、お前たちが面倒を見ろよ」
「え? ああ、はい」
「お前も大概お人よしだな。天狗なんぞを拾うとは」
「最後まで面倒見ろよ」
口々に言われる言葉に、釈然としないながらも、紙月と未来は天狗だという子供を預かった。他の冒険屋たちは、見事に昏倒している大嘴鶏食いに舌を巻きながら、しっかりととどめを刺して大嘴鶏の背に載せ、手早く帰り始めた。
勇敢な子供のことなど見もしない。
「なあんだ、ありゃ」
「なんだろうね」
二人は顔を見合わせて、肩をすくめた。
子供は未来よりもまだ小さく、十歳になるかどうかというくらいだろうか。
話には聞いていた天狗という種族らしく、確かに端々に鳥の特徴が見て取れた。
口を開ければ見えるのは歯ではなく、そのように見えるひとつながりの嘴であるし、瞳は大きく、白目の部分がほとんどない。
暴れるのを抱き上げて大嘴鶏に載せてやった時に気付いたが、靴には靴底というものがなく、鱗のある鳥のような足がそこから覗いていた。成程、木などに掴まるとき、靴底があっては邪魔だろう。
また、服があまりにも上等な刺繍がなされていたので飾り物かと思っていたが、その手首からひじのあたりに生えているのは紛れもなく羽毛である。羽毛というより、立派な翼の一部と言っていい。
飾り羽のようだが、話に聞くところ、天狗はこれで空を飛ぶという。
「ほら、暴れんなって。お前らちっちゃいんだから乗り切るだろ」
「ちっちゃいっていうな!」
馬上に押し込まれてぎゃいぎゃいとうるさい子供二人は、手綱を取る紙月の腕の中で声をそろえた。
「俺は紙月で、こいつは相棒の未来」
「未来だよ、よろしく」
「ふん、冒険屋風情かあっだだだだだだ」
「名乗られたら名乗り返すくらいは教わってないのか」
「あだ、あだだ、ス、スピザエト! スピザエトである!」
「よし、よし」
頬をつねってやって、ようやく名を聞き出せて、第一歩である。
「よ、よくもわしに手を上げたな! わしはな!」
「うん、うん、よくわかるぞ。お前は立派な奴だ」
「お、おう?」
「一人で大嘴鶏食いに立ち向かおうなんてなかなかできることじゃあない。怖かったろ」
「こわくなどあるものか!」
「勇敢な奴だ。それで、どうして一人でこんなところに?」
「うむ。それが、連れとともにおったはずなのだが、彼奴ら、いつの間にか逸れてしもうてな。付き人としてなっとらんのじゃ」
それは多分お前の方が逸れたんだろうな、とは思いながらも紙月は口を出さなかった。口ぶりからどうもいいとこの坊ちゃんであるらしいし、余計な口をはさんでこじれるのも面倒だったからだ。
「それでひとりで散歩しておったら、あの可哀そうな大嘴鶏どもが彷徨っておった」
「おお、お前が見つけてくれたのか」
「そうとも。わしはきっとこいつらはきっと親から逸れてしもうたんじゃ、かわいそうになと思って、折角だから親元まで返してやろうと付き添ってやったんじゃ」
迷子が迷子の世話見ようとしている、などと言いだそうとした未来の口はそっと塞いでおいた。
「それからどうした」
「うむ、そうしたらあのトカゲども! 野蛮な大嘴鶏食いめが追いかけてきおったのじゃ」
「おお、大変だったな」
「そうとも、そうだとも! わしは哀れな大嘴鶏を守ってやらねばと思って矢を番えては射たのじゃが、何しろあいつらすばしっこくての、さしものわしもなかなか当たらん」
(まるでとは言わないでやろう)
「そうこうしているうちに矢も尽きて、こうなれば仕方がない、わしの鍛え上げた蹴り足をお見舞いしてやろうとしておったところに、おぬしの茶々が入ったのじゃ」
「俺か」
「おぬしじゃ」
「紙月だね」
「そうだ、シヅキとかいったか。おぬしが茶々を入れねばわしがぼっこぼこにしておったのじゃ、ほんとじゃぞ」
まあ持ち上げるのもこの辺でいいかと、紙月はそうかそうかと適当に頷いた。
「それじゃあ、俺たちが助けないでも、お前ひとりで倒せたのか」
「そうとも、そうだとも!」
「本当にか」
「本当だとも! 疑うのか!」
「ここにゃ俺たちしかいないんだ。誰にも言わねえよ」
「……ま、まあちょっぴり、ほんのちょっぴり危なかったかもしれんな」
「そしたら、大嘴鶏たちは危なかったな」
「う……うむ。そうだ。危なかったかもしれん」
「もしお前が万が一足を滑らせでもしたら、万が一だぞ、それじゃあ大嘴鶏たちは酷い目に遭っていたな」
「ひどい目に遭っていたのか?」
「間違いないな」
「で、でもなんとかなったのじゃ」
「もしかしたら俺達は来なかったかもしれないな」
「む、むう」
「お前は一人でよくやったよ。でも一人じゃ大変なことだっていっぱいある。一人じゃ護り切れない時もある。そういうときは、助けを求めていいんだ」
「し、しかしな、しかしわしは……」
「お前は自分一人でやれると思ってるだろうし、それは大事な気構えだけど、それで護るべきものが傷ついたんじゃあ仕方がないだろ」
「む、むう」
「護りたいと思ったんなら、そのことをまず大事にしなきゃな。自分のことはおいておいて、誰かのことを考えられる方が、ずっと格好いいと思わないか」
「お、思う、かもしれん」
「そうか」
「そ、そうだ」
「それがわかったならお前さんは立派な勇者だよ」
「そ、そうか?」
「そうだとも」
そうか、とはにかむように笑うスピザエトの頬を、紙月はつねった。
「あだだだだだ激痛でない程度の適度な痛み!」
「それじゃあできる天狗様はまず助けてもらった感謝! それに悪態ついた謝罪な!」
「ありがとうございます! ごめんなさい!」
「よし」
「紙月、ほんと多芸だよね」
「これくらい子守のバイトしたらすぐ慣れる」
「ほんと多芸だよね、ほんと」
腕の中ですっかり大人しくなったスピザエトは、緊張が解けたためか、ぐったりと脱力し、それを未来が支えてやっている状態だった。
「しっかし、こんな子供相手におっさんたちはなんでピリピリしてんだろうな」
これが紙月には疑問であった。
単に子供嫌いであるというのは、これはない。
実際、未来が鎧を脱いだ姿を見せた時も、成人前だというのに立派だなと大いに褒められ、成人前の子供を冒険屋稼業に連れまわすなどと紙月は怒られたぐらいだった。帝国では一般的に成人と言えば十四歳であるらしく、なるほど未来はまだ二、三年程足りない。
この例で行くと、その未来よりいくらか幼いスピザエトの奮闘は、褒め称えられてしかるべきであって、間違ってもその逆はないはずだった。それなのに実際は、スピザエトは敬遠され、すっかり紙月に面倒を任されてしまっている。
首をかしげる二人に、スピザエトは眠たげながらも唇を尖らせた。
「それはきっと、わしが天狗だからなのじゃ……」
帰り着き、それが事実だと知って、紙月は激怒するのであった。
用語解説
・スピザエト(Spizaeto)
天狗の少年。非常に身なりが良く、良いところのお坊ちゃんであるようだ。
弓を持っていたが腕前は杜撰なもので、年若いこともあってまだ一人で飛ぶのは難しいようだ。
無事大嘴鶏と子供を救助した二人。
しかし冒険屋たちの様子がおかしくて……。
「おい、その天狗を連れて行くなら、お前たちが面倒を見ろよ」
「え? ああ、はい」
「お前も大概お人よしだな。天狗なんぞを拾うとは」
「最後まで面倒見ろよ」
口々に言われる言葉に、釈然としないながらも、紙月と未来は天狗だという子供を預かった。他の冒険屋たちは、見事に昏倒している大嘴鶏食いに舌を巻きながら、しっかりととどめを刺して大嘴鶏の背に載せ、手早く帰り始めた。
勇敢な子供のことなど見もしない。
「なあんだ、ありゃ」
「なんだろうね」
二人は顔を見合わせて、肩をすくめた。
子供は未来よりもまだ小さく、十歳になるかどうかというくらいだろうか。
話には聞いていた天狗という種族らしく、確かに端々に鳥の特徴が見て取れた。
口を開ければ見えるのは歯ではなく、そのように見えるひとつながりの嘴であるし、瞳は大きく、白目の部分がほとんどない。
暴れるのを抱き上げて大嘴鶏に載せてやった時に気付いたが、靴には靴底というものがなく、鱗のある鳥のような足がそこから覗いていた。成程、木などに掴まるとき、靴底があっては邪魔だろう。
また、服があまりにも上等な刺繍がなされていたので飾り物かと思っていたが、その手首からひじのあたりに生えているのは紛れもなく羽毛である。羽毛というより、立派な翼の一部と言っていい。
飾り羽のようだが、話に聞くところ、天狗はこれで空を飛ぶという。
「ほら、暴れんなって。お前らちっちゃいんだから乗り切るだろ」
「ちっちゃいっていうな!」
馬上に押し込まれてぎゃいぎゃいとうるさい子供二人は、手綱を取る紙月の腕の中で声をそろえた。
「俺は紙月で、こいつは相棒の未来」
「未来だよ、よろしく」
「ふん、冒険屋風情かあっだだだだだだ」
「名乗られたら名乗り返すくらいは教わってないのか」
「あだ、あだだ、ス、スピザエト! スピザエトである!」
「よし、よし」
頬をつねってやって、ようやく名を聞き出せて、第一歩である。
「よ、よくもわしに手を上げたな! わしはな!」
「うん、うん、よくわかるぞ。お前は立派な奴だ」
「お、おう?」
「一人で大嘴鶏食いに立ち向かおうなんてなかなかできることじゃあない。怖かったろ」
「こわくなどあるものか!」
「勇敢な奴だ。それで、どうして一人でこんなところに?」
「うむ。それが、連れとともにおったはずなのだが、彼奴ら、いつの間にか逸れてしもうてな。付き人としてなっとらんのじゃ」
それは多分お前の方が逸れたんだろうな、とは思いながらも紙月は口を出さなかった。口ぶりからどうもいいとこの坊ちゃんであるらしいし、余計な口をはさんでこじれるのも面倒だったからだ。
「それでひとりで散歩しておったら、あの可哀そうな大嘴鶏どもが彷徨っておった」
「おお、お前が見つけてくれたのか」
「そうとも。わしはきっとこいつらはきっと親から逸れてしもうたんじゃ、かわいそうになと思って、折角だから親元まで返してやろうと付き添ってやったんじゃ」
迷子が迷子の世話見ようとしている、などと言いだそうとした未来の口はそっと塞いでおいた。
「それからどうした」
「うむ、そうしたらあのトカゲども! 野蛮な大嘴鶏食いめが追いかけてきおったのじゃ」
「おお、大変だったな」
「そうとも、そうだとも! わしは哀れな大嘴鶏を守ってやらねばと思って矢を番えては射たのじゃが、何しろあいつらすばしっこくての、さしものわしもなかなか当たらん」
(まるでとは言わないでやろう)
「そうこうしているうちに矢も尽きて、こうなれば仕方がない、わしの鍛え上げた蹴り足をお見舞いしてやろうとしておったところに、おぬしの茶々が入ったのじゃ」
「俺か」
「おぬしじゃ」
「紙月だね」
「そうだ、シヅキとかいったか。おぬしが茶々を入れねばわしがぼっこぼこにしておったのじゃ、ほんとじゃぞ」
まあ持ち上げるのもこの辺でいいかと、紙月はそうかそうかと適当に頷いた。
「それじゃあ、俺たちが助けないでも、お前ひとりで倒せたのか」
「そうとも、そうだとも!」
「本当にか」
「本当だとも! 疑うのか!」
「ここにゃ俺たちしかいないんだ。誰にも言わねえよ」
「……ま、まあちょっぴり、ほんのちょっぴり危なかったかもしれんな」
「そしたら、大嘴鶏たちは危なかったな」
「う……うむ。そうだ。危なかったかもしれん」
「もしお前が万が一足を滑らせでもしたら、万が一だぞ、それじゃあ大嘴鶏たちは酷い目に遭っていたな」
「ひどい目に遭っていたのか?」
「間違いないな」
「で、でもなんとかなったのじゃ」
「もしかしたら俺達は来なかったかもしれないな」
「む、むう」
「お前は一人でよくやったよ。でも一人じゃ大変なことだっていっぱいある。一人じゃ護り切れない時もある。そういうときは、助けを求めていいんだ」
「し、しかしな、しかしわしは……」
「お前は自分一人でやれると思ってるだろうし、それは大事な気構えだけど、それで護るべきものが傷ついたんじゃあ仕方がないだろ」
「む、むう」
「護りたいと思ったんなら、そのことをまず大事にしなきゃな。自分のことはおいておいて、誰かのことを考えられる方が、ずっと格好いいと思わないか」
「お、思う、かもしれん」
「そうか」
「そ、そうだ」
「それがわかったならお前さんは立派な勇者だよ」
「そ、そうか?」
「そうだとも」
そうか、とはにかむように笑うスピザエトの頬を、紙月はつねった。
「あだだだだだ激痛でない程度の適度な痛み!」
「それじゃあできる天狗様はまず助けてもらった感謝! それに悪態ついた謝罪な!」
「ありがとうございます! ごめんなさい!」
「よし」
「紙月、ほんと多芸だよね」
「これくらい子守のバイトしたらすぐ慣れる」
「ほんと多芸だよね、ほんと」
腕の中ですっかり大人しくなったスピザエトは、緊張が解けたためか、ぐったりと脱力し、それを未来が支えてやっている状態だった。
「しっかし、こんな子供相手におっさんたちはなんでピリピリしてんだろうな」
これが紙月には疑問であった。
単に子供嫌いであるというのは、これはない。
実際、未来が鎧を脱いだ姿を見せた時も、成人前だというのに立派だなと大いに褒められ、成人前の子供を冒険屋稼業に連れまわすなどと紙月は怒られたぐらいだった。帝国では一般的に成人と言えば十四歳であるらしく、なるほど未来はまだ二、三年程足りない。
この例で行くと、その未来よりいくらか幼いスピザエトの奮闘は、褒め称えられてしかるべきであって、間違ってもその逆はないはずだった。それなのに実際は、スピザエトは敬遠され、すっかり紙月に面倒を任されてしまっている。
首をかしげる二人に、スピザエトは眠たげながらも唇を尖らせた。
「それはきっと、わしが天狗だからなのじゃ……」
帰り着き、それが事実だと知って、紙月は激怒するのであった。
用語解説
・スピザエト(Spizaeto)
天狗の少年。非常に身なりが良く、良いところのお坊ちゃんであるようだ。
弓を持っていたが腕前は杜撰なもので、年若いこともあってまだ一人で飛ぶのは難しいようだ。