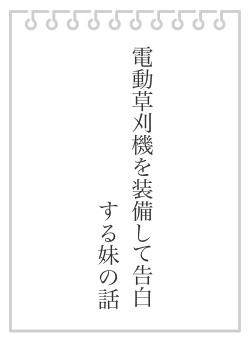「あなた、あなた。こんなところにいらしたのですね」
袖を引かれて振り返れば、その女性はあっと息を呑んだふうだった。三十代ほどで、古風なまとめ髪の瓜ざね顔が私をまじまじと見つめる。
そうして、まあ、いやだわ、ちっとも似ていないと呟いた。責めるような、咎めるようなその口調。
半ば反射的にすみませんと返せば、彼女は大事なものを落とした子どものような、あるいは遠いところへお遣いに出されたけれど少しのお金が足りなかったかのような、ますます悲しげな面持ちとなった。
そうなると私もさらにすまない心地になり、かといって何も悪くないので重ねて謝るのも妙で、それこそ子どもに語りかけるように柔らかく尋ねた。
「誰か、お捜しですか?」
「ええ、いいえ、違っていました」
私の問い掛けに、彼女は妙にきっぱりとした口振りで、けれど、どちらかわかりかねる奇妙な受け答えをした。こちらの腑に落ちない心中を読み取ったらしく、正当な主張といわんばかりに続ける。
「捜していたわけじゃありません。ただ、偶然、似ていた背を見掛けたから、つい。いえ、でも全然似ていません、どうして間違えたのかしら」
「それは……大変失礼しました」
ソフト帽を取り、私は慇懃に頭を下げた。そうするのがごく自然というか、一番収まり良い気がしたからである。
女性は小首を傾げてわずかに微笑み、いいえ、お気になさらないで、と言ってすたすた歩き出す。
その背に木漏れ日を浴び、ちらちら、ちらちら、小さな火が燃えるようにも、白い狐が跳ね遊んでいるようにも見えた。
土曜の昼下がり。私は昨日の残務を片付けに出勤して、遅い昼食を摂り、自宅へ帰る途中だった。
気持ちの良い秋の午後で、多少遠回りになるが、玉川上水に沿って整備された緑道を歩いていた。まだ秋は足踏みして、木々の葉には緑と黄色が入り混じっている。空気は清澄で葉擦れの音は心を安らがせた。
今年の春に東北から異動したばかりで、三鷹の借家に待つ人がいるわけでもなし。私は女性の背を眺めながら、ことさらゆっくり歩を進めた。
もちろん、これがストーキングと呼ばれる行為だとは承知している。四十暮れの公的機関の勤め人がするにはハイリスクだとも。だから通報されぬよう十分に間隔を空けて。
女性は川流れと同じ方向へ歩きながらも、すれ違う人、対岸を往く人が現れると身を固め、そのくせ喰い入るように見つめる。けれどしばらくして詰めた息を吐いて、とぼとぼ歩き出す。そして小橋に差し掛かると、真ん中まで進み、欄干から川面を見下ろし、肩を落とすのだった。
玉川上水は全長四三キロメートル、現在でいうところの多摩地域羽村市から新宿区四谷までの上水であり、完成は一六五三年。爆発的に人口が増えた江戸市中へ飲料水を引くために築かれ、また武蔵野台地の農業用水としても活用されてきた。
上水の開通まで一年足らず、随分な突貫工事だが、同時に困難を極めた事業でもあったという。
さきの羽村から四谷までの標高差はわずか百メートル、また水を吸い込む関東ローム層であることが災いし、当初計画していた導水の経路を変更せざるを得なかった。その責任を問われて処刑された役人は数多、彼らの嘆きから、現場の坂は「かなしい坂」と名付けられたという。
多くの人々の生活を支えた一方、無慈悲に命を奪った水脈。
とあるひとつの橋の真ん中で、彼女はことさら長い時間佇んでいた。上水の露となった人を悼んでいる、あるいは殺した川を憎んでいる、なんて、まさか。
ふと、私は玉川上水の別名を思い出した――人喰い川。それほどにかつては流れが性急だった。
今は緩やかで清らかなプロムナードという顔しか見せないけれど、彼女が覗き込む、その奥の奥の、そのまた奥の暗渠には。
あの、と私は橋の袂から声をかけた。『むらさき橋』と書かれた親柱の手前で。
「随分長いことそうしていますね。まだ、帰らないのですか?」
彼女は振り返り、私を一瞥した。が、黙したまま、また川面に視線を落とす。私はめげずにもう一度声を掛けた。
「秋の日はつるべ落とし。じきに暗くなってしまいますよ」
お節介は承知の上で、放っておけなかった。
実際、夕暮れにはまだ早い時間だったが、雑木林の間から見上げる陽はいくらか傾いており、甘やかな柿色を帯びていた。
彼女自身、もう帰らねばと葛藤していたのかもしれない。理知的な瞳が私を射る。そして呟いた。
――帰って、また待つの?
彼女は嘆息一つ落とし、再び歩き出した。私は先ほどより少し距離を縮め、後ろを着いて行く。
瀟洒な門構えの記念館らしき前を横切り、萬助橋と名付けられた橋を渡り、今度は玉川上水を外れて進んでいく。
その先は散歩道よりなお豊かな緑、多量の湧水――井の頭恩賜公園だった。
イヌシデ、コナラ、クヌを中心とした雑木林、サギ、カイツブリ、カワセミ、カルガモ、その他越冬にやってきた鳥たち、そして四季折々の多様な草花。
その敷地は武蔵野市の南東から三鷹市の北東に渡り、ともかく広大だ。私は家来衆のごとく彼女に付き従い、彼女もまた勝手気ままな姫君のごとく、思うままに歩き続けた。途中、ペットボトルの果実水を買って渡せば、歩きながらごくごくと飲み干す。
そして彼女は、唐突に足を止めた。
広い広い池の畔、最早、陽が黒々とした針葉樹に突き刺さり沈みゆくその時だった。
ぶすぶすと刺された太陽が金色の血を滴らせて世界を染め上げ、黒影の水鳥たちが、蒔絵のごとき波紋を描く――そんな情景。
どうして、と彼女は涙ぐんでひとりごちる。
「どうして、こんなにきれいなのかしら。どうして、こんなにかなしいのかしら」
私はそのひとりごとを掬い上げる。
「きっと、待っている人がいるからですよ」
東京八景に数えられた、でもそれとは少し違う夕陽だから。彼女はようよう私と目を合わせ、そうかしら、と自信なさげに零した。
「ちょっと、いきちがってしまっただけです。ご主人はもう帰っていて、あなたの帰りを待ちくたびれているかもしれない」
叱られて帰るのを躊躇っている子どもみたく俯く彼女に、帰りましょう、送っていきますと手を差し出した。
帰り道ではとっぷり夜更けていて、街燈が煌々と輝いて眩しかった。
「やあ、先生。今お帰りで?」
三鷹へと折れる最初の道で声を掛けられた。行きつけの弁当屋の店主で、私は繋いだ手とは反対の手で帽子を取り挨拶をする。
暗くなるのが早くなってきた、お二人とも気を付けてという言葉に私は礼を告げた。
道々、彼女はやはり塞いだふうで、私はこんな話を始めた。
「遠野物語をご存じですか?」
「……東北、特に岩手の民話とか伝承を集めたものでしょう」
「ええ。その中の一つに、大海嘯《おおつなみ》で妻と子を失った男の話があるのですが」
何が言いたいのという無言の問い掛けから、私は先を続けた。
「霧の立ち込める夏の夜、妻子を失った男は、男女が波打ちを歩いているのを見掛けます。近寄れば、女はまさしく亡くなった妻で、名を呼ぶと振り返って笑い掛けてきました。隣の男はやはり海嘯《つなみ》で死んだ者で、妻とは昔深い仲であり、死んでしまった後夫婦となったと言うのです。二人は足早に立ち去り、男は立ちすくみ、いつの間にか夜が明けていた」
――そんな話です、そう締めれば彼女はひどい話と顔をしかめた。そしてよりにもよって、どうして自分にするのだと愁眉にて非難する。
「あんまり、やりきれないじゃない」
「でも、もしかしたら、男もまた誰かに待たれているのかもしれません。気付いていない、あるいは忘れているだけで」
しばし彼女は私を見上げ、言った。あなた慰め方が下手だわ、と。
彼女を家まで送り届け、私たちは玄関の前で別れた。家の中には明かりが点いておらず、誰かが待っている気配はない。
やっぱり、あの時、迎えに行かなかったことを怒っているのかもしれないという彼女に、もう少しだけ待ってごらんなさいと諭し、小さな背を押した。
そうして、明かりが点され、私は安堵の息を漏らし、自分も帰るべく、元来た道を辿る。
小半時ほど経った頃、私は彼女の背を押した先の、三鷹の借家の引き戸を開けた。
「ただいま」
居間に入れば、彼女――妻は、ちゃぶ台に突っ伏して寝入っていた。さすがに歩き疲れたのだろう。私の足も棒になっている。
このまま寝かせてやりたい気もしたが、軽く肩を叩いて呼び掛ける。
「……お帰りなさい、あなた」
顔を上げて、微笑んで、辺りを見回して……ええ、もう夜、ご飯炊いていないわ、買い物も、何もしていない!
と、ひとしきり叫んだ妻に、私は弁当屋のロゴが入ったビニル袋を掲げた。鼻をひくつかせた彼女にはわかったろう。甘辛たれの天丼は妻の好物だった。
妊娠して、ひどいつわりが収まり、安定期に入った頃から、妻は奇妙な言動をするようになった。春から暮らすこの町は文豪ゆかりの地であるが、なぜだか、自分を、かの作家の妻と思い込む。妻以外の女性と心中した、あの。
生まれ変わりや、口寄せのようなものなのか。いや、後年、その人が発表していた回想記とは印象を異にするが妻なりの解釈なのか。ともかく妊娠という過敏な時に、何らか感応してしまうことはあるのかもしれない。
地元に残る家族に相談すべきか、医者に診せるべきなのか、私は決めかねていた。今は大事に至っていない。が、いずれ。
正直に言えば、怖かったのだ。私は教鞭を執っているが、図抜けた高級取りではなく、見合いで紹介された一回り歳下の妻と結婚できたのには様々な事情が絡んでいる。もしも、心因性の病などと診断されて引き離されたなら。
こちらの不安をよそに、私が譲った海老天の二本目を平らげ、五分で用意した即席漬けをぱりぱりと実に良い音を立てて咀嚼しながら、夢をみていたの、と妻は言う。どんなですかと問えば、破顔して答えた。
「あなたを捜しに行く夢を」
今日も、明日も、十年、二十年、そのずっと先も。妻が探し出してくれるのを、いつまでも。
袖を引かれて振り返れば、その女性はあっと息を呑んだふうだった。三十代ほどで、古風なまとめ髪の瓜ざね顔が私をまじまじと見つめる。
そうして、まあ、いやだわ、ちっとも似ていないと呟いた。責めるような、咎めるようなその口調。
半ば反射的にすみませんと返せば、彼女は大事なものを落とした子どものような、あるいは遠いところへお遣いに出されたけれど少しのお金が足りなかったかのような、ますます悲しげな面持ちとなった。
そうなると私もさらにすまない心地になり、かといって何も悪くないので重ねて謝るのも妙で、それこそ子どもに語りかけるように柔らかく尋ねた。
「誰か、お捜しですか?」
「ええ、いいえ、違っていました」
私の問い掛けに、彼女は妙にきっぱりとした口振りで、けれど、どちらかわかりかねる奇妙な受け答えをした。こちらの腑に落ちない心中を読み取ったらしく、正当な主張といわんばかりに続ける。
「捜していたわけじゃありません。ただ、偶然、似ていた背を見掛けたから、つい。いえ、でも全然似ていません、どうして間違えたのかしら」
「それは……大変失礼しました」
ソフト帽を取り、私は慇懃に頭を下げた。そうするのがごく自然というか、一番収まり良い気がしたからである。
女性は小首を傾げてわずかに微笑み、いいえ、お気になさらないで、と言ってすたすた歩き出す。
その背に木漏れ日を浴び、ちらちら、ちらちら、小さな火が燃えるようにも、白い狐が跳ね遊んでいるようにも見えた。
土曜の昼下がり。私は昨日の残務を片付けに出勤して、遅い昼食を摂り、自宅へ帰る途中だった。
気持ちの良い秋の午後で、多少遠回りになるが、玉川上水に沿って整備された緑道を歩いていた。まだ秋は足踏みして、木々の葉には緑と黄色が入り混じっている。空気は清澄で葉擦れの音は心を安らがせた。
今年の春に東北から異動したばかりで、三鷹の借家に待つ人がいるわけでもなし。私は女性の背を眺めながら、ことさらゆっくり歩を進めた。
もちろん、これがストーキングと呼ばれる行為だとは承知している。四十暮れの公的機関の勤め人がするにはハイリスクだとも。だから通報されぬよう十分に間隔を空けて。
女性は川流れと同じ方向へ歩きながらも、すれ違う人、対岸を往く人が現れると身を固め、そのくせ喰い入るように見つめる。けれどしばらくして詰めた息を吐いて、とぼとぼ歩き出す。そして小橋に差し掛かると、真ん中まで進み、欄干から川面を見下ろし、肩を落とすのだった。
玉川上水は全長四三キロメートル、現在でいうところの多摩地域羽村市から新宿区四谷までの上水であり、完成は一六五三年。爆発的に人口が増えた江戸市中へ飲料水を引くために築かれ、また武蔵野台地の農業用水としても活用されてきた。
上水の開通まで一年足らず、随分な突貫工事だが、同時に困難を極めた事業でもあったという。
さきの羽村から四谷までの標高差はわずか百メートル、また水を吸い込む関東ローム層であることが災いし、当初計画していた導水の経路を変更せざるを得なかった。その責任を問われて処刑された役人は数多、彼らの嘆きから、現場の坂は「かなしい坂」と名付けられたという。
多くの人々の生活を支えた一方、無慈悲に命を奪った水脈。
とあるひとつの橋の真ん中で、彼女はことさら長い時間佇んでいた。上水の露となった人を悼んでいる、あるいは殺した川を憎んでいる、なんて、まさか。
ふと、私は玉川上水の別名を思い出した――人喰い川。それほどにかつては流れが性急だった。
今は緩やかで清らかなプロムナードという顔しか見せないけれど、彼女が覗き込む、その奥の奥の、そのまた奥の暗渠には。
あの、と私は橋の袂から声をかけた。『むらさき橋』と書かれた親柱の手前で。
「随分長いことそうしていますね。まだ、帰らないのですか?」
彼女は振り返り、私を一瞥した。が、黙したまま、また川面に視線を落とす。私はめげずにもう一度声を掛けた。
「秋の日はつるべ落とし。じきに暗くなってしまいますよ」
お節介は承知の上で、放っておけなかった。
実際、夕暮れにはまだ早い時間だったが、雑木林の間から見上げる陽はいくらか傾いており、甘やかな柿色を帯びていた。
彼女自身、もう帰らねばと葛藤していたのかもしれない。理知的な瞳が私を射る。そして呟いた。
――帰って、また待つの?
彼女は嘆息一つ落とし、再び歩き出した。私は先ほどより少し距離を縮め、後ろを着いて行く。
瀟洒な門構えの記念館らしき前を横切り、萬助橋と名付けられた橋を渡り、今度は玉川上水を外れて進んでいく。
その先は散歩道よりなお豊かな緑、多量の湧水――井の頭恩賜公園だった。
イヌシデ、コナラ、クヌを中心とした雑木林、サギ、カイツブリ、カワセミ、カルガモ、その他越冬にやってきた鳥たち、そして四季折々の多様な草花。
その敷地は武蔵野市の南東から三鷹市の北東に渡り、ともかく広大だ。私は家来衆のごとく彼女に付き従い、彼女もまた勝手気ままな姫君のごとく、思うままに歩き続けた。途中、ペットボトルの果実水を買って渡せば、歩きながらごくごくと飲み干す。
そして彼女は、唐突に足を止めた。
広い広い池の畔、最早、陽が黒々とした針葉樹に突き刺さり沈みゆくその時だった。
ぶすぶすと刺された太陽が金色の血を滴らせて世界を染め上げ、黒影の水鳥たちが、蒔絵のごとき波紋を描く――そんな情景。
どうして、と彼女は涙ぐんでひとりごちる。
「どうして、こんなにきれいなのかしら。どうして、こんなにかなしいのかしら」
私はそのひとりごとを掬い上げる。
「きっと、待っている人がいるからですよ」
東京八景に数えられた、でもそれとは少し違う夕陽だから。彼女はようよう私と目を合わせ、そうかしら、と自信なさげに零した。
「ちょっと、いきちがってしまっただけです。ご主人はもう帰っていて、あなたの帰りを待ちくたびれているかもしれない」
叱られて帰るのを躊躇っている子どもみたく俯く彼女に、帰りましょう、送っていきますと手を差し出した。
帰り道ではとっぷり夜更けていて、街燈が煌々と輝いて眩しかった。
「やあ、先生。今お帰りで?」
三鷹へと折れる最初の道で声を掛けられた。行きつけの弁当屋の店主で、私は繋いだ手とは反対の手で帽子を取り挨拶をする。
暗くなるのが早くなってきた、お二人とも気を付けてという言葉に私は礼を告げた。
道々、彼女はやはり塞いだふうで、私はこんな話を始めた。
「遠野物語をご存じですか?」
「……東北、特に岩手の民話とか伝承を集めたものでしょう」
「ええ。その中の一つに、大海嘯《おおつなみ》で妻と子を失った男の話があるのですが」
何が言いたいのという無言の問い掛けから、私は先を続けた。
「霧の立ち込める夏の夜、妻子を失った男は、男女が波打ちを歩いているのを見掛けます。近寄れば、女はまさしく亡くなった妻で、名を呼ぶと振り返って笑い掛けてきました。隣の男はやはり海嘯《つなみ》で死んだ者で、妻とは昔深い仲であり、死んでしまった後夫婦となったと言うのです。二人は足早に立ち去り、男は立ちすくみ、いつの間にか夜が明けていた」
――そんな話です、そう締めれば彼女はひどい話と顔をしかめた。そしてよりにもよって、どうして自分にするのだと愁眉にて非難する。
「あんまり、やりきれないじゃない」
「でも、もしかしたら、男もまた誰かに待たれているのかもしれません。気付いていない、あるいは忘れているだけで」
しばし彼女は私を見上げ、言った。あなた慰め方が下手だわ、と。
彼女を家まで送り届け、私たちは玄関の前で別れた。家の中には明かりが点いておらず、誰かが待っている気配はない。
やっぱり、あの時、迎えに行かなかったことを怒っているのかもしれないという彼女に、もう少しだけ待ってごらんなさいと諭し、小さな背を押した。
そうして、明かりが点され、私は安堵の息を漏らし、自分も帰るべく、元来た道を辿る。
小半時ほど経った頃、私は彼女の背を押した先の、三鷹の借家の引き戸を開けた。
「ただいま」
居間に入れば、彼女――妻は、ちゃぶ台に突っ伏して寝入っていた。さすがに歩き疲れたのだろう。私の足も棒になっている。
このまま寝かせてやりたい気もしたが、軽く肩を叩いて呼び掛ける。
「……お帰りなさい、あなた」
顔を上げて、微笑んで、辺りを見回して……ええ、もう夜、ご飯炊いていないわ、買い物も、何もしていない!
と、ひとしきり叫んだ妻に、私は弁当屋のロゴが入ったビニル袋を掲げた。鼻をひくつかせた彼女にはわかったろう。甘辛たれの天丼は妻の好物だった。
妊娠して、ひどいつわりが収まり、安定期に入った頃から、妻は奇妙な言動をするようになった。春から暮らすこの町は文豪ゆかりの地であるが、なぜだか、自分を、かの作家の妻と思い込む。妻以外の女性と心中した、あの。
生まれ変わりや、口寄せのようなものなのか。いや、後年、その人が発表していた回想記とは印象を異にするが妻なりの解釈なのか。ともかく妊娠という過敏な時に、何らか感応してしまうことはあるのかもしれない。
地元に残る家族に相談すべきか、医者に診せるべきなのか、私は決めかねていた。今は大事に至っていない。が、いずれ。
正直に言えば、怖かったのだ。私は教鞭を執っているが、図抜けた高級取りではなく、見合いで紹介された一回り歳下の妻と結婚できたのには様々な事情が絡んでいる。もしも、心因性の病などと診断されて引き離されたなら。
こちらの不安をよそに、私が譲った海老天の二本目を平らげ、五分で用意した即席漬けをぱりぱりと実に良い音を立てて咀嚼しながら、夢をみていたの、と妻は言う。どんなですかと問えば、破顔して答えた。
「あなたを捜しに行く夢を」
今日も、明日も、十年、二十年、そのずっと先も。妻が探し出してくれるのを、いつまでも。