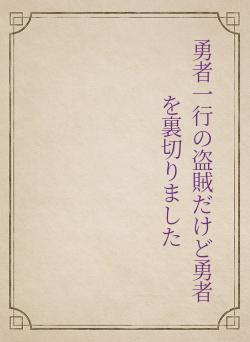_石でもわかる踊りの踊り方_
私は手に取った本を、その辺に投げ捨てた。
店の店主が大慌てで本を取りに行くが、私は知らんぷりをする。
あんな本捨てればいいのに。
どう見ても嘘じゃない。
石のどこに踊れる足があるのよ。
細長い柔らかな手首に妖艶に魅せられる顔つき。
私が思う踊り子とは全く異なるものだった。
そんなに簡単き踊れるなら、もうとっくに私は国のトップになってるわ。
私は、本屋から出て国立公園に向かった。
恐らく、太陽がてっぺんに登る頃だから一通りも多くなっているだろう。
私がいる砂漠の街は、国立公園を中心に据えて東西南北に広がっている。
なんでもはるか昔、この場所に自然があった頃の王妃様が、たいそう自然を愛したらしい。
そのため、国王は王妃のための公園を行ったそうだ。
今でも飽きずに語られている昔話である。
聞く限り本当の話のように思えるが、本当かどうか本人しか知らない。
太陽が照りつける中、公園を目指して歩くと昼休憩であろう大人たちとすれ違う。
私は邪魔にならないように端っこに寄り、大人たちの波をやり過ごした。
最初のうちはあっさり人の波に流されてしまうが、慣れればどうということは無い。
むしろ、これだけ人がいることに感謝したくなる。
人取りが多すぎず少なすぎない国立公園の前に行くと、クシャクシャになった帽子を取り出した。
新しいものを買うべきか悩むほどの襤褸さだが、商売道具にお金を使いたいから節約しなければならない。
いつかのために貯めておかなければ。
「またせたね」
襤褸の下で煌びやかに輝き始めるのを待ってる商売道具達に語りかけた。
そして、帽子を五歩先の場所に置き後ろに下がる。
そして私は踊り出した。
私が踊り子に見せられたのは幼少の頃である。
確かその日はたまたま劇団が砂漠の街にやって来ていて、私は暇つぶしに来ていた。
有名な団体で、町中のあちこちから人が見学に来ていた。
私は来るのが遅かったようで、前の席は既に人が座っており、少しでも近くで見ようとする立ち見客が大勢いた。
最初は頑張って背伸びをしたり、隙間をかき分けて進んでいこうとしたが、押しつぶされて結局押し戻されてしまった。
なので、後ろの方の誰もいないような席に腰を下ろした。
元々視力は良くないので、はるか遠くにいる演者たちの姿なんて見えない。
それどころか、声も聞こえずらい。
もし隣に人がいて話しかけられれば、聞こえないぐらいだ。
もう諦めて家に帰ろうかと思ったが、家に帰っても特にすることは無い。
寝てばっかの生活には飽き飽きだ。
心躍るようなことをしてみたい。
そんな時、あの人が話しかけてきた。
その人は私の隣に席に腰を下ろした。
襤褸を纏い、フードを被った姿からは怪しさが溢れている。
私の危険センサーにしたがって、私ら気になるが特に気にしていない振りをすることにした。
たまに首を伸ばして一生懸命見てみたり、拍手をしてみたり……とりあえず、できることはしたと思う。
「凄かったな。"愛を一身に受けてほしい”なんてダサいわ。」
その人は私の隣でそんなことを言い出した。
「きこえてたの?わたしにはなにもきこえなかったけど」
気づけば、幼かった私は知らない人には話しかけないという約束をそっちのけにして、話しかけていた。
その人は首を縦に振る。そして、
「俺の仕事は音をしっかり聞かないと出来ないからな。あとリズム感も大切だし」
と言う。
もしかして演奏家なのだろうかと思い尋ねるも、首を横に振られた。
その時、その人が汗が酷かったのか腕で顔を拭うような仕草をした。
チラリとか細い腕とよく分からないデザインの袖が見えた。
こんなに暑い砂漠なのに、長袖を着れている我慢力がすごい。
私はその人の袖をさして、「あつくないの?」と尋ねた。
そうすると、その人は「もちろん暑い」と言って、また汗を拭った。
「でも、すぐ仕事なんだ。ここを出発しなければならない。」
「……しごと?」
その人は首を縦に降って、何を思ったのか急に立ち上がって私の腕を引いた。
急なことに抵抗できず一緒に立ち上がると、その人は襤褸を脱ぎ捨ててすぐに煌びやかな白い衣装が現れた。
細かなデザインまで一つ一つ丁寧に仕上げられているのが分かる。
その人は顕になった純白の衣装と短髪を利用して、次々に人の視線を集めていく。
そして、手先から足まで全身を使った踊りを披露した。
激を見ていた観客たちは全員その人の虜になる。
私もそのうちの一人だ。
まさに水のような人だった。
性格も踊りも。
彼が手を下ろすと、その場にいた観客たちは拍手をした。
年寄から子供や劇団員まで。
皆が皆拍手をしたのだ。
その場の雰囲気に乗って、劇はさらに大盛り上がりをみせ、私のような子供を前の席に案内するというサービスまでしてくれた。
軽い暇つぶしのつもりだったのに、私は夜遅くまでその場にいた。
劇の荷物を載せた馬車が、次々と横を通り過ぎていった。
重々しい音を立てながら。
この道は馬車が通るように設計されてないので、御者からすれば地獄だろう。
車が御者、どちらが先にギブアップするだろうか。
ただ目的もなく歩いていると、私の隣で一台の馬車が止まった。
事故だろうかと頭をかしげると、中からあの人が顔を出した。
そして、私に向けて手をこまねいた。
言う通りに、近づいていくと頭に何がが乗せられた。
頭に手をやると、どうやらサークレットのようだった。
「似合ってる」
そう言って、彼はすぐに馬車を動かしてしまった。
私はお礼言ったが、聞こえていたのか分からない。
それから、私は暇を見つけては踊っているのだ。