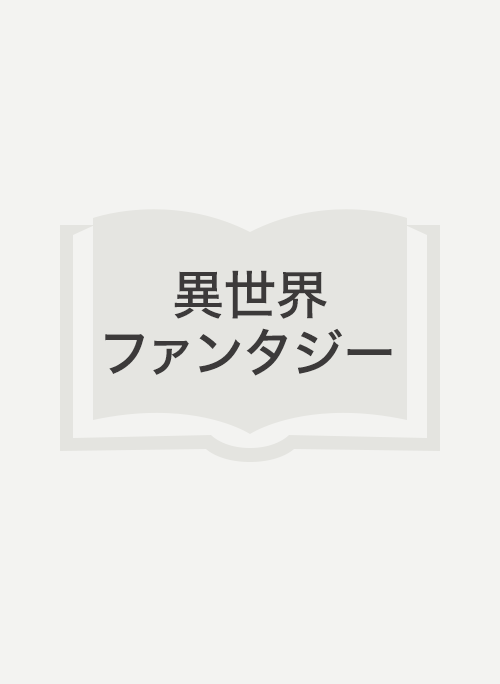前回のあらすじ
あまりにも唐突に吹雪の森に迷い込んだトルンペート。
作者は疲れているのだろうか。
森は驚くほど平穏だった。
靄は相変わらず濃く、先は見通せず、後ろも見通せず、右も左もわからなきゃ、時折上下の区別もつきがたい。
まっすぐ歩いているつもりでも、木々に邪魔され足場に狂い、いまやどこをどう歩いているかなんてとっくの昔に分からなくなっていた。
歩いてきた歩数と角度のいちいちを覚えている私にとってみれば、それをさかのぼれば元の道に戻れるという理屈はある。あるけれど、今日ばかりは確信が持てなかった。何しろこんな靄の中で、自分の記憶力を試したことはない。
変りばえのしない景色。
変りばえのしない歩み。
こうも変わりばえがないと、不安以上に頭がしびれてくるような退屈さえあった。
もうどれだけ歩いたことか、それさえも判然としないけれど、いまだにパフィストの姿は見つからず、リリオとトルンペートの気配も見当たらない。
何度か私らしくもなく大きく声を張って二人を呼んでみたが、帰ってくるのはむなしいやまびこめいた残響ばかりだ。
私が大声を出すなんてかなりレアなイベントだというのに、全く。
ひたすらに単調な景色と単調な歩みは、どんどんと思考を鈍麻させ、半分眠っているような心地で、何度か足を止めて本当に眠りこけそうになるほどだった。
そんな場合ではないとその都度頬を張って歩き続けたけれど、正直なところこうして歩き続けている行為にそれほど意味があるのか、実際疑問だ。
もしかしたら自分は二人からひたすらに離れる方向へと、森の奥へ奥へと一人歩き続けているのではないか。そんな不安がないではなかった。パフィストにはめられて同じところをぐるぐると回っているだけなのではないか。そんな迷いがないではなかった。
しかし靄の中をぼんやりとする頭で歩いていると、不安も迷いもどんどん靄の中に零れていって、ただひたすらに眠い、退屈だという実際的な思考ばかりが巡るようだった。
こうしてひたすらに歩いているというのは、意味もなく地面を掘り返しては、また埋め戻すという拷問だか懲罰のようだなと感じられた。ドストエフスキーだったか。もっとも私はロシア文学があまり肌に合わず、この懲罰が示唆された本も読んだことはない。
私にとり、映画『惑星ソラリス』を半分眠りかけながら見て以来、ロシア関係の創作物はある種の拷問のようなイメージを伴って忌避してきているのだ。例外はフィギュアスケートくらいだが、それ自体もさほど興味はない。思えば『ソラリス』もこの靄のごとく理解不能な退屈に満ちていたように思う。
もちろんこれは私の勝手な、それもたった一つの創作物の影響によるイメージに過ぎないのだが、あえてそれを乗り越えて『地下室の手記』に手を出すほどの意欲は終電と仲の良い人間には存在しないし、あまつさえ『苦痛を愛せよ』などとどうして言えようか。
しかしそれにしても私はなぜ『ソラリス』を途中で切り上げなかったのだろうか。冒頭ですでに眠気が走るような映画を私が愛していたようには思えないが、いや、そもそも観劇趣味も映画趣味もあまつさえSF趣味もなかった私がどうして、この『芸術作品』に三時間近くを捧げようと思ったのだったか。
疑問に思うまでもなく、私の脳は紐づけられた記憶を、思い出という地層の中からすぐさま掘り当てていた。
あれは私が中学校に上がったばかりの春のことだった。
いくらか小賢しい知性を獲得していたように思われる私は、なにということはない有り触れた日曜日に、珍しく父に誘われて、時折異音のする古いビデオ・デッキに、パッケージも日焼けした古びたレンタルのビデオ・テープを差し込んだのだった。
そんなものを体感したことはないとはいえ、人生において貴重とされる短い青春のおよそ三時間近くを拘束するこの映画に感じたのはひたすらに退屈と無理解であり、小賢しい中学生にとってはいささか難解にすぎる代物だった。正直なところこの年になって思い返してみてもいまいち感性にピンとこない。
父も私の退屈を察してはくれたようで、途中何度も観るのを止めても良いと言ってはくれたが、子供じみた意地と、そして父がこの映画から何を汲み取らんとしているのかを理解したいというささやかな願望から結局夢現に三時間近くを費やし、そして収穫はゼロだった。むしろNullだった。
きっかり秤で量ったような、実際計量器とタイマーを駆使した、私でさえ毎回ほとんど同じ味がすると太鼓判を押せる紅茶を淹れながら、父はこのように説明してくれた。
「原作家と監督が喧嘩別れしたと聞きまして、どれくらい内容に差異があるのか確認してみようと思いまして」
原作を読んでいなかった私は素直にどうだったのか尋ねた。今後も原作を読む気はないし、ネタバレを気にする道理もなかった。
父は分度器で測ったように正確な角度で小首を傾げ、それからこう言った。
「有意な差異は見受けられませんでした」
と。
父は私以上に不器用で、私以上に人間が苦手で、私以上に社会に馴染めない人だった。
私は人間が嫌いだが、父は人間が理解できなかった。
私は人を愛することが苦手だったが、父は人を愛するようにはできていなかった。
そのような機能をどこか破損して生まれてきたように思えた。
父がどれくらい不器用かと言えば、男手一人で育て上げてくれた私という存在がこんなろくでなしになり果ててしまったということがこれ以上ない証明だとは思うけれど、しかし反面教師としてよい教材になってくれたのは確かだ。
例えば、あれは私が小学校三年生の頃だ。
小学生とはいえ何しろ完全記憶能力者の上に小賢しいガキだった私は、あれやこれやと興味を持っては、父にあれはなにこれはなに、あれはどうしてこれはどうしてと質問攻めにしていたように思う。
そういった質問攻めに対しても、父は不器用だった。
「おとうさん、どうしてそらはあおいの?」
「光には波長の違いというものがありましてね」
「おとうさん、こどもはどうやってできるの?」
「人間を含む哺乳類は基本的に」
「おとうさん、どうしてうちにはおかあさんがいないの」
「閠さんを出産した後、体力が回復せず衰弱死してしまいました」
子供に対してレイリー散乱やら交尾行動を図説付きで説明するのはともかく、「お母さんはお前を生んだから死んだんだよ」みたいな説明をする親がどこにいるというのか。
しかもフォローも最悪だった。
「おかあさんは、わたしのせいでしんじゃったの?」
「出産を選んだのは暦さんですし、危険だとわかっていて止めなかったのは僕ですから、みんなのせいですね」
というかフォローになってない。
言い方を選べ。
しかも真顔。
思えば、というか強いて思い返そうとしなくても、父が表情を変える所を私はろくに見たことがなかった。表情筋が死滅しているんではないかというくらい無表情だった。
閠さんの情操教育に悪いかもしれませんので、とよりにもよって本人の前で説明しながら、当人曰く笑顔の練習とやらをしたときがその数少ない表情を変えた光景であったが、直後に私が泣き出したので結局有耶無耶になってしまった。
いや、悪いとは思うがあれは泣く。
不気味の谷現象というか、頭部を寄生獣に取って代わられた人がテレビ映像を参考に笑顔作ってるみたいというか、感情の伴わない完璧な笑顔というものに、子供心にひたすらに不気味な矛盾を感じたのだろう。
お陰様で私は周囲の人間の表情と感情の食い違いというものに早期の内から気付いてしまう羽目になり、大人を信用できない全く嫌なガキに育ったと思う。かといって子供が信用できるかと言えば、自分の感情さえろくすっぽ制御できない子供のほうが余程信用できないのは確かだったが。あいつら秒単位で態度変えるからな。
いやまったく、私の人生は不信と疑心とに彩られているような気さえする。
思い出を掘り起こしていけば、その記念すべき最初の一度は、それはすなわち私の記憶が始まるころだった。
つまり、私が生まれ、母が死んだ、その時のことだった。
用語解説
・父
閠の父親の事。
妛原 軅飛。享年五十二歳。
・母
閠の母親の事。
妛原 暦。旧姓悪澤。享年二十九歳。
あまりにも唐突に吹雪の森に迷い込んだトルンペート。
作者は疲れているのだろうか。
森は驚くほど平穏だった。
靄は相変わらず濃く、先は見通せず、後ろも見通せず、右も左もわからなきゃ、時折上下の区別もつきがたい。
まっすぐ歩いているつもりでも、木々に邪魔され足場に狂い、いまやどこをどう歩いているかなんてとっくの昔に分からなくなっていた。
歩いてきた歩数と角度のいちいちを覚えている私にとってみれば、それをさかのぼれば元の道に戻れるという理屈はある。あるけれど、今日ばかりは確信が持てなかった。何しろこんな靄の中で、自分の記憶力を試したことはない。
変りばえのしない景色。
変りばえのしない歩み。
こうも変わりばえがないと、不安以上に頭がしびれてくるような退屈さえあった。
もうどれだけ歩いたことか、それさえも判然としないけれど、いまだにパフィストの姿は見つからず、リリオとトルンペートの気配も見当たらない。
何度か私らしくもなく大きく声を張って二人を呼んでみたが、帰ってくるのはむなしいやまびこめいた残響ばかりだ。
私が大声を出すなんてかなりレアなイベントだというのに、全く。
ひたすらに単調な景色と単調な歩みは、どんどんと思考を鈍麻させ、半分眠っているような心地で、何度か足を止めて本当に眠りこけそうになるほどだった。
そんな場合ではないとその都度頬を張って歩き続けたけれど、正直なところこうして歩き続けている行為にそれほど意味があるのか、実際疑問だ。
もしかしたら自分は二人からひたすらに離れる方向へと、森の奥へ奥へと一人歩き続けているのではないか。そんな不安がないではなかった。パフィストにはめられて同じところをぐるぐると回っているだけなのではないか。そんな迷いがないではなかった。
しかし靄の中をぼんやりとする頭で歩いていると、不安も迷いもどんどん靄の中に零れていって、ただひたすらに眠い、退屈だという実際的な思考ばかりが巡るようだった。
こうしてひたすらに歩いているというのは、意味もなく地面を掘り返しては、また埋め戻すという拷問だか懲罰のようだなと感じられた。ドストエフスキーだったか。もっとも私はロシア文学があまり肌に合わず、この懲罰が示唆された本も読んだことはない。
私にとり、映画『惑星ソラリス』を半分眠りかけながら見て以来、ロシア関係の創作物はある種の拷問のようなイメージを伴って忌避してきているのだ。例外はフィギュアスケートくらいだが、それ自体もさほど興味はない。思えば『ソラリス』もこの靄のごとく理解不能な退屈に満ちていたように思う。
もちろんこれは私の勝手な、それもたった一つの創作物の影響によるイメージに過ぎないのだが、あえてそれを乗り越えて『地下室の手記』に手を出すほどの意欲は終電と仲の良い人間には存在しないし、あまつさえ『苦痛を愛せよ』などとどうして言えようか。
しかしそれにしても私はなぜ『ソラリス』を途中で切り上げなかったのだろうか。冒頭ですでに眠気が走るような映画を私が愛していたようには思えないが、いや、そもそも観劇趣味も映画趣味もあまつさえSF趣味もなかった私がどうして、この『芸術作品』に三時間近くを捧げようと思ったのだったか。
疑問に思うまでもなく、私の脳は紐づけられた記憶を、思い出という地層の中からすぐさま掘り当てていた。
あれは私が中学校に上がったばかりの春のことだった。
いくらか小賢しい知性を獲得していたように思われる私は、なにということはない有り触れた日曜日に、珍しく父に誘われて、時折異音のする古いビデオ・デッキに、パッケージも日焼けした古びたレンタルのビデオ・テープを差し込んだのだった。
そんなものを体感したことはないとはいえ、人生において貴重とされる短い青春のおよそ三時間近くを拘束するこの映画に感じたのはひたすらに退屈と無理解であり、小賢しい中学生にとってはいささか難解にすぎる代物だった。正直なところこの年になって思い返してみてもいまいち感性にピンとこない。
父も私の退屈を察してはくれたようで、途中何度も観るのを止めても良いと言ってはくれたが、子供じみた意地と、そして父がこの映画から何を汲み取らんとしているのかを理解したいというささやかな願望から結局夢現に三時間近くを費やし、そして収穫はゼロだった。むしろNullだった。
きっかり秤で量ったような、実際計量器とタイマーを駆使した、私でさえ毎回ほとんど同じ味がすると太鼓判を押せる紅茶を淹れながら、父はこのように説明してくれた。
「原作家と監督が喧嘩別れしたと聞きまして、どれくらい内容に差異があるのか確認してみようと思いまして」
原作を読んでいなかった私は素直にどうだったのか尋ねた。今後も原作を読む気はないし、ネタバレを気にする道理もなかった。
父は分度器で測ったように正確な角度で小首を傾げ、それからこう言った。
「有意な差異は見受けられませんでした」
と。
父は私以上に不器用で、私以上に人間が苦手で、私以上に社会に馴染めない人だった。
私は人間が嫌いだが、父は人間が理解できなかった。
私は人を愛することが苦手だったが、父は人を愛するようにはできていなかった。
そのような機能をどこか破損して生まれてきたように思えた。
父がどれくらい不器用かと言えば、男手一人で育て上げてくれた私という存在がこんなろくでなしになり果ててしまったということがこれ以上ない証明だとは思うけれど、しかし反面教師としてよい教材になってくれたのは確かだ。
例えば、あれは私が小学校三年生の頃だ。
小学生とはいえ何しろ完全記憶能力者の上に小賢しいガキだった私は、あれやこれやと興味を持っては、父にあれはなにこれはなに、あれはどうしてこれはどうしてと質問攻めにしていたように思う。
そういった質問攻めに対しても、父は不器用だった。
「おとうさん、どうしてそらはあおいの?」
「光には波長の違いというものがありましてね」
「おとうさん、こどもはどうやってできるの?」
「人間を含む哺乳類は基本的に」
「おとうさん、どうしてうちにはおかあさんがいないの」
「閠さんを出産した後、体力が回復せず衰弱死してしまいました」
子供に対してレイリー散乱やら交尾行動を図説付きで説明するのはともかく、「お母さんはお前を生んだから死んだんだよ」みたいな説明をする親がどこにいるというのか。
しかもフォローも最悪だった。
「おかあさんは、わたしのせいでしんじゃったの?」
「出産を選んだのは暦さんですし、危険だとわかっていて止めなかったのは僕ですから、みんなのせいですね」
というかフォローになってない。
言い方を選べ。
しかも真顔。
思えば、というか強いて思い返そうとしなくても、父が表情を変える所を私はろくに見たことがなかった。表情筋が死滅しているんではないかというくらい無表情だった。
閠さんの情操教育に悪いかもしれませんので、とよりにもよって本人の前で説明しながら、当人曰く笑顔の練習とやらをしたときがその数少ない表情を変えた光景であったが、直後に私が泣き出したので結局有耶無耶になってしまった。
いや、悪いとは思うがあれは泣く。
不気味の谷現象というか、頭部を寄生獣に取って代わられた人がテレビ映像を参考に笑顔作ってるみたいというか、感情の伴わない完璧な笑顔というものに、子供心にひたすらに不気味な矛盾を感じたのだろう。
お陰様で私は周囲の人間の表情と感情の食い違いというものに早期の内から気付いてしまう羽目になり、大人を信用できない全く嫌なガキに育ったと思う。かといって子供が信用できるかと言えば、自分の感情さえろくすっぽ制御できない子供のほうが余程信用できないのは確かだったが。あいつら秒単位で態度変えるからな。
いやまったく、私の人生は不信と疑心とに彩られているような気さえする。
思い出を掘り起こしていけば、その記念すべき最初の一度は、それはすなわち私の記憶が始まるころだった。
つまり、私が生まれ、母が死んだ、その時のことだった。
用語解説
・父
閠の父親の事。
妛原 軅飛。享年五十二歳。
・母
閠の母親の事。
妛原 暦。旧姓悪澤。享年二十九歳。