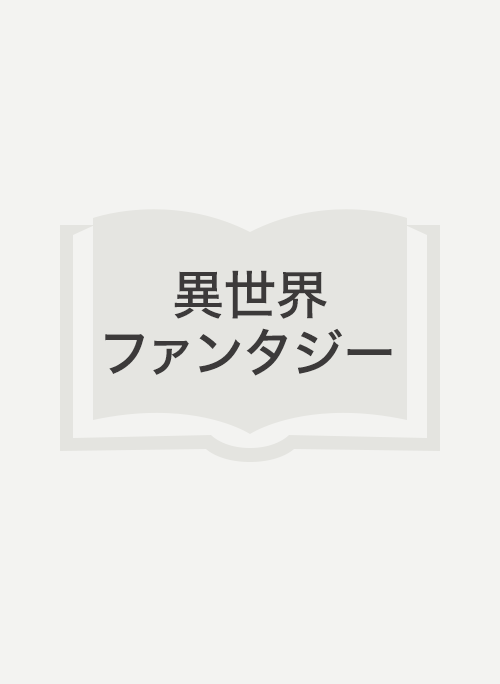前回のあらすじ
マジかよ。マジで飯だけで終わっちまった。しかも八千字近くもひたすら飯の話だよ。
どうなってるんだ。
鮫っていうのは初めて食べたけれど、なかなか悪い物じゃなかったね。
食べたことがない身としては、ちょっとゲテモノ枠というか、食材としてはなかなか見れない生き物だったけれど、調理して食べてしまえば、普通に美味しいものだった。
刺し身はちょっと微妙かなー、美味しいけどちょっと気になるかなーという感じだったけれど、煮込みは普通に白身魚として美味しい部類。
フカヒレとかキャビアとか、変な例としては肝油ドロップとか、鮫由来の食品は割と見かけたことあるけど、鮫の肉って出回らないよなあ。
普通にスーパーとか、回転寿司屋とかで見かけるものだったら、普通に食材として受け入れる感じだよね。
いや、出回ってるとこには出回ってるんだろうけど、私の住んでたとこ、別に沿岸地帯でもなし、そういうの見たことなかったな。
そもそもスーパーでお買い物、なんて随分してないけど。
鮫もとい温泉魚を美味しくいただいて、心配していた温泉魚絶滅も、軽くおやつ程度にいただいてたくらいだったらしいので杞憂に済んだし、私たちは焚火にあたりながらのんびりと茶などを頂いていた。
そう、茶だ。甘茶じゃない。南部産のお茶なのだ。
帝国各地で飲まれている甘茶は、ベリー系やハーブ系など、甘いお茶はなんでも甘茶と呼ぶので、地方によって全然違うというのは前にも言ったと思う。
南部にはいわゆる甘茶というのはない。
他の地域の甘茶がそれ自体甘いのに比べると、お茶に蜂蜜とか砂糖とかを自分で加えて甘さを調節するのが南部流だ。
西方から茶葉も輸入しているし、茶の木自体の栽培もしてるらしいから、実際、私の知るお茶と同じか、品種がちょっと違うくらいのものなのかもしれないというか、うん、普通に紅茶だな、これ。
私なんかは懐かしいような気もして少しホッとするけど、帝国では茶の木のお茶はそこまで人気じゃないらしい。栽培が難しいし、発酵も難しいし、渋みがあんまり好きじゃなかったり。
南部で栽培してるのは、お茶好きの貴族が頑張って挑戦し続けた成果みたいなもので、完全に趣味の産物らしい。
庶民なんかはむしろ、南大陸とかいうところから輸入したり、自前でもちょこちょこ栽培したりしているという、豆茶の方が好みなんだとか。
豆茶も大概苦いけど、伝わってきた時に砂糖と乳をたっぷり入れて飲む甘い飲み物として紹介されたみたいで、ブラックで飲むのは少数派だ。
こう、丼みたいなでかい器にたっぷりとカフェオレ注いで飲むんだよ、南部人のティータイム。
下手な甘茶よりよほど甘いよね、あれ。
メザーガなんかはいつもブラックで飲んでたっけ。胃が荒れそうな顔してるのに。
彼の場合はあんまり甘いものが好きじゃないのと、覚醒作用が目的みたいなところはあると思うけど。
マテンステロさんは甘ったるいカフェオレ大好きみたいだけど、今回の旅には豆茶は持ってきていない。
乳の類はあんまり日持ちしないから旅には持ってこれず、しかし乳がないのに豆茶なんか飲めるかという、そういう理由らしい。
このお茶は、まあ少しくらい渋みはあるけど、砂糖でどうにかなる程度だから、許容範囲らしい。
私にはよくわからない感覚だ。
お茶を済ませて、歯を磨いて、肌に保湿用の油を塗って、あとは寝るだけなんだけど、あくび交じりにもそもそ竜車に向かった私たちに、マテンステロさんが宣言した。
「今夜は組み分け変えましょ!」
眠そうで実際眠い我々三人と違って、マテンステロさんは実に元気だ。
この人が元気じゃないところ見たことないけど。
もっともらしく語るところによれば、竜車での旅は長く退屈で、閉塞感に満ち、倦み飽きてしまう。そんな状態は心身によろしくないことは明白である。だから、刺激が必要なのだと。
私としては変わったご飯食べられるし、温泉にも入れたし、十分刺激たっぷりな一日だったのだけれど、旅慣れたマテンステロさんにはそうではないのかもしれない。
面倒くさいから明日でいいんじゃないですかね、と消極的なムード漂う我々を気にした風もなく、マテンステロさんは楽しげに私たちを見回して、そして密かに身を潜めようとしたトルンペートの首根っこを問答無用で掴んだ。
あれ怖いんだよなあ。
目の前にいるのに挙動が読めないんだもん。
いつの間にか掴まれてるんだよ。
マテンステロさんに言わせれば、単なる手先の技らしいけど。
借りてきた猫よろしく大人しくなったトルンペートを引っ提げて、マテンステロさんは意気揚々と竜車に乗り込んでいった。
去り際に垣間見えたトルンペートの目は必死で助けを求めていたように見えなくもないけど、お腹いっぱいでお茶もいただいてお目目がしぱしぱするくらい眠いから、多分見間違いだろう。私は何も見てない。知らない。わからない。
リリオも悟りを開いたような目で見送っていることだし、我々は何も見なかった。うん。
私たちはどちらともなく頷きあって、もそもそと竜車に乗り込み、《鳰の沈み布団》に潜り込んだ。
いつもは三人で包まっている《布団》は、やはり二人だと、少し広く感じる。
もともと一人用の《布団》なんだから、これでも定員オーバーのはずなんだけど。
一日空いたせいか、ちょっと遠慮しがちに潜り込むリリオを、今日は私が抱きすくめて枕代わりにする。普段はリリオの方から抱き着いてきて、放っておいてもくっついているから、私の方から抱きしめると、どこら辺に手を当てたものか、どう抱えたものか、ちょっと要領がわからなくて、少しまごつく。
リリオの方も、私からそうしてくるとは思わなかったようで、きょとんとしている。
トルンペートと同じ感じでいいとは思うけど、トルンペートとは違って、子供みたいに体温が高いから、なんだか腕の中がほっこり暖かくて、不思議な感じだ。
別に何日も何週間も離れていたってわけじゃないのに、なんだかそのぬくもりが不思議と懐かしく感じられた。
なんだか居心地が悪いというか、座りが悪いというか、もぞもぞと抱きなおしているうちに、リリオも落ち着いてきたらしくて、いつものようにむぎゅうと抱き着いてきて、おかしそうに笑う。
「今日はなんだか、随分と積極的ですね」
「うん。寂しかったから」
「ふなっ!?」
明らかにからかうような口調だったけれど、私は昼間の内にトルンペートとの会話の中で、ある程度自分の中の寂しさというものを認識し終えている。
自分でもちょっと子供っぽいかなとは思うけれど、ずっと一緒に旅をしてきたリリオが取られてしまったような気持ちだったのかもしれない。
いまは、なんだかちょっと安心しているような感じだよ。
うつらうつらとしながらも、ある程度まとめ終えた素直な所を伝えてみると、リリオは意外そうに、でもなんだかくすぐったそうに、小さく笑った。
「いつもはつれないのに、今日は随分素直です」
「うん、まあ、トルンペートとお話してね、ちょっと気づいたっていうか」
「気づいたって寂しいってことですか?」
「それもある」
確かに私は寂しさを感じている。
そのことに気付かされた。
そして、寂しい理由にも。
「私さ」
「はい」
「私、結構君たちのこと、リリオとトルンペートのこと、気に入ってるみたいだ」
「まあ、そうなんでしょうねえ」
「うん、君たちのこと、大事で、大切で、一緒に居たい」
「……はい」
「はなれたくない」
「……はい」
「ねむい」
「もうちょっとがんばってっ」
「おやすむ……」
「あああ……勿体ないような惜しいような……」
腕の中に抱きすくめた体温。
顔を埋めた髪から漂う、お手製リンスの少し甘酸っぱい香りと、ささやかな皮脂の匂い。
そっと回された小さな腕。
どれも、以前ならばきっとおぞましくさえ感じたいきものの感触が、なぜだか今の私にはとても安らいで感じられるのだった。
用語解説
・カフェオレ
豆茶は南大陸で発見されたが、当初は原住民の間で食用とされるほかは、その効用を偶然知ったものが眠気覚ましなどに用いる程度だった。
いつごろからか豆茶の豆を潰し、湯で溶いて飲用とする飲み方が始まったが、この頃はある種の秘薬のような扱いだった。
南大陸の開拓が進んでいく中で豆茶は薬用として目をつけられ始めたが、まだ一部の宗教関係者などが用いる程度だった。
いつごろからか、恐らくは偶然から、豆を炒ると香ばしく香りが立つことが発見され、焙煎されるようになると、豆茶は嗜好品として広まるようになった。
人々の間に広まっていくうちに、より飲みやすくするために砂糖や乳を入れる飲み方が一般的になっていったとされる。
南大陸で一般化されたこの風習は商人たちによって帝国に持ち込まれ、気候の近い南部で何とか栽培に成功し、南部での豆茶の喫茶文化が洗練されていったという。
渋みや苦みを伝統的に苦手とする帝国全体としては、すでに甘茶が喫茶文化の柱となっていたこともあり、趣味人のあいだでのみ流通することとなり、「知ってはいるが飲んだことはない」という人間が増えた。
このため、南部外の人間が砂糖や乳を入れる「正しい」飲み方を知っていると、情報通であるとみなされることがある。
なお、諸説あるが、最初に豆茶に砂糖や乳を入れる飲み方を提案して、大々的に広めた人物は、神の啓示を受けたと証言したとされる。「神はこーひーぶれいくを望まれている!」という発言が当時の新聞に残っているが、完全に発狂していて詳しくはわからなかったとのことである。
マジかよ。マジで飯だけで終わっちまった。しかも八千字近くもひたすら飯の話だよ。
どうなってるんだ。
鮫っていうのは初めて食べたけれど、なかなか悪い物じゃなかったね。
食べたことがない身としては、ちょっとゲテモノ枠というか、食材としてはなかなか見れない生き物だったけれど、調理して食べてしまえば、普通に美味しいものだった。
刺し身はちょっと微妙かなー、美味しいけどちょっと気になるかなーという感じだったけれど、煮込みは普通に白身魚として美味しい部類。
フカヒレとかキャビアとか、変な例としては肝油ドロップとか、鮫由来の食品は割と見かけたことあるけど、鮫の肉って出回らないよなあ。
普通にスーパーとか、回転寿司屋とかで見かけるものだったら、普通に食材として受け入れる感じだよね。
いや、出回ってるとこには出回ってるんだろうけど、私の住んでたとこ、別に沿岸地帯でもなし、そういうの見たことなかったな。
そもそもスーパーでお買い物、なんて随分してないけど。
鮫もとい温泉魚を美味しくいただいて、心配していた温泉魚絶滅も、軽くおやつ程度にいただいてたくらいだったらしいので杞憂に済んだし、私たちは焚火にあたりながらのんびりと茶などを頂いていた。
そう、茶だ。甘茶じゃない。南部産のお茶なのだ。
帝国各地で飲まれている甘茶は、ベリー系やハーブ系など、甘いお茶はなんでも甘茶と呼ぶので、地方によって全然違うというのは前にも言ったと思う。
南部にはいわゆる甘茶というのはない。
他の地域の甘茶がそれ自体甘いのに比べると、お茶に蜂蜜とか砂糖とかを自分で加えて甘さを調節するのが南部流だ。
西方から茶葉も輸入しているし、茶の木自体の栽培もしてるらしいから、実際、私の知るお茶と同じか、品種がちょっと違うくらいのものなのかもしれないというか、うん、普通に紅茶だな、これ。
私なんかは懐かしいような気もして少しホッとするけど、帝国では茶の木のお茶はそこまで人気じゃないらしい。栽培が難しいし、発酵も難しいし、渋みがあんまり好きじゃなかったり。
南部で栽培してるのは、お茶好きの貴族が頑張って挑戦し続けた成果みたいなもので、完全に趣味の産物らしい。
庶民なんかはむしろ、南大陸とかいうところから輸入したり、自前でもちょこちょこ栽培したりしているという、豆茶の方が好みなんだとか。
豆茶も大概苦いけど、伝わってきた時に砂糖と乳をたっぷり入れて飲む甘い飲み物として紹介されたみたいで、ブラックで飲むのは少数派だ。
こう、丼みたいなでかい器にたっぷりとカフェオレ注いで飲むんだよ、南部人のティータイム。
下手な甘茶よりよほど甘いよね、あれ。
メザーガなんかはいつもブラックで飲んでたっけ。胃が荒れそうな顔してるのに。
彼の場合はあんまり甘いものが好きじゃないのと、覚醒作用が目的みたいなところはあると思うけど。
マテンステロさんは甘ったるいカフェオレ大好きみたいだけど、今回の旅には豆茶は持ってきていない。
乳の類はあんまり日持ちしないから旅には持ってこれず、しかし乳がないのに豆茶なんか飲めるかという、そういう理由らしい。
このお茶は、まあ少しくらい渋みはあるけど、砂糖でどうにかなる程度だから、許容範囲らしい。
私にはよくわからない感覚だ。
お茶を済ませて、歯を磨いて、肌に保湿用の油を塗って、あとは寝るだけなんだけど、あくび交じりにもそもそ竜車に向かった私たちに、マテンステロさんが宣言した。
「今夜は組み分け変えましょ!」
眠そうで実際眠い我々三人と違って、マテンステロさんは実に元気だ。
この人が元気じゃないところ見たことないけど。
もっともらしく語るところによれば、竜車での旅は長く退屈で、閉塞感に満ち、倦み飽きてしまう。そんな状態は心身によろしくないことは明白である。だから、刺激が必要なのだと。
私としては変わったご飯食べられるし、温泉にも入れたし、十分刺激たっぷりな一日だったのだけれど、旅慣れたマテンステロさんにはそうではないのかもしれない。
面倒くさいから明日でいいんじゃないですかね、と消極的なムード漂う我々を気にした風もなく、マテンステロさんは楽しげに私たちを見回して、そして密かに身を潜めようとしたトルンペートの首根っこを問答無用で掴んだ。
あれ怖いんだよなあ。
目の前にいるのに挙動が読めないんだもん。
いつの間にか掴まれてるんだよ。
マテンステロさんに言わせれば、単なる手先の技らしいけど。
借りてきた猫よろしく大人しくなったトルンペートを引っ提げて、マテンステロさんは意気揚々と竜車に乗り込んでいった。
去り際に垣間見えたトルンペートの目は必死で助けを求めていたように見えなくもないけど、お腹いっぱいでお茶もいただいてお目目がしぱしぱするくらい眠いから、多分見間違いだろう。私は何も見てない。知らない。わからない。
リリオも悟りを開いたような目で見送っていることだし、我々は何も見なかった。うん。
私たちはどちらともなく頷きあって、もそもそと竜車に乗り込み、《鳰の沈み布団》に潜り込んだ。
いつもは三人で包まっている《布団》は、やはり二人だと、少し広く感じる。
もともと一人用の《布団》なんだから、これでも定員オーバーのはずなんだけど。
一日空いたせいか、ちょっと遠慮しがちに潜り込むリリオを、今日は私が抱きすくめて枕代わりにする。普段はリリオの方から抱き着いてきて、放っておいてもくっついているから、私の方から抱きしめると、どこら辺に手を当てたものか、どう抱えたものか、ちょっと要領がわからなくて、少しまごつく。
リリオの方も、私からそうしてくるとは思わなかったようで、きょとんとしている。
トルンペートと同じ感じでいいとは思うけど、トルンペートとは違って、子供みたいに体温が高いから、なんだか腕の中がほっこり暖かくて、不思議な感じだ。
別に何日も何週間も離れていたってわけじゃないのに、なんだかそのぬくもりが不思議と懐かしく感じられた。
なんだか居心地が悪いというか、座りが悪いというか、もぞもぞと抱きなおしているうちに、リリオも落ち着いてきたらしくて、いつものようにむぎゅうと抱き着いてきて、おかしそうに笑う。
「今日はなんだか、随分と積極的ですね」
「うん。寂しかったから」
「ふなっ!?」
明らかにからかうような口調だったけれど、私は昼間の内にトルンペートとの会話の中で、ある程度自分の中の寂しさというものを認識し終えている。
自分でもちょっと子供っぽいかなとは思うけれど、ずっと一緒に旅をしてきたリリオが取られてしまったような気持ちだったのかもしれない。
いまは、なんだかちょっと安心しているような感じだよ。
うつらうつらとしながらも、ある程度まとめ終えた素直な所を伝えてみると、リリオは意外そうに、でもなんだかくすぐったそうに、小さく笑った。
「いつもはつれないのに、今日は随分素直です」
「うん、まあ、トルンペートとお話してね、ちょっと気づいたっていうか」
「気づいたって寂しいってことですか?」
「それもある」
確かに私は寂しさを感じている。
そのことに気付かされた。
そして、寂しい理由にも。
「私さ」
「はい」
「私、結構君たちのこと、リリオとトルンペートのこと、気に入ってるみたいだ」
「まあ、そうなんでしょうねえ」
「うん、君たちのこと、大事で、大切で、一緒に居たい」
「……はい」
「はなれたくない」
「……はい」
「ねむい」
「もうちょっとがんばってっ」
「おやすむ……」
「あああ……勿体ないような惜しいような……」
腕の中に抱きすくめた体温。
顔を埋めた髪から漂う、お手製リンスの少し甘酸っぱい香りと、ささやかな皮脂の匂い。
そっと回された小さな腕。
どれも、以前ならばきっとおぞましくさえ感じたいきものの感触が、なぜだか今の私にはとても安らいで感じられるのだった。
用語解説
・カフェオレ
豆茶は南大陸で発見されたが、当初は原住民の間で食用とされるほかは、その効用を偶然知ったものが眠気覚ましなどに用いる程度だった。
いつごろからか豆茶の豆を潰し、湯で溶いて飲用とする飲み方が始まったが、この頃はある種の秘薬のような扱いだった。
南大陸の開拓が進んでいく中で豆茶は薬用として目をつけられ始めたが、まだ一部の宗教関係者などが用いる程度だった。
いつごろからか、恐らくは偶然から、豆を炒ると香ばしく香りが立つことが発見され、焙煎されるようになると、豆茶は嗜好品として広まるようになった。
人々の間に広まっていくうちに、より飲みやすくするために砂糖や乳を入れる飲み方が一般的になっていったとされる。
南大陸で一般化されたこの風習は商人たちによって帝国に持ち込まれ、気候の近い南部で何とか栽培に成功し、南部での豆茶の喫茶文化が洗練されていったという。
渋みや苦みを伝統的に苦手とする帝国全体としては、すでに甘茶が喫茶文化の柱となっていたこともあり、趣味人のあいだでのみ流通することとなり、「知ってはいるが飲んだことはない」という人間が増えた。
このため、南部外の人間が砂糖や乳を入れる「正しい」飲み方を知っていると、情報通であるとみなされることがある。
なお、諸説あるが、最初に豆茶に砂糖や乳を入れる飲み方を提案して、大々的に広めた人物は、神の啓示を受けたと証言したとされる。「神はこーひーぶれいくを望まれている!」という発言が当時の新聞に残っているが、完全に発狂していて詳しくはわからなかったとのことである。