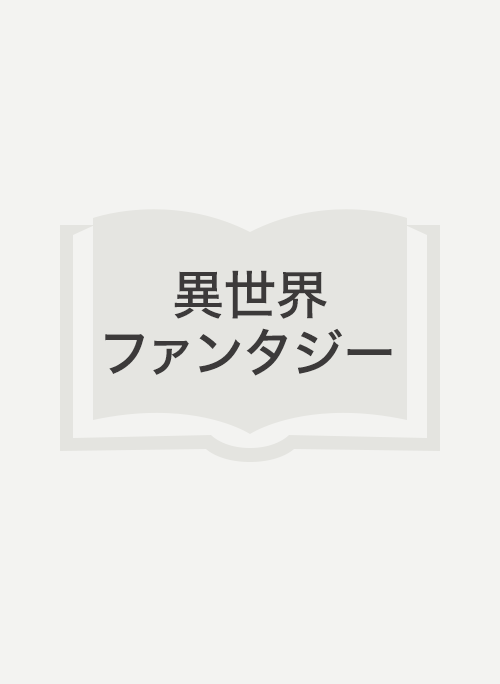前回のあらすじ
香辛料をめぐって煩悶するウルウ。
完全記憶能力の敗北である。
三人で市を見て回って、度胸試しでサシミとやらを食べて、香辛料を見て回って、あたしたちは全くこの見慣れない様相の市に飽きるということがなかった。
例えばもう驚くことはないと思っていた魚介の類には、まだまだ驚かされた。細長い笹穂のような形の魚や、まるで円盤みたいに丸い魚、顔が片方に寄ってしまったような奇妙な魚、そして今でもちょっと丸のままの姿だと敬遠してしまう烏賊や章魚。
そのいくらかは、妙に物知りなウルウが、これは何々だ、これは何かの仲間じゃないかな、これは見たことがあるけど名前を知らない、と教えてくれることもあったけれど、時々その知識も外れることはあったし、ほとんどはお手上げだと言わんばかりだった。
実際、海の生き物というものは限りというものを知らないようで、昔から漁をしている漁師たちでも、いまだにこれは何者なのだろうかと首を傾げるような生き物が捕れることもざらではないという。そう言う珍しい生き物を狙って港近くに居を構えている学者たちもいるそうで、いい小金稼ぎになるそうだった。
沖に船を出すと、油断のならないもので、たいてい一つや二つは妙なことが起きるらしかった。例えば時折、人が捕れるときがあるという。海水浴を楽しんでいて沖に流されたもの、船が難破して遭難していたもの、海賊船から突き落とされたもの、様々だ。
そう言うものは拾い上げて助けてやるのだそうだけれど、海賊らしきものは見捨ててやろうかと思う時もあるそうだった。
「たまに見慣れた顔が流れてる時もある」
「同じ漁師ってこと?」
「そう言う時もあるが、何度も漂流してるやつがいるんだよ」
そんな奇特な奴がいるのかと思って聞けば、私たちが乗る予定の輸送船を持っているプロテーゾ社の社長が、勇猛なことで危なそうな船には必ず乗り込んで自分で指揮を執り、結果として船から落ちて漂流することがしばしばあるらしい。
大丈夫なのかその人とは思ったけど、どうも海の神の加護で、少なくとも海を漂流していて死ぬことはないとかいう便利人間のようだった。そりゃあ無茶もするか。
「あたしたちが乗る船には乗ってるのかしら」
「普通の輸送船みたいですし、本拠地のハヴェノで忙しくしてるみたいですから、乗ってないと思いますよ」
「そりゃあよかったような、残念なような」
良くも悪くも目立つ人である様なので、あったら挨拶でもしてみたいものだ。
買取もしている店では、北部でたんまりと採った干し茸がいい値で売れた。とくに石茸は香りも良く、南部では非常に高値になるということで、たっぷり儲けさせてもらった。
もっぱらとろりとした煮汁にして麺と絡めて食うのが店の主の好きな食い方のようであった。また店の主だけでなく、南部は全体に麺類が好きなようで、北部に比べると麺を食べる機会が多いようだった。
また麺の形だけでなく、南部小麦の粗く挽いた粉を卵や水、塩と練って、貝殻のような形や、筆のような形、蝶のような形や、平たい布のような形など、様々な形に成型して茹でたり煮込んだりして食べるのだという。
「練り物と一言に言っても、何しろ基本的な形だけでも何十種類もあるし、細かいところまで比べて行ったら、南部全体で何百種類もあるよ。それに和えるたれや煮汁、また食い方なんかも加えて行ったら、帝都大学にそれを調べて本にまとめている学者がいるくらいさ」
何と恐ろしいことに、その何十種類、何百種類という練り物を専門に扱っている店もあって、しかも市に並べてあるのは乾燥させたもののうちでもさらに壊れづらいものばかりで、商店街にある店舗では、更に数多くの種類が並べられて、注文通りの形に店で成型したりもするらしい。
「この学者が実にしっかりした人でね、南部生まれだからってのもあるんだろうけれど、練り物愛が素晴らしいんだ。形も全部図柄で説明していてね、うちでもお客さんから注文された時に便利なんで、愛用してるよ。市井の店で愛読されてる学術書なんて、まあこれくらいだろうね」
いつも一冊持ち歩いているんだという本は大判で、しかもかなり分厚いもので、店主はこれを専用の入れ物を手作りして腰に下げているのだった。
読ませてもらうとかなり面白い本で、確かに学者特有の小難しい言葉遣いや分類なんかも書いてあるのだけれど、読む人を飽きさせることのない南部人特有の明るい調子で、ちょくちょく小粋な冗談をはさんでくる。時には一面丸々練り物にまつわる冗句が書き連ねてあったり、一章丸々練り物の関わる逸話を紹介していたりした。ほとんど本の厚みはこれらの部分にあるんじゃなかろうか。
また実際実用的でもあって、麺の形状を図柄で描き連ねてあるのだけれど、この図柄は本文での小難しい分類とはすっかり切り離されて、純粋に形状が似通った順に並べてあるので、探す側としてはこれ以上ありがたいことはないだろう。
「学術書なんてまあ、大概の町じゃあ一冊二冊あればいいくらいだけど、バージョの練り物屋には必ず置いてあるし、本屋にだって必ず置いてある。勝手に置いてある家だって少なくないんだから、これほど売れ行きのいい学術書ってのは他に知らないね」
店主が饒舌に語る言葉は全く頷かざるを得ない具合だった。
そしてその調子で根切交渉までするする進めさせられて、気づけばたっぷりの練り物を買わされていたのだから、全く南部人というものは油断がならない。
「フムン。これは確かに立派な本だね。あとで見かけたら、買っていこう」
「やあ、お母さん、食べ盛りの娘さんを二人もつれて大変だね」
「こんなでかい娘が二人もいてたまるか!」
南部ではウルウも思わず突っ込みが飛び出るようだった。
用語解説
・章魚
いわゆるタコ。
ただし油断ならないのがこの異世界、硬い鱗に覆われたタコや、毒液で狙撃してくるタコなどもいるというからびっくりだ。
・練り物
小麦粉を卵や水、塩と練って、麺にしたり、貝殻状に成型したりと加工したもの。パスタ。
・
香辛料をめぐって煩悶するウルウ。
完全記憶能力の敗北である。
三人で市を見て回って、度胸試しでサシミとやらを食べて、香辛料を見て回って、あたしたちは全くこの見慣れない様相の市に飽きるということがなかった。
例えばもう驚くことはないと思っていた魚介の類には、まだまだ驚かされた。細長い笹穂のような形の魚や、まるで円盤みたいに丸い魚、顔が片方に寄ってしまったような奇妙な魚、そして今でもちょっと丸のままの姿だと敬遠してしまう烏賊や章魚。
そのいくらかは、妙に物知りなウルウが、これは何々だ、これは何かの仲間じゃないかな、これは見たことがあるけど名前を知らない、と教えてくれることもあったけれど、時々その知識も外れることはあったし、ほとんどはお手上げだと言わんばかりだった。
実際、海の生き物というものは限りというものを知らないようで、昔から漁をしている漁師たちでも、いまだにこれは何者なのだろうかと首を傾げるような生き物が捕れることもざらではないという。そう言う珍しい生き物を狙って港近くに居を構えている学者たちもいるそうで、いい小金稼ぎになるそうだった。
沖に船を出すと、油断のならないもので、たいてい一つや二つは妙なことが起きるらしかった。例えば時折、人が捕れるときがあるという。海水浴を楽しんでいて沖に流されたもの、船が難破して遭難していたもの、海賊船から突き落とされたもの、様々だ。
そう言うものは拾い上げて助けてやるのだそうだけれど、海賊らしきものは見捨ててやろうかと思う時もあるそうだった。
「たまに見慣れた顔が流れてる時もある」
「同じ漁師ってこと?」
「そう言う時もあるが、何度も漂流してるやつがいるんだよ」
そんな奇特な奴がいるのかと思って聞けば、私たちが乗る予定の輸送船を持っているプロテーゾ社の社長が、勇猛なことで危なそうな船には必ず乗り込んで自分で指揮を執り、結果として船から落ちて漂流することがしばしばあるらしい。
大丈夫なのかその人とは思ったけど、どうも海の神の加護で、少なくとも海を漂流していて死ぬことはないとかいう便利人間のようだった。そりゃあ無茶もするか。
「あたしたちが乗る船には乗ってるのかしら」
「普通の輸送船みたいですし、本拠地のハヴェノで忙しくしてるみたいですから、乗ってないと思いますよ」
「そりゃあよかったような、残念なような」
良くも悪くも目立つ人である様なので、あったら挨拶でもしてみたいものだ。
買取もしている店では、北部でたんまりと採った干し茸がいい値で売れた。とくに石茸は香りも良く、南部では非常に高値になるということで、たっぷり儲けさせてもらった。
もっぱらとろりとした煮汁にして麺と絡めて食うのが店の主の好きな食い方のようであった。また店の主だけでなく、南部は全体に麺類が好きなようで、北部に比べると麺を食べる機会が多いようだった。
また麺の形だけでなく、南部小麦の粗く挽いた粉を卵や水、塩と練って、貝殻のような形や、筆のような形、蝶のような形や、平たい布のような形など、様々な形に成型して茹でたり煮込んだりして食べるのだという。
「練り物と一言に言っても、何しろ基本的な形だけでも何十種類もあるし、細かいところまで比べて行ったら、南部全体で何百種類もあるよ。それに和えるたれや煮汁、また食い方なんかも加えて行ったら、帝都大学にそれを調べて本にまとめている学者がいるくらいさ」
何と恐ろしいことに、その何十種類、何百種類という練り物を専門に扱っている店もあって、しかも市に並べてあるのは乾燥させたもののうちでもさらに壊れづらいものばかりで、商店街にある店舗では、更に数多くの種類が並べられて、注文通りの形に店で成型したりもするらしい。
「この学者が実にしっかりした人でね、南部生まれだからってのもあるんだろうけれど、練り物愛が素晴らしいんだ。形も全部図柄で説明していてね、うちでもお客さんから注文された時に便利なんで、愛用してるよ。市井の店で愛読されてる学術書なんて、まあこれくらいだろうね」
いつも一冊持ち歩いているんだという本は大判で、しかもかなり分厚いもので、店主はこれを専用の入れ物を手作りして腰に下げているのだった。
読ませてもらうとかなり面白い本で、確かに学者特有の小難しい言葉遣いや分類なんかも書いてあるのだけれど、読む人を飽きさせることのない南部人特有の明るい調子で、ちょくちょく小粋な冗談をはさんでくる。時には一面丸々練り物にまつわる冗句が書き連ねてあったり、一章丸々練り物の関わる逸話を紹介していたりした。ほとんど本の厚みはこれらの部分にあるんじゃなかろうか。
また実際実用的でもあって、麺の形状を図柄で描き連ねてあるのだけれど、この図柄は本文での小難しい分類とはすっかり切り離されて、純粋に形状が似通った順に並べてあるので、探す側としてはこれ以上ありがたいことはないだろう。
「学術書なんてまあ、大概の町じゃあ一冊二冊あればいいくらいだけど、バージョの練り物屋には必ず置いてあるし、本屋にだって必ず置いてある。勝手に置いてある家だって少なくないんだから、これほど売れ行きのいい学術書ってのは他に知らないね」
店主が饒舌に語る言葉は全く頷かざるを得ない具合だった。
そしてその調子で根切交渉までするする進めさせられて、気づけばたっぷりの練り物を買わされていたのだから、全く南部人というものは油断がならない。
「フムン。これは確かに立派な本だね。あとで見かけたら、買っていこう」
「やあ、お母さん、食べ盛りの娘さんを二人もつれて大変だね」
「こんなでかい娘が二人もいてたまるか!」
南部ではウルウも思わず突っ込みが飛び出るようだった。
用語解説
・章魚
いわゆるタコ。
ただし油断ならないのがこの異世界、硬い鱗に覆われたタコや、毒液で狙撃してくるタコなどもいるというからびっくりだ。
・練り物
小麦粉を卵や水、塩と練って、麺にしたり、貝殻状に成型したりと加工したもの。パスタ。
・