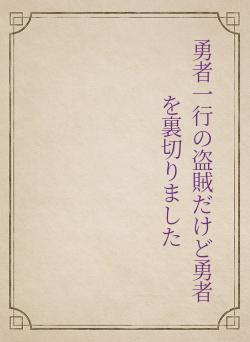「いきましたね。」
彼奴の母親が、すすり泣きながら首を縦に振る。
目の前では今からコールドスリープされるとか思いこんで清々しい顔をした桜恋がいる。
今にも起き上がりそうだ。
「……信じてんじゃねえよ。頭の中まで脳筋なのかよ。少し考えれば、嘘って分かるじゃねえか。」
彼奴の周りには精密機械がびっしりと並べられていた。
未知の病。
結局それは何かわからなかった。
現代でも解明できない。
未来でも改名できているか分からない。
コールドスリープという手を思いついたのは俺だった。
でも、コールドスリープだって目覚めることが出来るか分からないのだ。
コールドスリープで延命したところで、此奴が生きれる時間なんて限られている。
俺は彼奴の病院服からはみ出す身体を見た。
真っ黒だった。
桜恋の身体は、健康時から考えられないほどに病魔に蝕まれていたのだ。
本人に気付かれないように、この病室には鏡が置かれていない。
さぞかし暇だっただろう。
精密機械が近くにあるため動き回ることは出来ないし、ケータイも使えない。
あれだけ身体を動かしていた桜恋が、じっとしているなんて無理だっただろうな。
早く元気になればいいなんて思っていただろう。
コールドスリープの件も無くなればいいとも。
もう冷たくなった桜恋の手を握った。
意外に小さい手だった。
顔を合わせる毎に殴りかかってきた手とは思えない。
やっぱり女子なのか。
ゴリラと言ったことを訂正しよう。
俺は、涙を拭いて持ってきたピアノを持って部屋を出た。
無理言って電子ピアノを持ってきた甲斐が有った。
桜恋の楽しそうな顔が見れた。
それで十分だ。
泣きっ面で死なれるよりマシだ。
そう、きっとそうだ。
今頃、コールドスリープが嘘だと知って怒りそうだ。
そして、ぶん殴られるか。
まあ、今日ぐらいはいいだろう。
俺は頬のまだ腫れの引かない傷跡に手を伸ばした。
「どれだけ苦しむようにやったんだよ。……痛いな。」
彼奴の母親が、すすり泣きながら首を縦に振る。
目の前では今からコールドスリープされるとか思いこんで清々しい顔をした桜恋がいる。
今にも起き上がりそうだ。
「……信じてんじゃねえよ。頭の中まで脳筋なのかよ。少し考えれば、嘘って分かるじゃねえか。」
彼奴の周りには精密機械がびっしりと並べられていた。
未知の病。
結局それは何かわからなかった。
現代でも解明できない。
未来でも改名できているか分からない。
コールドスリープという手を思いついたのは俺だった。
でも、コールドスリープだって目覚めることが出来るか分からないのだ。
コールドスリープで延命したところで、此奴が生きれる時間なんて限られている。
俺は彼奴の病院服からはみ出す身体を見た。
真っ黒だった。
桜恋の身体は、健康時から考えられないほどに病魔に蝕まれていたのだ。
本人に気付かれないように、この病室には鏡が置かれていない。
さぞかし暇だっただろう。
精密機械が近くにあるため動き回ることは出来ないし、ケータイも使えない。
あれだけ身体を動かしていた桜恋が、じっとしているなんて無理だっただろうな。
早く元気になればいいなんて思っていただろう。
コールドスリープの件も無くなればいいとも。
もう冷たくなった桜恋の手を握った。
意外に小さい手だった。
顔を合わせる毎に殴りかかってきた手とは思えない。
やっぱり女子なのか。
ゴリラと言ったことを訂正しよう。
俺は、涙を拭いて持ってきたピアノを持って部屋を出た。
無理言って電子ピアノを持ってきた甲斐が有った。
桜恋の楽しそうな顔が見れた。
それで十分だ。
泣きっ面で死なれるよりマシだ。
そう、きっとそうだ。
今頃、コールドスリープが嘘だと知って怒りそうだ。
そして、ぶん殴られるか。
まあ、今日ぐらいはいいだろう。
俺は頬のまだ腫れの引かない傷跡に手を伸ばした。
「どれだけ苦しむようにやったんだよ。……痛いな。」