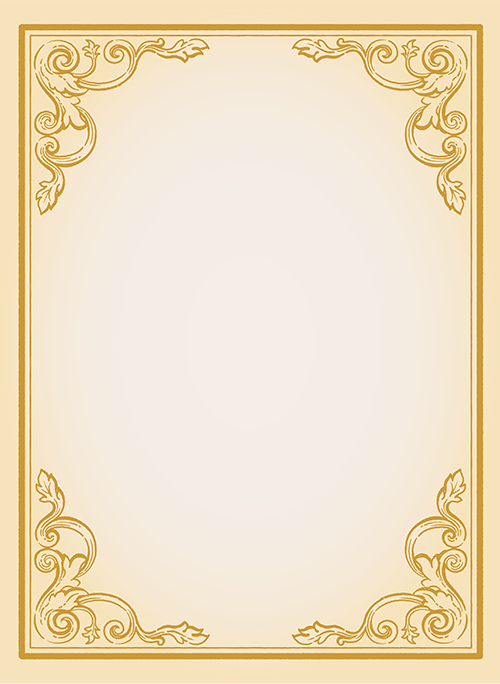桜井萌笑が学校に来てから一ヶ月が経過した。
彼女はクラスにもすっかり馴染んで、休憩時間にわざわざ俺の元を訪れることはなくなった。しかし、適度な距離感を保てているか、と問われれば怪しい。
俺たちは授業中に手紙交換のようなことをずっとしている。小学生の頃流行っていたあれだ。
まさか高校生にもなってすることになるとは思わなかったが、体育や音楽などの移動教室を除き、基本的に紙切れを渡され、返事を書かされる。
無視すれば良かったのに、付き合ってしまう俺にはまだ良心があったのかもしれない。俺が距離を詰めたくないという勝手な理由で、彼女を傷つけていいわけがないのだ。だから、惰性で続けている。俺の返事は素っ気ないし、つまらないものなのに、彼女はよくこんなことを続けるな、と最近は感心する。
『ねぇねぇ、たまには一緒に帰らない?』
そんな珍しいメッセージが書かれていた。俺たちは連絡先も知らないので、基本的な会話は授業中のみで行われていた。一緒に帰ったことなんて当然なかった。
『いいよ』
俺はそう書いて、彼女に渡した。
受け取った彼女は、屈託のない笑顔で返してくれた。萌笑という名前は、彼女にぴったりだと思った。
放課後になって、彼女の元に「かえろー」と誘いに来た友達数名に、「今日はごめん! 一緒に帰る人がいるから」と謝っている姿を見ていると、友達数名に申し訳ない気持ちになった。きっと彼女たちと帰った方が会話は弾むだろうし、楽しいものになると思う。
「そっかー。もしかして、男?」
「え、ど、どうかなぁ?」
彼女は嘘が下手だ。わかりやすい。
「絶対そうだー!」
彼女の友達の声はそれなりに大きくて、教室にいる人には聞こえているんじゃないだろうか。ちらっと教室を見渡すと、男子が横目でこちらを見ている。気になるんだろうな。相手が俺だと知ったら、逆に安心するんじゃないだろうか。
彼女が困り果てていたので、俺はカバンを持って、何も言わずに教室を出た。校門前で待つことにした。
数分後、息を切らしながら、彼女は走ってやってきた。
「はぁはぁ……ふぅ。ごめんね。待たせちゃって」
「全然大丈夫。それにしても、大変だね」
「え、あぁ、うん。迷惑かけちゃったね」
「暇だし大丈夫だよ。帰ろうか」
彼女はこくんとうなずいた。
彼女の提案で、少し帰り道からは逸れるが、公園に寄ることになった。ブランコとベンチ以外に何もない殺風景な公園だ。
俺たちはブランコに座った。
「どうして、俺と帰ろうと思ったの?」
「やっぱり、気になる? 教えて欲しいー?」
彼女は、小悪魔みたいにニヤッと笑う。
なんだか彼女のペースで会話が進むのはシャクだ。けれど、気になる。
「あぁ」
「晴翔くんのことをもっと知りたいって思ったから」
「前にも似たようなこと言ってたけど、俺のことを知って何になるって言うの?」
俺のことはあまり知らない方がいい。その人のことをよく知ることで、関係は深くなっていく。一緒に帰る選択をした時点で、手遅れなのかもしれないけれど、希薄なままでいたい俺からすればあまり好ましいことではなかった。
「んー、何になるとか、そういう話じゃなくてさ。んー。難しいなぁ」
彼女は手を顎に当てて、考えるポーズした。俺は続きを待った。
「私たち似てるところあると思うから。って答えじゃダメかな」
彼女はそう付け加えた。
「それも前に言ってたけど、似てるところなんて一つもないと思うけど」
「あるよ」
たった一言。それなのに今まで彼女の口から出てきたどの言葉よりも強かった。
「どういうこと?」
「あった。って言った方が正しいかもね。私ね。お母さんいないんだ」
彼女は淡々と、まるで当然であるかのように言った。
「二年前くらいかな? 突然死でね。いたって健康な人だったから予兆なんて全然なくて、朝起きたらお母さんが動かなくて、冷たくて。あぁ、生きてないんだってすぐにわかったよ」
彼女はブランコを漕ぎながら、沈み始めている夕日に語りかけているようだった。俺は何も言えなかった。
「でね、それから私は大好きだったお母さんがいなくなったことに、どうしていいかわかんなくて。お父さんを残して、死のうとまで思ったことがあったんだ。酷い娘だよね」
ははっ、と乾いた笑いが遅れて聞こえる。笑っているのに決して、笑っていない。
「そこから私は、今の君みたいになった」
彼女が言っていた、俺らが似ているという意味がやっとわかった。
過去の悲しみから抜け出せず、現実に目を向けることができていない。それが今の俺で、昔の彼女なのだろう。
「でもね、私は救われた。君のおかげで」
「え? 俺? ちょっと待って、どういうこと?」
「ふふっ、覚えてないでしょ? 半年くらい前かな。この町に引っ越すことになって、物件探しのためにこの町に来てたときにね、君と一回出会ってるんだよ」
俺のよく知る笑顔を彼女は見せてくれた。決してハリボテなんかじゃなくて、心の底から笑顔を見せるその姿は、いつも通りで安心感を与えてくれた。
「……」
どれだけ記憶を遡っても、彼女と初めて出会ったのは教室で、それ以前のどこを探しても彼女との思い出は出てこなかった。
「やっぱり、覚えてないよねー。学校に向かう途中の角なんだけどね。私が角を曲がるとね、君が棒立ちで突っ立っていたんだよ。意味わかんなくない? なんで? って普通思うじゃん? 驚く私のことを不思議そうに晴翔くんは見ていて、つい、話しかけちゃったの」
思い出した。
『!』が視界に現れて、このまま歩き続けるときっと角から出てくる何かにぶつかるんだと思って、立ち止まったときだ。でも、あのときの少女はもっと髪が長かった。顔は彼女に似ていた気がするけれど、もっと暗い印象が蘇ってきた。今の彼女とは似ても似つかぬ、と言った感じだ。
「覚えてる?」
「うん。何してるんですか、って聞かれたと思う」
「そう。そしたら、ぶつかる気がしたから、って平然と言っちゃうんだよ。超能力者かっ! って思って、そんなわけないか、って考え直して、じゃあ、毎度毎度角ではああいう風に立ち止まっているのかな? って思って、その姿を想像しただけで、ちょっと笑えてきて。久しぶりに笑えて、なんだか嬉しくて、少し前を向けた気がしたの」
毎度毎度立ち止まっているわけではない。『!』が現れたときだけだ。だから、彼女が却下した前者の方が正しいのだけれど、そんなこと言えるはずもない。
「君は意味があって、何かをしたわけではないと思うけれど、私は救われたんだー。そしてね、転校した先の学校に君がいた。しかも、同じクラスの、隣の席。運命だと思ったよ。でもね、君の目は、昔の私みたいだった。半年前に会ったときは、自分のことで精一杯で気づかなかったけど、君も何か抱えているような気がした。今度は私が何かしてあげたいって思ってたんだけど、中々上手くいかないね」
彼女は、へへっ、と笑った。
どうして俺を気にかけるのか、ずっと不思議だった。陰鬱なオーラ全開だった俺に話しかける人なんて、彼女以外に誰もいなくて、転校してきたばかりだから事情は知らないとは言え、他の誰も話しかけてこないのだから、色々察する部分もあったと思う。それでも、転校してきて一ヶ月が経っても、変わらず話しかけてくる。
最初は意味がわからなかったし、放っておいてくれよ、と思ったこともあった。思い返せば、それでも彼女と会話を続けていたのは、俺自身も救われていたからじゃないのか?
最初は傷つけていい理由なんてない、というところから会話は続けていたけれど、いつしかうざったいとも思わなくなっていたし、話しかけてくれることが嬉しかったんじゃないのか?
そういう風に考えられるようになっただけでも、俺は十分変わったし、救われた。そう思う。
「──救われたよ。こうして話ができているんだから。救われた。俺の話もしていい?」
彼女は静かに、頷いた。
俺は家族のことやどうして一人で過ごすのか、そういったことを包み隠さず話した。初めてのことだった。こんなこと俺の中だけに留めておくべきだ。そう思っていても、一度口にし始めると、ダムが決壊したかのようにドバドバ溢れ出てきて、止められなかった。
俺が話し終えるまで、彼女は静かに聞いてくれた。それだけで、また一つ彼女に救われた。
『!』
少し前よりも頻繁に現れるようになった気がする。特にこの日を境に。
休日に桜井さんと出かけるのは、初めてだった。
私服姿を見るのは初めてだったので、新鮮で、視線のやり場に困った。
水族館へ行き、その後はショッピングモールで買い物をして、夕方になったので、自宅を目指して帰っているところだった。
『!』
今日はやけに多い。日に日に回数が多くなっているけれど、今日は一段と多い。十分に一回くらいは出てきている気がする。
出てきても俺の身には何も起こることなく、いつも通り過ごすことができている。ややこしいし、やめてほしい。故障だろうか? 特殊能力にも故障とかそもそもあるのだろうか?
「ねえねえ!」
「ん?」
「楽しかった?」
彼女はまるで俺の答えがわかっているかのように訊いてきた。
「うん。楽しかったよ」
「そっかそっかー」
俺の答えを聞いて、満足そうだった。俺の過去の話をしたあの日から、彼女のことが気になっている。多分、恋愛感情で合っていると思う。
こんな風に感じるのはとても久々で、どう彼女と接していいものなのか少し困っている。
彼女はどう思っているのだろう。こうして休日に誘ってくるということは、アリかナシかで言えば、アリ派か……?
んー、でも、彼女が話しかけてきてくれるのは、俺が彼女を救った恩返しという意味合いが強そうだし……。んー。
「青だよー」
少し遠くから彼女の声が聞こえてきた。
考え事をしていて、信号が青に変わったことに気がつかなかった。俺よりも少し前を彼女は歩いていて、追いつこうとしたとき──
『!!!』
一瞬、足が止まった。
今までにないくらい、激しく危険を知らせてくる。なんだよ、これ。
少し先に信号が赤だと言うのに、スピードを全然緩めない車が迫ってきていることに気がついた。このままだと、交差点に入ってくる。
「逃げろ!」
叫んだ。喉がちぎれそうなくらいに。
俺の声に気がついた人たちは、一斉に逃げる。彼女はパニックになる人たちに押し倒され、逃げ遅れていた。
考えるよりも先に足が動いた。どんどん車は迫ってきているというのに、俺はその危険な場所に自ら向かっている。
『!!!』
自ら危険を冒してまで、彼女を助けたいと思う気持ちが強かった。俺がどうなってもいい。彼女だけは助けたい。
彼女を道路の外に押し出した後、車は俺を轢いた。一瞬、彼女の顔が見えた。全然笑っていなかった。
君は笑顔が似合うのに。
劈く悲鳴が聞こえる。意識が遠のく。誰かに抱き抱えられる。彼女だ。
何か言っているけれど、何も聞こえない。死がそこまで迫っていることがよくわかった。
『!』
彼女と話すときに現れたのは、今日の日の危険を予知するものだったのかもしれない。関係が濃くなることで、俺に危険が及ぶ。けれど、そのことがわかっていても、俺はこうして出かけて、彼女を救った。胸を張って、そう言える。
もうダメだ。
最後の力を振り絞って、言う。
「わ……らっ、て」
届いただろうか。わからない。ほとんど何も見えないけれど、微かに見える彼女の表情は笑っていた。涙でくしゃくしゃになっているけれど、確かに笑っていた。下手くそだ。全然上手く笑えていない。それでも、彼女は笑顔が似合う。
彼女との思い出が蘇ってきた。走馬灯とはこのことか。
色々あったけれど、前を向いて、笑うことができたのは、彼女のおかげだ。最後は感謝の言葉の方が良かったかな。それとも、好きってことを伝えた方が良かったのかもしれない。とにかく、彼女の笑顔を最後に見たい一心で口走ったけれど、相応しくなかったのかな。
もうどこに意識があるのかわからない。どこか遠く、俺の知らないところに意識が運ばれる。
目を覚ますと、見知らぬ真っ白な天井がそこにはあった。太ももの辺りに重みを感じる。
視線をやると、桜井萌笑がスヤスヤ寝ていた。
俺は助かったんだと気がついた。
車に轢かれて意識を失った記憶はあるけれど、断片的に覚えているだけでかなり曖昧なものだった。
「……ん?」
俺が動いたせいで、彼女を起こしてしまったようだ。
「おはよう」俺は優しく言った。
彼女は俺を一点に見つめ、静かに涙を流した。そして、破顔した。
「……おはよう。晴翔くん。寝坊助さんだね」
くしゃっと笑う彼女につられて、俺も笑みが溢れた。
これからは君を悲しい表情になんてさせない。だって、君には笑顔が一番似合うんだから。
彼女はクラスにもすっかり馴染んで、休憩時間にわざわざ俺の元を訪れることはなくなった。しかし、適度な距離感を保てているか、と問われれば怪しい。
俺たちは授業中に手紙交換のようなことをずっとしている。小学生の頃流行っていたあれだ。
まさか高校生にもなってすることになるとは思わなかったが、体育や音楽などの移動教室を除き、基本的に紙切れを渡され、返事を書かされる。
無視すれば良かったのに、付き合ってしまう俺にはまだ良心があったのかもしれない。俺が距離を詰めたくないという勝手な理由で、彼女を傷つけていいわけがないのだ。だから、惰性で続けている。俺の返事は素っ気ないし、つまらないものなのに、彼女はよくこんなことを続けるな、と最近は感心する。
『ねぇねぇ、たまには一緒に帰らない?』
そんな珍しいメッセージが書かれていた。俺たちは連絡先も知らないので、基本的な会話は授業中のみで行われていた。一緒に帰ったことなんて当然なかった。
『いいよ』
俺はそう書いて、彼女に渡した。
受け取った彼女は、屈託のない笑顔で返してくれた。萌笑という名前は、彼女にぴったりだと思った。
放課後になって、彼女の元に「かえろー」と誘いに来た友達数名に、「今日はごめん! 一緒に帰る人がいるから」と謝っている姿を見ていると、友達数名に申し訳ない気持ちになった。きっと彼女たちと帰った方が会話は弾むだろうし、楽しいものになると思う。
「そっかー。もしかして、男?」
「え、ど、どうかなぁ?」
彼女は嘘が下手だ。わかりやすい。
「絶対そうだー!」
彼女の友達の声はそれなりに大きくて、教室にいる人には聞こえているんじゃないだろうか。ちらっと教室を見渡すと、男子が横目でこちらを見ている。気になるんだろうな。相手が俺だと知ったら、逆に安心するんじゃないだろうか。
彼女が困り果てていたので、俺はカバンを持って、何も言わずに教室を出た。校門前で待つことにした。
数分後、息を切らしながら、彼女は走ってやってきた。
「はぁはぁ……ふぅ。ごめんね。待たせちゃって」
「全然大丈夫。それにしても、大変だね」
「え、あぁ、うん。迷惑かけちゃったね」
「暇だし大丈夫だよ。帰ろうか」
彼女はこくんとうなずいた。
彼女の提案で、少し帰り道からは逸れるが、公園に寄ることになった。ブランコとベンチ以外に何もない殺風景な公園だ。
俺たちはブランコに座った。
「どうして、俺と帰ろうと思ったの?」
「やっぱり、気になる? 教えて欲しいー?」
彼女は、小悪魔みたいにニヤッと笑う。
なんだか彼女のペースで会話が進むのはシャクだ。けれど、気になる。
「あぁ」
「晴翔くんのことをもっと知りたいって思ったから」
「前にも似たようなこと言ってたけど、俺のことを知って何になるって言うの?」
俺のことはあまり知らない方がいい。その人のことをよく知ることで、関係は深くなっていく。一緒に帰る選択をした時点で、手遅れなのかもしれないけれど、希薄なままでいたい俺からすればあまり好ましいことではなかった。
「んー、何になるとか、そういう話じゃなくてさ。んー。難しいなぁ」
彼女は手を顎に当てて、考えるポーズした。俺は続きを待った。
「私たち似てるところあると思うから。って答えじゃダメかな」
彼女はそう付け加えた。
「それも前に言ってたけど、似てるところなんて一つもないと思うけど」
「あるよ」
たった一言。それなのに今まで彼女の口から出てきたどの言葉よりも強かった。
「どういうこと?」
「あった。って言った方が正しいかもね。私ね。お母さんいないんだ」
彼女は淡々と、まるで当然であるかのように言った。
「二年前くらいかな? 突然死でね。いたって健康な人だったから予兆なんて全然なくて、朝起きたらお母さんが動かなくて、冷たくて。あぁ、生きてないんだってすぐにわかったよ」
彼女はブランコを漕ぎながら、沈み始めている夕日に語りかけているようだった。俺は何も言えなかった。
「でね、それから私は大好きだったお母さんがいなくなったことに、どうしていいかわかんなくて。お父さんを残して、死のうとまで思ったことがあったんだ。酷い娘だよね」
ははっ、と乾いた笑いが遅れて聞こえる。笑っているのに決して、笑っていない。
「そこから私は、今の君みたいになった」
彼女が言っていた、俺らが似ているという意味がやっとわかった。
過去の悲しみから抜け出せず、現実に目を向けることができていない。それが今の俺で、昔の彼女なのだろう。
「でもね、私は救われた。君のおかげで」
「え? 俺? ちょっと待って、どういうこと?」
「ふふっ、覚えてないでしょ? 半年くらい前かな。この町に引っ越すことになって、物件探しのためにこの町に来てたときにね、君と一回出会ってるんだよ」
俺のよく知る笑顔を彼女は見せてくれた。決してハリボテなんかじゃなくて、心の底から笑顔を見せるその姿は、いつも通りで安心感を与えてくれた。
「……」
どれだけ記憶を遡っても、彼女と初めて出会ったのは教室で、それ以前のどこを探しても彼女との思い出は出てこなかった。
「やっぱり、覚えてないよねー。学校に向かう途中の角なんだけどね。私が角を曲がるとね、君が棒立ちで突っ立っていたんだよ。意味わかんなくない? なんで? って普通思うじゃん? 驚く私のことを不思議そうに晴翔くんは見ていて、つい、話しかけちゃったの」
思い出した。
『!』が視界に現れて、このまま歩き続けるときっと角から出てくる何かにぶつかるんだと思って、立ち止まったときだ。でも、あのときの少女はもっと髪が長かった。顔は彼女に似ていた気がするけれど、もっと暗い印象が蘇ってきた。今の彼女とは似ても似つかぬ、と言った感じだ。
「覚えてる?」
「うん。何してるんですか、って聞かれたと思う」
「そう。そしたら、ぶつかる気がしたから、って平然と言っちゃうんだよ。超能力者かっ! って思って、そんなわけないか、って考え直して、じゃあ、毎度毎度角ではああいう風に立ち止まっているのかな? って思って、その姿を想像しただけで、ちょっと笑えてきて。久しぶりに笑えて、なんだか嬉しくて、少し前を向けた気がしたの」
毎度毎度立ち止まっているわけではない。『!』が現れたときだけだ。だから、彼女が却下した前者の方が正しいのだけれど、そんなこと言えるはずもない。
「君は意味があって、何かをしたわけではないと思うけれど、私は救われたんだー。そしてね、転校した先の学校に君がいた。しかも、同じクラスの、隣の席。運命だと思ったよ。でもね、君の目は、昔の私みたいだった。半年前に会ったときは、自分のことで精一杯で気づかなかったけど、君も何か抱えているような気がした。今度は私が何かしてあげたいって思ってたんだけど、中々上手くいかないね」
彼女は、へへっ、と笑った。
どうして俺を気にかけるのか、ずっと不思議だった。陰鬱なオーラ全開だった俺に話しかける人なんて、彼女以外に誰もいなくて、転校してきたばかりだから事情は知らないとは言え、他の誰も話しかけてこないのだから、色々察する部分もあったと思う。それでも、転校してきて一ヶ月が経っても、変わらず話しかけてくる。
最初は意味がわからなかったし、放っておいてくれよ、と思ったこともあった。思い返せば、それでも彼女と会話を続けていたのは、俺自身も救われていたからじゃないのか?
最初は傷つけていい理由なんてない、というところから会話は続けていたけれど、いつしかうざったいとも思わなくなっていたし、話しかけてくれることが嬉しかったんじゃないのか?
そういう風に考えられるようになっただけでも、俺は十分変わったし、救われた。そう思う。
「──救われたよ。こうして話ができているんだから。救われた。俺の話もしていい?」
彼女は静かに、頷いた。
俺は家族のことやどうして一人で過ごすのか、そういったことを包み隠さず話した。初めてのことだった。こんなこと俺の中だけに留めておくべきだ。そう思っていても、一度口にし始めると、ダムが決壊したかのようにドバドバ溢れ出てきて、止められなかった。
俺が話し終えるまで、彼女は静かに聞いてくれた。それだけで、また一つ彼女に救われた。
『!』
少し前よりも頻繁に現れるようになった気がする。特にこの日を境に。
休日に桜井さんと出かけるのは、初めてだった。
私服姿を見るのは初めてだったので、新鮮で、視線のやり場に困った。
水族館へ行き、その後はショッピングモールで買い物をして、夕方になったので、自宅を目指して帰っているところだった。
『!』
今日はやけに多い。日に日に回数が多くなっているけれど、今日は一段と多い。十分に一回くらいは出てきている気がする。
出てきても俺の身には何も起こることなく、いつも通り過ごすことができている。ややこしいし、やめてほしい。故障だろうか? 特殊能力にも故障とかそもそもあるのだろうか?
「ねえねえ!」
「ん?」
「楽しかった?」
彼女はまるで俺の答えがわかっているかのように訊いてきた。
「うん。楽しかったよ」
「そっかそっかー」
俺の答えを聞いて、満足そうだった。俺の過去の話をしたあの日から、彼女のことが気になっている。多分、恋愛感情で合っていると思う。
こんな風に感じるのはとても久々で、どう彼女と接していいものなのか少し困っている。
彼女はどう思っているのだろう。こうして休日に誘ってくるということは、アリかナシかで言えば、アリ派か……?
んー、でも、彼女が話しかけてきてくれるのは、俺が彼女を救った恩返しという意味合いが強そうだし……。んー。
「青だよー」
少し遠くから彼女の声が聞こえてきた。
考え事をしていて、信号が青に変わったことに気がつかなかった。俺よりも少し前を彼女は歩いていて、追いつこうとしたとき──
『!!!』
一瞬、足が止まった。
今までにないくらい、激しく危険を知らせてくる。なんだよ、これ。
少し先に信号が赤だと言うのに、スピードを全然緩めない車が迫ってきていることに気がついた。このままだと、交差点に入ってくる。
「逃げろ!」
叫んだ。喉がちぎれそうなくらいに。
俺の声に気がついた人たちは、一斉に逃げる。彼女はパニックになる人たちに押し倒され、逃げ遅れていた。
考えるよりも先に足が動いた。どんどん車は迫ってきているというのに、俺はその危険な場所に自ら向かっている。
『!!!』
自ら危険を冒してまで、彼女を助けたいと思う気持ちが強かった。俺がどうなってもいい。彼女だけは助けたい。
彼女を道路の外に押し出した後、車は俺を轢いた。一瞬、彼女の顔が見えた。全然笑っていなかった。
君は笑顔が似合うのに。
劈く悲鳴が聞こえる。意識が遠のく。誰かに抱き抱えられる。彼女だ。
何か言っているけれど、何も聞こえない。死がそこまで迫っていることがよくわかった。
『!』
彼女と話すときに現れたのは、今日の日の危険を予知するものだったのかもしれない。関係が濃くなることで、俺に危険が及ぶ。けれど、そのことがわかっていても、俺はこうして出かけて、彼女を救った。胸を張って、そう言える。
もうダメだ。
最後の力を振り絞って、言う。
「わ……らっ、て」
届いただろうか。わからない。ほとんど何も見えないけれど、微かに見える彼女の表情は笑っていた。涙でくしゃくしゃになっているけれど、確かに笑っていた。下手くそだ。全然上手く笑えていない。それでも、彼女は笑顔が似合う。
彼女との思い出が蘇ってきた。走馬灯とはこのことか。
色々あったけれど、前を向いて、笑うことができたのは、彼女のおかげだ。最後は感謝の言葉の方が良かったかな。それとも、好きってことを伝えた方が良かったのかもしれない。とにかく、彼女の笑顔を最後に見たい一心で口走ったけれど、相応しくなかったのかな。
もうどこに意識があるのかわからない。どこか遠く、俺の知らないところに意識が運ばれる。
目を覚ますと、見知らぬ真っ白な天井がそこにはあった。太ももの辺りに重みを感じる。
視線をやると、桜井萌笑がスヤスヤ寝ていた。
俺は助かったんだと気がついた。
車に轢かれて意識を失った記憶はあるけれど、断片的に覚えているだけでかなり曖昧なものだった。
「……ん?」
俺が動いたせいで、彼女を起こしてしまったようだ。
「おはよう」俺は優しく言った。
彼女は俺を一点に見つめ、静かに涙を流した。そして、破顔した。
「……おはよう。晴翔くん。寝坊助さんだね」
くしゃっと笑う彼女につられて、俺も笑みが溢れた。
これからは君を悲しい表情になんてさせない。だって、君には笑顔が一番似合うんだから。