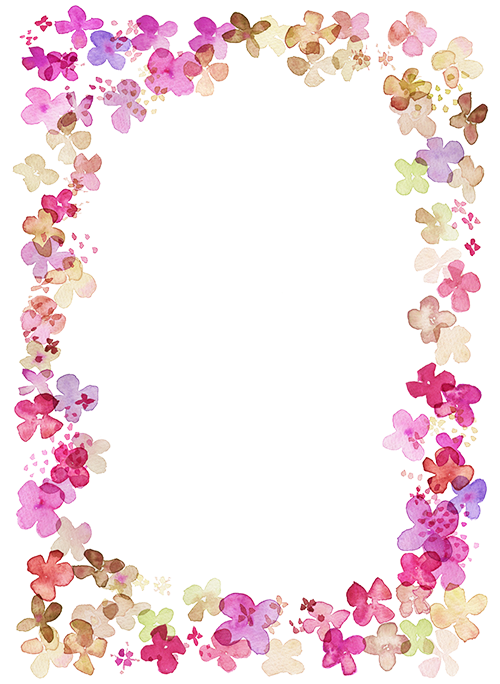よく晴れた真昼の空の下、俺はオープンカフェに来ていた。
「返事を聞かせてもらえますか?」
ランチの後、俺は同席している二人に恐る恐る問いかける。
俺の向かい側にはみことさんが座っている。涼しげな美人で、俺はこの人にみつめられると未だにどきどきする。
先日検察事務官から次席検事へと華麗に転身した彼女は、今後とも活躍が期待されるところだ。
みことさんはちらと横を見やった。
彼女の隣には彼女の前夫との息子である純君が足をぶらぶらさせながら座っている。純君は母親の視線の意味をすぐに察したようで、俺に向かって口を開いた。
「貴正おじさんは、お母さんをぶったりしない?」
みことさんの前夫は彼女に暴力を振るっていた。それは純君にとっても辛い記憶だ。
「絶対しない」
「お母さんをいじめない?」
「うん」
心配そうに問いかける純君に、俺は頷く。
「お母さんが誰かにいじめられてたら、庇ってくれる?」
八歳の純君は、その聡明な瞳で射抜くように俺をみつめる。
「僕、お母さんを一番大事にしてくれる人じゃなきゃ、認めないよ。本当は僕がお母さんを幸せにするんだって決めてたんだから」
俺はゆっくりと答えた。
「約束する。みことさんを一番大事にするよ」
純君はそれを聞いてにこっと笑った。
「じゃあ僕はいいよ。ね、お母さん」
振り向いた純君に、みことさんが微笑み返した。
「私は見ての通り若くもありませんし、純もお世話になりますが」
俺の心臓が高鳴る。
「それでよろしければ、プロポーズを受けさせてください」
俺は心の中で大きくガッツポーズをして、やったと叫んでいた。
午後に霧島教会に立ち寄ると、ちょうどミサが終わってパーティが開かれていた。
「やあ、貴正」
祭服をまとった神父がすぐさま俺をみつけて声をかけてくる。
「何かいいことでもあったかい?」
「よくわかったな」
「職業柄、人の心の機微を察することは得意でね」
「まあお前は神父以外の仕事はできないだろうがな」
「そうだね。これが私の天職だろう」
友人の向聖は朗らかに笑う。俺と同じでもう三十八だというのに、向聖は加齢の疲れが全く見えない。
「こんにちは」
「ああ、こんにちは。聖也君」
少年神父がそっと歩み寄って来て挨拶してきた。
「お久しぶりです。お元気でしたか?」
「うん。君も元気そうで何よりだ」
輝くようなブロンドを綺麗に結わえて、青い瞳はどこまでも澄み渡っている。この霧島教会の養親子の神父たちは、今日も静寂をまといながら光の中に存在していた。
時折挨拶にやってくる信者たちに答えながら、ふいに向聖は俺に言った。
「貴正、君には本当に感謝してるよ」
「なんだ、改まって」
「聖也君が虐待を受けていた時に、彼を保護して法的手段を取ってくれたおかげで、私と聖也君はここにいられるんだ」
向聖は目を伏せて告げる。
「君が間に入ってくれなかったら、私は聖也君の実父を許せなかった。報復を考えた」
「その緩衝材になるのが法だよ」
俺は軽く向聖の肩を叩く。
「そして俺たちの仕事だ。任せとけ」
友人の役に立つことができて、俺も嬉しかった。
「元々俺の事務所ではその手の分野が専門だからな」
「ある意味その関係で、みことさんと知り合えたようだしね」
みことさんの名前に、俺は柄でもなく赤面する。
「わかってるよ、貴正。何て言ってプロポーズしたんだい?」
「お、お前な。神父がそういうおじさんみたいなこと言うなよ」
「ふふ。私もそろそろいい年したおじさんだからね」
向聖が愉快そうに笑うと、聖也君もくすりと笑った。
「あ、シルバー」
聖也君はテーブルカバーを引っ張っている子猫を抱き上げて、めっと叱る。
「駄目だよ。もう、すぐ悪戯するんだから」
その拗ねたような顔には全然迫力がなくて、灰色の子猫は喉を鳴らして彼の頬に擦りよった。
「彼、教会の前に捨てられた子猫、全部拾っちゃうんじゃないかな」
「大丈夫。里親探しは私が責任もってするから」
向聖は微笑ましそうに聖也君を見やる。
「でもシルバーはうちで飼い続けようと思ってるよ。生きたものを愛するのもいいからね」
「生きた人間を愛するのも幸せだぞ。俺みたいにな」
俺が少しのろけると、向聖は穏やかに俺を見やる。
「君が幸せなのは、周りの人たちが少しずつ分けてくれた幸せのおかげだよ。だから彼女らを大事にしなければね」
「そうだな」
俺は頷き返す。俗世と離れたゆるやかな時が流れていく。
教会で休日を過ごすのもいいものだと思いながら、俺は向聖や聖也君と笑っていた。
日が落ちて夜が訪れようとしていた。俺は約束の時間に間に合うように、中心街の方に向かう。
球場の待ち合わせ場所に来たら、すぐにひときわ立派な体格を持つ男をみつけることができた。
「ねえ、おじさん。あれやってー」
「ああ」
百九十を超す長身の男が、袖を引いた純君を腕にぶら下げて回す。
みことさんの弟で、純君の叔父の海藤だ。
鋭い双眸は彼が警官であることを周囲に見せつけるようだが、純君を見る彼の目はとても穏やかだ。
「すごいすごい!」
きゃいきゃいとはしゃぐ純君に柔らかく笑う彼を見ていると、純君を彼以上にかわいがることのできる大人の男はいないだろうなと思う。
「あ」
純君が俺をみつけて顔を上げる。
「あのね、おじさん。貴正おじさんは僕のお父さんになるんだよ」
海藤は俺を気にいらなさそうに見やった。
「よう、海藤。遠慮なく義兄さんと呼んでくれ」
「一生呼ばん」
むっつりと顔を引き結んだ海藤に、後ろから飛びついて来た影があった。
「もーもちゃんっ! お待たせー」
茶髪の癖毛を揺らして、陽気な声を響かせる。
「その呼び方やめろ、陽介」
「えー、だって桃ちゃんの方がかわいいじゃん」
海藤の相棒で俺の弟の陽介だ。
「純君。ナイター楽しみだね。おじさん、何買ってあげようかなー」
「アイスがいい! アイス!」
気さくでいつもにこやかな陽介には、純君もよく懐いている。
「姉さんが弁当を作ってきてくれる。菓子ばかりじゃなくちゃんと食え、純」
「こらこら。お菓子くらいいいじゃない」
言葉を挟んだ海藤に、陽介は笑う。
「兄貴の顔を見るからに、おめでたい日だしね。やったね、兄貴」
「お前から祝いの言葉が出るとは思わなかったな」
海藤が意外そうに言う。
「ん、なんで?」
「お前、昔から氷牙にべったりだっただろうが」
「まあね。そりゃ本心から言えば、兄貴を取ってく奴は一息にやっちゃいたいくらいだよ」
物騒なと俺と海藤が眉を寄せると、陽介は苦笑する。
「でもしょうがないさ。俺はお巡りさんのお世話にはなりたくないもん。完全犯罪ができるっていうなら話は別だけど、そんなものないでしょ」
ぷっと笑って、陽介は頭をかく。
陽介は振り返って建物の影に声を投げる。
「兄貴以外を追いかけるのも案外面白いしさ。おーい、愛ちゃん何してんの。早くおいでよ」
「誰が愛ちゃんよ!」
ぷりぷりと頭から湯気を出しながら、すごい勢いで女性が駆けてくる。
「あんたね、私がどれだけ気まずい思いしながら来てるか全然わかってないじゃないの」
「そろそろ時効なんじゃない? ね、兄貴。許してやってよ」
検事としてエリートコースを突進している山根は、以前俺のストーカーをしていたことがある。いろいろ、彼女は走りだすと止まらない。
「いいよ、もう。十年近く前の話だし」
俺があっさりと言うと、山根は目を逸らす。
「悪かったわよ。ストーカーされる側になると、何かと見えてくるものもあったわ」
「愛ちゃん。誰がストーカーだって?」
陽介がひょいと後ろから腕を巻き付けると、愛理は食ってかかる。
「あんたよ! 大体何、年下のしがない平警官が私に釣り合うと思ってるの?」
「いや、ストーカー同士気が合うかと思って」
にやにや笑う陽介は楽しそうだった。
ふと思い出して、俺は言ってみる。
「そうだ、陽介。最近母さんには会ったか?」
「ん? そっとしておいてるよ」
「もう七十だしな。俺が引き取った方がいいんじゃないかと思って」
「あ、それ駄目」
陽介は肩をすくめて言う。
「母さんは一生同居するつもりないってさ。やっと兄貴が結婚する気になってくれたのに、姑が家にいると何かと難しいからって」
「はぁ」
「みことさんのことも気に入ってるみたいだし、早く孫の顔を見せてほしいって言ってたよ」
「母さんらしいな」
みことさんと知り合って十年以上になるというのに、四十前まで結婚しなかった息子を、母はもどかしく思っていたに違いない。
「あ、もうすぐ開始時間だよ」
みことさんは先に球場の中に入っている。
あれこれと言い合いながら、俺たちは連れ立ってナイターに向かった。
わいわいと賑やかな休日の夜だった。
試合が終わって、夜十時を回る頃になっていた。純君ははしゃぎまわって疲れたのが、舟をこいでいた。
「じゃあ俺たちは純を連れて帰るから」
「おやすみなさい」
海藤は純君をおぶって、みことさんと一緒に帰って行った。
「俺は愛ちゃんを送ってくよ」
「じゃあね」
陽介は山根と一緒に反対方向に向かう。
一人になると少し寂しさが訪れたが、俺の足取りは軽かった。
この時間になっても町はイルミネーションで華やいでいる。行きかう人々も、まだまだ眠らない。
駅前通りを歩いていて、ふと俺は人波の中に目を留める。
「パパ、ママ。ごはんおいしかったねー」
「そうね。みっちゃん、お残ししなかったものね」
「また行こうな」
外食帰りだろうか。小学生くらいの女の子の手を取って、仲の好さそうな夫婦が歩いていた。
その母親の方に見覚えがあって、俺は目を細める。
「でも私、ママのエビフライが一番好きー」
「あらあら」
優子は俺が大学生の頃に付き合っていた。大学の卒業と同時に別れたから、もうずいぶん顔を見ていなかった。
「ママ、からあげも得意なのよ。今度まとめて作ってあげましょうね」
「やった! パパ、ママがからあげ作るって」
「よかったな」
彼女と結婚していたら、俺にも今頃あれくらいの年の子どもがいただろうか。そんなことをふと思う。
通り過ぎていく優しい微笑みを見やって、俺は口の中で呟く。
「……おめでとう」
俺は確かに君のことが好きだったけど、君が幸せでいてくれることの方が嬉しい。今は素直にそう思うことができた。
駅の前まで来たら、そこには小さな人だかりができていた。
「メリークリスマス」
その中心で、サンタクロースの服を着た高校生ほどの少女が、シルクハットを片手にお辞儀をする。
「ごきげんよう、みなさん。私はテラ。こちらは相棒のホーラです」
「こんばんは。これから手品をお見せするよ」
腹話術なのか、シルクハットから少年の声が飛び出す。
「でも、テラ。手品をするには、道具を持ってないように見えるけど」
「いえいえ。私は何でも持っていますよ」
サンタ服の少女は、シルクハットの中に手を突っ込む。
「まず、灯り」
サイズ的に収まらないと思われる大きさのカンテラが、シルクハットから出てくる。
「防寒具」
これまたビッグサイズの毛布が出て来て、観客からどよめきが起こる。
「トランクだって入ってます」
年季の入った赤茶色のトランクを取り出して、少女はそれを地面に置く。
「でもあんまり使いませんね。ホーラがいれば何でも入りますから」
心地よい笑い声が満ちて、その中で彼女は俺を見た。
「時に、そちらの方。少しお手伝いをして頂けますか?」
「俺?」
自分を指さすと、サンタ服の少女は頷く。
「クリスマスにふさわしい笑顔の方ですから」
俺は他人にまでわかってしまうほど緩んだ顔をしているのかと、苦笑する。
「結婚が決まってね」
「おめでとうございます」
前に進み出て彼女のところまで来ると、サンタ服の少女はシルクハットの中に手を入れる。
「これで私の手を刺してみてください」
彼女が取り出したのはナイフだった。
手品の一環だと、俺はそれを受け取る。
瞬間、俺は時間が止まったような錯覚を覚えた。
懐かしい学生の頃の優子の姿が見えた。俺と付き合っていた頃によく着ていた、青いワンピースを身に着けていた。
優子の前に同い年くらいの、彼女に少し似た華やかな美貌の少女が立つ。
はっと息を呑む。
少女が優子の腹に刃を突き刺したのだ。
けれど血は流れることがなく、優子も何も感じていないようだった。
少女に気づかなかったように、何事もなく優子は去っていく。それを見送って、少女は微笑んだ。
「正しいものを貫いた。私は、正義の刃」
少女の姿は霧のように消えうせて行く。満足げに空を仰ぎながら。
……見たこともないのに、その少女がひどく懐かしい。
そんな幻想が目の前を通り過ぎる。
現在の自分を取り戻してナイフを見下ろす。なぜかその手は少し震えていた。幸せな過去の夢を見た時のように、目が少し涙で滲んだ。
「どうぞ」
サンタ服の少女は手を差し出したまま立っている。
「……ごめん。俺には刺せない」
彼女の手品を台無しにしてしまうとわかっていながら、俺は小声で口にしていた。
「そうでしょうね。あなたはとても優しい方のようですから」
サンタ服の少女はナイフを持った俺の手を上から包み込む。
ぽんっと弾けるような音がして、次の瞬間俺の腕に抱えきれないほどの花束が現れていた。
観客から拍手が湧きあがる。サンタ服の少女は笑顔でお辞儀をする。
その中で、俺は理由もわからず涙を落としていた。
手品が終わった後、サンタ服の少女はシルクハットに観客からお金を入れてもらっていた。
それがほどほどに落ち着いて散っていく観客の中で、俺はそっと彼女に歩み寄る。
「おや、さっきのおじさん」
シルクハットから少年の声が出る。サンタ服の少女は俺に背を向けて座っているのに、よくわかったものだと驚いた。
「手品は楽しんでもらえたかい? テラはプロの手品師じゃないし、ちょっとした余興だけどね」
「ああ、面白かったよ。君も大活躍だったな、ホーラ」
シルクハットの名前を呼ぶと、少年の声は得意げに返した。
「まあね。僕がいないとテラは旅が出来ないからね」
「君らは旅行者?」
「うん。仲間を集める旅をしてるのさ。おじさんもたくさん見たろ?」
「手品道具かい?」
「本来の使い道はどれも物騒だから、手品道具として使ってる方がいいよね」
おしゃべりな少年の顔が見えるように、シルクハットからは次々と言葉が飛び出す。
「たとえばおじさんに渡したナイフ。ここだけの話、あれは人を殺した者を一突きで殺せてしまう、すごい道具なんだよ」
「そりゃ怖い」
俺はふと、サンタ服の少女を見やる。
彼女は手品に使って道に散っている、カラーテープや花を集め終わったところだった。
「テラさん、だっけ。さっきのナイフだけど」
「ああ、この「正義の刃」ですか?」
彼女はベルトに挟んだナイフを手に取って俺に見せる。
俺はその何の変哲もないナイフを見下ろして、迷いながら言う。
「よければ、その……譲ってくれないか」
なんだかとても大事なものだった気がするのだ。初めて見るはずのものなのに、ひどく懐かしい。
テラさんはゆっくりと首を横に振る。
「できません。この刃も、私の大切な旅の仲間ですから」
「そう、だよな」
俺が目を伏せると、シルクハットから少年の声が言う。
「いいじゃん。おじさんにはそっちの方が似合ってるよ」
俺は腕の中の色とりどりの花束をみつめて黙った。
テラさんはシルクハットの中に元通りに手品道具を仕舞っていく。カンテラも毛布もトランクも、そしてナイフさえ吸い込まれるように中に消えていく。
「そういえば、あなたは検事でしたね」
「いや? 俺は弁護士だが」
「あ、そうでした」
スーツの上の弁護士バッチを見せると、テラさんは間違えたとばかりに頬をかいた。
「今のこの国で正しいことって何でしょう?」
俺は肩をすくめて苦笑した。
「それが決まっていれば、法も神も必要ないさ」
それに、テラさんはにっこりと微笑む。
「ではそろそろ出発しましょうか」
シルクハットだけ持って歩き出そうとする彼女に、俺は声をかける。
「あ、この花束は」
「差し上げますよ。ご結婚祝いです」
彼女は涼やかな笑い声を立てた。
「ハッピークリスマス。あなたにとっても幸せな時が、いつまでも続きますよう」
そう言って俺の横を通り過ぎる。
「いい時間だったね。誰も死ななくてさ」
「私は少し残念です」
困ったような口調で、彼女はシルクハットに返す。
「あのおいしいビールが二度と飲めないのだと思うと」
「あはっ! テラは食べ物のことばっかり」
彼女は本当にシルクハットと話しているようだった。
「皆さん、用意はいいですね?」
「いつでもいいよー」
「では参りますよ。次の時へ」
俺は何気なく振り返った。
一瞬だけ、シルクハットを被って燕尾服を着た、長い銀髪の少女の後ろ姿が見えた。
「チェックアウト」
パチンと指が鳴る音と共に、銀髪の少女の姿が消えうせる。
俺は一度瞬きをする。
しんとした静寂の中に、何か大きな哀しみが降ってきた。
舞い落ちる雪の中で、俺は立ちすくむ。
旅人はもういない。あるのは俺の現実だけ。幸せで大切な時間の中で、どこかで手放した何かがあったような、かすかな後悔。
でも俺は俺の時を生きていかなければいけない。俺は人間だから。
俺は花束を抱きしめると、家に向かって歩き出した。
「返事を聞かせてもらえますか?」
ランチの後、俺は同席している二人に恐る恐る問いかける。
俺の向かい側にはみことさんが座っている。涼しげな美人で、俺はこの人にみつめられると未だにどきどきする。
先日検察事務官から次席検事へと華麗に転身した彼女は、今後とも活躍が期待されるところだ。
みことさんはちらと横を見やった。
彼女の隣には彼女の前夫との息子である純君が足をぶらぶらさせながら座っている。純君は母親の視線の意味をすぐに察したようで、俺に向かって口を開いた。
「貴正おじさんは、お母さんをぶったりしない?」
みことさんの前夫は彼女に暴力を振るっていた。それは純君にとっても辛い記憶だ。
「絶対しない」
「お母さんをいじめない?」
「うん」
心配そうに問いかける純君に、俺は頷く。
「お母さんが誰かにいじめられてたら、庇ってくれる?」
八歳の純君は、その聡明な瞳で射抜くように俺をみつめる。
「僕、お母さんを一番大事にしてくれる人じゃなきゃ、認めないよ。本当は僕がお母さんを幸せにするんだって決めてたんだから」
俺はゆっくりと答えた。
「約束する。みことさんを一番大事にするよ」
純君はそれを聞いてにこっと笑った。
「じゃあ僕はいいよ。ね、お母さん」
振り向いた純君に、みことさんが微笑み返した。
「私は見ての通り若くもありませんし、純もお世話になりますが」
俺の心臓が高鳴る。
「それでよろしければ、プロポーズを受けさせてください」
俺は心の中で大きくガッツポーズをして、やったと叫んでいた。
午後に霧島教会に立ち寄ると、ちょうどミサが終わってパーティが開かれていた。
「やあ、貴正」
祭服をまとった神父がすぐさま俺をみつけて声をかけてくる。
「何かいいことでもあったかい?」
「よくわかったな」
「職業柄、人の心の機微を察することは得意でね」
「まあお前は神父以外の仕事はできないだろうがな」
「そうだね。これが私の天職だろう」
友人の向聖は朗らかに笑う。俺と同じでもう三十八だというのに、向聖は加齢の疲れが全く見えない。
「こんにちは」
「ああ、こんにちは。聖也君」
少年神父がそっと歩み寄って来て挨拶してきた。
「お久しぶりです。お元気でしたか?」
「うん。君も元気そうで何よりだ」
輝くようなブロンドを綺麗に結わえて、青い瞳はどこまでも澄み渡っている。この霧島教会の養親子の神父たちは、今日も静寂をまといながら光の中に存在していた。
時折挨拶にやってくる信者たちに答えながら、ふいに向聖は俺に言った。
「貴正、君には本当に感謝してるよ」
「なんだ、改まって」
「聖也君が虐待を受けていた時に、彼を保護して法的手段を取ってくれたおかげで、私と聖也君はここにいられるんだ」
向聖は目を伏せて告げる。
「君が間に入ってくれなかったら、私は聖也君の実父を許せなかった。報復を考えた」
「その緩衝材になるのが法だよ」
俺は軽く向聖の肩を叩く。
「そして俺たちの仕事だ。任せとけ」
友人の役に立つことができて、俺も嬉しかった。
「元々俺の事務所ではその手の分野が専門だからな」
「ある意味その関係で、みことさんと知り合えたようだしね」
みことさんの名前に、俺は柄でもなく赤面する。
「わかってるよ、貴正。何て言ってプロポーズしたんだい?」
「お、お前な。神父がそういうおじさんみたいなこと言うなよ」
「ふふ。私もそろそろいい年したおじさんだからね」
向聖が愉快そうに笑うと、聖也君もくすりと笑った。
「あ、シルバー」
聖也君はテーブルカバーを引っ張っている子猫を抱き上げて、めっと叱る。
「駄目だよ。もう、すぐ悪戯するんだから」
その拗ねたような顔には全然迫力がなくて、灰色の子猫は喉を鳴らして彼の頬に擦りよった。
「彼、教会の前に捨てられた子猫、全部拾っちゃうんじゃないかな」
「大丈夫。里親探しは私が責任もってするから」
向聖は微笑ましそうに聖也君を見やる。
「でもシルバーはうちで飼い続けようと思ってるよ。生きたものを愛するのもいいからね」
「生きた人間を愛するのも幸せだぞ。俺みたいにな」
俺が少しのろけると、向聖は穏やかに俺を見やる。
「君が幸せなのは、周りの人たちが少しずつ分けてくれた幸せのおかげだよ。だから彼女らを大事にしなければね」
「そうだな」
俺は頷き返す。俗世と離れたゆるやかな時が流れていく。
教会で休日を過ごすのもいいものだと思いながら、俺は向聖や聖也君と笑っていた。
日が落ちて夜が訪れようとしていた。俺は約束の時間に間に合うように、中心街の方に向かう。
球場の待ち合わせ場所に来たら、すぐにひときわ立派な体格を持つ男をみつけることができた。
「ねえ、おじさん。あれやってー」
「ああ」
百九十を超す長身の男が、袖を引いた純君を腕にぶら下げて回す。
みことさんの弟で、純君の叔父の海藤だ。
鋭い双眸は彼が警官であることを周囲に見せつけるようだが、純君を見る彼の目はとても穏やかだ。
「すごいすごい!」
きゃいきゃいとはしゃぐ純君に柔らかく笑う彼を見ていると、純君を彼以上にかわいがることのできる大人の男はいないだろうなと思う。
「あ」
純君が俺をみつけて顔を上げる。
「あのね、おじさん。貴正おじさんは僕のお父さんになるんだよ」
海藤は俺を気にいらなさそうに見やった。
「よう、海藤。遠慮なく義兄さんと呼んでくれ」
「一生呼ばん」
むっつりと顔を引き結んだ海藤に、後ろから飛びついて来た影があった。
「もーもちゃんっ! お待たせー」
茶髪の癖毛を揺らして、陽気な声を響かせる。
「その呼び方やめろ、陽介」
「えー、だって桃ちゃんの方がかわいいじゃん」
海藤の相棒で俺の弟の陽介だ。
「純君。ナイター楽しみだね。おじさん、何買ってあげようかなー」
「アイスがいい! アイス!」
気さくでいつもにこやかな陽介には、純君もよく懐いている。
「姉さんが弁当を作ってきてくれる。菓子ばかりじゃなくちゃんと食え、純」
「こらこら。お菓子くらいいいじゃない」
言葉を挟んだ海藤に、陽介は笑う。
「兄貴の顔を見るからに、おめでたい日だしね。やったね、兄貴」
「お前から祝いの言葉が出るとは思わなかったな」
海藤が意外そうに言う。
「ん、なんで?」
「お前、昔から氷牙にべったりだっただろうが」
「まあね。そりゃ本心から言えば、兄貴を取ってく奴は一息にやっちゃいたいくらいだよ」
物騒なと俺と海藤が眉を寄せると、陽介は苦笑する。
「でもしょうがないさ。俺はお巡りさんのお世話にはなりたくないもん。完全犯罪ができるっていうなら話は別だけど、そんなものないでしょ」
ぷっと笑って、陽介は頭をかく。
陽介は振り返って建物の影に声を投げる。
「兄貴以外を追いかけるのも案外面白いしさ。おーい、愛ちゃん何してんの。早くおいでよ」
「誰が愛ちゃんよ!」
ぷりぷりと頭から湯気を出しながら、すごい勢いで女性が駆けてくる。
「あんたね、私がどれだけ気まずい思いしながら来てるか全然わかってないじゃないの」
「そろそろ時効なんじゃない? ね、兄貴。許してやってよ」
検事としてエリートコースを突進している山根は、以前俺のストーカーをしていたことがある。いろいろ、彼女は走りだすと止まらない。
「いいよ、もう。十年近く前の話だし」
俺があっさりと言うと、山根は目を逸らす。
「悪かったわよ。ストーカーされる側になると、何かと見えてくるものもあったわ」
「愛ちゃん。誰がストーカーだって?」
陽介がひょいと後ろから腕を巻き付けると、愛理は食ってかかる。
「あんたよ! 大体何、年下のしがない平警官が私に釣り合うと思ってるの?」
「いや、ストーカー同士気が合うかと思って」
にやにや笑う陽介は楽しそうだった。
ふと思い出して、俺は言ってみる。
「そうだ、陽介。最近母さんには会ったか?」
「ん? そっとしておいてるよ」
「もう七十だしな。俺が引き取った方がいいんじゃないかと思って」
「あ、それ駄目」
陽介は肩をすくめて言う。
「母さんは一生同居するつもりないってさ。やっと兄貴が結婚する気になってくれたのに、姑が家にいると何かと難しいからって」
「はぁ」
「みことさんのことも気に入ってるみたいだし、早く孫の顔を見せてほしいって言ってたよ」
「母さんらしいな」
みことさんと知り合って十年以上になるというのに、四十前まで結婚しなかった息子を、母はもどかしく思っていたに違いない。
「あ、もうすぐ開始時間だよ」
みことさんは先に球場の中に入っている。
あれこれと言い合いながら、俺たちは連れ立ってナイターに向かった。
わいわいと賑やかな休日の夜だった。
試合が終わって、夜十時を回る頃になっていた。純君ははしゃぎまわって疲れたのが、舟をこいでいた。
「じゃあ俺たちは純を連れて帰るから」
「おやすみなさい」
海藤は純君をおぶって、みことさんと一緒に帰って行った。
「俺は愛ちゃんを送ってくよ」
「じゃあね」
陽介は山根と一緒に反対方向に向かう。
一人になると少し寂しさが訪れたが、俺の足取りは軽かった。
この時間になっても町はイルミネーションで華やいでいる。行きかう人々も、まだまだ眠らない。
駅前通りを歩いていて、ふと俺は人波の中に目を留める。
「パパ、ママ。ごはんおいしかったねー」
「そうね。みっちゃん、お残ししなかったものね」
「また行こうな」
外食帰りだろうか。小学生くらいの女の子の手を取って、仲の好さそうな夫婦が歩いていた。
その母親の方に見覚えがあって、俺は目を細める。
「でも私、ママのエビフライが一番好きー」
「あらあら」
優子は俺が大学生の頃に付き合っていた。大学の卒業と同時に別れたから、もうずいぶん顔を見ていなかった。
「ママ、からあげも得意なのよ。今度まとめて作ってあげましょうね」
「やった! パパ、ママがからあげ作るって」
「よかったな」
彼女と結婚していたら、俺にも今頃あれくらいの年の子どもがいただろうか。そんなことをふと思う。
通り過ぎていく優しい微笑みを見やって、俺は口の中で呟く。
「……おめでとう」
俺は確かに君のことが好きだったけど、君が幸せでいてくれることの方が嬉しい。今は素直にそう思うことができた。
駅の前まで来たら、そこには小さな人だかりができていた。
「メリークリスマス」
その中心で、サンタクロースの服を着た高校生ほどの少女が、シルクハットを片手にお辞儀をする。
「ごきげんよう、みなさん。私はテラ。こちらは相棒のホーラです」
「こんばんは。これから手品をお見せするよ」
腹話術なのか、シルクハットから少年の声が飛び出す。
「でも、テラ。手品をするには、道具を持ってないように見えるけど」
「いえいえ。私は何でも持っていますよ」
サンタ服の少女は、シルクハットの中に手を突っ込む。
「まず、灯り」
サイズ的に収まらないと思われる大きさのカンテラが、シルクハットから出てくる。
「防寒具」
これまたビッグサイズの毛布が出て来て、観客からどよめきが起こる。
「トランクだって入ってます」
年季の入った赤茶色のトランクを取り出して、少女はそれを地面に置く。
「でもあんまり使いませんね。ホーラがいれば何でも入りますから」
心地よい笑い声が満ちて、その中で彼女は俺を見た。
「時に、そちらの方。少しお手伝いをして頂けますか?」
「俺?」
自分を指さすと、サンタ服の少女は頷く。
「クリスマスにふさわしい笑顔の方ですから」
俺は他人にまでわかってしまうほど緩んだ顔をしているのかと、苦笑する。
「結婚が決まってね」
「おめでとうございます」
前に進み出て彼女のところまで来ると、サンタ服の少女はシルクハットの中に手を入れる。
「これで私の手を刺してみてください」
彼女が取り出したのはナイフだった。
手品の一環だと、俺はそれを受け取る。
瞬間、俺は時間が止まったような錯覚を覚えた。
懐かしい学生の頃の優子の姿が見えた。俺と付き合っていた頃によく着ていた、青いワンピースを身に着けていた。
優子の前に同い年くらいの、彼女に少し似た華やかな美貌の少女が立つ。
はっと息を呑む。
少女が優子の腹に刃を突き刺したのだ。
けれど血は流れることがなく、優子も何も感じていないようだった。
少女に気づかなかったように、何事もなく優子は去っていく。それを見送って、少女は微笑んだ。
「正しいものを貫いた。私は、正義の刃」
少女の姿は霧のように消えうせて行く。満足げに空を仰ぎながら。
……見たこともないのに、その少女がひどく懐かしい。
そんな幻想が目の前を通り過ぎる。
現在の自分を取り戻してナイフを見下ろす。なぜかその手は少し震えていた。幸せな過去の夢を見た時のように、目が少し涙で滲んだ。
「どうぞ」
サンタ服の少女は手を差し出したまま立っている。
「……ごめん。俺には刺せない」
彼女の手品を台無しにしてしまうとわかっていながら、俺は小声で口にしていた。
「そうでしょうね。あなたはとても優しい方のようですから」
サンタ服の少女はナイフを持った俺の手を上から包み込む。
ぽんっと弾けるような音がして、次の瞬間俺の腕に抱えきれないほどの花束が現れていた。
観客から拍手が湧きあがる。サンタ服の少女は笑顔でお辞儀をする。
その中で、俺は理由もわからず涙を落としていた。
手品が終わった後、サンタ服の少女はシルクハットに観客からお金を入れてもらっていた。
それがほどほどに落ち着いて散っていく観客の中で、俺はそっと彼女に歩み寄る。
「おや、さっきのおじさん」
シルクハットから少年の声が出る。サンタ服の少女は俺に背を向けて座っているのに、よくわかったものだと驚いた。
「手品は楽しんでもらえたかい? テラはプロの手品師じゃないし、ちょっとした余興だけどね」
「ああ、面白かったよ。君も大活躍だったな、ホーラ」
シルクハットの名前を呼ぶと、少年の声は得意げに返した。
「まあね。僕がいないとテラは旅が出来ないからね」
「君らは旅行者?」
「うん。仲間を集める旅をしてるのさ。おじさんもたくさん見たろ?」
「手品道具かい?」
「本来の使い道はどれも物騒だから、手品道具として使ってる方がいいよね」
おしゃべりな少年の顔が見えるように、シルクハットからは次々と言葉が飛び出す。
「たとえばおじさんに渡したナイフ。ここだけの話、あれは人を殺した者を一突きで殺せてしまう、すごい道具なんだよ」
「そりゃ怖い」
俺はふと、サンタ服の少女を見やる。
彼女は手品に使って道に散っている、カラーテープや花を集め終わったところだった。
「テラさん、だっけ。さっきのナイフだけど」
「ああ、この「正義の刃」ですか?」
彼女はベルトに挟んだナイフを手に取って俺に見せる。
俺はその何の変哲もないナイフを見下ろして、迷いながら言う。
「よければ、その……譲ってくれないか」
なんだかとても大事なものだった気がするのだ。初めて見るはずのものなのに、ひどく懐かしい。
テラさんはゆっくりと首を横に振る。
「できません。この刃も、私の大切な旅の仲間ですから」
「そう、だよな」
俺が目を伏せると、シルクハットから少年の声が言う。
「いいじゃん。おじさんにはそっちの方が似合ってるよ」
俺は腕の中の色とりどりの花束をみつめて黙った。
テラさんはシルクハットの中に元通りに手品道具を仕舞っていく。カンテラも毛布もトランクも、そしてナイフさえ吸い込まれるように中に消えていく。
「そういえば、あなたは検事でしたね」
「いや? 俺は弁護士だが」
「あ、そうでした」
スーツの上の弁護士バッチを見せると、テラさんは間違えたとばかりに頬をかいた。
「今のこの国で正しいことって何でしょう?」
俺は肩をすくめて苦笑した。
「それが決まっていれば、法も神も必要ないさ」
それに、テラさんはにっこりと微笑む。
「ではそろそろ出発しましょうか」
シルクハットだけ持って歩き出そうとする彼女に、俺は声をかける。
「あ、この花束は」
「差し上げますよ。ご結婚祝いです」
彼女は涼やかな笑い声を立てた。
「ハッピークリスマス。あなたにとっても幸せな時が、いつまでも続きますよう」
そう言って俺の横を通り過ぎる。
「いい時間だったね。誰も死ななくてさ」
「私は少し残念です」
困ったような口調で、彼女はシルクハットに返す。
「あのおいしいビールが二度と飲めないのだと思うと」
「あはっ! テラは食べ物のことばっかり」
彼女は本当にシルクハットと話しているようだった。
「皆さん、用意はいいですね?」
「いつでもいいよー」
「では参りますよ。次の時へ」
俺は何気なく振り返った。
一瞬だけ、シルクハットを被って燕尾服を着た、長い銀髪の少女の後ろ姿が見えた。
「チェックアウト」
パチンと指が鳴る音と共に、銀髪の少女の姿が消えうせる。
俺は一度瞬きをする。
しんとした静寂の中に、何か大きな哀しみが降ってきた。
舞い落ちる雪の中で、俺は立ちすくむ。
旅人はもういない。あるのは俺の現実だけ。幸せで大切な時間の中で、どこかで手放した何かがあったような、かすかな後悔。
でも俺は俺の時を生きていかなければいけない。俺は人間だから。
俺は花束を抱きしめると、家に向かって歩き出した。