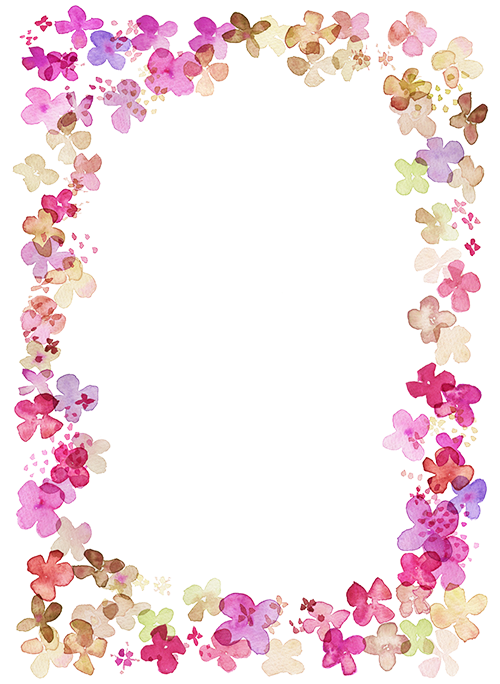俺は休日に仕事をしようとしても、全然進まないのが常だった。
「おとうさん。今お仕事してる?」
「いや、いいよ。入っておいで」
正子が戸口で顔を覗かせると、俺はもう正子と話すことに頭が切り替わってしまったから。
俺が振り向くと、正子はてくてくと歩いて来ていつものように俺の膝の上に座った。
「難しい漢字だ。読めないや」
デスクトップのパソコン画面を見て、正子は首をひねる。俺はその柔らかい髪の上に手を置いて笑う。
「仕方ない。正子にはまだ難しい」
「おとうさんはいつも難しいもの読んでる」
「それが仕事だからね」
正子はまんまるな目で俺を見上げる。
「おとうさんは検事なんだって、おかあさんが言ってた。どんなお仕事してるの?」
「悪いことをした人を法の前に連れて行って、罪を決めてもらう仕事だよ」
「悪いことってどんなこと?」
「そうだな……」
俺は正子を抱き上げて立ち上がると、本棚から一冊の本を手に取って、居間に向かった。
また正子を膝に乗せてコタツに入ると、俺は本を開く。
「これは刑法。悪いことが何か書いてある」
ページをめくって、俺はじっと本をみつめる正子に話しかける。
「246条、詐欺罪。人をだましてはいけません」
「うん」
「235条、窃盗罪。人の物をとってはいけません」
「どろぼうは、悪いこと」
正子は少し考えて顔を上げる。
「聖也君の本にも書いてあった。「You shall not steal.」」
正子はバイリンガルの聖也君と遊ぶうちに、簡単な英語は読めて理解できるようになっていた。
「そうだな。聖書でも、悪いことなんだよ」
「他には、どんなことが悪いこと?」
せかす正子に、俺はページをめくって続ける。
「231条、侮辱罪。人の悪口を言ってはいけません。204条、傷害罪。人を傷つけてはいけません」
噛み砕いて説明しながら条文をさかのぼっていって、俺は一つの罪の前でページをめくる手を止める。
「そして199条、殺人罪。人を殺してはいけません」
「「You shall not murder.」」
「一つの罪としては一番悪いことかもしれないな」
正子はくるりと振り向く。
「人を殺すとどうなるの?」
「刑務所に入れられる。それか、もっと悪い場合だと……」
俺は声を低めて告げる。
「死刑。罰として、命を取られる」
正子ははっとして青ざめる。
「どうしよう、人を殺しちゃったら。私も死刑?」
「正子はそんなことしない」
俺は正子を抱き上げてこちらを向かせる。
「怖がらなくて大丈夫だ。死刑は本当に最後の方法。めったにない」
「そっか」
正子はほっとしたように表情を緩めて、ぺとりと俺にくっついた。
「おとうさんは、人を殺したことある?」
子どもゆえの刃のように鋭い言葉に、俺は一瞬喉を詰まらせる。
「死刑を求めたことか? まだ無いな」
小さな頭を撫でながら俺は言う。
「だけどその時が来たら、怖いだろうな。きっと迷うだろう」
「どうしてそんな怖いことするの?」
「誰かがやらないといけないことだからだ」
俺は目を伏せる。
「法を守る者がいなくなったら、みんな罪を犯すようになる。弱い人から順番に傷つけられて、殺されてしまう。それは止めなければ」
「弱い人を守るの?」
「そう。みんなが安心して暮らせる世界を作る。おとうさんたちはそのための、正義の刃だ」
しばらく正子は俺にくっついたまま黙っていた。
正子は明るい元気な子だったが、時々じっと何かを考え込んでいることがある。今もそうだった。
「……おとうさん。私も検事になる」
ふいに正子は言う。
「大変だぞ。いっぱい勉強しなきゃいけない。検事になってからも、寝る時間もないくらい忙しい」
少し茶化した俺に、正子はきっぱりと返す。
「いっぱい勉強する。がんばって、たくさん働く」
顔を上げて、正子は透明に輝く瞳を俺に向けた。
「それで正義の刃になって、弱い人を守るの」
俺はふっと笑って、正子の頭を撫でた。
「いい子だな、正子は」
台所から、優子が昼ごはんの時間だと知らせる声が聞こえた。
よく正子を膝に乗せて入っていたコタツの前で、俺は膝を立てて座りこんでいた。
正子たちと暮らしていた昔のアパートに来て、そろそろ五時間が過ぎる。
辺りは既に真っ暗だったが、目が慣れてきたので物の輪郭は捉えられる。
テーブルの上のデジタル時計はぴかりと光って、夜十一時を示した。その瞬間に、もう一つテーブルに置いたものも光を反射する。
そこに置かれたものは一本の刃。ただの包丁にしか見えない。
向聖の命を奪った刃は、一般家庭にある包丁と変わりのないものだった。平凡な刃渡りで、細工も何もない、特徴のない刃物のようなものだ。
しかしそれが三十数人にも及ぶ殺人を犯してきた凶器だというなら、犯人は必ずこれを取りに来るはずだ。
いつまでも待つ覚悟がある。十年近く犯人を追ってきた俺に、その待ち時間など大したものではない。
……来い、と俺は念じる。
今まで奪われてきた命にかけて、俺はお前を捕まえる。
鍵を外す音が玄関から聞こえた。
俺は息を呑む。この家の鍵を持っている者は、今や俺ともう一人しかいない。
滑るように気配が近づいてきて、居間の入り口で止まった。暗闇の中でスイッチを探り、電気をつける。
「久しぶり」
光の中に浮かび上がったのは、華やかな美貌の少女だった。長く艶やかな黒髪に、白い頬、作りもののように整った目鼻立ちをしていて、すらりとした長身に黒いコートを羽織っていた。
印象的なのは目だった。みつめた者を委縮させてしまうほどの強い光を持った瞳で、彼女は俺を見た。
「また会えて嬉しい。お父さん」
しかしどれだけ時を経ても俺が正子を見間違えるはずがなかった。彼女はまぎれもなく、俺のたった一人の娘だった。
「俺もだ。こんな形でなければもっとな」
ふっと正子は微笑んだ。
「この家を警察が囲んでいるね。盗聴器もしかけてあるかな」
世間話のように正子は言って、あっさりとコタツの向かい側に腰を下ろす。
「まあいいよ。刃を使えば時は止まる」
光を内蔵したような目を、正子は細める。
「どの道、生きられるのは一人だ。私か、お父さんか」
「俺はお前を刺さない」
「いずれ刺す。法の刃で」
迷わずその言葉を口にする。彼女の目に恐れは少しも見えなかった。
「構わない。私は法に反した。罪を問われるだけのことはしてきた」
正子はテーブルの中心に置かれた刃とデジタル時計を見やる。
「クリスマスまであと一時間だね。あれから十年か」
事件の日から、ちょうど十年になる。
時計と刃を間に、俺たちは向かい合った。
俺は正子をみつめながら、口を開く。
「正子。「人を殺した者」を次々に殺していったのはお前か?」
「そうだよ」
正子は目を逸らさずに頷く。
「山根を、陽介を、みことさんを殺したのも?」
「それも私」
「そして」
俺は床に手をついて言う。
「十年前にこの家で母さんを、お前のおばあちゃんを殺したのもお前なのか?」
正子は顎を引いた。
「私が殺した」
「なぜ!」
俺はギッと正子を睨む。
「母さんはお前をかわいがっていた。お前も母さんを慕っていたじゃないか」
「うん」
「だったらどうして」
正子は綺麗な黒の双眸で俺をみつめて言う。
「この家には魔物が住んでいたから」
正子は淡々と告げる。
「魔物が母を殺した。山根愛理の脅迫だけじゃない。母の自殺の原因の半分は、この家に住む魔物だった」
「魔物だと?」
「名前を氷牙麗子という。あなたの母で私の祖母だ」
困惑する俺に、正子は俺が考えもしなかったことを告げた。
「祖母は母をいじめていたんだよ。言葉の刃で、繰り返し母を貫いた」
「そんなこと……」
「あなたは嫁としてふさわしくない。なぜこんな下手な料理しかできない。あなたが来てから家が暗くなった」
「母さんはそんなことを言わない!」
「「出来た人だった。人格者だった」?」
正子は口の端を上げたが、少しも目が笑っていなかった。
「世間に、あなたに、私にとってはそうだったね。でも母にとっては違う。あの人はあなたを自分のものだと信じていた。子どもが出来ただけで家に上がり込んだ女を、心の底から疎んでいたよ」
「嘘を言うな。お前は母さんが嫌いだったのか?」
「信じないだろうね、お父さんは。十年前もそうだった」
正子は探るように俺の目を覗き込む。
「私は何度もあなたに言った。「おばあちゃんがおかあさんをいじめている」と。でもあなたは信じなかったね」
「それは……」
記憶に微かに引っ掛かりを感じて俺は言葉につまる。確かに、正子がそんなことを言っていたことがあった。
でも俺は笑って相手にしなかった。子どもの言葉遊びと甘く見ていたかもしれない。
「あなたが信じようと信じまいと、現実にいじめはあったんだ。けれど母は助けを求めることができなかった。出て行くこともできなかった。自分がいなくなったら娘の私にあの人の矛先が向くと思っていた」
静寂が満ちる。まるで世界には俺と正子二人だけしかいないかのように、正子の声以外何も聞こえない。
「やがて、魔物は母に死ぬようにと繰り返すようになった。孫の正子は私も大切だ、けれどあなたはこの家に要らないのだと」
俺はもう言葉を挟むことができない。次第に険しくなる正子の目から、目を逸らすことができない。
「そして十年前のクリスマス。私が家に帰ったら、母は自分で胸を刺して死んでいた」
息を呑んだ俺に、正子は思い出すように目を細める。
「母は弱くて、優しい人だった。大好きだった。誰にも刃を向けない、女神のような人だった」
正子にとって、彼女は信仰に近かったのかもしれなかった。
「私はそれからのことを考えていた。もう少ししたら祖母が帰ってくる。彼女は良き姑の顔をして母の死を悼む。そしてお父さんが帰ってきたら、悲しむかもしれないがいずれ忘れる。世間の人は、ありふれた自殺だと相手にもしないだろう」
正子は自分の手に目を落とした。
「祖母は人を殺したのに何の罰も与えられない。人にとって一番重いはずの命を奪ったのに、法に反していないだけで無罪だ」
正子の黒い瞳が、目の前の俺を飲みこむように動いた。
ぐっと手を握り締めて、正子は告げる。
「……赦すものか。誰も裁かないのなら、私が裁く。そう決めた」
俺は乾いた喉に息を通して、掠れた声を出した。
「殺すことはなかった」
「祖母より母を信じる人がどこにいた?」
正子は強く唇を噛む。
「夫のあなたさえ母より祖母を信じたに違いないのに?」
否定の言葉は出て来なかった。確かに、正子の言う通りだった。もし優子に相談されたとしても、俺は母を庇ったに違いなかった。
「あなたと私は共犯だよ、お父さん。私たちは家族を守るために、この家で一番弱い人を見殺しにしたんだ」
「もし……お前が言っていることが本当だとしても」
俺は正子に気圧されそうになりながら言う。
「お前は姿を現してすべて話すべきだった」
「五年前に覚悟を決めたんだ。私は誰に許されなくても構わない。法にも、神にも、あなたにさえ」
正子は一点の曇りもない澄んだ目で俺を見る。
「誰も命を奪われない、みんなが安心して暮らせる世界を作る。声なき弱者を、私は守ってみせる」
助けを求めることもできずに死んでいった優子のような存在を、二度と作ることがないようにと願ったのだろうか。
「あなたは法を守ればいい。聖也君は神の言葉で人々を救えばいい。私はそれで取りこぼされる命を守る」
正子の手がテーブルの上の刃に伸びる。
「……駄目だ、正子」
俺はその手を握って止める。
「お前はその刃を握ってはいけない。もう、殺すな」
ずっと掴みたかった正子の手を、俺は悲しい思いで握りしめる。
「刃は俺が自分の胸に突き付けたまま一生持ち続ける。簡単に人を殺せてしまえるような悪魔の道具は、この世に要らないんだ」
俺は正子をみつめて言う。
「だからお前は戻ってくるんだ。人の世界に。……戻って来てくれ」
十年前の事件の日、俺はこの家に三十分早く帰ってこれば正子に会うことができた。たった三十分だ。その時が帰って来たのなら、俺は何をしてでも正子を止めた。
「お前は誰も殺すべきじゃなかった。お前を止められなかった俺も同罪だ。一生かけて一緒に償う」
「あなたは私が間違っていたと言うの?」
「そうだ」
断定した俺に、正子の手がぴくりと動いた。
「人を殺した者だとしても、刃を向けてはいけない」
俺の言葉に、正子がつと息を呑む気配がした。
「母さんが優子を死に追いやったのだとしても、それは死という方法以外で償わせるべきだったんだ」
「……あなたは」
正子の目から光が消えうせる。
「母の命の重みをわかっていない」
「お前の祖母も同じ命の重みがあるんだ。奪ってはいけなかった」
「違う。あなたにとっては母より祖母の命の方が重いんだ」
失望のため息をついて、正子は目を伏せる。
「私はもういいんだ、お父さん」
次の瞬間、正子の目を暗黒が支配した。
俺の手を振り払って、正子は両手で刃を手に取る。
「……でもお母さんの命を否定するのは、許せない」
力いっぱい、正子は俺の胸に刃を突き刺した。
激痛と共に息ができなくなる。
「な……これは、「正義の刃」じゃない!」
刃を握り締めてうろたえた正子の手を、俺は両手で掴む。
「俺は、お前に教えてやらなきゃいけなかった……」
一撃で死にはしなかった。だがこの怪我では長くはもたないだろう。
「どんな大義があっても……人に刃を向けた瞬間……それはもう正義じゃなくなるんだ……」
俺の持っていた法の刃でさえ、人に向けたらもはや正義とはいえないのだ。
正子は俺に手を掴まれたまま震える。彼女は普通の刃で人を貫いたことはなかったのだ。
「わかるか? これが人を刺すってことだ……。瞬間的に心臓が止まるような都合のいいものじゃない……。痛みと苦しみの中で、死んでいく……」
人に刃を向けることがどういうことか、俺は正子に教える。正子にこれ以上誰かを殺させないために、止めるために。
血を吐きだして、俺は床に倒れる。
「正子」
俺は霞んでいく視界の中で、たった一人の娘を見上げる。
「おとうさんは、誰より、お前を愛している……よ」
目が見えなくなっていく。体から、血が溢れだしていく。
「嫌ぁ!」
正子が悲鳴のような声を上げた。
「おとうさん、おとうさんっ! 死んじゃだめ、嫌ぁ!」
俺の頬に正子の涙が落ちるのを感じた。
「どうして。私はただ、誰にも死んでほしくなかっただけなのに!」
正子は声を震わせた。
「おばあちゃんも、おかあさんも、おとうさんも、みんな幸せに生きられる世界にしたかっただけなのに!」
俺はもう正子の顔を見ることもできなかった。ただ手を伸ばした。
「……わかって、る」
お前は人一倍正義感が強くて、誰より優しい子だと知っている。
「お前は、いい子、だ……」
だから、もう苦しんでほしくない。幸せに生きてほしい。
俺の体はもう限界だった。
体が沈んでいくような気がする。正子の姿も声も、何もかもが消えていく。
ああ俺は死ぬのか。静かな心で思った時だった。
暗闇の中で何かが光った。奇妙に鮮明に、デジタル時計が見えた。
ちょうど零時ぴったりで、時計が止まった。同時に声が聞こえた。
「時間ですね」
いつかのシルクハットの旅行者の声だった。
「あなたが何者か、わかりましたか?」
旅行者が、誰かに話しかけている声だけが響いていた。
「そう。ならば、あなたが貫くものが何かもわかりましたね?」
満足そうに、旅行者が頷く気配がした。
「では、参りましょうか。あなたにとって最初で最後の時に」
眩しいばかりの光が辺りを包み込んだ。
「おとうさん。今お仕事してる?」
「いや、いいよ。入っておいで」
正子が戸口で顔を覗かせると、俺はもう正子と話すことに頭が切り替わってしまったから。
俺が振り向くと、正子はてくてくと歩いて来ていつものように俺の膝の上に座った。
「難しい漢字だ。読めないや」
デスクトップのパソコン画面を見て、正子は首をひねる。俺はその柔らかい髪の上に手を置いて笑う。
「仕方ない。正子にはまだ難しい」
「おとうさんはいつも難しいもの読んでる」
「それが仕事だからね」
正子はまんまるな目で俺を見上げる。
「おとうさんは検事なんだって、おかあさんが言ってた。どんなお仕事してるの?」
「悪いことをした人を法の前に連れて行って、罪を決めてもらう仕事だよ」
「悪いことってどんなこと?」
「そうだな……」
俺は正子を抱き上げて立ち上がると、本棚から一冊の本を手に取って、居間に向かった。
また正子を膝に乗せてコタツに入ると、俺は本を開く。
「これは刑法。悪いことが何か書いてある」
ページをめくって、俺はじっと本をみつめる正子に話しかける。
「246条、詐欺罪。人をだましてはいけません」
「うん」
「235条、窃盗罪。人の物をとってはいけません」
「どろぼうは、悪いこと」
正子は少し考えて顔を上げる。
「聖也君の本にも書いてあった。「You shall not steal.」」
正子はバイリンガルの聖也君と遊ぶうちに、簡単な英語は読めて理解できるようになっていた。
「そうだな。聖書でも、悪いことなんだよ」
「他には、どんなことが悪いこと?」
せかす正子に、俺はページをめくって続ける。
「231条、侮辱罪。人の悪口を言ってはいけません。204条、傷害罪。人を傷つけてはいけません」
噛み砕いて説明しながら条文をさかのぼっていって、俺は一つの罪の前でページをめくる手を止める。
「そして199条、殺人罪。人を殺してはいけません」
「「You shall not murder.」」
「一つの罪としては一番悪いことかもしれないな」
正子はくるりと振り向く。
「人を殺すとどうなるの?」
「刑務所に入れられる。それか、もっと悪い場合だと……」
俺は声を低めて告げる。
「死刑。罰として、命を取られる」
正子ははっとして青ざめる。
「どうしよう、人を殺しちゃったら。私も死刑?」
「正子はそんなことしない」
俺は正子を抱き上げてこちらを向かせる。
「怖がらなくて大丈夫だ。死刑は本当に最後の方法。めったにない」
「そっか」
正子はほっとしたように表情を緩めて、ぺとりと俺にくっついた。
「おとうさんは、人を殺したことある?」
子どもゆえの刃のように鋭い言葉に、俺は一瞬喉を詰まらせる。
「死刑を求めたことか? まだ無いな」
小さな頭を撫でながら俺は言う。
「だけどその時が来たら、怖いだろうな。きっと迷うだろう」
「どうしてそんな怖いことするの?」
「誰かがやらないといけないことだからだ」
俺は目を伏せる。
「法を守る者がいなくなったら、みんな罪を犯すようになる。弱い人から順番に傷つけられて、殺されてしまう。それは止めなければ」
「弱い人を守るの?」
「そう。みんなが安心して暮らせる世界を作る。おとうさんたちはそのための、正義の刃だ」
しばらく正子は俺にくっついたまま黙っていた。
正子は明るい元気な子だったが、時々じっと何かを考え込んでいることがある。今もそうだった。
「……おとうさん。私も検事になる」
ふいに正子は言う。
「大変だぞ。いっぱい勉強しなきゃいけない。検事になってからも、寝る時間もないくらい忙しい」
少し茶化した俺に、正子はきっぱりと返す。
「いっぱい勉強する。がんばって、たくさん働く」
顔を上げて、正子は透明に輝く瞳を俺に向けた。
「それで正義の刃になって、弱い人を守るの」
俺はふっと笑って、正子の頭を撫でた。
「いい子だな、正子は」
台所から、優子が昼ごはんの時間だと知らせる声が聞こえた。
よく正子を膝に乗せて入っていたコタツの前で、俺は膝を立てて座りこんでいた。
正子たちと暮らしていた昔のアパートに来て、そろそろ五時間が過ぎる。
辺りは既に真っ暗だったが、目が慣れてきたので物の輪郭は捉えられる。
テーブルの上のデジタル時計はぴかりと光って、夜十一時を示した。その瞬間に、もう一つテーブルに置いたものも光を反射する。
そこに置かれたものは一本の刃。ただの包丁にしか見えない。
向聖の命を奪った刃は、一般家庭にある包丁と変わりのないものだった。平凡な刃渡りで、細工も何もない、特徴のない刃物のようなものだ。
しかしそれが三十数人にも及ぶ殺人を犯してきた凶器だというなら、犯人は必ずこれを取りに来るはずだ。
いつまでも待つ覚悟がある。十年近く犯人を追ってきた俺に、その待ち時間など大したものではない。
……来い、と俺は念じる。
今まで奪われてきた命にかけて、俺はお前を捕まえる。
鍵を外す音が玄関から聞こえた。
俺は息を呑む。この家の鍵を持っている者は、今や俺ともう一人しかいない。
滑るように気配が近づいてきて、居間の入り口で止まった。暗闇の中でスイッチを探り、電気をつける。
「久しぶり」
光の中に浮かび上がったのは、華やかな美貌の少女だった。長く艶やかな黒髪に、白い頬、作りもののように整った目鼻立ちをしていて、すらりとした長身に黒いコートを羽織っていた。
印象的なのは目だった。みつめた者を委縮させてしまうほどの強い光を持った瞳で、彼女は俺を見た。
「また会えて嬉しい。お父さん」
しかしどれだけ時を経ても俺が正子を見間違えるはずがなかった。彼女はまぎれもなく、俺のたった一人の娘だった。
「俺もだ。こんな形でなければもっとな」
ふっと正子は微笑んだ。
「この家を警察が囲んでいるね。盗聴器もしかけてあるかな」
世間話のように正子は言って、あっさりとコタツの向かい側に腰を下ろす。
「まあいいよ。刃を使えば時は止まる」
光を内蔵したような目を、正子は細める。
「どの道、生きられるのは一人だ。私か、お父さんか」
「俺はお前を刺さない」
「いずれ刺す。法の刃で」
迷わずその言葉を口にする。彼女の目に恐れは少しも見えなかった。
「構わない。私は法に反した。罪を問われるだけのことはしてきた」
正子はテーブルの中心に置かれた刃とデジタル時計を見やる。
「クリスマスまであと一時間だね。あれから十年か」
事件の日から、ちょうど十年になる。
時計と刃を間に、俺たちは向かい合った。
俺は正子をみつめながら、口を開く。
「正子。「人を殺した者」を次々に殺していったのはお前か?」
「そうだよ」
正子は目を逸らさずに頷く。
「山根を、陽介を、みことさんを殺したのも?」
「それも私」
「そして」
俺は床に手をついて言う。
「十年前にこの家で母さんを、お前のおばあちゃんを殺したのもお前なのか?」
正子は顎を引いた。
「私が殺した」
「なぜ!」
俺はギッと正子を睨む。
「母さんはお前をかわいがっていた。お前も母さんを慕っていたじゃないか」
「うん」
「だったらどうして」
正子は綺麗な黒の双眸で俺をみつめて言う。
「この家には魔物が住んでいたから」
正子は淡々と告げる。
「魔物が母を殺した。山根愛理の脅迫だけじゃない。母の自殺の原因の半分は、この家に住む魔物だった」
「魔物だと?」
「名前を氷牙麗子という。あなたの母で私の祖母だ」
困惑する俺に、正子は俺が考えもしなかったことを告げた。
「祖母は母をいじめていたんだよ。言葉の刃で、繰り返し母を貫いた」
「そんなこと……」
「あなたは嫁としてふさわしくない。なぜこんな下手な料理しかできない。あなたが来てから家が暗くなった」
「母さんはそんなことを言わない!」
「「出来た人だった。人格者だった」?」
正子は口の端を上げたが、少しも目が笑っていなかった。
「世間に、あなたに、私にとってはそうだったね。でも母にとっては違う。あの人はあなたを自分のものだと信じていた。子どもが出来ただけで家に上がり込んだ女を、心の底から疎んでいたよ」
「嘘を言うな。お前は母さんが嫌いだったのか?」
「信じないだろうね、お父さんは。十年前もそうだった」
正子は探るように俺の目を覗き込む。
「私は何度もあなたに言った。「おばあちゃんがおかあさんをいじめている」と。でもあなたは信じなかったね」
「それは……」
記憶に微かに引っ掛かりを感じて俺は言葉につまる。確かに、正子がそんなことを言っていたことがあった。
でも俺は笑って相手にしなかった。子どもの言葉遊びと甘く見ていたかもしれない。
「あなたが信じようと信じまいと、現実にいじめはあったんだ。けれど母は助けを求めることができなかった。出て行くこともできなかった。自分がいなくなったら娘の私にあの人の矛先が向くと思っていた」
静寂が満ちる。まるで世界には俺と正子二人だけしかいないかのように、正子の声以外何も聞こえない。
「やがて、魔物は母に死ぬようにと繰り返すようになった。孫の正子は私も大切だ、けれどあなたはこの家に要らないのだと」
俺はもう言葉を挟むことができない。次第に険しくなる正子の目から、目を逸らすことができない。
「そして十年前のクリスマス。私が家に帰ったら、母は自分で胸を刺して死んでいた」
息を呑んだ俺に、正子は思い出すように目を細める。
「母は弱くて、優しい人だった。大好きだった。誰にも刃を向けない、女神のような人だった」
正子にとって、彼女は信仰に近かったのかもしれなかった。
「私はそれからのことを考えていた。もう少ししたら祖母が帰ってくる。彼女は良き姑の顔をして母の死を悼む。そしてお父さんが帰ってきたら、悲しむかもしれないがいずれ忘れる。世間の人は、ありふれた自殺だと相手にもしないだろう」
正子は自分の手に目を落とした。
「祖母は人を殺したのに何の罰も与えられない。人にとって一番重いはずの命を奪ったのに、法に反していないだけで無罪だ」
正子の黒い瞳が、目の前の俺を飲みこむように動いた。
ぐっと手を握り締めて、正子は告げる。
「……赦すものか。誰も裁かないのなら、私が裁く。そう決めた」
俺は乾いた喉に息を通して、掠れた声を出した。
「殺すことはなかった」
「祖母より母を信じる人がどこにいた?」
正子は強く唇を噛む。
「夫のあなたさえ母より祖母を信じたに違いないのに?」
否定の言葉は出て来なかった。確かに、正子の言う通りだった。もし優子に相談されたとしても、俺は母を庇ったに違いなかった。
「あなたと私は共犯だよ、お父さん。私たちは家族を守るために、この家で一番弱い人を見殺しにしたんだ」
「もし……お前が言っていることが本当だとしても」
俺は正子に気圧されそうになりながら言う。
「お前は姿を現してすべて話すべきだった」
「五年前に覚悟を決めたんだ。私は誰に許されなくても構わない。法にも、神にも、あなたにさえ」
正子は一点の曇りもない澄んだ目で俺を見る。
「誰も命を奪われない、みんなが安心して暮らせる世界を作る。声なき弱者を、私は守ってみせる」
助けを求めることもできずに死んでいった優子のような存在を、二度と作ることがないようにと願ったのだろうか。
「あなたは法を守ればいい。聖也君は神の言葉で人々を救えばいい。私はそれで取りこぼされる命を守る」
正子の手がテーブルの上の刃に伸びる。
「……駄目だ、正子」
俺はその手を握って止める。
「お前はその刃を握ってはいけない。もう、殺すな」
ずっと掴みたかった正子の手を、俺は悲しい思いで握りしめる。
「刃は俺が自分の胸に突き付けたまま一生持ち続ける。簡単に人を殺せてしまえるような悪魔の道具は、この世に要らないんだ」
俺は正子をみつめて言う。
「だからお前は戻ってくるんだ。人の世界に。……戻って来てくれ」
十年前の事件の日、俺はこの家に三十分早く帰ってこれば正子に会うことができた。たった三十分だ。その時が帰って来たのなら、俺は何をしてでも正子を止めた。
「お前は誰も殺すべきじゃなかった。お前を止められなかった俺も同罪だ。一生かけて一緒に償う」
「あなたは私が間違っていたと言うの?」
「そうだ」
断定した俺に、正子の手がぴくりと動いた。
「人を殺した者だとしても、刃を向けてはいけない」
俺の言葉に、正子がつと息を呑む気配がした。
「母さんが優子を死に追いやったのだとしても、それは死という方法以外で償わせるべきだったんだ」
「……あなたは」
正子の目から光が消えうせる。
「母の命の重みをわかっていない」
「お前の祖母も同じ命の重みがあるんだ。奪ってはいけなかった」
「違う。あなたにとっては母より祖母の命の方が重いんだ」
失望のため息をついて、正子は目を伏せる。
「私はもういいんだ、お父さん」
次の瞬間、正子の目を暗黒が支配した。
俺の手を振り払って、正子は両手で刃を手に取る。
「……でもお母さんの命を否定するのは、許せない」
力いっぱい、正子は俺の胸に刃を突き刺した。
激痛と共に息ができなくなる。
「な……これは、「正義の刃」じゃない!」
刃を握り締めてうろたえた正子の手を、俺は両手で掴む。
「俺は、お前に教えてやらなきゃいけなかった……」
一撃で死にはしなかった。だがこの怪我では長くはもたないだろう。
「どんな大義があっても……人に刃を向けた瞬間……それはもう正義じゃなくなるんだ……」
俺の持っていた法の刃でさえ、人に向けたらもはや正義とはいえないのだ。
正子は俺に手を掴まれたまま震える。彼女は普通の刃で人を貫いたことはなかったのだ。
「わかるか? これが人を刺すってことだ……。瞬間的に心臓が止まるような都合のいいものじゃない……。痛みと苦しみの中で、死んでいく……」
人に刃を向けることがどういうことか、俺は正子に教える。正子にこれ以上誰かを殺させないために、止めるために。
血を吐きだして、俺は床に倒れる。
「正子」
俺は霞んでいく視界の中で、たった一人の娘を見上げる。
「おとうさんは、誰より、お前を愛している……よ」
目が見えなくなっていく。体から、血が溢れだしていく。
「嫌ぁ!」
正子が悲鳴のような声を上げた。
「おとうさん、おとうさんっ! 死んじゃだめ、嫌ぁ!」
俺の頬に正子の涙が落ちるのを感じた。
「どうして。私はただ、誰にも死んでほしくなかっただけなのに!」
正子は声を震わせた。
「おばあちゃんも、おかあさんも、おとうさんも、みんな幸せに生きられる世界にしたかっただけなのに!」
俺はもう正子の顔を見ることもできなかった。ただ手を伸ばした。
「……わかって、る」
お前は人一倍正義感が強くて、誰より優しい子だと知っている。
「お前は、いい子、だ……」
だから、もう苦しんでほしくない。幸せに生きてほしい。
俺の体はもう限界だった。
体が沈んでいくような気がする。正子の姿も声も、何もかもが消えていく。
ああ俺は死ぬのか。静かな心で思った時だった。
暗闇の中で何かが光った。奇妙に鮮明に、デジタル時計が見えた。
ちょうど零時ぴったりで、時計が止まった。同時に声が聞こえた。
「時間ですね」
いつかのシルクハットの旅行者の声だった。
「あなたが何者か、わかりましたか?」
旅行者が、誰かに話しかけている声だけが響いていた。
「そう。ならば、あなたが貫くものが何かもわかりましたね?」
満足そうに、旅行者が頷く気配がした。
「では、参りましょうか。あなたにとって最初で最後の時に」
眩しいばかりの光が辺りを包み込んだ。