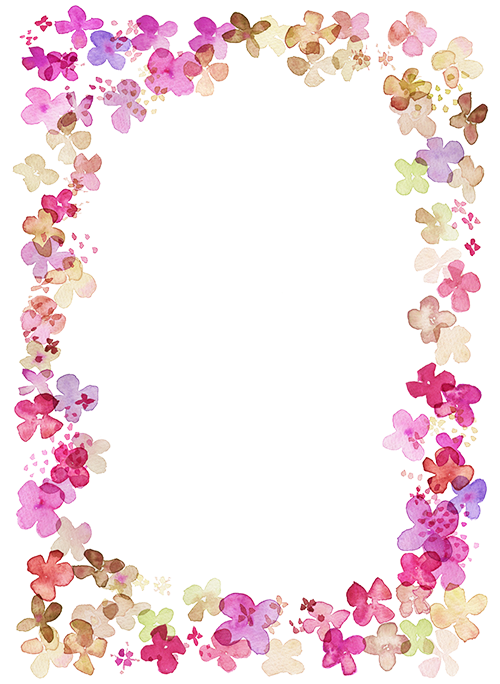正子と思われる少女の映像を見て一番に抱いた感情は、やはり嬉しさだった。
思いだすのは十八年前のことだった。俺はまだ二十歳の、法学部の大学生だった。
当時付き合っていた優子との間に子どもが出来たと知って、俺は優子との結婚を決めた。
実を言えばその頃まで、俺と優子の付き合いはそんなに真剣なものじゃなかった。俺は優子のことを好きではあったが将来のことを真面目に話したこともなく、大学を卒業したら別れるかもしれないとも思っていた。
けれど責任を取るつもりで結婚をして、半年が過ぎて正子は生まれた。
……その時、今の俺もまた生まれたのだ。
小さな温もりを持った赤ん坊の正子を抱いた時、俺の中で何かが変わった気がした。
家族も妻ももちろん大切だったが、正子に抱いた鮮烈な感情とは違う。
心の底から愛おしいと思ったのは初めてだった。
彼女に誇れる父親になると決意した。必死で勉強して試験に合格して、検事になった。たぶん正子がいなければ検事の道を志すこともなかった。
正子がいなくなって、俺の人生を照らしてくれていた光がついえたように思えた。その光がもう一度蘇るというのだから、嬉しくないはずがない。
だがここに来て、警察の捜査線上に犯人として正子の名が浮かび上がった。
身柄を拘束されている向聖より、行方不明の正子の方が数々の殺人事件の引き金をひける。そして十年前の家族以外の痕跡がない妻と母の殺人事件でも、正子なら犯行を行うことができるのだ。
俺は信じられなかった。正子以外の犯人を求めた。
マスコミでは産婦人科での大量殺人事件が大きく取り上げられていた。新たに警察が正義の刃事件に加えた俺の家族の事件も再び報道されて、その中には正子の犯行を疑うものもあった。
「貴正、待ってくれ」
向聖の初公判は明日に迫っていた。彼は相変わらず落ち着いていたが、面会に行ったら珍しく自ら俺を引きとめた。
「聖也君に手紙を届けてくれないか。大丈夫、警察のチェックは通ってる」
振り向くと、警官も頷いた。俺は向聖から白い封筒を受け取る。
「私のことは心配要らない、無理に公判に来なくていいから、ゆっくり体を休めるようにと伝えてくれ」
「どうかしたのか?」
「昨日、聖也君が倒れたそうなんだ」
俺は知らなかったので、思わず眉をひそめる。
「彼は傷つきやすい、繊細な心の持ち主なんだよ。私のことも、続く殺人事件にもひどく心を痛めてる。頼んだよ」
その晩、俺は聖也君の教会を訪ねた。
聖堂の横に立つ質素な一軒家が聖也君の家だ。以前は向聖も住んでいたが、神父職を聖也君に譲ってからは聖也君が一人で住んでいる。
少し吹雪いていた。俺は聖也君の家の玄関の前に立って、何気なく庭を見やる。
「聖也君!」
雪にまみれながら、聖也君が庭にいた。コートも着ずに薄いスータン姿のまま、途方に暮れたように立ちつくしている。
「何をしてるんだ。君、倒れたばかりだろう」
慌てて駆け寄ると、聖也君は弱弱しく俺を見やる。
「誰か、来ていませんか。救いを求める人は……」
「こんな吹雪の夜に来る人はいないよ。さ、こっちへ」
俺は聖也君に自分のコートを着せかけて家までひっぱってくると、室内に入る。
「どちらまで行かれていたんですか。早くベッドに戻ってください」
中には白衣の青年がいて、雪に濡れた聖也君の姿を見て怒った声を出す。
「いつまでも子どもですね、あなたは」
その慣れた口調に、どうやら馴染みの看護師らしいと俺は思う。
「お客様ですか?」
「あ、はい。手紙を届けに」
「果物をお出ししましょう。今お茶も入れますからね」
俺を通してきびきびと台所に向かう看護師の青年を見送って、俺は部屋の中に目を戻す。
「すみません。こんな格好で」
「いや、ゆっくり休みなさい。向聖も心配していたよ」
ベッドの横には点滴の器具や薬などが並んでいた。テーブルの上には見舞い品らしき見事なユリが活けてある。聖也君の一番好きな花だ。
「この花は向聖から?」
「いえ、向聖さんの会社の株主の方です。僕は平気だと言ったのですが、看護師までよこしてくださって」
例の大株主の信者か。俺は言葉には出さずに思う。
まもなく看護師の青年が、やはり見舞い品と思われる剥いたラ・フランスと紅茶を持ってきた。
「こんばんは、シルバー」
看護師の彼が去っていくのと入れ違いに、子猫がするりと部屋に入ってくる。
耳が折れているのがかわいらしい、灰色のスコティッシュフォールドだ。彼女はぴょんとベッドに飛び乗ると、聖也君の膝の上に収まる。
「確かシルバーも信者の方がくださったんだったね」
「はい。向聖さんが別に暮らすことになって、僕が寂しくないようにと」
聖也君が子猫を抱き上げると、彼女はごろごろと鳴いて聖也君の頬に擦りよる。
聖也君は俺が渡した向聖の手紙を読んでいた。目を伏せて、何度も繰り返し文章を辿っているようだった。
「……聖也君。君に訊きたいことがある」
ストーブが空気を暖め始めた頃、俺は意を決して問いかけた。
「君の教会の信者に、正義の刃の関係者と思われる者はいないだろうか」
聖也君は目を上げて俺を見る。
「信者の方が殺人を犯したと仰るのですか」
「俺は、刃は何らかの信念を持っていると思うんだ」
そしてそれは人々の支持を得られるような、社会悪を倒すというような存在かと思っていた。つまり人気取りだ。
だが産婦人科殺人事件でそれは一線を越えた。堕胎を行った妊婦に対する社会の同情は強く、また病院内のすべての者を殺しつくすという徹底した手段には大多数が戦慄している。
この期に及んで刃を支持している者は、ほんの一部でしかない。
「君たちの信仰では、堕胎を禁じているね」
刃は宗教関係者ではないかという疑問も、当然以前からあった。
「殺人も禁じています」
聖也君は俺の言葉に、悲しそうに目を歪めた。
「神には慈悲があります。罪を許せます。たとえ咎人であっても、死をもって償わせるなどということはしません」
おそらくそうなのだろう。それに法だって聖書の規範を形にした部分が大きい。社会に真向から反抗する信念ではない。
「すまない……」
俺は視線を落として、彼らの信仰を貶めたことを謝る。
「俺は、別の犯人がいることを願ってしまってる。警察内部でも正子を疑う声が上がってることに、焦っていて」
「正子さんが?」
聖也君は驚いたように身を乗り出す。
「彼女の居場所がわかったのですか?」
「いや。ただ、テレビとかで見てないか? 報道機関に正子の存在を示唆する記録が寄せられたって。同日に警察にも届いたんだ」
俺が聞いた山根の死亡直前の記録は、警察と報道機関に同時に届いたらしい。
聖也君は青い目を見開いてシルバーをみつめる。初耳だったのだらしい。俗世に疎い彼はワイドショーなど見ていないのだ。
「一斉にマスコミの目が正子に向いた。向聖を疑う声が消えかけてるくらいだ。その記録を送ったのが誰かはわからないが……」
俯いて、聖也君は小声で問う。
「僕を疑う声も、消えかけているのですね?」
察しのいい彼は、俺が何を言おうとしたのか感じ取ったらしい。
「以前は報道関係の方がよく教会にいらっしゃいました。僕を刃の容疑者と疑って取材を求める方も。でもある時からそれがぴたりと止みました。僕も不思議に思っていたんです」
シルバーを撫でながら、聖也君は呟く。
「刃は向聖さんや僕を庇っているのではないかとお思いなのですね」
少しの間、沈黙があった。
俺ははっとする。聖也君の目に涙が溜まっていた。
「ご、ごめんよ」
涙が溢れる前に、聖也君の膝からシルバーが飛び降りる。
「聖也君?」
聖也君は吸い寄せられるようにして子猫を追う。迷わず部屋を飛び出していく彼を、俺も椅子から立ちあがって追った。
「ちょっと、どこ行かれるんですか!」
「すまない。すぐ連れ戻すから」
台所にいた看護師の青年に伝えて、俺は外に出た。
暗闇に沈んだ世界で、白い聖堂の裏口に寝間着が消えるのが見えた。俺はこちらの入り口は初めてだと思いながら裏口から聖堂の中に入る。
そこは四畳半程度の狭い懺悔室だった。おそらく裏口ごしに中にいる神父と話すのだろう。
冷え切った懺悔室の中で、聖也君が立ち竦んでいた。壁には脚立が立てかけてあって、その視線の先の天井から光が漏れている。
「天井裏があったのか?」
光がなければ何もないように見える構造だった。驚いた俺に、聖也君は振り向く。
「僕が様子を見てきます」
「いや、俺が行くよ。誰かいるみたいだ」
俺は聖也君を制して脚立に足をかけようとする。
「待ってください!」
聞いたこともない激しい声に、俺は思わず動きを止めた。
「僕からです。合図したら後から来てください」
有無を言わさず聖也君は先に脚立を上り始めた。
一番上まで辿りついて聖也君は辺りを見回してから、俺に声をかける。
「どうぞ」
脚立を上って屋根裏に入る。そこは懺悔室と同じくらいの、小さな部屋だった。
そこには聖也君以外にも人がいた。
「おや、見つかってしまいましたか」
毛布にくるまって、いつかの不思議な旅行者が寝そべっていた。彼女の傍らにはパーティ用品のような、とんがり帽子が置かれている。
「テラさん?」
彼女はおもちゃの猫じゃらしを持って、シルバーをちょいちょいとつついていた。けれど聖也君の姿をみとめると、彼女はその遊びをやめる。
「勝手に屋根裏をお借りしています。神父様」
起き上がって、テラさんは聖也君に会釈した。
古いランタンのような灯りを見やって、俺はその横に目を留める。
「今までここに誰かがいなかったかい?」
そこには飲みかけの紅茶のカップが二つ並べられていた。まだ湯気が上がっている。
「ええ。外よりこちらの方が暖かいと仰って、私をここに案内してくださったのです。しばらくお話をしていました」
「その人はどこに?」
俺が問いかけると、テラさんは奥の木戸を指さす。それは押して開くようになっていて、どうやら教会の屋根に出られるようになっているようだった。
「神父様に、彼女から伝言を預かっています」
テラさんは聖也君を見上げてゆっくりと告げた。
「「もうあなたを苦しめたくない。告白して、心を安らかにしてください」」
無言で立ち竦む聖也君に、テラさんは締めくくる。
「「あなたの友、正子より」」
「……正子?」
心臓を掴まれたような思いがして、俺は震える。
俺は木戸を開け放って外を見た。雪が吹き付ける暗闇に飛び出そうとしたが、テラさんの声に制される。
「追えませんよ。とても身軽な方だったから」
「正子が今ここにいたんだろう!」
心に迫ってくる感情が大きすぎて、俺は声を荒げる。
「聖也君、なぜ隠してた? 正子はここにいたんだな? 君は……」
詰め寄る俺の前で、聖也君は沈黙していた。
自らがまとう静寂に凍らされたように、聖也君は微動だにしなかった。
「神父様。私は席を外しています」
テラさんはとんがり帽子をひっくり返して、その中にティーカップを放り込む。どういうマジックなのか毛布まで突っ込んで仕舞った。
とんがり帽子をかぶって手にランタンをぶらさげながら、テラさんは脚立を下りていった。
光がなくなって、辺りは暗黒に包まれる。
押し殺したような声で、聖也君は呟いた。
「……わかりました。僕が知っていることをお話しします」
聖也君の輪郭だけがうっすらと見えていた。
闇の中で、聖也君は語り始める。
「始まりは、十年前のクリスマスの夜。聖堂にいた僕のところに、正子さんがやってきました」
「俺の妻と母が死んだ、事件の日の夜?」
「はい」
短く肯定が返ってくる。
「正子さんは顔を涙でぐしゃぐしゃにしながら、僕に言ったんです。「悪いことをしちゃった、どうしよう」と」
俺は泣き顔の正子を無意識に思い返していた。
「「おばあちゃんを殺しちゃった。おとうさんは絶対許してくれない。もうおうちに帰れない」と言って泣いていました」
小さな正子が、途方に暮れたように泣く様が目の前に浮かぶようだった。
「その後、すぐに警察が来ました。犯人と正子さんを探しに。僕はこの屋根裏部屋に正子さんを隠して、誰も来ていないと言いました。……貴正さんにも」
「なぜその時に正子を出してくれなかった?」
俺は責める口調になってしまう。
「警察に言うのが怖かったなら、俺にだけでも伝えてくれればよかったじゃないか」
「警察など怖くありません。僕も、正子さんも」
聖也君は迷わず答える。
「正子さんが怖がっていたのはただ一つだけ。あなただけです」
「俺?」
「貴正さんは、正子さんの「神」で、「法」なのです。正子さんにとって絶対で、もっとも恐ろしいもの、そして愛するもの」
暗闇の中で、聖也君がうつむく気配がした。
「正子さんは繰り返し、「おとうさんに嫌われたくない」と言いました。あなたにだけは罪を知られたくなくて、隠れ続けたのです」
彼は憂い声で続ける。
「僕は正子さんが自分で罪を告白できる時まで見守ろうと、彼女を匿いました。身の回りの世話をしたり、勉強を教えたり。向聖さんは気づいていたと思います。けど何も仰いませんでした」
聖也君の行うことはすべて受け入れる向聖のことだ。そうするに違いないと思った。
「五年が過ぎようとした頃、異変が起きました」
暗闇の中で勝手知ったるように聖也君は動いて、懐中電灯をみつけてくる。
聖也君がスイッチを入れると、光が現れた。
「正子さんは突然言ったのです。「私は悪くない」と」
その中に浮かび上がった聖也君の表情は、深い苦悩にかげっていた。
「これを。五年前まで正子さんが肌身離さず持っていたものです」
聖也君に渡されたそれは、短いメモ書きだった。
くしゃくしゃになっていて、所々滲んでいるから読みにくい。懐中電灯の力を借りて目を凝らしてから、俺ははっとする。
「これは……」
メモ書きの筆跡は、俺の妻の優子のものだった。
『しょうちゃん、エビフライ作ってあげられなくてごめんね』
確かクリスマスの夜は優子がエビフライを作る約束になっていた。正子はそれを心待ちにしていた。
だがその日、優子は自殺したのだ。約束は果たされることがなかった。
「正子さんが現場から持っていった唯一のもの。彼女のお母様の遺書です」
たった一文の遺書をにじませているのは、正子の涙だろうか。
「正子さんは何度もこれを握り締めて泣いていました。「おかあさんを守ってあげられなかった」と後悔して。そしてこれをみつめて考えていました。五年もの間ずっと」
「五年前に、何が起こったんだ?」
「彼女はこの遺書を僕に託しました」
聖也君は目を上げる。
「その代わりに、彼女は刃を手にしました」
「刃?」
「彼女のおばあさまを刺した凶器を、彼女は再び手に取ったのです」
彼は俺を正面からみつめながら噛みしめるように告げる。
「その刃で、彼女は次々と「人を殺した者」を殺していきました。正子さんはもう泣きませんでした。ただ、一人殺すたび、僕のところに来て懺悔をしていくのです」
聖也君は悲しそうに告げる。
「神の道を説いて彼女を救おうとしました。どんな罪深い存在でも許される日は来る、だから人の心を取り戻しなさいと説得して。けれど、彼女はもう……」
外の吹雪がまた強くなったようだった。人の手では止めることのできない激しさで家々に吹き付けてくる。
「その頃から彼女は外出することが多くなりました。名義を向聖さんのものとして会社を設立して資金を集めたのもその一貫です。しかしその利益の半分は僕に贈りました。「あなたのおかげで私は生きていられたから」と」
正子にとって聖也君は、最後のよりどころだったのだろう。自分を守り、側で支えてくれた友達だった。
俺は何も知らずに、正子が作った会社のビールを飲んでいた。その利益の一部が、刃の活動のために使われていたのに。
俺はごくりと息を呑んで、ずっと心に抱いていた疑問を吐きだす。
「正子は誰に殺人をやらされたんだ? 一体誰に刃を持たされた?」
「誰も。彼女はすべて自分の意思で殺人を行ったのです」
聖也君の言葉に、俺は首を横に振る。
「そんなはずはない。正子は八歳の子どもだぞ」
「なぜ罪を犯したのかを彼女は話しませんでした。でも確かに自分がやったと言っていました」
「嘘だ。誰かいるはずだ、誰か……」
俺は混乱で言葉が出なくなる。
どうして正子が祖母を殺すのだ。祖母は正子を唯一の孫としてかわいがっていたし、あの子も懐いていたのに。
しばらく沈黙が流れた。やがて聖也君は口を開く。
「告白します」
目を伏せて、聖也君は懺悔するように告げる。
「僕は正子さんを……いや、しょうちゃんを愛しています」
苦悩を浮かべて彼は告げる。
「向聖さんより、救うべき人々より、神より。最初の殺人事件の夜、泣きながら聖堂の入り口に立っていた彼女を見た瞬間に、もう僕は彼女しか見えなくなっていました。涙に濡れたしょうちゃんは魔物のように美しかったのです」
聖也君は唇を噛む。
「僕が彼女を救わなければいけないと思いました。僕だけは味方であろうと。けれど僕が彼女を隠したせいで、彼女の救いの道まで闇に沈んでしまった」
両手を体の横で握りしめて、聖也君は声も上げずに泣いた。
「神の言葉では彼女を救えませんでした。それを語っているのは、彼女を愛しているだけの僕、人間でしかなかった……!」
ぽろぽろと涙を零して、聖也君は俺を見上げる。
「お願いします、貴正さん。しょうちゃんを止めてください」
溢れる涙を拭いもせずに、聖也君はただ人を想う綺麗な瞳で真っ直ぐに俺をみつめる。
「人の法で彼女を救ってあげてください……!」
お願いします、と聖也君は繰り返した。
聖也君の足元で、彼を慰めるように子猫が小さく鳴いた。
向聖の初公判の日がやって来た。
早朝、俺は最後の向聖の接見に向かった。手に、聖也君からの手紙を携えて。
「そうか。聖也君は告白したんだな」
手紙に目を通してすぐに、向聖は呟いた。
向聖はやはり聖也君を庇っていた。聖也君が犯人を隠した罪に問われることがないように。
「俺は信じられない。正子が人を殺したなんて」
光の入らない狭い一室で、俺と向聖は向き合う。
「誰かにやらされたに違いないんだ」
「なぜそう言いきれる?」
「だって、当たり前だろう? 八歳の子どもが一突きに大人を殺せるか?」
人を刺すには力が要る。それも正確に心臓を狙って一撃で殺すことなど、プロでもなければできるものじゃない。
「それにどうして正子が祖母を殺すんだ。理由がない」
接見といいながらまるで相談に乗ってもらっているようだと思いながら、俺は止められなかった。
向聖は表情を変えずに言った。
「「なぜ」かはわからないが、「どうやって」の部分なら答えられる」
「何?」
「君は現実主義者だし宗教家でもないから、信じられないかもしれないが」
どうするとその瞳が問いかける。浮世離れした落ち着きをもって、向聖は言ってくる。
「教えてくれ。刃とは何だ?」
俺はその目を見返して訊ねた。
「刃とは人ではない。「物」だ」
向聖は一拍黙って、口を開く。
「四つの特性を持っている。一つ目、使用する瞬間に時が止まる」
「時だと?」
にわかには信じられない非現実的な話に、俺は怪訝そうな声を出す。
「誰も刺したところを見ていないのはそういう理由だ」
向聖は淡々と続けた。
「二つ目、誰でも一突きで心臓を止められる」
「向聖、お前が俺をからかってるとは思いたくないが……」
「三つ目、人を殺した者しか刺せない」
困惑する俺から目を逸らさずに、向聖は告げた。
「そして最後の一つ。殺したいものができた瞬間に現れる」
彼の声には切羽詰まった色が見えて、俺はつと言葉を収める。
「信じられないだろうな。私もそうだった。だが現実に、そんな悪魔のような道具はあるんだよ」
俺は目を見開く。
「……そう、ここにね」
テーブルの下から、向聖はそれを取り出して突き付けた。
「動くな、貴正」
喉元にひやりとした金属の感触があった。
「な!」
監視をしていた係官が慌てた様子で駆け寄ろうとする。
「君も動かないでくれ」
向聖は素早く動いて俺の首に後ろから腕をまきつけると、喉元に刃の切っ先を当てて係官を制する。
「神父が刃なんか振り回していいのか?」
「ごあいにくと、私は既に神父ではないんだ」
不思議と恐ろしくはなかった。俺は静かに彼と言葉を交わす。
「神より愛する子をみつけたのでね。何もかもが美しい聖也君。誰より神父にふさわしい彼に信仰を教えることができたのだから、私は神に対する役目を果たした」
「お前がこんなことをしているとわかったら、聖也君は泣くぞ」
「だろうな。だが彼は私を許してくれるよ」
向聖は俺を拘束しながら壁際まで後ずさる。
「君は私に死刑を求刑しないのだね」
係官に聞こえないような小声で、向聖は告げる。
「私は正子ちゃんに賛同していたから、今まで刃について黙秘していたのに。確かに、命の代償は命でしか払えない……そう思う」
唐突に、俺は向聖が何をしようとしているのか気づく。
「まさか」
「でも私の聖なる存在が彼女の罪を明らかにすることを望むなら、私はそれに従おう」
声を低めて、向聖は告げる。
「……貴正。刃を取れ。君が、終わらせるんだ」
どんっと俺は強く突き飛ばされる。
「やめろ!」
振り向いて俺は向聖に手を伸ばす。その先で、向聖が刃の切っ先を自分の胸に向けるのが奇妙にゆっくりと見える。
「さよなら。君のことも、私はけっこう好きだったよ」
穏やかな微笑を浮かべて、向聖は刃で自らの胸を刺した。
思いだすのは十八年前のことだった。俺はまだ二十歳の、法学部の大学生だった。
当時付き合っていた優子との間に子どもが出来たと知って、俺は優子との結婚を決めた。
実を言えばその頃まで、俺と優子の付き合いはそんなに真剣なものじゃなかった。俺は優子のことを好きではあったが将来のことを真面目に話したこともなく、大学を卒業したら別れるかもしれないとも思っていた。
けれど責任を取るつもりで結婚をして、半年が過ぎて正子は生まれた。
……その時、今の俺もまた生まれたのだ。
小さな温もりを持った赤ん坊の正子を抱いた時、俺の中で何かが変わった気がした。
家族も妻ももちろん大切だったが、正子に抱いた鮮烈な感情とは違う。
心の底から愛おしいと思ったのは初めてだった。
彼女に誇れる父親になると決意した。必死で勉強して試験に合格して、検事になった。たぶん正子がいなければ検事の道を志すこともなかった。
正子がいなくなって、俺の人生を照らしてくれていた光がついえたように思えた。その光がもう一度蘇るというのだから、嬉しくないはずがない。
だがここに来て、警察の捜査線上に犯人として正子の名が浮かび上がった。
身柄を拘束されている向聖より、行方不明の正子の方が数々の殺人事件の引き金をひける。そして十年前の家族以外の痕跡がない妻と母の殺人事件でも、正子なら犯行を行うことができるのだ。
俺は信じられなかった。正子以外の犯人を求めた。
マスコミでは産婦人科での大量殺人事件が大きく取り上げられていた。新たに警察が正義の刃事件に加えた俺の家族の事件も再び報道されて、その中には正子の犯行を疑うものもあった。
「貴正、待ってくれ」
向聖の初公判は明日に迫っていた。彼は相変わらず落ち着いていたが、面会に行ったら珍しく自ら俺を引きとめた。
「聖也君に手紙を届けてくれないか。大丈夫、警察のチェックは通ってる」
振り向くと、警官も頷いた。俺は向聖から白い封筒を受け取る。
「私のことは心配要らない、無理に公判に来なくていいから、ゆっくり体を休めるようにと伝えてくれ」
「どうかしたのか?」
「昨日、聖也君が倒れたそうなんだ」
俺は知らなかったので、思わず眉をひそめる。
「彼は傷つきやすい、繊細な心の持ち主なんだよ。私のことも、続く殺人事件にもひどく心を痛めてる。頼んだよ」
その晩、俺は聖也君の教会を訪ねた。
聖堂の横に立つ質素な一軒家が聖也君の家だ。以前は向聖も住んでいたが、神父職を聖也君に譲ってからは聖也君が一人で住んでいる。
少し吹雪いていた。俺は聖也君の家の玄関の前に立って、何気なく庭を見やる。
「聖也君!」
雪にまみれながら、聖也君が庭にいた。コートも着ずに薄いスータン姿のまま、途方に暮れたように立ちつくしている。
「何をしてるんだ。君、倒れたばかりだろう」
慌てて駆け寄ると、聖也君は弱弱しく俺を見やる。
「誰か、来ていませんか。救いを求める人は……」
「こんな吹雪の夜に来る人はいないよ。さ、こっちへ」
俺は聖也君に自分のコートを着せかけて家までひっぱってくると、室内に入る。
「どちらまで行かれていたんですか。早くベッドに戻ってください」
中には白衣の青年がいて、雪に濡れた聖也君の姿を見て怒った声を出す。
「いつまでも子どもですね、あなたは」
その慣れた口調に、どうやら馴染みの看護師らしいと俺は思う。
「お客様ですか?」
「あ、はい。手紙を届けに」
「果物をお出ししましょう。今お茶も入れますからね」
俺を通してきびきびと台所に向かう看護師の青年を見送って、俺は部屋の中に目を戻す。
「すみません。こんな格好で」
「いや、ゆっくり休みなさい。向聖も心配していたよ」
ベッドの横には点滴の器具や薬などが並んでいた。テーブルの上には見舞い品らしき見事なユリが活けてある。聖也君の一番好きな花だ。
「この花は向聖から?」
「いえ、向聖さんの会社の株主の方です。僕は平気だと言ったのですが、看護師までよこしてくださって」
例の大株主の信者か。俺は言葉には出さずに思う。
まもなく看護師の青年が、やはり見舞い品と思われる剥いたラ・フランスと紅茶を持ってきた。
「こんばんは、シルバー」
看護師の彼が去っていくのと入れ違いに、子猫がするりと部屋に入ってくる。
耳が折れているのがかわいらしい、灰色のスコティッシュフォールドだ。彼女はぴょんとベッドに飛び乗ると、聖也君の膝の上に収まる。
「確かシルバーも信者の方がくださったんだったね」
「はい。向聖さんが別に暮らすことになって、僕が寂しくないようにと」
聖也君が子猫を抱き上げると、彼女はごろごろと鳴いて聖也君の頬に擦りよる。
聖也君は俺が渡した向聖の手紙を読んでいた。目を伏せて、何度も繰り返し文章を辿っているようだった。
「……聖也君。君に訊きたいことがある」
ストーブが空気を暖め始めた頃、俺は意を決して問いかけた。
「君の教会の信者に、正義の刃の関係者と思われる者はいないだろうか」
聖也君は目を上げて俺を見る。
「信者の方が殺人を犯したと仰るのですか」
「俺は、刃は何らかの信念を持っていると思うんだ」
そしてそれは人々の支持を得られるような、社会悪を倒すというような存在かと思っていた。つまり人気取りだ。
だが産婦人科殺人事件でそれは一線を越えた。堕胎を行った妊婦に対する社会の同情は強く、また病院内のすべての者を殺しつくすという徹底した手段には大多数が戦慄している。
この期に及んで刃を支持している者は、ほんの一部でしかない。
「君たちの信仰では、堕胎を禁じているね」
刃は宗教関係者ではないかという疑問も、当然以前からあった。
「殺人も禁じています」
聖也君は俺の言葉に、悲しそうに目を歪めた。
「神には慈悲があります。罪を許せます。たとえ咎人であっても、死をもって償わせるなどということはしません」
おそらくそうなのだろう。それに法だって聖書の規範を形にした部分が大きい。社会に真向から反抗する信念ではない。
「すまない……」
俺は視線を落として、彼らの信仰を貶めたことを謝る。
「俺は、別の犯人がいることを願ってしまってる。警察内部でも正子を疑う声が上がってることに、焦っていて」
「正子さんが?」
聖也君は驚いたように身を乗り出す。
「彼女の居場所がわかったのですか?」
「いや。ただ、テレビとかで見てないか? 報道機関に正子の存在を示唆する記録が寄せられたって。同日に警察にも届いたんだ」
俺が聞いた山根の死亡直前の記録は、警察と報道機関に同時に届いたらしい。
聖也君は青い目を見開いてシルバーをみつめる。初耳だったのだらしい。俗世に疎い彼はワイドショーなど見ていないのだ。
「一斉にマスコミの目が正子に向いた。向聖を疑う声が消えかけてるくらいだ。その記録を送ったのが誰かはわからないが……」
俯いて、聖也君は小声で問う。
「僕を疑う声も、消えかけているのですね?」
察しのいい彼は、俺が何を言おうとしたのか感じ取ったらしい。
「以前は報道関係の方がよく教会にいらっしゃいました。僕を刃の容疑者と疑って取材を求める方も。でもある時からそれがぴたりと止みました。僕も不思議に思っていたんです」
シルバーを撫でながら、聖也君は呟く。
「刃は向聖さんや僕を庇っているのではないかとお思いなのですね」
少しの間、沈黙があった。
俺ははっとする。聖也君の目に涙が溜まっていた。
「ご、ごめんよ」
涙が溢れる前に、聖也君の膝からシルバーが飛び降りる。
「聖也君?」
聖也君は吸い寄せられるようにして子猫を追う。迷わず部屋を飛び出していく彼を、俺も椅子から立ちあがって追った。
「ちょっと、どこ行かれるんですか!」
「すまない。すぐ連れ戻すから」
台所にいた看護師の青年に伝えて、俺は外に出た。
暗闇に沈んだ世界で、白い聖堂の裏口に寝間着が消えるのが見えた。俺はこちらの入り口は初めてだと思いながら裏口から聖堂の中に入る。
そこは四畳半程度の狭い懺悔室だった。おそらく裏口ごしに中にいる神父と話すのだろう。
冷え切った懺悔室の中で、聖也君が立ち竦んでいた。壁には脚立が立てかけてあって、その視線の先の天井から光が漏れている。
「天井裏があったのか?」
光がなければ何もないように見える構造だった。驚いた俺に、聖也君は振り向く。
「僕が様子を見てきます」
「いや、俺が行くよ。誰かいるみたいだ」
俺は聖也君を制して脚立に足をかけようとする。
「待ってください!」
聞いたこともない激しい声に、俺は思わず動きを止めた。
「僕からです。合図したら後から来てください」
有無を言わさず聖也君は先に脚立を上り始めた。
一番上まで辿りついて聖也君は辺りを見回してから、俺に声をかける。
「どうぞ」
脚立を上って屋根裏に入る。そこは懺悔室と同じくらいの、小さな部屋だった。
そこには聖也君以外にも人がいた。
「おや、見つかってしまいましたか」
毛布にくるまって、いつかの不思議な旅行者が寝そべっていた。彼女の傍らにはパーティ用品のような、とんがり帽子が置かれている。
「テラさん?」
彼女はおもちゃの猫じゃらしを持って、シルバーをちょいちょいとつついていた。けれど聖也君の姿をみとめると、彼女はその遊びをやめる。
「勝手に屋根裏をお借りしています。神父様」
起き上がって、テラさんは聖也君に会釈した。
古いランタンのような灯りを見やって、俺はその横に目を留める。
「今までここに誰かがいなかったかい?」
そこには飲みかけの紅茶のカップが二つ並べられていた。まだ湯気が上がっている。
「ええ。外よりこちらの方が暖かいと仰って、私をここに案内してくださったのです。しばらくお話をしていました」
「その人はどこに?」
俺が問いかけると、テラさんは奥の木戸を指さす。それは押して開くようになっていて、どうやら教会の屋根に出られるようになっているようだった。
「神父様に、彼女から伝言を預かっています」
テラさんは聖也君を見上げてゆっくりと告げた。
「「もうあなたを苦しめたくない。告白して、心を安らかにしてください」」
無言で立ち竦む聖也君に、テラさんは締めくくる。
「「あなたの友、正子より」」
「……正子?」
心臓を掴まれたような思いがして、俺は震える。
俺は木戸を開け放って外を見た。雪が吹き付ける暗闇に飛び出そうとしたが、テラさんの声に制される。
「追えませんよ。とても身軽な方だったから」
「正子が今ここにいたんだろう!」
心に迫ってくる感情が大きすぎて、俺は声を荒げる。
「聖也君、なぜ隠してた? 正子はここにいたんだな? 君は……」
詰め寄る俺の前で、聖也君は沈黙していた。
自らがまとう静寂に凍らされたように、聖也君は微動だにしなかった。
「神父様。私は席を外しています」
テラさんはとんがり帽子をひっくり返して、その中にティーカップを放り込む。どういうマジックなのか毛布まで突っ込んで仕舞った。
とんがり帽子をかぶって手にランタンをぶらさげながら、テラさんは脚立を下りていった。
光がなくなって、辺りは暗黒に包まれる。
押し殺したような声で、聖也君は呟いた。
「……わかりました。僕が知っていることをお話しします」
聖也君の輪郭だけがうっすらと見えていた。
闇の中で、聖也君は語り始める。
「始まりは、十年前のクリスマスの夜。聖堂にいた僕のところに、正子さんがやってきました」
「俺の妻と母が死んだ、事件の日の夜?」
「はい」
短く肯定が返ってくる。
「正子さんは顔を涙でぐしゃぐしゃにしながら、僕に言ったんです。「悪いことをしちゃった、どうしよう」と」
俺は泣き顔の正子を無意識に思い返していた。
「「おばあちゃんを殺しちゃった。おとうさんは絶対許してくれない。もうおうちに帰れない」と言って泣いていました」
小さな正子が、途方に暮れたように泣く様が目の前に浮かぶようだった。
「その後、すぐに警察が来ました。犯人と正子さんを探しに。僕はこの屋根裏部屋に正子さんを隠して、誰も来ていないと言いました。……貴正さんにも」
「なぜその時に正子を出してくれなかった?」
俺は責める口調になってしまう。
「警察に言うのが怖かったなら、俺にだけでも伝えてくれればよかったじゃないか」
「警察など怖くありません。僕も、正子さんも」
聖也君は迷わず答える。
「正子さんが怖がっていたのはただ一つだけ。あなただけです」
「俺?」
「貴正さんは、正子さんの「神」で、「法」なのです。正子さんにとって絶対で、もっとも恐ろしいもの、そして愛するもの」
暗闇の中で、聖也君がうつむく気配がした。
「正子さんは繰り返し、「おとうさんに嫌われたくない」と言いました。あなたにだけは罪を知られたくなくて、隠れ続けたのです」
彼は憂い声で続ける。
「僕は正子さんが自分で罪を告白できる時まで見守ろうと、彼女を匿いました。身の回りの世話をしたり、勉強を教えたり。向聖さんは気づいていたと思います。けど何も仰いませんでした」
聖也君の行うことはすべて受け入れる向聖のことだ。そうするに違いないと思った。
「五年が過ぎようとした頃、異変が起きました」
暗闇の中で勝手知ったるように聖也君は動いて、懐中電灯をみつけてくる。
聖也君がスイッチを入れると、光が現れた。
「正子さんは突然言ったのです。「私は悪くない」と」
その中に浮かび上がった聖也君の表情は、深い苦悩にかげっていた。
「これを。五年前まで正子さんが肌身離さず持っていたものです」
聖也君に渡されたそれは、短いメモ書きだった。
くしゃくしゃになっていて、所々滲んでいるから読みにくい。懐中電灯の力を借りて目を凝らしてから、俺ははっとする。
「これは……」
メモ書きの筆跡は、俺の妻の優子のものだった。
『しょうちゃん、エビフライ作ってあげられなくてごめんね』
確かクリスマスの夜は優子がエビフライを作る約束になっていた。正子はそれを心待ちにしていた。
だがその日、優子は自殺したのだ。約束は果たされることがなかった。
「正子さんが現場から持っていった唯一のもの。彼女のお母様の遺書です」
たった一文の遺書をにじませているのは、正子の涙だろうか。
「正子さんは何度もこれを握り締めて泣いていました。「おかあさんを守ってあげられなかった」と後悔して。そしてこれをみつめて考えていました。五年もの間ずっと」
「五年前に、何が起こったんだ?」
「彼女はこの遺書を僕に託しました」
聖也君は目を上げる。
「その代わりに、彼女は刃を手にしました」
「刃?」
「彼女のおばあさまを刺した凶器を、彼女は再び手に取ったのです」
彼は俺を正面からみつめながら噛みしめるように告げる。
「その刃で、彼女は次々と「人を殺した者」を殺していきました。正子さんはもう泣きませんでした。ただ、一人殺すたび、僕のところに来て懺悔をしていくのです」
聖也君は悲しそうに告げる。
「神の道を説いて彼女を救おうとしました。どんな罪深い存在でも許される日は来る、だから人の心を取り戻しなさいと説得して。けれど、彼女はもう……」
外の吹雪がまた強くなったようだった。人の手では止めることのできない激しさで家々に吹き付けてくる。
「その頃から彼女は外出することが多くなりました。名義を向聖さんのものとして会社を設立して資金を集めたのもその一貫です。しかしその利益の半分は僕に贈りました。「あなたのおかげで私は生きていられたから」と」
正子にとって聖也君は、最後のよりどころだったのだろう。自分を守り、側で支えてくれた友達だった。
俺は何も知らずに、正子が作った会社のビールを飲んでいた。その利益の一部が、刃の活動のために使われていたのに。
俺はごくりと息を呑んで、ずっと心に抱いていた疑問を吐きだす。
「正子は誰に殺人をやらされたんだ? 一体誰に刃を持たされた?」
「誰も。彼女はすべて自分の意思で殺人を行ったのです」
聖也君の言葉に、俺は首を横に振る。
「そんなはずはない。正子は八歳の子どもだぞ」
「なぜ罪を犯したのかを彼女は話しませんでした。でも確かに自分がやったと言っていました」
「嘘だ。誰かいるはずだ、誰か……」
俺は混乱で言葉が出なくなる。
どうして正子が祖母を殺すのだ。祖母は正子を唯一の孫としてかわいがっていたし、あの子も懐いていたのに。
しばらく沈黙が流れた。やがて聖也君は口を開く。
「告白します」
目を伏せて、聖也君は懺悔するように告げる。
「僕は正子さんを……いや、しょうちゃんを愛しています」
苦悩を浮かべて彼は告げる。
「向聖さんより、救うべき人々より、神より。最初の殺人事件の夜、泣きながら聖堂の入り口に立っていた彼女を見た瞬間に、もう僕は彼女しか見えなくなっていました。涙に濡れたしょうちゃんは魔物のように美しかったのです」
聖也君は唇を噛む。
「僕が彼女を救わなければいけないと思いました。僕だけは味方であろうと。けれど僕が彼女を隠したせいで、彼女の救いの道まで闇に沈んでしまった」
両手を体の横で握りしめて、聖也君は声も上げずに泣いた。
「神の言葉では彼女を救えませんでした。それを語っているのは、彼女を愛しているだけの僕、人間でしかなかった……!」
ぽろぽろと涙を零して、聖也君は俺を見上げる。
「お願いします、貴正さん。しょうちゃんを止めてください」
溢れる涙を拭いもせずに、聖也君はただ人を想う綺麗な瞳で真っ直ぐに俺をみつめる。
「人の法で彼女を救ってあげてください……!」
お願いします、と聖也君は繰り返した。
聖也君の足元で、彼を慰めるように子猫が小さく鳴いた。
向聖の初公判の日がやって来た。
早朝、俺は最後の向聖の接見に向かった。手に、聖也君からの手紙を携えて。
「そうか。聖也君は告白したんだな」
手紙に目を通してすぐに、向聖は呟いた。
向聖はやはり聖也君を庇っていた。聖也君が犯人を隠した罪に問われることがないように。
「俺は信じられない。正子が人を殺したなんて」
光の入らない狭い一室で、俺と向聖は向き合う。
「誰かにやらされたに違いないんだ」
「なぜそう言いきれる?」
「だって、当たり前だろう? 八歳の子どもが一突きに大人を殺せるか?」
人を刺すには力が要る。それも正確に心臓を狙って一撃で殺すことなど、プロでもなければできるものじゃない。
「それにどうして正子が祖母を殺すんだ。理由がない」
接見といいながらまるで相談に乗ってもらっているようだと思いながら、俺は止められなかった。
向聖は表情を変えずに言った。
「「なぜ」かはわからないが、「どうやって」の部分なら答えられる」
「何?」
「君は現実主義者だし宗教家でもないから、信じられないかもしれないが」
どうするとその瞳が問いかける。浮世離れした落ち着きをもって、向聖は言ってくる。
「教えてくれ。刃とは何だ?」
俺はその目を見返して訊ねた。
「刃とは人ではない。「物」だ」
向聖は一拍黙って、口を開く。
「四つの特性を持っている。一つ目、使用する瞬間に時が止まる」
「時だと?」
にわかには信じられない非現実的な話に、俺は怪訝そうな声を出す。
「誰も刺したところを見ていないのはそういう理由だ」
向聖は淡々と続けた。
「二つ目、誰でも一突きで心臓を止められる」
「向聖、お前が俺をからかってるとは思いたくないが……」
「三つ目、人を殺した者しか刺せない」
困惑する俺から目を逸らさずに、向聖は告げた。
「そして最後の一つ。殺したいものができた瞬間に現れる」
彼の声には切羽詰まった色が見えて、俺はつと言葉を収める。
「信じられないだろうな。私もそうだった。だが現実に、そんな悪魔のような道具はあるんだよ」
俺は目を見開く。
「……そう、ここにね」
テーブルの下から、向聖はそれを取り出して突き付けた。
「動くな、貴正」
喉元にひやりとした金属の感触があった。
「な!」
監視をしていた係官が慌てた様子で駆け寄ろうとする。
「君も動かないでくれ」
向聖は素早く動いて俺の首に後ろから腕をまきつけると、喉元に刃の切っ先を当てて係官を制する。
「神父が刃なんか振り回していいのか?」
「ごあいにくと、私は既に神父ではないんだ」
不思議と恐ろしくはなかった。俺は静かに彼と言葉を交わす。
「神より愛する子をみつけたのでね。何もかもが美しい聖也君。誰より神父にふさわしい彼に信仰を教えることができたのだから、私は神に対する役目を果たした」
「お前がこんなことをしているとわかったら、聖也君は泣くぞ」
「だろうな。だが彼は私を許してくれるよ」
向聖は俺を拘束しながら壁際まで後ずさる。
「君は私に死刑を求刑しないのだね」
係官に聞こえないような小声で、向聖は告げる。
「私は正子ちゃんに賛同していたから、今まで刃について黙秘していたのに。確かに、命の代償は命でしか払えない……そう思う」
唐突に、俺は向聖が何をしようとしているのか気づく。
「まさか」
「でも私の聖なる存在が彼女の罪を明らかにすることを望むなら、私はそれに従おう」
声を低めて、向聖は告げる。
「……貴正。刃を取れ。君が、終わらせるんだ」
どんっと俺は強く突き飛ばされる。
「やめろ!」
振り向いて俺は向聖に手を伸ばす。その先で、向聖が刃の切っ先を自分の胸に向けるのが奇妙にゆっくりと見える。
「さよなら。君のことも、私はけっこう好きだったよ」
穏やかな微笑を浮かべて、向聖は刃で自らの胸を刺した。