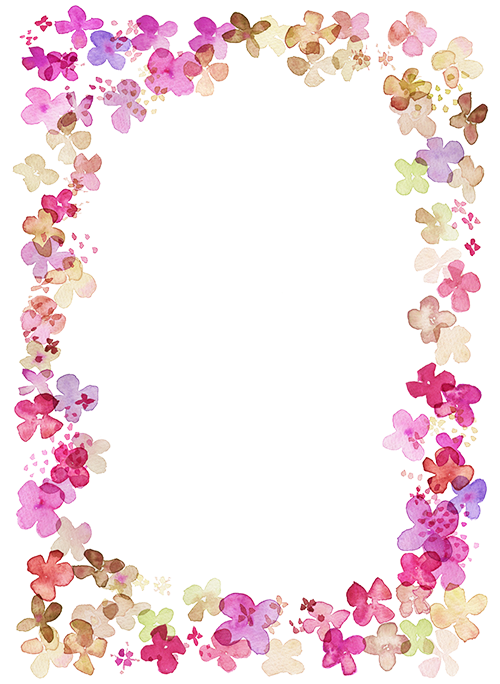大方の仕事がそういうものだが、俺の仕事もまた基本的に地味なものだと思う。
法廷で戦うという一面ももちろんあるが、アフターファイブは狭い一室で黙々とデスクワークをする。
「これは起訴」
山と積まれた資料に両側を挟まれていると、自分が小人になったような気になる。
室内に響くのは、俺が判断する声以外には送検資料をめくる音と検察事務官がタイプを打つ音くらいだ。
「次。これも起訴」
淡々としたタイプ音を聞きながら、俺は書類に目を通し終えて告げる。
俺は机の上から次の案件を取ってめくる。ざっと全部目を通したところで、俺は首をひねった。
「……ううん、どっちだろう」
パチ、とタイプ音が止まった。
俺は書類の隙間から事務官の席を覗き見る。ちょうど、そこに背筋を伸ばして座っている女性がパソコンから目を上げるところだった。
「寝ぼけていらっしゃいます?」
「う」
冷ややかに駄目出しが入った。
「最初から最後まで再読してください」
俺は彼女に言われた通り資料を読み直して、短く声を上げた。
落ち着いて読み通せば、何も迷うことはなかった。
「不起訴」
何事もなかったかのように、タイプ音が再開される。
時々彼女が書類や物証を入れ替えに来る。少し減ったかと思えばまた山積みにされるので、ついため息が漏れそうになることがある。
「今日最後の分です」
「はい。行きましょう」
しかしこの事務官のみことさんのおかげで、俺は仕事がやってこられたのだと思っている。
一分の無駄もなく俺のミスを指摘してくれる。決して俺を甘やかさない。俺がどこまで出来るかを正確に見極めて、鍛えてくれたのはみことさんだ。
年は俺の二つ上で、離婚した夫との間に息子が一人いる。俺が地検に配属されるたびにコンビを組むので、もう十年以上の付き合いになるだろうか。
眼光が鋭く眼鏡をかけていてかなり手厳しい感じだが、すらりとした美人でもある。
本日最後の案件を片づけて腕時計を見下ろすと、既に十時を回っていた。
「おつかれさまです。がんばりましたね」
彼女にそう言われるのが、俺は嬉しくもくすぐったい。
「ありがとうございます。みことさんもおつかれさまです」
頭を下げ合って、俺たちはそれぞれ帰り支度に入る。
コートを着て鞄を手に取ろうとして、俺は強く目を閉じた。
「……この後時間あります?」
俺は迷いながらも、意を決して顔を上げる。
「仕事の相談でしたらいつでも」
みことさんは姉御肌で、どんな時でも俺の仕事の相談に乗ってくれた。
「娘さんについても、私のできることなら」
正子を探すことについても、時間のある時なら手伝ってくれる。
しかし、今日俺が話したいのは仕事でも正子のことでもない。
「俺は一度ちゃんと話したいんです」
みことさんは尊敬する先輩で、同僚で、相棒だ。きれいな女性だとは思うが、恋愛感情を抱いたことはない。
「先月のことも含めて」
一か月前にたった一度、男女の関係になるまでは。
みことさんは怜悧な顔立ちに焦りを浮かべた気がした。
「私はそのことについてはなかったことにして頂きたいと言って、あなたも承諾したはずですよね?」
「そうですが……」
「なら私はこれで失礼します」
そっけなく背を向けて、みことさんは部屋の外に足を向けた。俺は慌てて鞄を持って後を追う。
確かにあの時はお互い酔っていた。俺は正子の手掛かりがつかめないことで落ち込んでいて、みことさんも子育てで悩んでいたらしく多少飲みすぎていた。
それでも俺の意識ははっきりしていたし、みことさんも一人でしっかり歩いていた。
みことさんがなぜ俺と関係を持ったのかはわからない。俺にだって自分がわからない。
けれど後悔もしていない。この感情の正体は掴めなくとも、みことさんから目を逸らしたいと思ったことはなかった。
時間が遅くてエレベーターは止まっているので、階段で下りて正面玄関まで来た。
声をかけようとした時、前を歩くみことさんが止まった。
「おつかれ。姉さん」
玄関の横のソファーから、私服姿の海藤が立ちあがるのが見えた。
「わざわざ迎えに来てくれなくてもいいのよ」
「こんな遅くに一人は危ない」
海藤はほとんど毎日姉を迎えに来て、家まで送っていくのだ。
彼はみことさんの鞄を取って、軽々と肩に背負う。
「またあいつが来たらどうするんだ。姉さんを一人にはさせておけない」
みことさんの元夫は彼女に暴力を振るっていたので、彼女は海藤の家に避難していたこともあるらしい。
「何度でも俺が追い払うが」
姉を連れ戻しに来た元夫を海藤が背負い投げたことは、警察仲間も検察仲間も皆知っていることだ。
「あのさ」
一瞥しただけで人間を凍りつかせるくらいの気迫を持つ海藤は、姉の前でだけはその激しさを収める。
労りと心配を目に浮かべて、彼はそっと姉を見下ろしていた。
「一緒に暮さないか、姉さん。嫁も心配してる」
女性としては背の高いみことさんも、百九十を超える海藤に比べればずいぶん小さく見える。海藤はその立派な体できれいな姉をずっと守って来たのだろう。
「私にはその勇気がないの」
みことさんは苦笑して弟の肩を叩いた。
「ありがとう。私は大丈夫よ、挑」
歩き出したみことさんの背中を、海藤は心配そうにみつめていた。
それから三日後、珍しく定時に仕事を切り上げることができた日のことだった。
「ああ、そう。ええ、私のことは気にしないでいいの。無理しないのよ」
帰り支度をしていた俺の横で、みことさんが携帯電話を切った。
「どうかしました?」
「挑が、今日は遅くなるから迎えにこられないと」
「俺が送りましょうか?」
まだちゃんと話ができていない。むしろ送らせてほしいと思いながら言うと、みことさんは眼鏡の奥の目を細める。
「そうですね。一緒に警察署に行きませんか」
俺が少し怪訝な顔をすると、彼女はじっと俺をみつめた。
「挑が今、刃の容疑者の取り調べをしているそうです」
はっとして、俺はすぐに同行させてもらうことにした。
みことさんは途中で弁当屋に寄って、その後俺と一緒に警察署内に入った。
「ああ、おつかれ。氷牙君」
「ご無沙汰してます」
職務上警察署に来ることも多いので、職員は俺たちを見咎めるどころか挨拶してくる。
元々いろいろな人間の出入りする場所だ。ひっきりなしに人が行き交う。
みことさんは難しい顔をして言う。
「今回が本物かはわかりませんが」
「いえ。海藤が取り調べるんですから、それなりの容疑があるんでしょう」
海藤は一度目星をつけた容疑者を執拗なまでに追うが、それはそれなりの確信があってのことなのだ。
「陽介」
「兄貴。みことさんも」
待合室に入ったら、陽介が煙草を片手に笑いかけてきた。
「海藤が刃の容疑者を取り調べてるってことだが」
「うん。あれ見て」
テレビでは、ちょうど六時のニュースが流れていた。
「『……区内にある霧島教会で、集会中に信者の男性が胸を刃物のようなもので刺されました。男性は病院へ搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました』」
まだアナログの若干不鮮明なテレビの中で、リポーターが白い教会の前に立って事件を説明している。
「聖也君の教会だ」
俺は思わず呟いて、食い入るように画面をみつめる。
「『警察は、会社経営者の霧島向聖を被疑者として拘束しました』」
俺は自分の耳を疑う。
霧島向聖……と聞こえた。彼は俺もよく知っている。
そんな馬鹿なと思う。あいつが殺人なんてやるはずがない。
俺は聞き違いだと思って画面から目を逸らす。
「『被疑者は容疑を認めていますが、警察はさらなる取り調べを……』」
別のニュースに切り替わったところで、俺は陽介に目を向けた。
「彼は容疑を認めている、と?」
「そう。確かに自分が刺したと言っている。署にも自分から出頭してきた」
そこで陽介は眉を寄せる。
「例によって、誰も被害者が刺されたところを見てないけど」
「被害者は集会の最中に殺されたんだろう?」
「霧島神父はそう言う。でも信者たちに一人一人話を聞いたのに、神父が刺したとは誰一人言わなかったらしい」
「凶器は?」
「みつかっていない」
嫌な予感がして、俺は陽介に問う。
「被害者は「人を殺した者」か?」
陽介はゆっくりと頷く。
「十年前に、泥酔状態で妻を殴って死亡させてる。犯行時心神喪失と認定されて、処罰はされていない」
物証、人証がともに無く、凶器が不明確、被害者が人を殺した者。「正義の刃」事件の条件は揃っていることになる。
「向聖さんを解放してください!」
廊下で声が上がって、俺は聞き覚えのある声にそちらへ目を向けた。
雑多な人間がいる警察署の中でも、まぶしいブロンドでスータン姿の神父の少年は目立っていた。
「向聖さんが殺人なんて犯すはずがありません。犯人だなんて何かの間違いです」
聖也君は彼にしては珍しく声を荒げて、たじろいでいる警官に詰め寄っていた。
「疑うなら僕の方でしょう。現場の教会に住んでいる神父は僕です」
「い、いやしかし。君は今朝から霧島教会を留守にしていたと聞いているし」
神の芸術品ともいわれる美貌に迫られると、たとえ雑多な人間を相手にしてきた警官でも動揺が隠せていなかった。
「殺されたのは僕の実父でしょう?」
「ならなおさら、君が手をかけるとは……」
「動機ならあります」
聖也君は肩を跳ねさせた警官に一歩近づいて言う。
「僕が実父から虐待を受けていたことなら、もう突き止めていらっしゃるでしょう?」
少年神父の剣幕に、廊下を歩いていく警官たちでさえ思わず足を止めていた。けれど誰も割って入ることができなかった。
「聖也君。心を穏やかになさい」
ふいに優しい声が聖也君を制した。
警官に両横を固められた男性が、こちらに向かって歩いてくるところだった。若々しく見えるが、年齢は俺と同じくらいの働き盛りだ。仕立てのいい灰色のスーツを上品に着こんでいて、柔和な表情をしている。
聖也君の養父である、霧島向聖だ。
「向聖……」
俺は彼がここにいることが信じられず、待合室の戸口に立ったまま凍りつく。
「お義父さん、戻りましょう。あなたが殺人なんて犯すはずがない」
「私だよ」
駆け寄った聖也君に、聖書を朗読するような美しい声で向聖が答える。
「後悔していないよ。正義だと思っている」
その言葉に俺は心に火がつくような思いがしたが、唇を噛んでこらえた。
向聖は聖也君の前に立つと、仰ぎ見るように聖也君をみつめる。
「君を傷つけた者は許せなかった。君は私の聖なるものだから」
そっと手を伸ばして、向聖は聖也君の頬に触れる直前で手を止める。
一歩後ずさって、向聖は聖也君から離れる。
警官に連れられて、向聖は俺の横を通り過ぎようとする。
何もかも受け入れたような、静かな瞳と目が合った。
昔からそうだった。初めて会った時からずっと、向聖は聖人のようにどこか遠い世界からこちらを見ているようだった。
彼は俺が前のアパートから離れるまで、公園を挟んで隣人だった。引っ越してからもよく会った。
「向聖」
親友同士だと思っていた。いや、今だってそう思い続けている。
それがもしかしたら母と妻を殺し、正子を連れ去ったかもしれないなんて、思いたくなかった。
通り過ぎ際に、俺は低く呟いた。
「お前が正義の刃なら、俺はお前を許さない」
向聖は目だけを動かしたが、何も答えることはなかった。
なお後を追おうとする聖也君を、やんわりと陽介が留める。
「聖也君。おじさんがコーヒーおごってあげるから、こっちおいで」
「いえ、僕は」
「霧島さんのはただの任意聴取だよ。霧島さんが嫌になったらいつでも帰れるんだ。だから、もう少し警察に話だけでも聞かせてもらえないかな?」
陽介は聖也君を宥めて待合室に導いていった。こういう優しい警官の役をやらせると、陽介に敵う者はなかなかいない。
彼との組み合わせで最適な相棒は厳しい警官だが。そう思って顔を上げたところで、ちょうどその相棒が廊下を通りかかるところだった。
「挑、食事は取ったの?」
「いや、まだ」
「お弁当を買って来たの。一緒に食べましょう」
たぶん少し休憩してすぐに仕事に戻るつもりだったのだろうが、海藤はしっかりみことさんに捕まった。
ビニール袋を持ち上げて、みことさんは俺に一瞥をくれる。
「貴正さんの分もあるんですよ」
そんなわけで、俺たちは廊下の脇にあるベンチに並んで座って弁当を食べることになった。
「なんで氷牙がここにいるんだ、姉さん」
みことさんの手前、海藤の声にいつもほどの険悪さはない。
「そんなことはどうでもいいでしょう」
どうでもいいことにされてしまった俺の立場は微妙だが、この際いいとしよう。
「先ほどの彼を正義の刃の容疑者としたということは、あなたの貴正さんへの疑いは晴れたとみていいのかしら」
弁当に箸を入れた瞬間、いきなりみことさんが切り出した。海藤はすぐに顔を険しくする。
「まだだ。今回の事件のことも、一連の刃との関連もまだ明らかじゃない」
「でもあなた、さっき電話してきた時に「刃の容疑者」と言ったわよね? いつもなら、また模倣犯だって言うのに」
「自分が殺人を犯したと言って出頭してきたのなら、一応は容疑者として扱うだろう」
「常識は聞いていないのよ」
丁寧に豆を一つずつ摘みながら、みことさんは淡々と言葉を返す。
「私が聞きたいのは、あなたが間違いを認める気になったかどうか」
「間違い? 何のことだ」
「貴正さんが奥さんとお母様を殺したわけじゃないって、あなたはもう確信を持ってるはずでしょう」
みことさんの言葉はいつも淀みない。そのせいで上司には嫌われているが、正しいと信じたことを堂々と口にする。
「意地だけで貴正さんに権力の刃を向けているのはあなたの方よ。不毛なことはやめて、協力することを覚えなさい」
「いくら姉さんでも言っていいことと悪いことがある」
じっとみつめるみことさんを、海藤は強く睨みつける。
「俺に情報を流せっていうのか」
「検事と警察は協働関係よ」
「こいつは検事として信頼できない!」
海藤は鋭く言い放って席を立つ。
「姉さんも氷牙も、検察が俺たちの仕事に口を出すな」
広い背中が遠ざかっていく。みことさんは止めることをしなかった。
「……余計なことをしてすみません」
曲がり角にその背中が消えた後、みことさんは呟いた。
「貴正さんにも挑にも、一人で背負ってほしくないんです」
俺は目を伏せるだけで、返す言葉が思い浮かばなかった。
翌日の夕刻、みことさんとデスクワークをしていた時、携帯電話が鳴った。
「失礼」
みことさんが携帯の通話に出て、部屋の外に足を向ける。
「……え?」
中途半端なところで、みことさんの足が止まった。
はい、はい、と単調な返事をして、やがて彼女は通話を切る。
何かの業務連絡かと思って俺は書類に目を落としていたが、いつまで経ってもみことさんが席に戻らない。
「みことさん?」
部屋の中央に立ち竦んでいる彼女に、俺は声をかける。
みことさんはただ立っていた。厳格でいつもきっちりしている彼女にしては珍しく、心がそこにないようなぼんやりした表情だった。
「どうしたんですか?」
俺が席から立ちあがって近付いても、みことさんは俺にすら気付いていないようだった。
その手から携帯電話が滑り落ちて、ひびが入る。
俺がそれを拾い上げて彼女に渡そうとしたところで、部屋の扉が開いた。
「おい、貴正。今情報が入ったんだが……」
同僚の検事が顔を覗かせて、そこでみことさんを見て痛ましい顔をする。
みことさんは鞄も持たずにふらりと部屋を出て行った。
「あ、みことさん」
「いいんだ。仕方ない」
同僚は首を横に振って俺を留める。
「何があった?」
「昨日から刃の容疑者が署で任意聴取を受けていただろう。先ほど、取り調べ中に警官が刺されたんだ」
俺は耳鳴りがするような、嫌な予感を抱いた。
「誰も刺したところを見ていないんだ。凶器もない」
「なあ」
訊いてはいけないとわかっていながら、俺はその言葉を口にしていた。
「取り調べをしていた警官って、もしかして」
同僚の顔が、どこか遠くにあるようだった。
「海藤挑だ。……即死だったそうだ」
俺の目の前を、昨夜見た海藤の大きな背中がよぎっていった。
「警察権力に対する挑戦だって騒ぐ輩もいる」
同僚の声はもう聞こえていなかった。
誰か嘘だと言ってくれ。こんなことはただの悪い夢なのだと。
海藤と俺は低くうめいて、顔を手で覆った。
法廷で戦うという一面ももちろんあるが、アフターファイブは狭い一室で黙々とデスクワークをする。
「これは起訴」
山と積まれた資料に両側を挟まれていると、自分が小人になったような気になる。
室内に響くのは、俺が判断する声以外には送検資料をめくる音と検察事務官がタイプを打つ音くらいだ。
「次。これも起訴」
淡々としたタイプ音を聞きながら、俺は書類に目を通し終えて告げる。
俺は机の上から次の案件を取ってめくる。ざっと全部目を通したところで、俺は首をひねった。
「……ううん、どっちだろう」
パチ、とタイプ音が止まった。
俺は書類の隙間から事務官の席を覗き見る。ちょうど、そこに背筋を伸ばして座っている女性がパソコンから目を上げるところだった。
「寝ぼけていらっしゃいます?」
「う」
冷ややかに駄目出しが入った。
「最初から最後まで再読してください」
俺は彼女に言われた通り資料を読み直して、短く声を上げた。
落ち着いて読み通せば、何も迷うことはなかった。
「不起訴」
何事もなかったかのように、タイプ音が再開される。
時々彼女が書類や物証を入れ替えに来る。少し減ったかと思えばまた山積みにされるので、ついため息が漏れそうになることがある。
「今日最後の分です」
「はい。行きましょう」
しかしこの事務官のみことさんのおかげで、俺は仕事がやってこられたのだと思っている。
一分の無駄もなく俺のミスを指摘してくれる。決して俺を甘やかさない。俺がどこまで出来るかを正確に見極めて、鍛えてくれたのはみことさんだ。
年は俺の二つ上で、離婚した夫との間に息子が一人いる。俺が地検に配属されるたびにコンビを組むので、もう十年以上の付き合いになるだろうか。
眼光が鋭く眼鏡をかけていてかなり手厳しい感じだが、すらりとした美人でもある。
本日最後の案件を片づけて腕時計を見下ろすと、既に十時を回っていた。
「おつかれさまです。がんばりましたね」
彼女にそう言われるのが、俺は嬉しくもくすぐったい。
「ありがとうございます。みことさんもおつかれさまです」
頭を下げ合って、俺たちはそれぞれ帰り支度に入る。
コートを着て鞄を手に取ろうとして、俺は強く目を閉じた。
「……この後時間あります?」
俺は迷いながらも、意を決して顔を上げる。
「仕事の相談でしたらいつでも」
みことさんは姉御肌で、どんな時でも俺の仕事の相談に乗ってくれた。
「娘さんについても、私のできることなら」
正子を探すことについても、時間のある時なら手伝ってくれる。
しかし、今日俺が話したいのは仕事でも正子のことでもない。
「俺は一度ちゃんと話したいんです」
みことさんは尊敬する先輩で、同僚で、相棒だ。きれいな女性だとは思うが、恋愛感情を抱いたことはない。
「先月のことも含めて」
一か月前にたった一度、男女の関係になるまでは。
みことさんは怜悧な顔立ちに焦りを浮かべた気がした。
「私はそのことについてはなかったことにして頂きたいと言って、あなたも承諾したはずですよね?」
「そうですが……」
「なら私はこれで失礼します」
そっけなく背を向けて、みことさんは部屋の外に足を向けた。俺は慌てて鞄を持って後を追う。
確かにあの時はお互い酔っていた。俺は正子の手掛かりがつかめないことで落ち込んでいて、みことさんも子育てで悩んでいたらしく多少飲みすぎていた。
それでも俺の意識ははっきりしていたし、みことさんも一人でしっかり歩いていた。
みことさんがなぜ俺と関係を持ったのかはわからない。俺にだって自分がわからない。
けれど後悔もしていない。この感情の正体は掴めなくとも、みことさんから目を逸らしたいと思ったことはなかった。
時間が遅くてエレベーターは止まっているので、階段で下りて正面玄関まで来た。
声をかけようとした時、前を歩くみことさんが止まった。
「おつかれ。姉さん」
玄関の横のソファーから、私服姿の海藤が立ちあがるのが見えた。
「わざわざ迎えに来てくれなくてもいいのよ」
「こんな遅くに一人は危ない」
海藤はほとんど毎日姉を迎えに来て、家まで送っていくのだ。
彼はみことさんの鞄を取って、軽々と肩に背負う。
「またあいつが来たらどうするんだ。姉さんを一人にはさせておけない」
みことさんの元夫は彼女に暴力を振るっていたので、彼女は海藤の家に避難していたこともあるらしい。
「何度でも俺が追い払うが」
姉を連れ戻しに来た元夫を海藤が背負い投げたことは、警察仲間も検察仲間も皆知っていることだ。
「あのさ」
一瞥しただけで人間を凍りつかせるくらいの気迫を持つ海藤は、姉の前でだけはその激しさを収める。
労りと心配を目に浮かべて、彼はそっと姉を見下ろしていた。
「一緒に暮さないか、姉さん。嫁も心配してる」
女性としては背の高いみことさんも、百九十を超える海藤に比べればずいぶん小さく見える。海藤はその立派な体できれいな姉をずっと守って来たのだろう。
「私にはその勇気がないの」
みことさんは苦笑して弟の肩を叩いた。
「ありがとう。私は大丈夫よ、挑」
歩き出したみことさんの背中を、海藤は心配そうにみつめていた。
それから三日後、珍しく定時に仕事を切り上げることができた日のことだった。
「ああ、そう。ええ、私のことは気にしないでいいの。無理しないのよ」
帰り支度をしていた俺の横で、みことさんが携帯電話を切った。
「どうかしました?」
「挑が、今日は遅くなるから迎えにこられないと」
「俺が送りましょうか?」
まだちゃんと話ができていない。むしろ送らせてほしいと思いながら言うと、みことさんは眼鏡の奥の目を細める。
「そうですね。一緒に警察署に行きませんか」
俺が少し怪訝な顔をすると、彼女はじっと俺をみつめた。
「挑が今、刃の容疑者の取り調べをしているそうです」
はっとして、俺はすぐに同行させてもらうことにした。
みことさんは途中で弁当屋に寄って、その後俺と一緒に警察署内に入った。
「ああ、おつかれ。氷牙君」
「ご無沙汰してます」
職務上警察署に来ることも多いので、職員は俺たちを見咎めるどころか挨拶してくる。
元々いろいろな人間の出入りする場所だ。ひっきりなしに人が行き交う。
みことさんは難しい顔をして言う。
「今回が本物かはわかりませんが」
「いえ。海藤が取り調べるんですから、それなりの容疑があるんでしょう」
海藤は一度目星をつけた容疑者を執拗なまでに追うが、それはそれなりの確信があってのことなのだ。
「陽介」
「兄貴。みことさんも」
待合室に入ったら、陽介が煙草を片手に笑いかけてきた。
「海藤が刃の容疑者を取り調べてるってことだが」
「うん。あれ見て」
テレビでは、ちょうど六時のニュースが流れていた。
「『……区内にある霧島教会で、集会中に信者の男性が胸を刃物のようなもので刺されました。男性は病院へ搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました』」
まだアナログの若干不鮮明なテレビの中で、リポーターが白い教会の前に立って事件を説明している。
「聖也君の教会だ」
俺は思わず呟いて、食い入るように画面をみつめる。
「『警察は、会社経営者の霧島向聖を被疑者として拘束しました』」
俺は自分の耳を疑う。
霧島向聖……と聞こえた。彼は俺もよく知っている。
そんな馬鹿なと思う。あいつが殺人なんてやるはずがない。
俺は聞き違いだと思って画面から目を逸らす。
「『被疑者は容疑を認めていますが、警察はさらなる取り調べを……』」
別のニュースに切り替わったところで、俺は陽介に目を向けた。
「彼は容疑を認めている、と?」
「そう。確かに自分が刺したと言っている。署にも自分から出頭してきた」
そこで陽介は眉を寄せる。
「例によって、誰も被害者が刺されたところを見てないけど」
「被害者は集会の最中に殺されたんだろう?」
「霧島神父はそう言う。でも信者たちに一人一人話を聞いたのに、神父が刺したとは誰一人言わなかったらしい」
「凶器は?」
「みつかっていない」
嫌な予感がして、俺は陽介に問う。
「被害者は「人を殺した者」か?」
陽介はゆっくりと頷く。
「十年前に、泥酔状態で妻を殴って死亡させてる。犯行時心神喪失と認定されて、処罰はされていない」
物証、人証がともに無く、凶器が不明確、被害者が人を殺した者。「正義の刃」事件の条件は揃っていることになる。
「向聖さんを解放してください!」
廊下で声が上がって、俺は聞き覚えのある声にそちらへ目を向けた。
雑多な人間がいる警察署の中でも、まぶしいブロンドでスータン姿の神父の少年は目立っていた。
「向聖さんが殺人なんて犯すはずがありません。犯人だなんて何かの間違いです」
聖也君は彼にしては珍しく声を荒げて、たじろいでいる警官に詰め寄っていた。
「疑うなら僕の方でしょう。現場の教会に住んでいる神父は僕です」
「い、いやしかし。君は今朝から霧島教会を留守にしていたと聞いているし」
神の芸術品ともいわれる美貌に迫られると、たとえ雑多な人間を相手にしてきた警官でも動揺が隠せていなかった。
「殺されたのは僕の実父でしょう?」
「ならなおさら、君が手をかけるとは……」
「動機ならあります」
聖也君は肩を跳ねさせた警官に一歩近づいて言う。
「僕が実父から虐待を受けていたことなら、もう突き止めていらっしゃるでしょう?」
少年神父の剣幕に、廊下を歩いていく警官たちでさえ思わず足を止めていた。けれど誰も割って入ることができなかった。
「聖也君。心を穏やかになさい」
ふいに優しい声が聖也君を制した。
警官に両横を固められた男性が、こちらに向かって歩いてくるところだった。若々しく見えるが、年齢は俺と同じくらいの働き盛りだ。仕立てのいい灰色のスーツを上品に着こんでいて、柔和な表情をしている。
聖也君の養父である、霧島向聖だ。
「向聖……」
俺は彼がここにいることが信じられず、待合室の戸口に立ったまま凍りつく。
「お義父さん、戻りましょう。あなたが殺人なんて犯すはずがない」
「私だよ」
駆け寄った聖也君に、聖書を朗読するような美しい声で向聖が答える。
「後悔していないよ。正義だと思っている」
その言葉に俺は心に火がつくような思いがしたが、唇を噛んでこらえた。
向聖は聖也君の前に立つと、仰ぎ見るように聖也君をみつめる。
「君を傷つけた者は許せなかった。君は私の聖なるものだから」
そっと手を伸ばして、向聖は聖也君の頬に触れる直前で手を止める。
一歩後ずさって、向聖は聖也君から離れる。
警官に連れられて、向聖は俺の横を通り過ぎようとする。
何もかも受け入れたような、静かな瞳と目が合った。
昔からそうだった。初めて会った時からずっと、向聖は聖人のようにどこか遠い世界からこちらを見ているようだった。
彼は俺が前のアパートから離れるまで、公園を挟んで隣人だった。引っ越してからもよく会った。
「向聖」
親友同士だと思っていた。いや、今だってそう思い続けている。
それがもしかしたら母と妻を殺し、正子を連れ去ったかもしれないなんて、思いたくなかった。
通り過ぎ際に、俺は低く呟いた。
「お前が正義の刃なら、俺はお前を許さない」
向聖は目だけを動かしたが、何も答えることはなかった。
なお後を追おうとする聖也君を、やんわりと陽介が留める。
「聖也君。おじさんがコーヒーおごってあげるから、こっちおいで」
「いえ、僕は」
「霧島さんのはただの任意聴取だよ。霧島さんが嫌になったらいつでも帰れるんだ。だから、もう少し警察に話だけでも聞かせてもらえないかな?」
陽介は聖也君を宥めて待合室に導いていった。こういう優しい警官の役をやらせると、陽介に敵う者はなかなかいない。
彼との組み合わせで最適な相棒は厳しい警官だが。そう思って顔を上げたところで、ちょうどその相棒が廊下を通りかかるところだった。
「挑、食事は取ったの?」
「いや、まだ」
「お弁当を買って来たの。一緒に食べましょう」
たぶん少し休憩してすぐに仕事に戻るつもりだったのだろうが、海藤はしっかりみことさんに捕まった。
ビニール袋を持ち上げて、みことさんは俺に一瞥をくれる。
「貴正さんの分もあるんですよ」
そんなわけで、俺たちは廊下の脇にあるベンチに並んで座って弁当を食べることになった。
「なんで氷牙がここにいるんだ、姉さん」
みことさんの手前、海藤の声にいつもほどの険悪さはない。
「そんなことはどうでもいいでしょう」
どうでもいいことにされてしまった俺の立場は微妙だが、この際いいとしよう。
「先ほどの彼を正義の刃の容疑者としたということは、あなたの貴正さんへの疑いは晴れたとみていいのかしら」
弁当に箸を入れた瞬間、いきなりみことさんが切り出した。海藤はすぐに顔を険しくする。
「まだだ。今回の事件のことも、一連の刃との関連もまだ明らかじゃない」
「でもあなた、さっき電話してきた時に「刃の容疑者」と言ったわよね? いつもなら、また模倣犯だって言うのに」
「自分が殺人を犯したと言って出頭してきたのなら、一応は容疑者として扱うだろう」
「常識は聞いていないのよ」
丁寧に豆を一つずつ摘みながら、みことさんは淡々と言葉を返す。
「私が聞きたいのは、あなたが間違いを認める気になったかどうか」
「間違い? 何のことだ」
「貴正さんが奥さんとお母様を殺したわけじゃないって、あなたはもう確信を持ってるはずでしょう」
みことさんの言葉はいつも淀みない。そのせいで上司には嫌われているが、正しいと信じたことを堂々と口にする。
「意地だけで貴正さんに権力の刃を向けているのはあなたの方よ。不毛なことはやめて、協力することを覚えなさい」
「いくら姉さんでも言っていいことと悪いことがある」
じっとみつめるみことさんを、海藤は強く睨みつける。
「俺に情報を流せっていうのか」
「検事と警察は協働関係よ」
「こいつは検事として信頼できない!」
海藤は鋭く言い放って席を立つ。
「姉さんも氷牙も、検察が俺たちの仕事に口を出すな」
広い背中が遠ざかっていく。みことさんは止めることをしなかった。
「……余計なことをしてすみません」
曲がり角にその背中が消えた後、みことさんは呟いた。
「貴正さんにも挑にも、一人で背負ってほしくないんです」
俺は目を伏せるだけで、返す言葉が思い浮かばなかった。
翌日の夕刻、みことさんとデスクワークをしていた時、携帯電話が鳴った。
「失礼」
みことさんが携帯の通話に出て、部屋の外に足を向ける。
「……え?」
中途半端なところで、みことさんの足が止まった。
はい、はい、と単調な返事をして、やがて彼女は通話を切る。
何かの業務連絡かと思って俺は書類に目を落としていたが、いつまで経ってもみことさんが席に戻らない。
「みことさん?」
部屋の中央に立ち竦んでいる彼女に、俺は声をかける。
みことさんはただ立っていた。厳格でいつもきっちりしている彼女にしては珍しく、心がそこにないようなぼんやりした表情だった。
「どうしたんですか?」
俺が席から立ちあがって近付いても、みことさんは俺にすら気付いていないようだった。
その手から携帯電話が滑り落ちて、ひびが入る。
俺がそれを拾い上げて彼女に渡そうとしたところで、部屋の扉が開いた。
「おい、貴正。今情報が入ったんだが……」
同僚の検事が顔を覗かせて、そこでみことさんを見て痛ましい顔をする。
みことさんは鞄も持たずにふらりと部屋を出て行った。
「あ、みことさん」
「いいんだ。仕方ない」
同僚は首を横に振って俺を留める。
「何があった?」
「昨日から刃の容疑者が署で任意聴取を受けていただろう。先ほど、取り調べ中に警官が刺されたんだ」
俺は耳鳴りがするような、嫌な予感を抱いた。
「誰も刺したところを見ていないんだ。凶器もない」
「なあ」
訊いてはいけないとわかっていながら、俺はその言葉を口にしていた。
「取り調べをしていた警官って、もしかして」
同僚の顔が、どこか遠くにあるようだった。
「海藤挑だ。……即死だったそうだ」
俺の目の前を、昨夜見た海藤の大きな背中がよぎっていった。
「警察権力に対する挑戦だって騒ぐ輩もいる」
同僚の声はもう聞こえていなかった。
誰か嘘だと言ってくれ。こんなことはただの悪い夢なのだと。
海藤と俺は低くうめいて、顔を手で覆った。