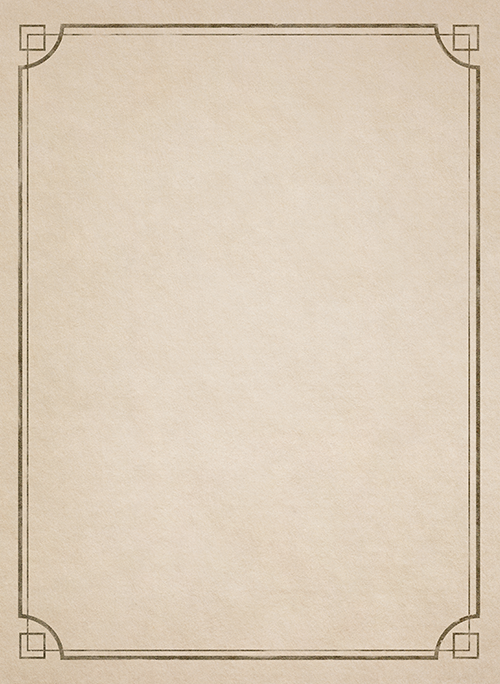先日、2年間付き合っていた彼女と「コロッケ」が原因で別れた。誰もが好きであろう食べ物の「コロッケ」が原因で……
今思えば、本当にくだらないことで喧嘩して、人には言えないような恥ずかしい別れ方だとは思うけれど、僕も、まだまだ大人にはなりきれずにいた。
自分の意見を曲げて、誰かに合わせたり、相手を傷付かない言葉選びだったりすることができなかったのである。一人っ子で、多くの人に可愛がって貰っていたこともあって、昔からわがままな性格ではあった。喧嘩する兄弟がいなかったから、基本な自分の思い通りになった。何かを我慢する経験なんて、ほとんどなかった。
そんな僕でも、好きでいてくれるだろう、許してくれるだろうと、どこかで彼女に甘えていた部分もあったのかもしれない。今思えば……
今更、後悔しても遅い、どうにもならない。だって僕は、スーパーヒーローでも、選ばれし者でもないから、時間を戻す能力なんて持っていない。過ぎた時間は、取り戻すことはできない、言ってしまったことを言ってないことにもできないのだ。
※※※
正直に言えば、彼女は美人とは言えなかった。特段らコミュニケーション能力が高いわけでもなかったので、大学でチヤホヤされるような感じもなかった。
それでも彼女を好きだと思えたのは、彼女とは、色々なものの好みが同じだったから……
俗に言う波長が合うってやつ。人間生きている中で、そんな人と巡り会える確率なんて相当低い。
「大きくなったら、僕、芸能人と結婚する」
「付き合うなら、美人だね。絶対に美人がいい。この中の誰よりも美人と付き合ってやる、結婚してやる!」
昔、こんなことを言っていた僕からしたら、成長したと思う。人を外見ではなく、内面で好きになれたのだから。
地元の幼なじみに彼女のことを紹介したら、驚いただろうな。結局、紹介することはなかったけれど。
彼女とは、面白いくらいに気が合った。
趣味は映画鑑賞と水族館巡り。好きな映画のジャンルはアクション系。映画館では、映画に集中するためにポップコーンは絶対に食べないという映画への向き合い方まで同じ。推しの海洋生物は、ペンギン。おそろいで買ったペンギンのマグカップにお互い名前を付けることにしたが、どちらも「ペンカちゃん」という名前を付けていた。
サスペンスドラマを見ている時は途中で犯人が分かっても言わないでおく。コーラよりもサイダーが好き。好きなものは最後まで取っておくタイプ。目玉焼きにはソースをかける、味噌汁は白味噌、ご飯は少しかための方が好み。どんなに忙しくても、いただきますとごちそうさまだけは言う。
それぞれ、違う家庭、違う環境で育ったというのに、不思議だった。
最初は恋愛対象というより、気心知れた友だちのように感じていた。ここまで気が合う人は、今までの友だちでもいなかった。
たぶん、僕らが同じ性別だったら、良き親友になれたと思う。
だけど、僕は男で彼女は女。それ以上の関係を求めてしまう、求められてしまう。僕と彼女が二人っきりで遊園地に行ったとする。それは、周りから見れば、遊びではなく、デート。世の中ってそういうものだ。
彼女もまた、同じように僕とは波長が合うと感じてくれたようで、僕たちは告白という告白なく、自然と流れ的に気づいたら付き合っていたという感覚だった。(一応、僕ら2人の中では、同棲を始めた日を交際スタートとした)
これは互いが恋愛において、内面を尊重しているものたちの特権みたいなものだ。顔を好きになった系の人たちは、一度告白という段階を挟まなければならない。それはそれで、ワクワクや楽しみがあるのかもしれないけれど。
波長が合う僕らだから、同棲する中で、不自由なことも不満もなかった。喧嘩なんてそれまで一度もなかった。
周りの人間たちからは、「喧嘩しないなんて、お前らは本当に仲良くていいね」「喧嘩はしないに越したことはないよ。喧嘩すると、絶対に嫌な気持ちになるから」なんて言われて羨ましがられていた。普通は、付き合い始めて3ヶ月、同棲を始めて1ヶ月、そういった節目節目に何かしらが原因で揉めるらしい。
言われた通り、喧嘩はしないに越したことはない。これからもずっと喧嘩なく仲良く過ごしていければ、僕らはこのまま自然と結婚して、子どもが出来て、幸せに暮らしたのかもしれない。両親が喧嘩せず仲良く暮らしているのは、子どもにとってもいい影響を与えられたかもしれない。
だけど、今まで喧嘩をしたことがない。僕らにとっては、これこそが、大きな問題だったのだと思う。あの日まで僕らは、1度も喧嘩をしたことがなかったから、分からなかったんだ。喧嘩した後、どうやって仲直りすればいいかってことを。どんな風に声を掛ければいいかを。
こうなるんなら、もっと喧嘩をしておくんだった。どちらかが約束の時間に遅れてきたとか、サスペンスドラマの犯人の名前をうっかり口に出しちゃったとか、そういうレベルでいいから、些細なことで喧嘩しておくべきだった。
「喧嘩するほど仲がいい」なんて言葉があるけれどあれは、本当だ。本当に喧嘩する必要まではないけれど、いつでも喧嘩はできるような関係であるべきだ。それが、仲がいいってことなんだと思う。
今思えば、本当にくだらないことで喧嘩して、人には言えないような恥ずかしい別れ方だとは思うけれど、僕も、まだまだ大人にはなりきれずにいた。
自分の意見を曲げて、誰かに合わせたり、相手を傷付かない言葉選びだったりすることができなかったのである。一人っ子で、多くの人に可愛がって貰っていたこともあって、昔からわがままな性格ではあった。喧嘩する兄弟がいなかったから、基本な自分の思い通りになった。何かを我慢する経験なんて、ほとんどなかった。
そんな僕でも、好きでいてくれるだろう、許してくれるだろうと、どこかで彼女に甘えていた部分もあったのかもしれない。今思えば……
今更、後悔しても遅い、どうにもならない。だって僕は、スーパーヒーローでも、選ばれし者でもないから、時間を戻す能力なんて持っていない。過ぎた時間は、取り戻すことはできない、言ってしまったことを言ってないことにもできないのだ。
※※※
正直に言えば、彼女は美人とは言えなかった。特段らコミュニケーション能力が高いわけでもなかったので、大学でチヤホヤされるような感じもなかった。
それでも彼女を好きだと思えたのは、彼女とは、色々なものの好みが同じだったから……
俗に言う波長が合うってやつ。人間生きている中で、そんな人と巡り会える確率なんて相当低い。
「大きくなったら、僕、芸能人と結婚する」
「付き合うなら、美人だね。絶対に美人がいい。この中の誰よりも美人と付き合ってやる、結婚してやる!」
昔、こんなことを言っていた僕からしたら、成長したと思う。人を外見ではなく、内面で好きになれたのだから。
地元の幼なじみに彼女のことを紹介したら、驚いただろうな。結局、紹介することはなかったけれど。
彼女とは、面白いくらいに気が合った。
趣味は映画鑑賞と水族館巡り。好きな映画のジャンルはアクション系。映画館では、映画に集中するためにポップコーンは絶対に食べないという映画への向き合い方まで同じ。推しの海洋生物は、ペンギン。おそろいで買ったペンギンのマグカップにお互い名前を付けることにしたが、どちらも「ペンカちゃん」という名前を付けていた。
サスペンスドラマを見ている時は途中で犯人が分かっても言わないでおく。コーラよりもサイダーが好き。好きなものは最後まで取っておくタイプ。目玉焼きにはソースをかける、味噌汁は白味噌、ご飯は少しかための方が好み。どんなに忙しくても、いただきますとごちそうさまだけは言う。
それぞれ、違う家庭、違う環境で育ったというのに、不思議だった。
最初は恋愛対象というより、気心知れた友だちのように感じていた。ここまで気が合う人は、今までの友だちでもいなかった。
たぶん、僕らが同じ性別だったら、良き親友になれたと思う。
だけど、僕は男で彼女は女。それ以上の関係を求めてしまう、求められてしまう。僕と彼女が二人っきりで遊園地に行ったとする。それは、周りから見れば、遊びではなく、デート。世の中ってそういうものだ。
彼女もまた、同じように僕とは波長が合うと感じてくれたようで、僕たちは告白という告白なく、自然と流れ的に気づいたら付き合っていたという感覚だった。(一応、僕ら2人の中では、同棲を始めた日を交際スタートとした)
これは互いが恋愛において、内面を尊重しているものたちの特権みたいなものだ。顔を好きになった系の人たちは、一度告白という段階を挟まなければならない。それはそれで、ワクワクや楽しみがあるのかもしれないけれど。
波長が合う僕らだから、同棲する中で、不自由なことも不満もなかった。喧嘩なんてそれまで一度もなかった。
周りの人間たちからは、「喧嘩しないなんて、お前らは本当に仲良くていいね」「喧嘩はしないに越したことはないよ。喧嘩すると、絶対に嫌な気持ちになるから」なんて言われて羨ましがられていた。普通は、付き合い始めて3ヶ月、同棲を始めて1ヶ月、そういった節目節目に何かしらが原因で揉めるらしい。
言われた通り、喧嘩はしないに越したことはない。これからもずっと喧嘩なく仲良く過ごしていければ、僕らはこのまま自然と結婚して、子どもが出来て、幸せに暮らしたのかもしれない。両親が喧嘩せず仲良く暮らしているのは、子どもにとってもいい影響を与えられたかもしれない。
だけど、今まで喧嘩をしたことがない。僕らにとっては、これこそが、大きな問題だったのだと思う。あの日まで僕らは、1度も喧嘩をしたことがなかったから、分からなかったんだ。喧嘩した後、どうやって仲直りすればいいかってことを。どんな風に声を掛ければいいかを。
こうなるんなら、もっと喧嘩をしておくんだった。どちらかが約束の時間に遅れてきたとか、サスペンスドラマの犯人の名前をうっかり口に出しちゃったとか、そういうレベルでいいから、些細なことで喧嘩しておくべきだった。
「喧嘩するほど仲がいい」なんて言葉があるけれどあれは、本当だ。本当に喧嘩する必要まではないけれど、いつでも喧嘩はできるような関係であるべきだ。それが、仲がいいってことなんだと思う。