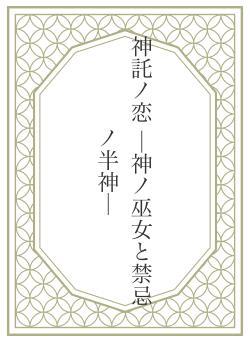最後に先輩に会ったのは、先輩が卒業する少し前のことだった。春が近づいてきているのを感じる暖かい日だった。
先輩の左腕には、薄れた傷痕を覆い隠すように小さな青い薔薇が咲いていた。白い肌に鮮やかに咲くその青薔薇は美しく映えていた。だけど先輩はファッション感覚でタトゥーを入れるようなタイプの人間ではないと思った。
「戒め、なのかもね。この先、他人に分かってほしいなんて思わないように。……そういう気持ちは罪深いものよ」
罪、だなんて言わないでほしかった。分かってほしい気持ちが罪だって言うなら、分かってあげられない人間は何なんだろうか。他人を理解できないことこそ、僕のような人間こそ、罪深いのではないだろうか。
そう言った僕に、先輩は笑ってこう言った。
「君は、優しかったよ。ちゃんと、優しかったよ」
先輩の左腕には、薄れた傷痕を覆い隠すように小さな青い薔薇が咲いていた。白い肌に鮮やかに咲くその青薔薇は美しく映えていた。だけど先輩はファッション感覚でタトゥーを入れるようなタイプの人間ではないと思った。
「戒め、なのかもね。この先、他人に分かってほしいなんて思わないように。……そういう気持ちは罪深いものよ」
罪、だなんて言わないでほしかった。分かってほしい気持ちが罪だって言うなら、分かってあげられない人間は何なんだろうか。他人を理解できないことこそ、僕のような人間こそ、罪深いのではないだろうか。
そう言った僕に、先輩は笑ってこう言った。
「君は、優しかったよ。ちゃんと、優しかったよ」