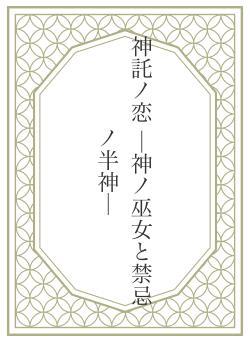先輩の左腕には赤みを帯びた無数の線が走っていた。白くて細い腕が痛々しかった。リストカットだよ、と先輩から聞いたことがある。
「自傷行為は、寄せては返す波のような痛みって表現されることがあるらしいの。綺麗だよね。文学的な表現だと思わない?」
ふっと悲しそうに微笑みながら先輩はそう言った。
文学的な表現――と言われてもその手の話に疎い僕にはよく分からなかった。
だけど、それは「綺麗」なのだろうか。綺麗という言葉で片付けられるほど容易いものではないように見えた。
「どうして、ですか……辛かったんですか、苦しかったんですか」
「どうして、なんて言葉はきっと意味を持たないよ。……あえて言うなら、痛みを、苦しみを理解されたかった、分かってほしかったのかもしれない」
先輩はこう続けた。
「あまねく全ての人間が自分のことを分かってほしいし、理解されたいと願ってる。
だけどそんなこと叶わない。だから私はもう、分かってほしいなんて願わない」
だけどそう言った先輩の後ろ姿が僕には寂しそうで、心細そうに映った。
「どうして叶わない、なんて言うんですか」
「絶対数が少ないからよ。さっきも言った通り、人間っていうのは分かってほしい、理解してほしいっていう承認欲求の塊。ある意味、それが本能なのよ。その本能を押し殺して他人を理解することに徹する人間っていうのはそういない。――だから私はそんなこと願わないし、望まない」
先輩の痛みが、苦しみが、僕にもちゃんと分かればいいと思った。僕みたいな鈍感な人間にも、分かればいいと。他人の痛みが分からない人間はたくさんいて、だけど他人の痛みや苦しみが分かってしまう繊細な人間も――先輩のような人も、確かにいる。だから、そういう人たちだけが苦しまなくていいように、悲しまなくていいようにしてあげたいと思った
「自傷行為は、寄せては返す波のような痛みって表現されることがあるらしいの。綺麗だよね。文学的な表現だと思わない?」
ふっと悲しそうに微笑みながら先輩はそう言った。
文学的な表現――と言われてもその手の話に疎い僕にはよく分からなかった。
だけど、それは「綺麗」なのだろうか。綺麗という言葉で片付けられるほど容易いものではないように見えた。
「どうして、ですか……辛かったんですか、苦しかったんですか」
「どうして、なんて言葉はきっと意味を持たないよ。……あえて言うなら、痛みを、苦しみを理解されたかった、分かってほしかったのかもしれない」
先輩はこう続けた。
「あまねく全ての人間が自分のことを分かってほしいし、理解されたいと願ってる。
だけどそんなこと叶わない。だから私はもう、分かってほしいなんて願わない」
だけどそう言った先輩の後ろ姿が僕には寂しそうで、心細そうに映った。
「どうして叶わない、なんて言うんですか」
「絶対数が少ないからよ。さっきも言った通り、人間っていうのは分かってほしい、理解してほしいっていう承認欲求の塊。ある意味、それが本能なのよ。その本能を押し殺して他人を理解することに徹する人間っていうのはそういない。――だから私はそんなこと願わないし、望まない」
先輩の痛みが、苦しみが、僕にもちゃんと分かればいいと思った。僕みたいな鈍感な人間にも、分かればいいと。他人の痛みが分からない人間はたくさんいて、だけど他人の痛みや苦しみが分かってしまう繊細な人間も――先輩のような人も、確かにいる。だから、そういう人たちだけが苦しまなくていいように、悲しまなくていいようにしてあげたいと思った