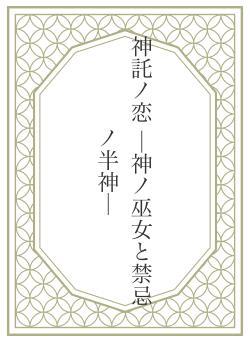僕は他人を受け止められるほど器が大きい人間じゃない。痛みに鈍感で、痛くて、痛くて堪らない痛みなんて知らない。
だから彼女が、美しく思えた。
先輩は見惚れてしまいそうなほど美しい人だった。陽に透けて輝く銀髪、陶器のように白い肌と桜色に色づいた唇に華奢な身体。
初めて出会ったときの伏し目がちで愁いを湛えた表情は妖艶な雰囲気を醸し出していて、触れてはいけないような、壊れてしまいそうな感じがした。
先輩と言葉を交わすようになったのは、僕が他人の心の機微に疎いからというのが最大の理由だろう。だいたいの人間は、泣いている女性がいたらそっとしておいてあげるものらしい。だけど、彼女ほど賢くて美しい人がどうして苦しむのか僕には分からなかった。
先輩は悲しいことや辛いことがあると決まって学校の屋上のフェンスにもたれかかり、街を見下ろしていた。
「また、何かあったんですか」
先輩が泣いているのを見たあの日から、僕はこうして声をかけずにはいられなかった。
「君、いつものことだけどしつこいね。それに図太い」
鈴の音のような澄んだ声でいつもの如くばっさりと切り捨てられる。
だけど僕は知っている。先輩がこうしてつっけんどんな態度をとるのは僕に対してだからということも。先輩が僕に心を許してくれている証だというのは思い上がりではないと思う。
最初は張り付いたような笑顔とよそいきの声で流されていたけれど、僕が何度も先輩に声をかけるうちに、ぽつりぽつりと先輩は本当の姿を、痛みを、見せてくれるようになった。
だから彼女が、美しく思えた。
先輩は見惚れてしまいそうなほど美しい人だった。陽に透けて輝く銀髪、陶器のように白い肌と桜色に色づいた唇に華奢な身体。
初めて出会ったときの伏し目がちで愁いを湛えた表情は妖艶な雰囲気を醸し出していて、触れてはいけないような、壊れてしまいそうな感じがした。
先輩と言葉を交わすようになったのは、僕が他人の心の機微に疎いからというのが最大の理由だろう。だいたいの人間は、泣いている女性がいたらそっとしておいてあげるものらしい。だけど、彼女ほど賢くて美しい人がどうして苦しむのか僕には分からなかった。
先輩は悲しいことや辛いことがあると決まって学校の屋上のフェンスにもたれかかり、街を見下ろしていた。
「また、何かあったんですか」
先輩が泣いているのを見たあの日から、僕はこうして声をかけずにはいられなかった。
「君、いつものことだけどしつこいね。それに図太い」
鈴の音のような澄んだ声でいつもの如くばっさりと切り捨てられる。
だけど僕は知っている。先輩がこうしてつっけんどんな態度をとるのは僕に対してだからということも。先輩が僕に心を許してくれている証だというのは思い上がりではないと思う。
最初は張り付いたような笑顔とよそいきの声で流されていたけれど、僕が何度も先輩に声をかけるうちに、ぽつりぽつりと先輩は本当の姿を、痛みを、見せてくれるようになった。