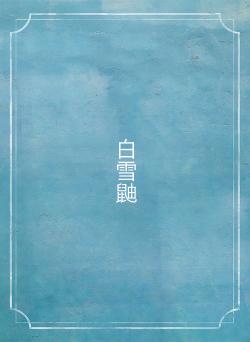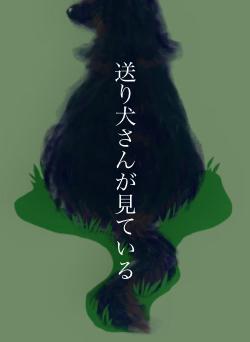***
どれほど長い間、青い髪の男の人は、わたしを抱えて走り続けているのでしょう。
とても人間とは思えない。いえ、もしかすると、この方も人間ではないのかも。
すっかり抵抗する力も無くなり、わたしは腕の中でぐったりとするばかり。
ーーーこれからどうなるのかしら…。義嵐さま…仁雷さま…。
「儂の塒が見えてきた。」
声の示す方に目をやります。
そこは断崖に掘られた大きな洞窟でした。
男の人は、洞窟の前の足場に立つと、わたしをその場に落とします。
「……あうっ。」
硬い地面に打ち付けてしまった箇所をさすりながらヨロヨロと立ち上がり、わたしは目の前の洞窟に目を凝らします。
中は薄暗く、様子が分かりません。どこまでも深く続いていそうな、気味の悪さを覚えました。
「……あの、なぜわたしをここへ…?
ええと…。」
呼び名に困っていると、男の人はなんともあっさりと、名を教えてくれました。
「儂は青衣。
この南の山々と、瓢箪池を治める主じゃ。」
瓢箪池、と聞いた時、わたしは義嵐さまの見せてくれた絵巻物を思い出しました。
南方の…瓢箪の形をした“狒々の池泉”。
とするとこの方が、第二の試練の…。
「青衣、さま……。わたしを連れて来たのは、巡礼と何か関係があるのですか…?」
「ほう、これは話が早い。
犬居の娘、話の続きは塒の中じゃ。」
そう言い、青衣さまは先導して、洞窟の中へ入って行きます。
わたしのことを見ていない…。今なら逃げられるかも…。
「…言っておくが、儂から逃げようなどと考えるなよ。この山には忠実な“猿共”を散らしておる。人間の小娘の手足を折って連れ戻すくらい、難しくもない。」
「…っ!」
すっかり見抜かれているようでした。
言う通りにするほかありません。わたしは促されるまま、暗く不気味な洞窟の中へ、勇気を振り絞って足を踏み入れました。
外から見ると様子の分からなかった洞窟も、奥へ奥へ進んでいくと、小さな灯りが見え始めました。通路に等間隔で松明が置かれているのです。
さらに通路を進んでいくと、急に開けた空間に出ました。
「……まあ…。」
洞窟内部の硬い岩を切り出して、外に運び出したのでしょう。壁も床も天井も広く、まっさらな平面の岩肌が見えています。
どのくらいの広さがあるのかは分かりません。ですが、大きな蔵や民家がいくつも建ち、最奥には朱塗りの社殿のような建物が構えています。この空間だけで、小さな村ひとつ分はありそうです。
そして驚くべきことに、そこで働いているのは皆、白い毛皮の“猿”なのです。
重い荷を運ぶ者、薪を割る者、魚を捌く者。人さながらの仕事ぶりです。
しかし、彼らの目には活気がありません。毛並みは乱れ放題で、中には痛々しい怪我を負っている者も。それでも一心不乱に働く姿からは、どこか…奴隷のような怖ろしさを覚えました。
その原因はまさか、目の前を歩くこの男が…?
「犬居の娘、足を止めるなよ。」
「は、はい…っ。」
青衣さまは、最奥に構える社殿の中へと入って行きました。
わたしもそれに続き、内部に足を踏み入れます。
内部は、外観と同じ朱塗りの柱が立ち並ぶ、広い板の間でした。
「貴様もそこへ座れ。」
「……はい…。」
命じられるままに、その場に座り込みます。
すかさず、わたしの背後に白毛のお猿が二匹、音もなく控えます。わたしが逃げ出さないよう見張るためでしょう。
片方のお猿は、右目に痛々しい裂き傷の痕を残していました。
青衣さまのほうを見直せば、煙管を蒸し始めていした。あたりに嗅ぎ慣れない匂いが漂います。
ふと、彼が懐から取り出した光り物に、わたしは目を奪われました。それは金色で、手の平に収まりそうな大きさの、円形の金属板でした。
美しいけれど、見たこともない装飾品です。何かの神具なのかしら?数珠に通して、首から提げています。
青衣さまはしばし一服した後、満足げにわたしのことを眺めます。
「ようやっと手に入れたわ。犬居の娘。十年待ち侘びた好機じゃ。」
十年前…。わたしの前の犬居の娘が、生贄に選ばれた年です。
「…わたしを、どうなさる気なのですか?」
「儂の言葉を遮るな、娘。
貴様は狒々の池泉の、試練の内容を知っておるか?」
わたしは首を横に振ります。
試練の内容を事前に聞くことが出来ませんでした。わたしが知っているのは、これから向かう場所が“狒々の池泉”と呼ばれていること。そして、そこで“宝”を得なければならないこと。
「ならば、儂が教えてやろう。
貴様はこれから瓢箪池へ行け。
そして、瓢箪池の底に沈んでおる“宝”を、儂の元へ持ってくるのじゃ。」
「……え?」
それは意外な言葉でした。
まさか本当に、この方が第二の試練を課すなんて。ですが、ではなぜこんな手荒な、拉致紛いな真似を…?
「巡礼は、義嵐さまと仁雷さま…山犬のお使いさまと一緒に行動するよう言われております。
なぜわたし一人だけを連れて来たのですか?」
「フン、野犬共の力など要らぬだろう。
これは貴様が生贄となるための巡礼。貴様一人で挑まず、何の意味があろうか?」
「………。」
青衣さまは長く煙を吐き出します。
自信に満ちた物言い。君影さまのように、これまでの巡礼をよく知る者なのだとしたら、やはりわたし一人で…?
ーーーでも…。
仁雷さまは仰っていました。
決して離れるな、と。
試練には危険が伴う。本当にわたし一人で挑むべきなの…?
それに、ひとつ気にかかることがあります。
「…青衣さまが瓢箪池の主なのでしたら、その宝もあなたの物では?
何か、得られない理由があるのですか?」
その言葉を発すると、一瞬で空気が凍りつきました。
青衣さまの顔がみるみる険しくなっていき、わたしの背後のお猿達が、小さく怯えた声を漏らし始めます。
「…生意気な小娘じゃ。儂に訊ねることは許さぬ。女は黙って儂の命じるままに働けばよいのじゃ。」
大きな体。恐いお顔。脅す言葉。
わたしは思わず怯んでしまいます。
しかし、その反応がますます、わたしの不信感を煽りました。雉子亭の君影さまと大違いなのです。高圧的で得体が知れない。
何より、この者は仁雷さまと義嵐さまのことを…、
「……そ、それに、あのお二人は“野犬”ではありません。口を謹んでください。」
青衣が握り締めていた煙管が、小枝のようにパキンと割れました。
「…小娘…、本当に生意気な奴じゃ。
腕の一本でもへし折ってやらねば、聞く耳を持たぬらしいな…?」
「!?」
大きな青衣の体が、みるみる膨れ上がります。
“山のよう”と形容できるほどに、腕や脚や胸の筋肉が盛り上がり、青い髪の毛が長く長く伸び始めます。
社殿の高い天井いっぱいに大きくなった青衣はもはや人ではなく、青い毛皮に身を包んだ“狒々”そのものでした。
【キ、キィー!!】
わたしの背後にいたお猿達は、とうとう悲鳴を上げて、転がるように社殿から逃げ出してしまいました。
しかし、右目を怪我したお猿が足をもつれさせ、その場に倒れ込みます。恐怖で足が竦み上がってしまったのです。
逃げ遅れたお猿を気にかけることなく、青衣はわたしに迫ります。水晶玉のように大きな二つの目玉が、わたしを強く睨みました。
剥き出しの歯は鋭く、弱いわたしなど、ひと噛みでやっつけてしまうでしょう。
鋭い爪は刀のよう。襲われてしまえば、恐らく無事では済みません。
【小娘、最後の機会じゃ。
瓢箪池へ行き、儂に宝を献上すると誓え。】
なんて恐ろしい姿。
人の身であるわたしが敵うはずもない。
震える唇で、なんとかこれだけを口にすることが出来ました。
「……わ、わたしは、小娘ではありません!
“早苗”と、いうのです…!」
青衣が大きく口を開きました。
わたしを動かすことを諦めたのです。
【貴様は気に入らぬ!
また十年、次の犬居の娘を待てばよいわ!!】
青衣の巨大な手が襲いかかって来るのが、ひどくゆっくりに見えました。
恐怖と緊張で汗が噴き出る。しかしこのままではわたしだけでなく、逃げ遅れたお猿も巻き添えに…。
【キッ!】
わたしはとっさに、お猿の体を力の限り、遠くへ突き飛ばしました。
その時頭の中に浮かんだのは義嵐さまと…仁雷さまのお顔。そして、亡き母の面影。これが走馬灯というものでしょうか。