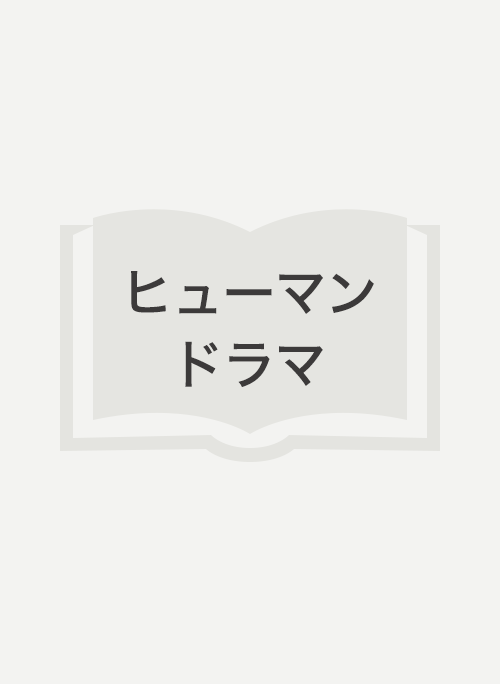「……べつに、嘘ついてないし」
やめろよ、そうやっていちいち俺の心を読み取るのは。
せっかく諦めがついたのに諦められなくなるだろ。
「何年、俺が小牧といると思ってるんだよ。中学一年の頃からの他校の顔馴染みで、高校入って二年目だぞ。おまえの嘘なんて秒で読み取れるっつーの」
こんな話になるなら、のこのことあとをついて行かなければよかった。
「だからなんだよ。俺が嘘ついてるとでも言うのかよ」
家族じゃなければ、ただの他人だ。
瀬戸が俺の全てを理解してるなんて、そんなことあり得るはずがない。
それなのに。
「小牧、おまえさぁ……誰よりもレギュラーに選ばれたいって言ってたじゃん」
──やめろ、やめろ。
せっかくの決心が揺らいでしまいそうになる。
「レギュラーに選ばれて親を認めさせてやるってずっと意気込んでたじゃん」
それは──…
「だから、毎日つらい練習も頑張ってここまで上り詰めたんだろ。それ全部、なかったことにするっつーのかよ!」
……やめろよ。
頭の奥で、ズキズキと痛みが増す。
「せっかく手に入れたレギュラーをみすみす手放して、他のやつが繰り上げでレギュラーに選ばれて、それでお前は後悔しないのかよ!」
──プチッ
〝何か〟が外れる音がして。
そして、頭の中は真っ白になり──
「後悔しまくりに決まってるだろ……!!」
怒号にも聞こえる声が漏れた。
「俺がどれだけ……」
どれだけ、レギュラーを目指していたか。
やっとの思いで手に入れたんだ。
「……悔しいに決まってるだろ……っ」
──そのときの俺の声は、まるで泣き叫んでいるようで。
俺、やっぱりレギュラーを諦めたくないんだ。
そう実感した。
もうあとには引けなかった。
「じゃあ、お前が出ろよ」
静かに落ちた言葉に、
「だから俺じゃあ無理なんだって……」
「お前の実力を勝手に決めつけてるんじゃねーよ!」
俺の言葉を遮るようにして現れたそれに驚いて、思考停止していると。
「自分は下手でずば抜けてる特技もなくて、足手まといになるから? ……ハッ。そんなの誰が決めたんだよ。誰が言ったんだよ」
──そんなの誰が、なんて。
「俺が……!」
怒りが爆発しそうになる。
けれど、落ち着け。
ここで感情的になるな。