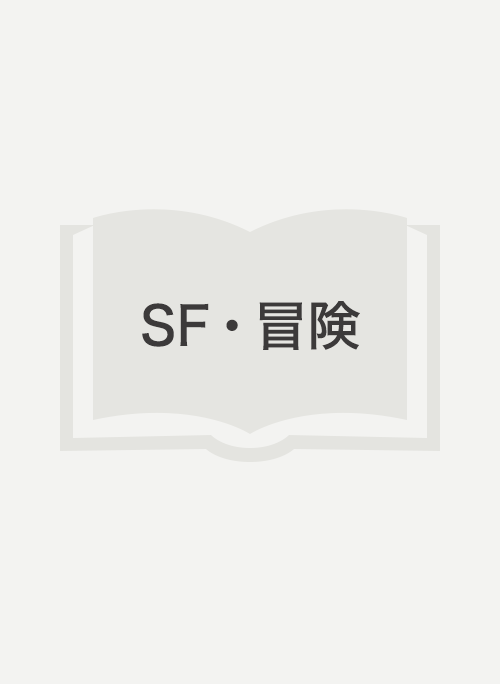一定の歴史がある村には必ず図書館があり、そこに独自の郷土史が収められている。逆に言えば、図書館のない村に大した歴史はない、ということでもあった。
さてこの村には、レンガ造りの立派な図書館があった。
ヤマトの期待通り、図書館の展示室には親書などの歴史的書物が置かれ、壁には村の大まかな成り立ちを説明する展示、著名な画家が描いたとされる絵画、そして歴代村長の肖像が掲げられていた。
ところどころに「正直村」という文字を見つけることができるものの、それでここが間違いなく正直村であるということにはならない。ヤマトは相変わらず疑い深く、それらを一つずつ検分していった。
『歴史の全てをここに記せるわけではない。』
そんな言い訳とも誠実さの発露ともとれる前置きの年表によれば、正直村の歴史とは、すなわちうそつき村の住人に騙される歴史であった。
うそつき村の住人の流入があって、それが村人を混乱させ、その都度新しい決まりだの制度だのが作られる。多くはそうして騒動が収まっていたが、上手くいかなかったときは決まって魔女狩りのようなことが行われた。
うそつきの嫌疑をかけられた者が、磔(はりつけ)にされて火にあぶられる。あぶられた者は「熱い、熱い」と泣き叫び、それに対して「うそをつくな」と周りがなじる――そんな様子が絵画によって表されていた。
そういった混沌の歴史は、王都から番兵が配備されたことで、一応の収束をみる。入村者管理の徹底により、「この村にうそつきはいない」という共通認識が広まったのだ。
『残酷な魔女狩りが行われることは、もう二度とないだろう。』との言葉で、この村の年表は終わっていた。
平和。それはヤマトには退化であるように感じられた。ちょうど、野性動物が外敵のいない檻の中で飼われ、闘争力を失うのと同じように。
自分はそれが嫌で旅を続けているのだという自覚が、彼の中にはあった。一度旅をやめてしまうと、旅をするだけの気力や体力といったものが、己の中から失われてしまうのではないか。ヤマトはそれを恐れていた。
年表の次には、村の特産品についての展示があった。正直村がある丘の岩壁には多くの黒頭白鷺(こくとうしらさぎ)が巣を作っており、村人は古くからその卵を採って重要な栄養源としていた。
さてこの村には、レンガ造りの立派な図書館があった。
ヤマトの期待通り、図書館の展示室には親書などの歴史的書物が置かれ、壁には村の大まかな成り立ちを説明する展示、著名な画家が描いたとされる絵画、そして歴代村長の肖像が掲げられていた。
ところどころに「正直村」という文字を見つけることができるものの、それでここが間違いなく正直村であるということにはならない。ヤマトは相変わらず疑い深く、それらを一つずつ検分していった。
『歴史の全てをここに記せるわけではない。』
そんな言い訳とも誠実さの発露ともとれる前置きの年表によれば、正直村の歴史とは、すなわちうそつき村の住人に騙される歴史であった。
うそつき村の住人の流入があって、それが村人を混乱させ、その都度新しい決まりだの制度だのが作られる。多くはそうして騒動が収まっていたが、上手くいかなかったときは決まって魔女狩りのようなことが行われた。
うそつきの嫌疑をかけられた者が、磔(はりつけ)にされて火にあぶられる。あぶられた者は「熱い、熱い」と泣き叫び、それに対して「うそをつくな」と周りがなじる――そんな様子が絵画によって表されていた。
そういった混沌の歴史は、王都から番兵が配備されたことで、一応の収束をみる。入村者管理の徹底により、「この村にうそつきはいない」という共通認識が広まったのだ。
『残酷な魔女狩りが行われることは、もう二度とないだろう。』との言葉で、この村の年表は終わっていた。
平和。それはヤマトには退化であるように感じられた。ちょうど、野性動物が外敵のいない檻の中で飼われ、闘争力を失うのと同じように。
自分はそれが嫌で旅を続けているのだという自覚が、彼の中にはあった。一度旅をやめてしまうと、旅をするだけの気力や体力といったものが、己の中から失われてしまうのではないか。ヤマトはそれを恐れていた。
年表の次には、村の特産品についての展示があった。正直村がある丘の岩壁には多くの黒頭白鷺(こくとうしらさぎ)が巣を作っており、村人は古くからその卵を採って重要な栄養源としていた。