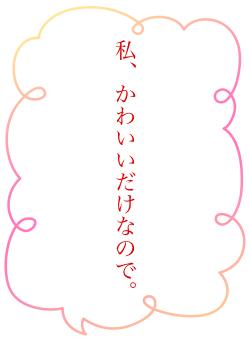「そういやさ。なんであの日、死にたいと思ったわけ?」
「別に。天気も良かったし、死ぬならあの日だと思っただけで、特に特別な理由なんてないです。私、恒常的に死にたいので」
「…………」
「でも、今は先輩がいるからいいです」
「……そう」
先輩が、顔を顰めて私から目を逸らす瞬間が好きだ。日を追うごとに増えていく、先輩の身体に出来た生傷をなぞる瞬間が好きだ。新しく出来た傷に口付け出来るのは、私だけだから、好きだ。
先輩を見ていると、呼吸することすら忘れてしまって、死にそうなほど胸が苦しくなるから、きっとこれが恋なんだと思う。
遠くを見つめる先輩の横顔を見ながら、そんなことを考えていた。
先輩のことを初めて知ったのは、1年前の春だった。
先輩はある意味有名人だったから、仲良くしている別の先輩から話を聞くことはあったけど、実際に見たのは初めてだった。
初めて見た時、まるで深夜2時の街中みたいな人だと思った。夜の空気を持つ人だった。いつも屋上にいて、静かにボロボロの本を読んでいた。先輩の周りだけ時が止まっているように感じたし、多分、実際止まっていたような気がする。
先輩は、身体中に出来た生傷を隠すように、いつも長袖を着込んでいた。それなのに暑苦しい感じはしなくて、先輩の周りだけずっと12月のような冷たさを纏っていたから、その冷たさに触れてみたいと思った。
それ以来ずっと、私は先輩に縋って生きている。
私が独りで生きていくには、この現実は厳しすぎて息が止まりそうだったから。だから、自分よりも傷だらけな先輩を思い描くことで、まだ生きていけると思い込むことで、命を先延ばしにした。
両親に、この先の人生を押し付けられた。
────大丈夫。先輩みたいに暴力を受けてるわけじゃないし。
先生にセクハラをされた。
────大丈夫。どれだけ汚れたって、私には先輩がいるから。私よりも汚れた、先輩が。
クラスメイトに陰口を言われた。
────大丈夫。こんなの、全部虚構だ。私には本物だけが、先輩だけが、いればいい。
「大丈夫、大丈夫、大丈夫。死にたいなんて私ごときが言ってどうするの。だって私には、先輩が、せんぱいが……」
そうやって、話したことすらない先輩に縋って縋って縋って縋って縋って、生を繋いで。
あぁ、もうダメだ。
「死にたい」
ある日突然、プツリと糸が切れた。
きっと、死にたい理由が増えすぎてしまったのだ。生きてる理由はちっとも増えてくれはしないのに、死にたい理由ばっかり雪だるま式で増えていくから現実は不公平だと思う。
死にたくなった。消えたくなった。汚い。息を吸って吐いて、肺に空気が溜まって、澱んでいく。
逃げなくちゃ。こんな世界から、早く。早く。早く。
その衝動に身を任せて首を吊る準備を整え、目蓋を閉じて……先輩のことを思い出した。
どうしよう。どうしよう。このまま私が死んだとしたら、この汚い世界に先輩を置いて行ってしまうことになる。散々縋ってきた先輩のことを、1人ぼっちにしてしまう。
それは、少し嫌だった。
抜け駆けをするみたいだと思ったし、私のいない世界で先輩が生きていることが、どうしようもなく嫌だった。
だから先輩に、心中を持ちかけた。
「ねぇ先輩。私と心中しませんか?」
私と一緒に、死んでくれると思った。
だって先輩は私よりも傷だらけなんだから。絶対に、私よりも生きる理由を持っていないに決まっている。
「……ごめん。死ぬなら、もっと有意義に死にたいから。君とは死んであげられない」
それなのに先輩は、私と心中してくれなかった。
その瞬間は悔しくて悲しくて、それこそ死んでしまいそうだったけれど、今ではそれで正解だったような気がしている。
だって、死んでしまったら、こんなに心地よい先輩の冷たさに触れることは出来なかっただろうし。
そう思って、先輩のひんやりとした指先をなぞる。傷だらけの手はゴツゴツとしていて、先輩もやっぱり男の人なんだなぁと実感して少し胸が熱くなった。
先輩の手は、いつも氷でも触っているかのように冷たい。心地よさすら通り越して、冷たすぎて息が止まりそうになるほどだ。
でも、先輩になら、息を止められて殺されたってうれしいと思ってしまう。このまま先輩が私の息を止めてくれたら、どんなにいいだろう。
首に手をかけて、霞む意識の中で先輩の声が聞こえて、そのセリフは、「愛してる」がいいな。多分、違うだろうけど。
私はその、仄暗い思考に蓋をして、目を伏せて俯く先輩にそっと囁くように声をかけた。
「先輩。私のこと、もう好きになりましたか?」
私が先輩に心中を持ちかけてから、3ヶ月が経った。先輩は、幾度となく使われてきた、心中を誘う私からの言葉に、首を横に振って答えた。
「ごめん。まだ、君と死んであげられない」
先輩はまだ、死ぬための意義とやらを見つけられていないらしい。
「ふふ、そうだと思ってました。……私はもうすっかり先輩のことが好きですから、今日も少しだけ、先輩の地獄を貰ってあげますね」
すっかりっていうか、多分、初めて見た瞬間から好きだったけど。だって私が先輩を心中にさそったのは、私のいない世界で先輩が一秒でも長く息を吸うのが嫌だったからだもん。
心の中でそう呟いて、狡い私は先輩の頬に手を添えた。そして、何処か遠くを見つめている先輩の興味を少しだけでも引くために、先輩の薄い唇に口付ける。
ねぇ先輩。これから私達、どうしますか。
地獄みたいな現実は変わらないままですか。
それでも私、先輩が隣にいてくれるなら、このままだっていい気がしてますよ。先輩が私の生きる理由になってくれてもいいですよ。
私のこと、どう思ってますか。せめて嫌いではないですか。いつ好きになってくれますか。
あーあ。少しでも早く死ぬためにこうしてるのに、先輩とならこのまま生きてもいいとは思ってるとか、矛盾しすぎてて笑えちゃいますね。
先輩はいつも冷たすぎて迂闊に話しかけられないから、キスをして私の想いを注ぎ込む。
先輩はいつも言葉を飲み込んでしまいがちだから、私はその言葉の欠片だけでも触れてみたくて、キスをする。
先輩とのキスは甘くて、でもそれ以上に苦くて、その味が忘れられないから、忘れたくないからやめられない。
いい加減、息が苦しくなってきたので先輩から唇を離して、冷たい空気を吸い込む。
私達の間で、糸を引いていた唾液がプツリと千切れた。
それを舐めとる先輩の様子が生々しくて、これでしか先輩が生きていることを感じとることが出来ないから。
「またキスするの?」と先輩に言われるたびに、私がキスをしたがるのは先輩のせいなのにって言いたくなる。言わないけど。
ぼぉっとそんなことを考えていると、先輩がまた、噛みつくように私の唇に先輩の唇を重ねた。
「せんぱい」
キスをしたがるのは、先輩だって同じなのに。
そんな言葉を、唇を塞がれているせいで言葉にすることが出来ずに、喉の奥へと飲み込んだ。
あぁ、でも、やっぱり先輩とのキスは好きだなぁ。
先輩の考えていることが、少しだけ分かるような気がするから。先輩と、少しでも繋がれるから。
それから、私はゆっくり目を閉じた。
本当はもう、私が死にたがっていないことがバレませんように。
────一生先輩が私のことを、好きになりませんように。