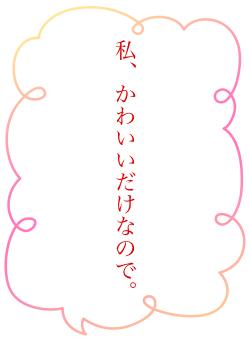「ねぇ先輩。私と心中しませんか?」
よく晴れた日だった。僕達以外誰もいない屋上で、柵を乗り越えた君が口角だけを上げて笑っていた。
「……なんで」
僕が何とか喉から答えを絞り出すと、彼女はクツクツと可笑そうに笑い声を上げる。
「その『なんで』は、どうして先輩が私と心中しなければいけないのか、の『なんで』ですか? それとも、私がどうして死にたいのか、の『なんで』ですか?」
「いや。僕と君は初対面なのに、『なんで』僕が心中の誘いに乗ると思ったのかが知りたくて」
「なんと、そこですか。それなら理由は、先輩が1番よく分かってますよね?」
その瞬間、風が吹いて彼女のスカートがヒラリと揺れた。今にも落ちてしまいそうな場所にいるくせに不適に笑った彼女は、柵を飛び越えてこちら側に戻り、歌うように軽やかに口を開く。
「だって先輩、有名ですもん。いつも長袖だし、絆創膏なんて貼ってても、そんなのじゃ誰も誤魔化されませんよ?」
そして、僕にツカツカと近づいてきて僕の腕を掴み、制服のシャツの長袖をまくり上げた。肘まで上げたシャツから覗いた、生傷とタバコを押し付けられた跡だらけの肌が外気に触れて、少し痛い。
顔をしかめた僕を見た彼女は、声を潜めて囁くように呟いた。
「先輩の家、家庭内暴力が酷いから関わらない方がいいっていうの、後輩の中でも有名な話ですから。……そんな先輩なら、私と一緒に死んでくれますよね? 先輩も、これ以上生きてる理由なんて持ってませんよね?」
人形のように整ったその顔に、嬉しくて堪らないとでも言うような満面の笑みを浮かべて。
死にたがりな後輩と、今にも死にそうな僕が出会ってから3ヶ月ほど経った、金曜日の放課後。
僕達は寒いわけでもないのに、身を寄せあうようにして学校の屋上の端に座っていた。
「そういやさ。なんであの日、死にたいと思ったわけ?」
「別に。天気も良かったし、死ぬならあの日だと思っただけで、特に特別な理由なんてないです。私、恒常的に死にたいので」
「…………」
「でも、今は先輩がいるからいいです」
「……そう」
僕は、彼女のベタつくような甘い声から逃れるように、彼女から目を逸らして答えた。
死にたい。恒常的に死にたい。僕だって、どうにかして死にたい。
学校ではイジメ、家では父親からの暴力。言語化すると、この世の地獄のオンパレードみたいで少し笑える。いや、笑えないか。今のは忘れて欲しい。
それでも、生きるためには働かないといけないし、逃げ出すにはお金がいる。
そんな僕が唯一、自分の所有物だと胸を張って言えるのは命だけだった。何せ、死は誰にでも平等に訪れてくれる素晴らしいコンテンツである。神に感謝しよう。
だから、今死ねない理由なんて、その唯一を1番有意義な形で使いたいと願っているだけなのだ。それの何が悪いのか。
それなのに、この死にたがりな後輩に出会ってしまってから、僕は少しおかしい。端から崩れていくように、浸食されるかのように、自分の感覚が狂っていっている気がする。
彼女は、誰からも目立つ人気者の後輩だった。どこにいたって人の目を集めた。こんな僕でも、存在を知っていたぐらいだ。学校のアイドルだと言っても過言ではないだろう。実際、彼女はそう呼ばれている。
その呼び名の通り、彼女には才能があって、顔がよくて、性格も明るかった。
それなのに、僕が大事に守ってきたものを、突然現れてアッサリと奪おうとした彼女のことが許せなかったから。
「……ごめん。死ぬなら、もっと有意義に死にたいから。君とは死んであげられない」
そう言った僕を見て、彼女は呆気にとられたような、悲しそうな顔をしてボタボタと涙を落とし始めた。驚いた。遠くから見ていた彼女はこんな風に、苦しそうに泣いたりなんてしない人種だと思っていた。
「あは。なんですか、それ。先輩、死に意義なんてないですよ。死んだら全部終わるだけです。っ私は、今すぐ死にたいんです。こんな汚れた世界、もう息もしたくない!!」
そして、嗚咽を漏らしながら叫び、その場にしゃがみ込んだ彼女は言葉を続けた。
「私、生きてたい理由は1つもないのに、死にたい理由はたくさん見つかるんです。死にたいんです。消えたいんです。なんでですか、先輩もそうじゃないんですか!? だって私、私よりも苦しそうな先輩を見て、私には仲間がいるんだって思ってて、だから」
「そんなに死にたいなら、1人で死ねばいいだろ。僕を巻き込まないでくれ」
「……それは、本当にこの世界に1人ぼっちになっちゃうから、絶対に嫌です…………」
この後輩は、なんて面倒くさいことを。それを言うなら、死んだ後の方がずっと1人ぼっちだろう。
呆れたような目で彼女を見ている僕に、彼女はその後も必死に説得を続けた。
両親が不仲なこと。クラスメイトに本当の友達なんていないこと。先生からセクハラをされていること。
まるで唄でも紡ぐように語る様子は、そのドロドロした内容とは相反するように綺麗で、何だか僕まで涙が出そうになった。
そして、僕よりも絶対的に輝くところにいた一等星が、僕と心中したいと思うぐらい堕ちてて薄汚れていることを知り、仄暗い喜びに胸が震えた。
しかし、彼女がどれだけ話を続けたって、まだ死にたくない僕と今すぐ死にたい彼女の意見が一致するわけがない。例え、濃度は違えど、同じ絶望を胸に秘めていたとしても。
それから30分ほどが経ち、ようやく僕の意思の固さに気付いたらしい彼女は、ついに観念したかのように形のいい唇から呆然と声を漏らした。
「……何でですか。先輩なら、先輩だけは、私と心中してくれると思ったのに」
それはなんというか、申し訳ないけれど。
しかし、彼女はまだ諦めたわけではなかったらしい。しばらく俯いていた彼女は、唐突に顔を上げて僕との距離を詰めた。
そして、深い闇を炎に焚べて、爛爛と輝やかせた瞳で、僕を真っ直ぐ見つめて言葉を紡ぐ。
「それなら、私と勝負しましょうよ」
僕は、この視線にめっぽう弱かった。
ギラギラ輝く彼女の目を見ることが耐え切れなくて、顔を顰めて目を逸らすことで、その視線から逃げることしか出来なかった。
しかし、彼女は僕が逃げることを許してくれなかったようだ。僕が目を逸らしても、覗き込むようにして僕を真っ直ぐに見つめてくる。
きっと彼女は何度だってそうすると思ったから、僕も諦めて彼女の目を見つめ返すことにした。その瞳の炎が僕にも燃え移りそうで、少し怖いと思った。
「…………勝負?」
「そうです。先輩が私を惚れさせて、生きる理由になってくれたとしたら先輩が死にたい時に一緒に死んであげます。それまでは、先輩の地獄みたいな世界を少しだけ貰ってあげます」
そして彼女は、この世界には2人だけだと主張するように僕の制服のネクタイを引っ張り、鼻先が触れ合うほどの距離に顔を近づけて囁く。
「その代わり、先輩が私のことを好きになっちゃったら、その瞬間に一緒に死んでください。私と心中してください」
あ。今、燃え移った。
その生を諦めきった表情に惹かれて、鈍く輝く目の恐ろしさに惹かれて、僕はその瞬間息が止まったような感覚に陥いる。
彼女があまりに死を真っ直ぐに見つめているから、うっかり引き寄せられて、焦がされて、恋をしてしまったんだ。
しかし僕は、それを表面に出さないように必死で表情を取り繕い、彼女の真似をして口角だけを上げる。それを了承の合図だと受け取ったらしい彼女は、微笑んで僕の両手を嬉しそうに握りしめた。
それ以来、僕と彼女は、毎週金曜日の放課後に屋上で会うようになった。
彼女と会う時。彼女はいつも、
「先輩。私のこと、もう好きになりましたか?」
という確認の言葉を口にする。それはきっと、僕と彼女だけの合言葉のようなものだった。
その、僕を死へ誘う質問に、僕はいつも首を横に振って答える。
「ごめん。まだ、君と死んであげられない」
僕の返事を聞き、諦めたような顔で笑った彼女を見て、僕は謝る代わりに手首をキツく握りしめた。
あぁ、認めよう。僕はもう、分かっている。
────僕はとっくに、彼女のことを好きになってしまったのだと。
今の僕は、完全におかしいのだ。身も心も、全てを彼女に浸食されてしまった。
死にたがりな彼女が僕に痺れを切らして死のうとしたなら、彼女を庇って死のうとすら思っているし、そうやって死ぬことが僕にとって一番有意義な死に方だとすら思っている。
それぐらい、彼女のことが好きだ。安易な言葉で言うならば、命に代えてもいいぐらい好きだ。
それでも彼女の誘いを拒否し続けるのは、彼女のせいで、僕の人生自体の意義を見つけ出してしまったからだ。彼女の言葉で言うならば、生きる理由というやつを。
僕は彼女と過ごすうちに、彼女の姿をもう少し見ていたくなってしまった。生きているのに、恐ろしいほど静かに燃える瞳を、もっと。いつまでも、隣で。
「ふふ、そうだと思ってました。……私はもうすっかり先輩のことが好きですから、今日も少しだけ、先輩の地獄を貰ってあげますね」
そう言って、彼女は僕の唇にそっと触れるように口づけをする。
死は、僕の唯一の救いだ。
何も持っていない僕に、唯一残されたラストチャンスのようなもので、大切に大切に、どれだけ苦しくても手放さずに持っていたものだ。
それなのに、彼女になら、その唯一をあけ渡しても構わないと思っている自分がいる。それは、この美しくて、厭世的な彼女の生が引き換えに手に入ると知っているからだろうか。
僕の死よりも価値のある彼女の生を得られるからだろうか。
そうかもしれない。そんな気もする。
お互いがお互いのせいで死ねないなんて、死んではいないのに、それでは実質心中みたいなものじゃないか。
僕だって、この状態が異常だということぐらい分かっている。彼女と僕の歪な関係は、いつか崩れ去る日が来るのかもしれない。
誰かに見つかってしまう日も来るかもしれない。
だから、何だというのだろう。心の中は僕達だけの世界だ。誰にも犯せはしない。立ち入らせない。彼女と僕の関係は、永遠のものだ。
そんなことを考えながら、目を閉じた彼女の顔をぼんやりと見ていた。
あぁ。僕にはもう、彼女のこと以外何も考えられそうにない。
彼女とのキスは、甘い毒を口移しされたみたいに思考が蕩けて、何も考えられなくなるから嫌いだ。クラクラして、真っ暗なはずの世界がチカチカと輝いて見えるから嫌いだ。
もしかしてこれが、彼女の言う、『先輩の地獄を貰ってあげる』とやらなのだろうか。
確かに、彼女のどろりとした甘い毒に浸っている間は現実のことなんて入り込む余地がなくなるから、彼女の言っていることは一理あるかもしれない。
彼女が、僕からゆっくりと唇を離す。そして、切なそうな、掠れた声で僕を呼んだ。
「せんぱい」
彼女は、うっすらと涙の膜を張った瞳で、真っ直ぐ僕を見つめている。
さっきまで、何を考えていたっけ。そうだ、彼女との関係性のことだった。
異常だからなんだ。間違ってるからどうした。誰かに何かを言われたぐらいで止まれるような想いなら、最初から抱かないように生きてきた。
そんなの、君の前ではどうだっていい。
僕にとって正しいのは、ただ目の前にいる君だけだ。信じるのは君だけでいい。盲目だと誰に言われたって構うものか。
不幸も君とだけ。
絶望も君となら。
死すらも、君と共有出来たら。
それはきっと、世界で一番美しいものになるだろう。
僕はそんなことを考えながら、彼女の頬に手を添えてもう一度口づけ、あっさりと、その唯一を手放した。