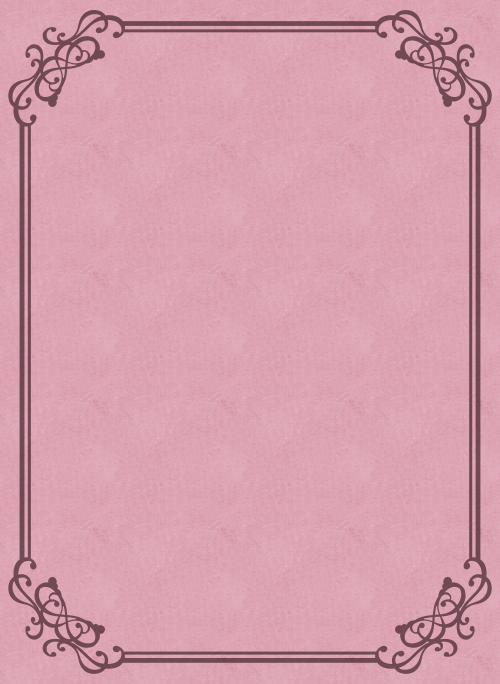夕方。帰宅途中にまたプール施設へ足を運んでいた。円盤は昨日と変わらず、そこに鎮座していた。機械的で、無機質。未来感があると言えばそうだし、想像通りの姿だと言えば期待値以下に思える。音は聞こえず、カメラには相変わらず映らない。昨日と違うのは、まだ明るい時間なのでその全姿が見えるということくらいだ。周りに通行人はいたが、なにか異変を指摘することも、騒ぎ立てる者もいなかった。
見えている僕だけがおかしいのだと、世界はそう言っているようだった。
「あのゆーふぉーみたいなやつ。ゆーふぉーじゃなくてタイムマシンなの」
明星瀬都奈はそう言った。
「えっ、見えるの?」
思えばこの質問はあまりにも頓珍漢め滑稽なモノだったのだが、その時の僕にとって誰かがあの“異常”を認識してくれていることのほうがずっと嬉しかった。だってゆーふぉーだぜ?
未確認飛行物体だぜ。
光の反射とか、見間違いとか、鳥とか飛行機じゃない。もっと、堂々と、それが当たり前で普通であるかのように《《そいつ》》はこの日常に居座りやがったんだ。東京に現れたガ○ダムのように、創造上でのみ存在していたモノが現実に紛れもなく現れたんだ。だけど、誰も気にしない。気が付かない。あんなにもはっきりと見え、巨大で、プール施設の屋上に登れば手が届く距離にあるのに、だれも。その一方で、日が変わってもなお見えるその未確認浮遊物体は『夢じゃないぞ』と、告げていた。それが誰にも理解してもらえないなんて。誰にもわかってもらえないなんて。こんなにも、すごいことなのに。楽しい事なのに。わくわくするのに。誰も、見ちゃくれない。そんな一日をーー正確には午前中だがーー過ごしてた後である。ゆーふぉーの話をしてくれるだけで、それはもう夢のようだった。自分のことを認めてくれたようで、嬉しかった。
「そりゃね、だって私のだから」
「えっ」
喜びを顔に張り付けると同時に彼女の言葉に混乱したため、おかしな表情と声になってしまった。絵に書いたような疑問符を並べる僕に、「《《あれ》》が見えるの? って聞きたいのはこっちよ。まったく。あのタイムマシン、この時間の現代人には見えないはずだったんだけど。あんた、なんで見えてるのよ」
「いや、そう言われても」
そう言われても、見えるものは見えるのだ。不具合だと言えば、そちら側の問題では?
「そうよ、その通り。まったく、こちらの不手際っていう、そういうことなんでしょうね。それがね、報告があったのよ。あんたも昨日会ったでしょ、あのスーツの男。そうそう、それで黒服が言うには、タイムマシンを認識しちゃっている現代人がいるって言うの。いい? それは大問題なわけ。だがら、この学校? なんて言うところに転校? とか言う手続きをさせられたわけなんだから。まあ、あのプールの少年とか分かりやすい事象があって良かったわよ」
そういうと、彼女はペン状の機械を取り出し、スイッチを入れてホログラム映像を映し出した。ここで僕の言うホログラム映像というのは、3D映像のことである。エスエフばかり読む癖に、勉強のできない阿呆であるので、虚像と実像も理解できていないのだ。まあ、中学二年生だと笑って許してほしい。
ともかく。
ここでいうところの、そのホログラム映像には僕が映し出されており、それはまさしく昨日のプールでの様相であった。彼女が言うにはその映像を辿った末にこの学校に辿り着き、僕への接触を果たしたのだという。
「しっかし、それにしても拍子抜けだったわ」と、彼女は、自分の調子を取り戻したロックバンド並みに続けざまに捲し立てて言った。「あんたみたいな子供だから、言いふらして回っているんじゃないかと思ったけど、全然そんな素振りないもの。そういうの、もう興味ない年頃なのかしら」
「いや、それは誰も、僕の話は聞いてくれないからでーー」
? 「なんで?」
疑問符が先行してはみ出す彼女の問に、自分の当たり前を続ける。
「いつも、ひとりだから」
だから、だから。
それ以上は、理由を話せなくなってしまった。
どうしてだろう。
いつもひとりでいるのはその方が楽というか、気を使わなくていいとか、他人がわからないとか、合わせたくないとか、たぶんそういうのもあるだろうけど、実はそうじゃないのは自分が一番わかっている。話すことができなかったんじゃなくて話し相手がいなかったんだってわかっている。なぜ一人でいるのかって、それは、どうしたら仲良くなれるのかわからないから《《ひとりになってしまった》》“だけ”なのだ。
「まあ、いいや」
「誰にも言わないでね。それだけ、じゃあーー」
「あの」
咄嗟に出た一言で彼女は、止まり振り返る。「何?」ってこちらに聞いてくれる。だから僕はそこで言うことが出来たんだ。
乗ってみたい、って。
* * *
「その、ゆーふぉー……じゃなかった、タイムマシン? に乗ってみたい。だ、誰にも言わないから」
「なんでよ。話聞いてた?」
瀬都奈は呆れ半分以上で少しのため息と一緒にそう返した。
「だめに決まってるじゃない。昨日あの男が言った通りよ。国家機密」
「じゃ、じゃあ、誰かに話しちゃう」
「だれに?」
「いや、だ、誰って、友達とか」
「ふぅ〜ん?」
なんだよ。
そう言い返したかったが、自分で先程誰にも聞いてもらえないと言ったばかりである。いつもひとりだ、と友達がいないことを見知らぬ昨日会ったばかりの転校生に話したばかりである。認めよう。誰にも何も言えないと。しかし、直接とは限らないのだ。
「え、SNSとかに書き込むから」
「SNS? あぁ、そんな時代もあったらしいわね」
まるで時代遅れだと言わんばかりだった。最先端なのに。
「ちょっと待って」
からかい気味であった瀬都奈であったが、「SNS……」と、なにやらあれこれつぶやくと、ややあってから気を変えた。どこかへ小型の通信機ーー名称不明。携帯やスマートフォンより小さいーーを使って連絡をし始めた。しかし、国家機密だ、禁則事項だ、などと口酸っぱく言っていたのになぜ、彼女が考えを変えたのかは分からない。SNSはそんなにも強かったのだろうか。乙女心とかそんなものだろうが、次の言葉に心を踊らせたのは言うまでもない。
「いいわ。乗せてあげる。少しだけなら、見せてあげる」
そういうわけで、未来からの侵略者こと明星瀬都奈と待ち合わせるため、まだ明るい夕方のこの時間に再び学校のプール施設前へと来ていたのであった。
見えている僕だけがおかしいのだと、世界はそう言っているようだった。
「あのゆーふぉーみたいなやつ。ゆーふぉーじゃなくてタイムマシンなの」
明星瀬都奈はそう言った。
「えっ、見えるの?」
思えばこの質問はあまりにも頓珍漢め滑稽なモノだったのだが、その時の僕にとって誰かがあの“異常”を認識してくれていることのほうがずっと嬉しかった。だってゆーふぉーだぜ?
未確認飛行物体だぜ。
光の反射とか、見間違いとか、鳥とか飛行機じゃない。もっと、堂々と、それが当たり前で普通であるかのように《《そいつ》》はこの日常に居座りやがったんだ。東京に現れたガ○ダムのように、創造上でのみ存在していたモノが現実に紛れもなく現れたんだ。だけど、誰も気にしない。気が付かない。あんなにもはっきりと見え、巨大で、プール施設の屋上に登れば手が届く距離にあるのに、だれも。その一方で、日が変わってもなお見えるその未確認浮遊物体は『夢じゃないぞ』と、告げていた。それが誰にも理解してもらえないなんて。誰にもわかってもらえないなんて。こんなにも、すごいことなのに。楽しい事なのに。わくわくするのに。誰も、見ちゃくれない。そんな一日をーー正確には午前中だがーー過ごしてた後である。ゆーふぉーの話をしてくれるだけで、それはもう夢のようだった。自分のことを認めてくれたようで、嬉しかった。
「そりゃね、だって私のだから」
「えっ」
喜びを顔に張り付けると同時に彼女の言葉に混乱したため、おかしな表情と声になってしまった。絵に書いたような疑問符を並べる僕に、「《《あれ》》が見えるの? って聞きたいのはこっちよ。まったく。あのタイムマシン、この時間の現代人には見えないはずだったんだけど。あんた、なんで見えてるのよ」
「いや、そう言われても」
そう言われても、見えるものは見えるのだ。不具合だと言えば、そちら側の問題では?
「そうよ、その通り。まったく、こちらの不手際っていう、そういうことなんでしょうね。それがね、報告があったのよ。あんたも昨日会ったでしょ、あのスーツの男。そうそう、それで黒服が言うには、タイムマシンを認識しちゃっている現代人がいるって言うの。いい? それは大問題なわけ。だがら、この学校? なんて言うところに転校? とか言う手続きをさせられたわけなんだから。まあ、あのプールの少年とか分かりやすい事象があって良かったわよ」
そういうと、彼女はペン状の機械を取り出し、スイッチを入れてホログラム映像を映し出した。ここで僕の言うホログラム映像というのは、3D映像のことである。エスエフばかり読む癖に、勉強のできない阿呆であるので、虚像と実像も理解できていないのだ。まあ、中学二年生だと笑って許してほしい。
ともかく。
ここでいうところの、そのホログラム映像には僕が映し出されており、それはまさしく昨日のプールでの様相であった。彼女が言うにはその映像を辿った末にこの学校に辿り着き、僕への接触を果たしたのだという。
「しっかし、それにしても拍子抜けだったわ」と、彼女は、自分の調子を取り戻したロックバンド並みに続けざまに捲し立てて言った。「あんたみたいな子供だから、言いふらして回っているんじゃないかと思ったけど、全然そんな素振りないもの。そういうの、もう興味ない年頃なのかしら」
「いや、それは誰も、僕の話は聞いてくれないからでーー」
? 「なんで?」
疑問符が先行してはみ出す彼女の問に、自分の当たり前を続ける。
「いつも、ひとりだから」
だから、だから。
それ以上は、理由を話せなくなってしまった。
どうしてだろう。
いつもひとりでいるのはその方が楽というか、気を使わなくていいとか、他人がわからないとか、合わせたくないとか、たぶんそういうのもあるだろうけど、実はそうじゃないのは自分が一番わかっている。話すことができなかったんじゃなくて話し相手がいなかったんだってわかっている。なぜ一人でいるのかって、それは、どうしたら仲良くなれるのかわからないから《《ひとりになってしまった》》“だけ”なのだ。
「まあ、いいや」
「誰にも言わないでね。それだけ、じゃあーー」
「あの」
咄嗟に出た一言で彼女は、止まり振り返る。「何?」ってこちらに聞いてくれる。だから僕はそこで言うことが出来たんだ。
乗ってみたい、って。
* * *
「その、ゆーふぉー……じゃなかった、タイムマシン? に乗ってみたい。だ、誰にも言わないから」
「なんでよ。話聞いてた?」
瀬都奈は呆れ半分以上で少しのため息と一緒にそう返した。
「だめに決まってるじゃない。昨日あの男が言った通りよ。国家機密」
「じゃ、じゃあ、誰かに話しちゃう」
「だれに?」
「いや、だ、誰って、友達とか」
「ふぅ〜ん?」
なんだよ。
そう言い返したかったが、自分で先程誰にも聞いてもらえないと言ったばかりである。いつもひとりだ、と友達がいないことを見知らぬ昨日会ったばかりの転校生に話したばかりである。認めよう。誰にも何も言えないと。しかし、直接とは限らないのだ。
「え、SNSとかに書き込むから」
「SNS? あぁ、そんな時代もあったらしいわね」
まるで時代遅れだと言わんばかりだった。最先端なのに。
「ちょっと待って」
からかい気味であった瀬都奈であったが、「SNS……」と、なにやらあれこれつぶやくと、ややあってから気を変えた。どこかへ小型の通信機ーー名称不明。携帯やスマートフォンより小さいーーを使って連絡をし始めた。しかし、国家機密だ、禁則事項だ、などと口酸っぱく言っていたのになぜ、彼女が考えを変えたのかは分からない。SNSはそんなにも強かったのだろうか。乙女心とかそんなものだろうが、次の言葉に心を踊らせたのは言うまでもない。
「いいわ。乗せてあげる。少しだけなら、見せてあげる」
そういうわけで、未来からの侵略者こと明星瀬都奈と待ち合わせるため、まだ明るい夕方のこの時間に再び学校のプール施設前へと来ていたのであった。