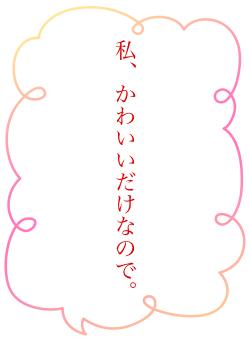「佐藤さん。佐藤さーん。もしもし?」
俺の後ろの席の佐藤円香は、よく寝ている。
それはもう気づいたら寝ている。休み時間も、なんなら授業中もわりと寝ている。
「……なんですか、吉野くん。今日もうるさいです」
「知ってる。じゃなきゃ目覚ましにならないだろ」
だから彼女を起こすのは、なんとなく俺の役割だと思っている。本当に、なんとなくだけど。
「うぅ……私はまだ寝れます! 寝させてください、コーチ!!」
「睡眠にスポ根要素を見出すな。あと誰がコーチじゃ! 早く起きろ!!」
病弱一歩手前の真っ白な肌に、肩まで真っ直ぐ伸びたボブヘアーに、きっちり着こなされた制服。外見だけはしっかり優等生な彼女は、意外と冗談も言うしケラケラと笑う。
クラスメイト全員に敬語で、実はちゃんと頭も良くて、趣味は読書でインドア派。確か図書委員もやっていたはずだ。
そんな彼女と、サッカー一筋で生きてきた俺には共通の趣味も多分ないし、話しかける口実も他にない。だから俺は、気がついたら率先して佐藤さんのことを起こすようになった。
そうしたら、こうやってすぐ近くで、笑顔を見ることが出来るから。
「ってか、マジで冗談言ってる場合じゃないんだって。俺、5時までに部活行かないと遅刻になるから早く起きて」
「……それは吉野くんの都合じゃないですかぁ。でも、仕方ないので起きてあげます。実は私、今日は吉野くんにお話したいことがあるので」
佐藤さんはニヤリと笑いながら起き上がって、そのまま立ち上がった。
夕暮れの教室。放課後。二人きり。
仲も深まってきた、高校二年生の秋。
そして、話したいこと。
それらから導き出されるものを俺は一つしか知らない。
告白されたら、どうしよう。
俺からする予定だったのに! ここで遮って俺から言うか!? いや恥ずいし。そもそも違う話だったら死ぬし、俺。
いや告白しようとは思ってたから前倒しになったと思えばさ。
「……好き……んです」
初デートはどこに行こう。この周り、イオンしかねぇからな。ちょっと遠出して遊園地とか行って────。
「だから吉野くん、聞いてます?」
「あっ、ご、ごめん。何?」
「もー。もっかいしか言いませんからね?」
ドク、ドク、と心臓の上でパーティーでもしているような音が全身に響く。
佐藤さんは、一度大きな深呼吸をしてから言葉を吐き出した。
「私、好きな人が出来たんです」
…………え?
「高橋くんって彼女いるんですか? 確か吉野くんと同じ部活でしたよね!」
好き。佐藤さんが。高橋のことを。
俺の友達の高橋のことを。
え、なんで?
俺の方が佐藤さんと全然仲良いじゃん。高橋なんて何も接点ないじゃん。それとも俺のいないところでなんかあるのかよ。おかしいだろ。
俺の方が絶対、佐藤さんのこと知ってるのに。好きなのに。
「ん、同じ。多分彼女いないと思うけど」
頭の中がパニックになっている。
それなのに、平然と返事をした俺がいたから、人間ってそう簡単には壊れないんだなぁと思った。
「そうなんですね! よかったぁ……!」
……あぁ、死にたい。
その週末。俺は佐藤さんと近くの映画館へ来ていた。ふわふわと、佐藤さんの着ている、品のいいグレーのワンピースが揺れる。
「おはようございます、吉野くん」
「……おはよ、佐藤さん」
意味がわからない状況だよな、俺もまだ夢だと思ってる。こうやって自問自答しちゃうぐらいには。
まずきっかけは何にというと、俺自ら佐藤さんと高橋の恋のキューピッドを名乗り出たことだ。我ながらメンタルが強すぎる。
だって、どんな形でもいいから関わってたかったんだよ。好きな人の友達でいいから、これからも佐藤さんに話しかける権利が欲しかった。
あの寝起きの顔が、とろんとした目が、ふにゃりと緩む口元が。俺の日常からなくなると思っただけで、苦しかったから。
そして、とりあえず高橋に彼女がいるのかを聞きに行った。もちろんいなかった。
なんでだよ、そこはいろよ。いやいないって知ってたけど、いるって言ってくれよ。嘘でもいいから。……いや嘘とかつかないのがお前のいいところだよな、高橋。ごめん、高橋。
そういうわけで、じゃあ高橋をデートに誘ってみようという話になった。好きな女の子と、俺相手じゃないデートのプランを立てるなんて拷問の極みみたいなことをよく耐えたと思う。
場所が沢山一目のあるファミレスじゃなければ発狂していた可能性もある。今後、人生の中で拷問する機会に恵まれたら絶対これやってやろ。いや、そんな機会恵まれたくねぇけど。
そんなことより、今は隣でキラキラと目を輝かせている佐藤さんに集中しなければ。
「佐藤さん、楽しい?」
「はい、超楽しいです。このまま寝れそうなぐらい素晴らしいですよね、映画館の椅子のクッションって」
「まさかの睡眠環境目当て……!?」
佐藤さんの趣味は映画鑑賞らしい。いや、もしかしたら映画館のクッション目当てかもしれない。佐藤さんは俺をからかっているのか、ニヤニヤ笑って席に着いた。普段が普段なだけに、これは冗談なのかなんなのか。
それはともかく、今見たい映画があるということで、それを高橋と観に行けばいいのではないかという話になったのだが、俺が強引にごねて予行練習が必要だと言った。
そうして勝ち取った機会が今日である。
「今日の映画はどんな感じの内容なんだ?」
何度も事前予習したせいで空で言えるぐらい分かりきっているくせに、佐藤さんと話したくてそんなことを言った。
「タイムリープものです。何度も時を戻して、何度も好きな人に忘れられながら幸せになるために頑張る話っぽいです」
「へー、そうなんだ」
さも感心したように言った。
我ながら白々しい。
「佐藤さんもポップコーン食べる?」
「……いらないです。手がベタベタするの、嫌いなので」
「いや俺が買ったの塩味だよ。キャラメルじゃないから大丈夫」
「え。なんでですか。吉野くん、ポップコーンはキャラメルしか食べないじゃないですか!」
「え? 俺、そんなこと言ったっけ」
俺、吉野健人はキャラメルポップコーン強火担である。だからぶっちゃけポップコーンはキャラメルしか許していない……が、今日は佐藤さんとの擬似デート。
佐藤さんがポップコーンは塩派ということは、前回のファミレスミーティングでさりげなく聞き出してあったから、今日は人生で初めて塩味を買ったのだった。
「吉野くん前に言ってましたよ。ポップコーンでキャラメルを選ばないやつは、キャラメルの素晴らしさに気づいたら人生が8倍楽しくなるって」
「えっ、恥ず」
そんなこと言うな昔の俺ーーッ!!
何の話の流れで言ったのか分からないが、どうやら本当に言っていたらしい。だってマジで俺が言いそうなセリフだもんな。詰んでる。
「もしかして吉野くん、私のために塩のポップコーン買ってくれたんですか」
バレてる!! 完全に!!!
「いや、その……はい」
「なんでそんな顔してるんですか。吉野くんが超良い人だってバレただけじゃないですか」
「え、いや、その」
だってそんなの、佐藤さん限定に決まってるし。俺、佐藤さんの前でしか超良い人じゃないし!
それを言ったら、俺が佐藤さんを好きだって一発でバレ────。
「吉野くん、さては照れてますね? ……吉野くんの彼女になれる人は幸せですね。そんな気遣いされたら、吉野くん以外好きになれなくなっちゃいますよ」
────バレても、意味ないんだった。
バレても、どうしても。
彼女は、俺以外を好きなんだった。
「……それは光栄だわ」
俺は今、初めて仄暗い映画館の中に感謝した。きっとここが、表情丸見えの明るい公園とかだったら、泣いていたと思う。
佐藤さんの顔が見えたら、泣いてしまうと思う。
多分、俺の彼女になったら幸せだと思うよ。
そう思わせるだけの努力、するよ。そのためなら全然苦しくないし、毎日塩味のポップコーン食ってもいいよ。キャラメルが一生食えなくなってもいい。
俺以外、好きになれなくていいよ。
高橋なんかより、絶対、絶対、俺の方が幸せにするのに、どうして俺じゃダメなんだろう。
それからはずっと、気づいたら始まっていた映画をぼんやり目で追いかけていた。
『何回時を戻しても、どうしてもあなたがいいの!』
スクリーンの中の主人公が、死んでしまった片想いの相手を抱きしめながら叫んでいる。
でも、きっと佐藤さんも、俺がどれだけ幸せにすると言ったって高橋がいいのだろう。
高橋じゃないとダメなのだろう。
そんなこと、分かってるよ。俺も、佐藤さんじゃないとダメだから。
数時間後。映画館と同じショッピングモール内のフードコートには泣きじゃくる俺がいた。
「超、良かった」
「号泣ですね、吉野くん」
「あれで泣かない奴いたら鬼だろ……すげぇよ主人公の愛の強さ。あんだけ思われたら俺、もう死んでもいいよ……」
「しっ、死んだら意味ないじゃないですか。主人公はそれを回避するために時を戻してるのに。てかそもそも、そんなドラマチックな恋、現実にはありませんし」
「はー!? そっちが見たいって言った割に随分冷めたこと言いますねぇ!!」
こっちは片想い中&失恋中。
感傷に浸っているどころか、水深50メートルの感傷プールに沈められている状況である。佐藤さんはもっと、感性ヒタヒタでズブズブな俺の気持ちになった方がいい。
「いや面白かったですよ。私だって、泣けるなぁって思います」
「涙からっからの人にそんなこと言われてもなぁ!」
「本当ですって。ただ、映画を何本も見てると段々泣けなくなってくるんですよ。最初は感動映画なら何見ても泣けるんですけど、なんていうかこう、使い果たしちゃうんです」
佐藤さんは、俯いて、ぎこちなく笑いながらそう言った。
「……ふーん、なるほど。てか、それなら今日の予行練習ダメじゃん。本番で、より一層泣けないじゃん」
女の涙は武器、とかよく言うし。
高橋なんて、佐藤さんが泣いてるの見たらイチコロだと思うよ。知らんけど。てか、知りたくないっていうか考えたくないけど。
そもそも、本番のことを意識した発言をしてしまった自分が許せない。普通に俺の方が泣きたい。さっきまで号泣してたせいで、体内の液体全部ないことが良い方向に働くとは夢にも思わなかった。
自分で言って自分でダメージを受けた俺を見て、その様子に気づいていないのか、佐藤さんはクスクスと笑って口を開く。
「本番こそ泣きたくないですよ。メイク、崩れちゃうじゃないですか! 私、好きな人の前でメイク取れるのはもう嫌なんです」
「そっか。……別に、佐藤さんはメイクなんてなくてもかわいいよ」
「っそんなお世辞はいいんです!」
「いや、マジマジ。だって佐藤さん、寝起きの瞬間すら超かわ……あ」
今、俺、何を口走ろうとしてるんだ。
パッと顔を上げる。
「あ、えと、その」
顔を、真っ赤にした佐藤さんが俺をじっと見つめていた。映画を見た後は少しも潤んでいなかった瞳が、みるみる内に涙でいっぱいになる。
えっ、俺、そんな泣かせるようなこと言った!? キモすぎたのか、俺!?
「いっ、今のは」
俺の言葉を遮るように、佐藤さんが叫んだ。
「っ私、飲み物買ってきます!! 吉野くんもいりますかっ!」
「あっ、はい!」
反射的に答えた俺を置いて、佐藤さんは走って行ってしまった。というか、まだそこそこ飲み物残ってるから正直いらないのだけれど。
泣いて……たよな。俺が泣かせたのか?
とにかく、戻ってきたら謝らないと。
てかそもそも、メイク崩れちゃうってなんだよ。高橋なんて絶対、メイクしてるかしてないかすら分かんねぇぞ。断言出来る。
俺なら、超気づくのに。前髪1ミリの変化も、絶対気づく。だから、俺でいいじゃん。
「あーー……」
中途半端に予行練習しよう、なんて未練がましいことしなければ良かった。
ふとかわいいな、と思うたびに、高橋にもこの顔を見せるのかと思って、何回も何回も嫉妬で死にたくなる。
「あぁーー……」
しばらく経って、遠くからパタパタと、両手に飲み物を抱えて走ってくる佐藤さんが見えた。むしろ休日のフードコートらしい人の多さなのに、佐藤さんしか見えないから助けてほしい。
そうだね。かわいいよ。高橋のことが好きだって、どうしたってかわいい。
「っこれ、吉野くっ、の分、です」
「そんなに急がなくても良かったのに」
「でも、時間が、っないから」
苦しそうに佐藤さんは言った。
「何の時間がないの」
「次の、バス、です! 私達このバスで帰らないとヤバいのに、ここで喋りすぎたせいであと10分しかないことに、飲み物買ってから気づいて……!!」
「え」
時計を見た。5時56分。
恋人でもない異性と二人でいられる、ギリギリの時間帯。
「やべぇじゃん、バス来るの6時5分とかだろ!」
「はいっ……! ここからバス停まで走らなきゃ!!」
「っしゃ、じゃあ荷物貸して。ここから全力ダッシュな!!」
「ちょ、えっ!? いいですって」
「いいよ、俺部活で鍛えてるから!」
俺は、明らかに走るのに邪魔そうな、佐藤さんの荷物を持って……というか半ば奪って走り始めた。っていうか好きな子にいいところ見せたいし。
まだあわよくば的な気持ち、まだ捨ててないし。
「はぁ……ギリ間に合ったな」
「二度とこんな思いはしたくないですね」
数分後。俺達は飛び乗ったバスの座席で、ゼハー、ゼハーと息を吐いていた。久しぶりの全力ダッシュのせいで肺が痛い。
「ッ、ハァ」
カラカラの喉に、ぬるくなってしまった、佐藤さんの買ってきてくれた飲み物を流し込む。オレンジジュースだった。
普通ファストフード店で飲み物を人に頼んだときは、大体コーラを頼まれるのに、珍しい。実際、佐藤さんはコーラ飲んでるっぽいし。
俺が実はコーラを飲めない……という話も、前にしたことがあったのだろうか。
「あのさぁ、……いや、なんでもない」
そのことを口実に話しかけようとして、俺は言葉を止めた。
俺、そういえば、佐藤さんの好きなもの、何も知らないな。佐藤さんのこと、何も知らない。基本的にいつも俺ばっかり喋ってるから。
そうだ。さっき、泣きかけた理由も。
「その、さっきはごめん」
「何がですか?」
「だから、さっきのことだよ。俺がいらないことを言ってしまったばっかりに」
「え!? いいですよ。なんで吉野くんが謝るんですか!」
佐藤さんは慌てたように首を振った。
「全部、私が悪いんです。ちょっと昔のことが重なってしまって」
何だよそれ。元カレかよ。
前にも彼氏、いたのかよ。
一気に、モヤモヤが流れ込む。
いや別に自由なんですけど。俺の佐藤さんじゃないくせに嫉妬する資格ないんですけど。
え、でも最初俺が話しかけたとき、超緊張してたじゃん。クラスでも俺以外の男とほとんど話さないじゃん。
いやでもさっき、好きな人の前でメイク取れるのはもう嫌って言ってたしな。高橋ではないだろうから、その前にも、好きな人はいたってことだし。
あぁああぁあああ!! もう!!!
なんで俺じゃねぇんだよ!!
俺は全部の言葉を飲み込んで、どうにか当たり障りのない言葉を探した。
「そう、なんだ。ま、色々あるよな。生きてたら」
「……そうですね。死んじゃったら、何もないですから」
そう言った佐藤さんの表情は、夕日に照らされていたせいで、ぼやけて見えた。
「吉野くん。私、月曜日に高橋くんをデートに誘います」
「……えっ!? 展開早くね!?」
「はい。思いきり、というやつです。親身になってくれた吉野くんのおかげでシュミレーションも出来ましたし、勇気も出ましたし」
思考に理解がついてこない。
反射のように飛び出した言葉だけが宙を待って、返ってこなくなった。
シュミレーション。
俺とのデートは、シュミレーションでしかない。
佐藤さんには、高橋との本番が控えている。
そんなことは、代役をやりたいと言った時から、分かっていたくせに。分かっていて、でも諦めたくなくて、声をかけたくせに。
いざ、現実としてつきつけられると、よく、意味がわからなくて。理解が、出来なくて。
「あのさ」
「はい」
「どうしても高橋じゃなきゃダメなの?」
高橋と俺の共通点。
サッカー部で、勉強があまり出来なくて、明るくて。いっぱいあるよ。だから友達なんだし。高橋ももちろん、いい奴だけどさ。
だったら俺でいいじゃん。
俺の方がさ、大事にするよ。
今なら告白成功率120%だよ。
妥協でいいから俺でいいって、言ってくれよ。
俺になくて、高橋にあるものって、何?
「はい。高橋くんが、いいんです」
佐藤さんは、控えめに微笑みながらそう言った。
ベキン、と。心から音が聞こえた。
月曜日。
「…………起きろー、放課後なったぞ」
俺は、いつものように眠る佐藤さんを起こした。
ふにゃりとした口。とろんとした目。ボーッとした顔。
明日から、この仕事は高橋のものになる。
この顔を見るのも、もちろん高橋の特権になるだろう。
「……おはようございます、吉野くん」
「ん、おはよ」
佐藤さんは高橋を、今日の5時にこの教室へ呼び出しているらしい。
今の時刻は4時40分。
本当は20分前には放課後になっていたのに、もう少しだけ寝顔が見ていたくて、気がついたらこの時間になっていた。
「あれ、空暗くないですか?」
「今日は先生の話が長かったから、HRが長引いてさ。今、4時40分だよ」
「えっ、マジです? 今から急いで準備しないと……!」
佐藤さんは俺の嘘を疑いもせずにそう言って、鞄の中からリップを取り出した。そして、唇に丁寧に塗っていく。
さっきまでの方が可愛いのに、なんて、もう絶対に言わない。どんな佐藤さんもかわいいよ。
それが、高橋のためなのが嫌なだけ。
「佐藤さん」
────それですら嫌だから、諦められるわけがねぇんだよ!!
「俺、佐藤さんのことが好き」
俺は、ずっと溜め込んでいた言葉を吐き出した。
まだ、諦めたくねぇよ。だってもしかしたらさ、考え直してくれるかもしれないじゃん。
言わないとワンチャンすらないじゃんよ。
「なんで、今言うの」
佐藤さんの細い喉から、掠れた声が漏れる。
「だって、私、高橋くんのことが好きって」
「でも、俺は佐藤さんのことが好き。想うだけなら自由じゃん。俺が考えるだけなら自由だろ?」
「……そう、だけど」
佐藤さんは、手に握っていたリップを鞄に放り投げて、空いた両手で顔を覆った。
「私は、吉野くんを好きにならないよ」
「知ってる。言いたかっただけなんだよ。ただ、好きでいたいだけなんだ」
「それがっ、迷惑だって、言ってるの!」
佐藤さんの目から、ボロボロ涙がこぼれ落ちる。
それぐらい、100も承知で、言葉にしてんだよ。覚悟してんだよ。高橋よりも俺のこと考えて欲しくて、今言ったんだ。
「知ってる。ごめんな。俺、最低で」
自分でも最低だって分かってるから、許してくれなんて言わないから。
「好きにならせてくれて、ありがとな」
後ろの席に好きな子がいる。
ただ、それだけで、学校が楽しかった。
「告白、頑張れよ」
「…………っ」
俺は佐藤さんに手を振って、教室を出た。
胸はガンガン痛い。なんなら頭も痛い。
頬をぼたぼたと熱いものが通り過ぎていく。
いいカッコすんなよ、俺。こんなに未練しかないくせに。
でも、せめて言えて良かったな。俺が佐藤さんを好きだって、事実だけは伝えられて良かった。
もし、高橋が告白を断ったらどうしよう。いや、それはないか。年中彼女募集中の高橋だし。
高橋、佐藤さんのこと大事にするだろうな。良い奴だもんな、アイツ。
もし、万が一、高橋が佐藤さんを不幸にするようなことがあったら、絶対佐藤さんの味方になろう。あわよくばの下心込みで助けよう。
こんな、汚い考えが出てくるくらい、俺は、佐藤さんのことが────あ?
「ぁ、え?」
おなかが、もえるように、あつい。
前から走ってきた人にぶつかられて、それで、なんでこんなにあついんだ?
視線を下に向ける。何かがお腹に突き刺さっていた。そこから赤い染みが広がって、びっくりするほど、あつくて、だから、おれは。
『それがっ、迷惑だって、言ってるの!』
閉じた瞼に、佐藤さんの泣き顔が浮かぶ。
あれ、そういえば、さとうさんのためぐちって、はじめて、きいたな。
あんなかお、させたかったわけじゃ、なかっ─────。