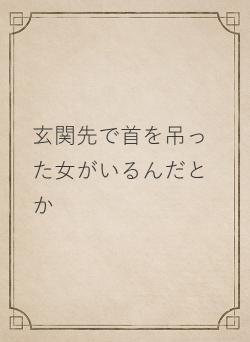それが余計に不振に感じさせなかっただろうかと、心臓が早鐘を打ち始める。
「あら、夫婦で仲良がいいわねぇ」
主婦は何気なく声をかけてきて、蘭が笑顔で応じている。
彰はそんな蘭の腕を掴み、主婦に軽く会釈してその場を早足に通り過ぎた。
家に戻ってきた彰は厳重に玄関の鍵をかけて、大きな窓のカーテンを閉めた。
「警戒してるの?」
蘭が心配そうに顔を覗き込んでくる。
「あぁ……」
「2人ともマスクをつけていたし、きっと大丈夫だよ」
「わかってる。俺の気にしすぎた」
彰は額に浮かんでいた冷や汗を手の甲でぬぐう。
それを見た蘭はすぐにキッチンへ向かい、冷たい水をコップに汲んできてくれた。
彰はそれを受け取り、喉を鳴らして一気に飲み干した。
少しだけ気分がスッキリした。
不安な気持ちも落ち着いてきた。
なにをここまで気にしているんだろう。
蘭はまだ自分の隣にいるし、今は自分の意思でここにいてくれている。
それなら誰が来たって、不安がることはない。
自分にそう言い聞かせて、まだ心配そうな表情を崩さない蘭へ向けて微笑んで見せた。
「あら、夫婦で仲良がいいわねぇ」
主婦は何気なく声をかけてきて、蘭が笑顔で応じている。
彰はそんな蘭の腕を掴み、主婦に軽く会釈してその場を早足に通り過ぎた。
家に戻ってきた彰は厳重に玄関の鍵をかけて、大きな窓のカーテンを閉めた。
「警戒してるの?」
蘭が心配そうに顔を覗き込んでくる。
「あぁ……」
「2人ともマスクをつけていたし、きっと大丈夫だよ」
「わかってる。俺の気にしすぎた」
彰は額に浮かんでいた冷や汗を手の甲でぬぐう。
それを見た蘭はすぐにキッチンへ向かい、冷たい水をコップに汲んできてくれた。
彰はそれを受け取り、喉を鳴らして一気に飲み干した。
少しだけ気分がスッキリした。
不安な気持ちも落ち着いてきた。
なにをここまで気にしているんだろう。
蘭はまだ自分の隣にいるし、今は自分の意思でここにいてくれている。
それなら誰が来たって、不安がることはない。
自分にそう言い聞かせて、まだ心配そうな表情を崩さない蘭へ向けて微笑んで見せた。