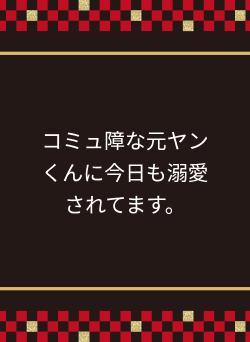「高崎の告白。なんて返事したんだよ。」
夏休み明けのことを言ってるんだろう。
もちろん、告白された翌日にお断りしたけど…
それを言ったら、勘のいい香月くんにはあっという間に私の隠した恋心がバレてしまう気がした。
私が何も言えず、モゴモゴしていると
香月くんは頬杖をつきながら上目遣いで私を見上げた。
滅多に見ないその表情に心臓がきゅんと縮こまる。
「答え焦らすなんていい度胸してんじゃん。」
「そんなんじゃ…」
香月くんはそっと私の髪に触れた。
さらさらと香月くんの指の上を滑る髪を見ていると、触覚はないはずなのに体がぞくぞくする。
まるで身体に触れられているような…
ってバカ!私の変態!!
私は慌てて自分の考えを振り払った。
それでも顔は火が出そうなほど火照っている。
「なに、その顔。」
「っ…///」
「……」
しばらく囚われたように香月くんと見つめあっていた。
数秒後、「はぁ」と香月くんがため息を漏らし、緊迫した空気が少し緩んだ。
「ま、いつも俺と帰ってるし、
なんなら部活で高崎と話す機会減ってるし、
どう考えても付き合ってないってわかるけどな。」
「っじゃあなんで聞いたのよ!」
香月くんは私から目をそらすと、
今まで私の髪に触れていた手でペンをとった。
「からかおうと思っただけ。」
「何よ…」
「この機会逃したら一生彼氏できないかもとか思わなかったのか。」
「し、失礼な!大丈夫だよ!きっと…」
香月くんは今までの熱っぽい視線とは逆に冷めた視線を向け、鼻で笑った。
私はムッとなり、
ペンを握り直して下を向いた。
そうだよ。最初からわかってたのに。
香月くんが私を好きになるわけない。
香月くんの一挙一動にドキドキして、虚しいだけだ。
もういいし。もう…
私は目に涙が浮かびそうになるのを理性で抑える。
絶対香月くんに好きだなんて言わない。
予知夢が変わったことも絶対絶対言わない。
私はそう固く誓った。