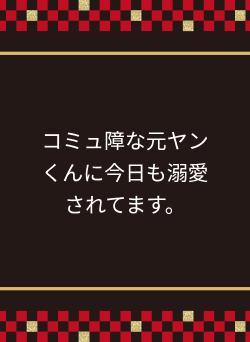「お前、おかしいぞ。
どうしたんだよ。」
「おかしいのはもともとだよ。」
私はぬぐってもぬぐっても溢れる涙をぬぐい続ける。
「傷口、洗って。」
泣きながら香月くんにそう言うと、
素直に近くの水道で洗ってくれた。
薄まった血液が排水溝に流れていく。
「助けられたと思ったのに…」
「また『予知夢の事故』かよ。」
「そうだよ、『また』だよ。
香月くん以上に懲り懲りだよ。」
「……。」
「変人扱いでもすればいいじゃん!
香月くんに私の気持ちなんてわかんないよ!」
「なにキレてんだよ…。」
ホントそうだ。
助けられたと、予知夢の鎖から逃れられたと
勘違いしたのは私だ。
八つ当たりも甚だしい。
「ごめんなさい…」
「別に今さら謝んなくてもいいよ。
今は自転車もないんだし…冷静になれ。」
「っ、冷静に!?なれないよ!!
ほぼ毎朝、私は香月くんを守れず死なせてるんだよ!?
血だらけで身体もぐちゃぐちゃで、
ピクリとも動かない香月くんを毎朝見て、
冷静になれるわけない!」
「……」
「ようやく…助けられたと…」
私はそれから声も出せないくらい泣いた。
香月くんは黙って私のとなりに座っていた。
いつもは適当言ってからかってくるくせに。
「うっ、うっ、お昼…終わっちゃう…。
ごはん食べに行って…。」
「いいよ、1食くらい。」
「ダメだよ。ノルマ2杯。
うっ、私マネージャーだから…」
「あんなグロい話聞かせといて、
2杯とか鬼畜かよ。」
「うっ、うっ…」
「ハァ…わかったよ。
東郷にも麻は体調悪くしたって言っとく。」
「っうん…」
香月くんはぽんっと私の頭に触れると、
静かに歩き去っていった。
遠くなっていく背中に
私は目を背けることしかできなかった。