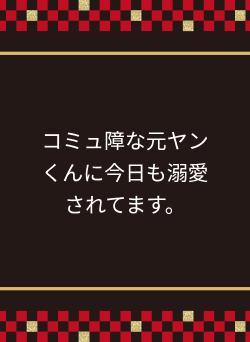「かく…隠すって?」
わー、我ながらとぼけんの下手すぎ!
落ち着け。
冷静になれ。
こんなときよっちゃんなら…
「なんであんなに必死に止めるわけ?」
私は深く息を吸い、唾をごくりと呑み込んだ。
「別にただ一緒に帰りたいからだよ。
置いてくなんてひどくない?」
「……」
「そりゃ私だってキレるよ。」
よし、怒ったってことにしよう。
さっきのは必死に止めてたのではなく、
激怒の咆哮よ!
「キレてたのに、俺の腕掴んで離さなかった。」
「え?」
「ぶん殴ればよかったじゃん。」
「いや、そんなひどいことできないよ…」
香月くんは私の目を覗き込み、
はーっとため息をついた。
「お前が泣きそうになるのはいつも俺が一人で
帰ろうとするときだ。」
心臓がドキリと嫌な音を立てる。
「そのくせ雨の日は喜んで一人で帰ってった。」
「あれは…ずぶぬれだったから早く帰りたくて」
「あと、このストーカーいつまで続けるのか
聞いたら、『"まだ"わからない』っつった。
"まだ"って何。」
「そ、それは…」
「なんで家や学校に着いた瞬間安心したような
顔する?
なんでお前は俺に謝るんだよ。」
「っ…」
次から次へと痛いところをつく香月くんの質問に
私は言葉を失ってしまった。
言い訳が見つからない…。
こんなことなら、香月くんのことが好きっていう
ことにしておけばよかった…。
「お前…俺のこと殺そうとしてんじゃねぇの。」
「っっ、バカにしないでよ!!」
私は思わず香月くんを突き放した。