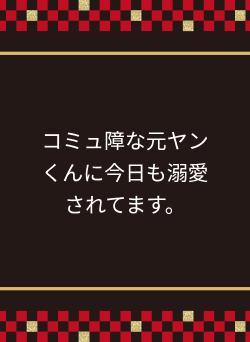「あとどんくらい?」
「あと20分。ごめんね…」
「謝りすぎ。ホント、どんくせぇな。」
そう言った香月くんの表情はからかうような愛おしむような、優しい笑顔。
心の中に閉じ込めた気持ちがどんどん大きくなるのを感じる。
枯らすにはどうしたらいいんだ。
いっそ気持ちを伝えて、玉砕する…?
いや、そもそも私は…
この気持ちを枯らしたいんだろうか…。
香月くんに知られないように
日陰でこっそりと
育てたらなにか実りはしないだろうか…。
バカだな…。
そんな希望あるわけ…
「麻、最近なんか隠してる?」
「え…」
手を止め、香月くんに視線を向ける。
途端に目が合い、離せなくなる。
「…ないよ。
どうして?」
「お前は隠し事も嘘も下手だよな。
女らしくない。」
「そんな女もいるの!」
「ふ~ん…」
ついむきになって反論してしまった私を
香月くんはいぶかしげに見下ろした。
そして、一歩。私との距離を縮めた。
狭い部室での一歩は大きい。
「な、に…?」
ペンを持つ手が震えないように必死に冷静を保つ。
心臓は苦しくなるくらい早鐘を打っている。
香月くんは私の髪にそっと触れた。
撫でるような香月くんの触り方…
ドキドキする。
ペンはいつの間にか手から離れていた。
「んっ…」
「なに。髪で感じてんの?」
「なっ、何を…!////」
「お前ってホント、ズルいよな。」
ズルい?
ズルいのは香月くんだ。
まるで私が逃げられないのをわかってるみたいに…
香月くんとの距離がさらに近くなる。
「ここ…部室だし…
あの、資料も…つ、作らないと…」
私の言葉を無視して、香月くんは私の身体を引き寄せた。
文化祭の時の感覚が全身に甦る。
「嫌なら逃げればいい」
やっぱり。
ズルいのは香月くんだよ。
嫌じゃない…
嫌じゃ…ない…けど…
今まで髪を撫でていた優しい手のひらが
私の頬から首筋を撫でる。
髪と全然違う。
全感覚が香月くんの触れた跡を追いかける。
「か…香月くん…っ」
「…」
私の首筋に当たる唇の感覚。
「っ…」
私の体温と同じ温度で、優しく
優しくたどっていく。
「かづ…き…くん」
再び名前を呼ぶと、香月くんは私との距離を広げた。