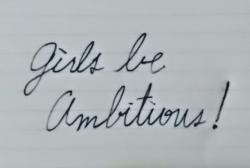丁寧に、しかしどこか言葉を選りながら一誠は言う。
「別に地元が嫌いなわけではないし、戻る日はあるかも知れんけど、でもずっとこっちにいるってのはないと思う」
確かに。
どこか一誠には、居場所を探して歩くような気持ちがなかったわけではない。
だから疎開から戻っても、何か見知らぬ場へ放り込まれたような、疎外感まではゆかないが自らが異物のように感じられることはあったらしい。
だから。
腐れ縁のはずの泉と一緒に帰るという選択肢は撰ばなかったのかも知れない。
「でも、一誠くんの言ってることって、私は分からないでもないかな」
由美子は言った。
「私、実は親の再婚でこっちに来たんやけど、言葉は分からないし、馴染めないしで、なんか孤独やったんよね」
そんなときに声をかけてくれたのがカナであったらしく、
「だから私は、いちばんの親友のカナを尊重して付き合ってくれる人なら、付き合ってもいいかなって」
かけがえのない人を大事にしてくれる男ならステディにしていい、というような意味なのであろう。
この日は結局、連絡先だけは交換したが、結論らしい結論は出さずに京橋で別れた。