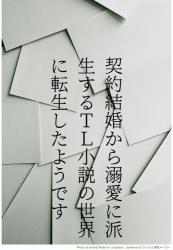***
とはいえ、いざ「やるぞ!」となるとそれはそれで緊張する物である。
その上真島は「布団もない部屋でやるのは嫌だ」と言い放ち、都心の一等地にある高層マンションに私を連れてきた。恐ろしい事に、そこが彼の自宅らしい。
入ってすぐ横の寝室に直行してしまったので部屋の全容はわからないが、きっと凄く眺めの良いリビングには高級家具なんかが並んでいるに違いない。
そちらにちょっと興味もあったが、緊張していたため部屋が見たいなんて言う余裕はなかったし、真島は「すぐ済ませるぞ」と言うなり私をベッドに押し倒した。
「ねえ、死んだって事は痛くないのかな?」
臆する気持ちを誤魔化すように、私は真島に尋ねた。
「安心しろ。幽霊の場合は、感じるのは快楽だけだそうだ」
「ホントに経験豊富なんだ」
「だからお前は、黙って俺に身をゆだねればいい」
と言われて、上手く身をゆだねられていたら今頃処女は卒業している。
抱きしめられるたびにガチガチに緊張し、キスではどう頑張っても舌を差し入れられず、服を脱ごうとすれば手や足が動かなくなり最後は絶対ずっこける。
そんなわたしを見かね、「もういいよ、萎えた」と白旗を揚げた彼氏は一人や二人ではない。
そしてその不器用っぷりは、たぶん死んでも治らない。
だからいくら相手が百戦錬磨のプレイボーイでも、緊張する物はするのだ。
「あの、やっぱり……」
「君はもう約束した」
「でもあなたには何百回のうちの1回かもしれないけど、私ははじめてなの。訳もわからず終わるなんて嫌だし」
「じゃあリードできるのか?」
「それは、無理だけど」
不器用な自分には無理だけど、それでもせめて天国まで持って行けるような1回にしたい。
そう言って視線を落とせば、真島は困った顔で私から離れる。
「さっきも言ったけど、終わったらちゃんと成仏するか」
頷くと、待ってろと告げて真島は部屋を出て行く。
一体何をするつもりだろうと不安になること5分。
彼は再び現れた。無駄にオシャレなBGMとカクテルを携えて。
「飲め」
と差し出されても、飲み方がわからず混乱した。死んでから今まで、飲食をしたことがない。
「お前くらい霊力があれば、実体がないことを覗けば生きてるのとほぼ同じだ」
だから飲めと言われてグラスに口を付ければ、味わったことのない味が口に広がる。
「これ凄く美味しい」
「気に入ったか?」
「気に入ったけど、これどうしたの?」
「そこで作ってきた」
作ってきたってどういう事だと唖然とし、それから開けたままになっている扉から、居間の方をそっとうかがう。
連れ込まれたときは緊張で気付かなかったが、リビングの側には無駄に凝ったバーカウンターが存在している。
「家にバーがあるの??」
「ああ。自慢のプレイベートバーだ」
「は?」
間抜けな声を上げてしまった私を誰が責めることが出来よう。
だってプレイベートバーである。プライベートなバーである。酒なんて居酒屋で飲めばいいのに、何でわざわざそんな物を家の中に作るのか。
そりゃあ家でビールやワインを飲むことは私だってあるが、飲むならテーブルが一つあれば良い。
「君、考えが透けてるぞ」
「ごめん、ちょっとアホっぽいとか思っちゃった。庶民には理解が及ばなすぎて」
「アホとはずいぶんだな。普通の女は、喜んでカウンターに座るぞ」
「マンションに来たときからうっすら感じてたけど、あなたって実は相当な金持ち?」
「腕利きだからな」
「でも陰陽師にプライベートバーって似合わない」
それに先ほどから気になっていたオシャレBGMはいったい何なのかと、私は合わせて指摘する。
「レコードだ。居間にあるのをかけてきた」
「何でかけるの」
「ムードを出そうと」
思わず、真島の顔にカクテルを噴き出してしまった。
慌てて袖で吹いたが、真島の顔は明らかに怒っている。
「ご、ごめんなさい。映画とかで見たことはあったけど、マジでやる人始めてみたからびっくりしちゃって」
「君がロマンチックな夜にしたいと言ってたんだろう」
「でも、コテコテすぎない?」
返事の代わりに返ってきた絶対零度の笑みを見て、さすがに言いすぎたなと私は後悔した。
態度は冷たいが、彼はきっとよかれと思ってロマンチックな演出をしてくれたのだ。
庶民のレベルにはあっていない物の、きっとこれが彼の標準ロマンチックなのだ。だからそれを笑う権利は私にはない。むしろ黙ってムードに酔いしれておくべきだった。
「ごめん、私のためにやってくれたのに」
だが謝罪すると、意外なほどあっけなく真島の顔から怒りが消えた。
それどころかチビチビお酒を飲んでいる私を見て、彼はふっと笑みをこぼす。
「別に良い、自分だって時々馬鹿らしくなる」
「でも毎回、こういうのやるの?」
「その方が女が良く喘ぐ」
相変わらず身も蓋もないが、無駄なロマンチストよりこういう即物的な方が好感が持てるのは確かだ。
「このカクテルも、実は媚薬入りとか?」
「そんな物を使わなくても、テクでどうにか出来る。ただ、シチュエーションに寄ってくれた方が後腐れが無くて良いからな」
「そういうもんなの?」
「死んだ女も生きてる女も、一夜限りの相手だ。ムードを出せば、無駄に自分のことを喋らなくても警戒を解いてくれるし、そう言う奴としか俺はやらない」
となると、私は彼の首尾範囲外なんだろう。そう思うと、申し訳ない気もちになる。
ここは少し大人になろう。いや、女になろう。好きでもない女を抱くなんて苦行を強いるのだから、それくらいはするべきだ。
だから私は残りの酒をあおると、覚悟を決め、来ていたTシャツを一気に脱いだ。
死んでも服って脱げるんだと、今更のようにちょっと驚いた。そしてそんな私に真島も驚いていた。
「何かやる気出てきた、私頑張るね!」
「いや、むしろ俺が……」
「ううん、私が頑張るの。だって頑張れなくて、それで失敗して未練になったんだもん。ここでやらなきゃきっと成仏できないし」
だから少しでも真島好みの女になろうと私は決める。
色々下手ではあるが、一応見てくれは良い方なのだ。
むしろ見てくれがそこそこ良いわりに、経験がついてこないので逆に失敗していたくらいである。
容姿が良いとそれなりの男が寄ってくるが、それなりの男は皆経験豊かすぎて私のレベルには合わせてくれなかった。
なにせ私はマグロ以下の女で、結局服を脱ぐ前に「バイバイさよなら」と言われる不器用レベルである。
でも今日は絶対にちゃんと脱ぐのだ。裸になってすることをするのだ。
だから私は覚悟を決め、Tシャツに続き、勢いよくズボンを降ろそうとした。
だがいくらやる気になっても、今まで1回も成功しなかった私の不器用さは伊達ではない。
死んでいるのに、今更緊張することはないのにやっぱり腕は震え、そしてなんと、下げようとしたデニムのチャックが咬んだ。
「ごっごめん……いきなり失敗した……」
こんな事ってあり得るのか。だってこれ、本物のズボンじゃないんだろうと内心慌てていると、今度は真島が噴き出す番だった。
一応笑みをこらえようと試みたようだが、ベッドに顔を押しつけていても笑い声がだだ漏れである。
笑うなと怒りたいところだが、それよりまずはこの状況を打破せねばと私はさらにチャックをいじる。
しかし無駄にオシャレな真島の寝室は、間接照明しかないので無駄に暗い。手元もよく見えず、必然的に私は自分の股間をのぞき込むという非常におかしな体勢になる。
そしてそこで、またしても事件は起きた。
男受けを狙って伸ばし続けていた髪が、あろう事かチャックに絡んだのである。
痛いと叫んで、やっぱり幽霊にも痛みがあるんじゃないかと訳もわからない怒りを口にすれば、笑いながら真島が私の側に来た。
きてくれたは良いが、正直こんなおかしな格好をしている私を見られたくない。
けれど動けば動くだけ髪は絡まり、情けなさと痛みは増すばかりだ。
「動くな、じっとしろ」
耳元で囁かれた言葉にうっかりドキドキしてしまった私を、真島はベッドに座らせる。
結局、私は股間をのぞき込むという珍妙な体勢のままでいろと命令され、チャックに絡んだ髪は真島が丁寧に外してくれた。
「……もう死にたい」
「安心しろ、もう死んでる」
「っていうか、今なら成仏できる気がする。すぐにこの場から消えてしまいたいし」
むしろ消えないかなと、私は自分の両の手を見た。
しかし消えない。どんだけセックスがしたいんだと、自分の下らない未練にこの時ばかりは呆れた。
「まあ、こんだけ恥かけばもう失敗はしないだろう」
「これ以上恥かいたら天国のお婆ちゃんに合わせる顔がないよ」
「じゃあ、こっからは本気だ」
どういう意味かと訪ねる間もなく手を取られ、そのままストンとベッドに倒された。
先ほどの事件のせいで緊張は増してしまったが、そんな私に真島はちゃんと気付いていた。
彼は私を安心させるように頭をやさしく撫で、ついばむような軽いキスを唇に落とす。
でもやっぱり緊張のほぐしかたがわからず、5回もキスしてくれたのに、フレンチキスのきっかけさえつかめかった。
けれどごめんと謝るより早く、真島がふっと笑う。
「そう言えば、君の名前を聞いてなかったな」
「凄く普通の名前だよ、清明とは釣り合わない感じの」
「言っておくが、俺も本名は田中啓治だ」
マジかと呟いたそのとき、遠ざかっていたはずの唇が私の唇に重なる。
中途半端に明いていた私の口に、彼の舌が差し入れられたのはすぐのことだった。
互いの舌を絡ませるなんて絶対無理だと延々悩んできたのに、彼はその悩みを一瞬で吹き飛ばす。
やろうとしてやるのではなく、その状況になるとそれは勝手に始まるのだ。
私の舌はまるで別の生き物のように真島の舌に絡まり、そこから息が止まるほど長いキスが始まる。
いや、だいぶ前にもう息は止まっているんだけど、でも何故だか最後は、真島より私の方が先に息苦しさを感じて唇を放してしまった。
「出来たじゃないか」
そういって微笑まれたが、息を整えるのに必死で、そしてその微笑みがあまりに素敵すぎて、彼の言葉に応えられない。
そうこうしているうちに、気がつけば真島は私の服と下着を綺麗に取り去ってしまった。
さすがイケメン陰陽師、女の霊の扱い方は超一流である。
「いくら喘いでも君の声は俺にしか聞こえない。だから好きなだけ乱れて良いぞ」
「乱れたことがないので乱れ方がわからないんだけど」
「我慢しなけりゃ自然と乱れる」
と言うなり、始まった愛撫に真島の言葉の意味を知った。
先ほどのキスと同じように、全ては自分の意志とは関係なく勝手に始まってしまう物なのだ。
だから、昔友達と興味本位で見た18禁ビデオそっくりなあえぎ声が部屋に響いているにも関わらず、それが自分の口からこぼれていると気付くのに少し時間がかかった。だって私の口からそんな物が出るとは思わなかったのだ。
ジェットコースターに乗っても、痴漢にあっても、階段でこけても「うぼぁっ」とか「あべっ」とか「あだだっ」等の珍妙な悲鳴しか上げられなかった私である。
可愛らしい悲鳴など、一生縁がないと思っていた。いやむしろ一生縁がなかった私である。
それが、イケメンに太ももを嘗められているだけで吐息とも嬌声ともつかない声を上げているのだ。
「死ぬって……すごい……」
思わずこぼすと、私を抱きしめていた真島が笑った。
「死んで良かったか?」
良いとは言いたくないが、そうしなければ彼に会うことが出来なかったことを思うと、否定は出来ない。
「真島さん……」
いや田中さんか、まあどっちでも良いかと思いつつ、私は生まれて初めて、自分から男の人にキスをした。
「ありがとう」
心の底からの感謝を込めて、私はそう言った。
今度こそちゃんと成仏できるようにがんばるねと、もう一度、私は彼にキスをする。
やっぱり緊張したし、照れたように笑ってしまったけど、自分的には上出来だと思った。
だがそのとき、先ほどまであんなに激しかった彼の愛撫が、唐突に止まった。
また何かいらんことを言ったのだろうかと慌てて彼を伺うと、わかりやすく動揺した顔がそこにはある。
「真島…さん?」
「……啓治だ」
「じゃあ、啓治さん?」
私が名前を呼んだ瞬間、真島、いや啓治の顔から動揺が消えた。
ついでに言えば色気と甘さも消えた。
「やめた」
そして放たれた言葉がそれである。
「やっ、やめた?」
「ああ、やめた。と言うかやめる」
言うと、啓治は私の体をシーツでくるみ、さっさとパンツとズボンをはいてしまう。
意味がわからない、理由がわからない、どうしていいかわからない。
その三重苦に苦しめられながらも、私は何とか言葉を探す。
「まっ待ってよ! さすがに寸止めで成仏しろって言われても無理!」
むしろ未練がたまりすぎて現世に居座っちゃうよと主張するが、啓治はこちらに背を向けたままだ。
「それでいい」
「いやいやいや、嫌だってば! だって私霊力が強いんでしょ! 放っておけば悪い霊に食べられちゃうんでしょ!」
「安心しろ、俺が守ってやる」
そんなカッコイイ台詞を言われても、と私はもちろん食い下がった。
すると啓治は、自分で脱がせた下着と服を私の方に放る。
「お前だって言ってただろう。好きな男とやりたいって」
「言ったけど、無理だから啓治さんで手を打とうとしたんでしょ! っていうか自分で手を打て的な事言って、部屋に連れ込んだのはそっちでしょう!」
だから責任をとれと、私は啓治の背中に縋り付いた。
オシャレBGMまでかけて、カクテルを飲ませた責任を取れと詰め寄った。
だが未だ返事をしない彼をじっと伺っていると、私はあることに気がついた。
それまで啓治は、私が何をしても笑うばかりで動揺はしなかった。甘い声音や表情はしても、それにすら余裕が見て取れた。
にもかかわらず、私が縋り付いた途端、彼は肩をびくりと弾ませたのだ。その上よく見ると、彼の頬と耳は驚くほど真っ赤に染まっていたのだ。
それが気になり、ふとしたイタズラ心で背中を指でなぞれば、彼は妙なうめき声を漏らす。
「啓治さん」
「離れろ」
「啓治さん」
「良いから離れろ」
「ねえ啓治さん」
「ともかく離れろ!」
「自分で言うのも恥ずかしいけど、もしかして私、啓治さんのストライクゾーンだったりする?」
途端に自慢のプライベートバーまで一目散に逃げ出した彼を見て、私は確信した。
セックスまでは行けなかったが、恋は人並みにしてきたのだ。多少なりとも感情の機微はわかる。
シーツを引きずりながら彼を追えば、プライベートバーのカウンターに彼は突っ伏していた。
耳を澄ませれば「なんでこんなブスに」とか「チャックに髪を絡めるような女だぞ」と失礼極まりない台詞が聞こえてくる。
だが悪い気がしないのは、そうする彼が無性に可愛らしく見えてしまったからだ。
正直プライベートバー持ちのイケメンなんていけ好かないし、女を使い捨てにするような男、こんな状況とテクがなければ抱かれたいとは思わなかった。
けれどこうして、悶々としている彼を見て気づいたのだ。
彼にも、人並みの恋心があるのだと。
まあそれを幽霊である自分に発動させるのはどうかとも思うが。
「カクテル作ってあげようか?」
言いつつ横に座れば、啓治はこちらをにらみつける。
「それはもう良い」
「でも中途半端にされるとこっちも困るんだけど」
そこでようやく啓治は僅かにだが表情を和らげた。それから大きなため息を一つこぼし、私の手をとる。
「つい数時間前までは成仏もせずゴロゴロしてたんだ。それが多少長くなっても問題はないだろう」
「でも」
「それに気付いたんだ。君みたいな幽霊ホイホイがあれば俺の仕事も楽になるって」
こいつ、自分の気持ちを認めないきかと思わずムッとしたが、どうやらその怒りに彼も気付いたようだ。
そこで慌てたように彼が私から目を背ける。
「あと実は、その、正直女にカクテル作るのはウンザリしてたんだ」
「洒落たBGMにも?」
「レコードなんてホントは好きじゃない。場所取るし」
だから、どっちにも無関心な女が、むしろ笑い飛ばすくらいの女が欲しかったんだと、上目遣いに私を見つめる眼差しは甘かった。
これだからイケメンはと思わず唸りつつ、彼の表情に目を離せなくなっている自分が憎い。
「さっきも言ったが、俺ならお前を守ってやれる。それにせっかくなら、セックスだけじゃなくていい男とデートもしたいだろう?」
「自分でいい男っていうんだ」
「俺は嘘は言ってない」
「じゃあ、自分の気持ちにも嘘つかないで」
私をどうしたいんですかと尋ねると、彼は私の体をじっと見つめる。
「1回したくらいじゃ満足できない体にしたい」
思わず頭をはたいたら、少しの間ののち「成仏されたら嫌だから」とようやく本音が漏れた。
「私も、出来ることなら好きな人としたいかな」
「俺は嫌いか?」
「人の体にお札を貼りまくったことをお忘れか」
「確かに悪かったと思ってる。今後はしないから許して欲しい」
別にそこまで気にしてはいないが、ここに来てようやくこちらのペースに彼を巻き込めるようになったのだ。
ここで素直に折れてしまうのは、ちょっと悔しい。
「許して欲しいなら、ちゃんと恋人として扱ってくれないと」
幽霊でもよければだけど付け加えた次の瞬間、啓治は私の体を抱き寄せた。
「問題ない。成仏さえしなきゃ、今すぐさっきの続きをしたいくらいだ」
でもちゃんと好きにさせるまではおあずけだと呟いて、啓治は次の作戦を考えると私に微笑みかけた――――。
遅刻しすぎのロマンチック【END】
とはいえ、いざ「やるぞ!」となるとそれはそれで緊張する物である。
その上真島は「布団もない部屋でやるのは嫌だ」と言い放ち、都心の一等地にある高層マンションに私を連れてきた。恐ろしい事に、そこが彼の自宅らしい。
入ってすぐ横の寝室に直行してしまったので部屋の全容はわからないが、きっと凄く眺めの良いリビングには高級家具なんかが並んでいるに違いない。
そちらにちょっと興味もあったが、緊張していたため部屋が見たいなんて言う余裕はなかったし、真島は「すぐ済ませるぞ」と言うなり私をベッドに押し倒した。
「ねえ、死んだって事は痛くないのかな?」
臆する気持ちを誤魔化すように、私は真島に尋ねた。
「安心しろ。幽霊の場合は、感じるのは快楽だけだそうだ」
「ホントに経験豊富なんだ」
「だからお前は、黙って俺に身をゆだねればいい」
と言われて、上手く身をゆだねられていたら今頃処女は卒業している。
抱きしめられるたびにガチガチに緊張し、キスではどう頑張っても舌を差し入れられず、服を脱ごうとすれば手や足が動かなくなり最後は絶対ずっこける。
そんなわたしを見かね、「もういいよ、萎えた」と白旗を揚げた彼氏は一人や二人ではない。
そしてその不器用っぷりは、たぶん死んでも治らない。
だからいくら相手が百戦錬磨のプレイボーイでも、緊張する物はするのだ。
「あの、やっぱり……」
「君はもう約束した」
「でもあなたには何百回のうちの1回かもしれないけど、私ははじめてなの。訳もわからず終わるなんて嫌だし」
「じゃあリードできるのか?」
「それは、無理だけど」
不器用な自分には無理だけど、それでもせめて天国まで持って行けるような1回にしたい。
そう言って視線を落とせば、真島は困った顔で私から離れる。
「さっきも言ったけど、終わったらちゃんと成仏するか」
頷くと、待ってろと告げて真島は部屋を出て行く。
一体何をするつもりだろうと不安になること5分。
彼は再び現れた。無駄にオシャレなBGMとカクテルを携えて。
「飲め」
と差し出されても、飲み方がわからず混乱した。死んでから今まで、飲食をしたことがない。
「お前くらい霊力があれば、実体がないことを覗けば生きてるのとほぼ同じだ」
だから飲めと言われてグラスに口を付ければ、味わったことのない味が口に広がる。
「これ凄く美味しい」
「気に入ったか?」
「気に入ったけど、これどうしたの?」
「そこで作ってきた」
作ってきたってどういう事だと唖然とし、それから開けたままになっている扉から、居間の方をそっとうかがう。
連れ込まれたときは緊張で気付かなかったが、リビングの側には無駄に凝ったバーカウンターが存在している。
「家にバーがあるの??」
「ああ。自慢のプレイベートバーだ」
「は?」
間抜けな声を上げてしまった私を誰が責めることが出来よう。
だってプレイベートバーである。プライベートなバーである。酒なんて居酒屋で飲めばいいのに、何でわざわざそんな物を家の中に作るのか。
そりゃあ家でビールやワインを飲むことは私だってあるが、飲むならテーブルが一つあれば良い。
「君、考えが透けてるぞ」
「ごめん、ちょっとアホっぽいとか思っちゃった。庶民には理解が及ばなすぎて」
「アホとはずいぶんだな。普通の女は、喜んでカウンターに座るぞ」
「マンションに来たときからうっすら感じてたけど、あなたって実は相当な金持ち?」
「腕利きだからな」
「でも陰陽師にプライベートバーって似合わない」
それに先ほどから気になっていたオシャレBGMはいったい何なのかと、私は合わせて指摘する。
「レコードだ。居間にあるのをかけてきた」
「何でかけるの」
「ムードを出そうと」
思わず、真島の顔にカクテルを噴き出してしまった。
慌てて袖で吹いたが、真島の顔は明らかに怒っている。
「ご、ごめんなさい。映画とかで見たことはあったけど、マジでやる人始めてみたからびっくりしちゃって」
「君がロマンチックな夜にしたいと言ってたんだろう」
「でも、コテコテすぎない?」
返事の代わりに返ってきた絶対零度の笑みを見て、さすがに言いすぎたなと私は後悔した。
態度は冷たいが、彼はきっとよかれと思ってロマンチックな演出をしてくれたのだ。
庶民のレベルにはあっていない物の、きっとこれが彼の標準ロマンチックなのだ。だからそれを笑う権利は私にはない。むしろ黙ってムードに酔いしれておくべきだった。
「ごめん、私のためにやってくれたのに」
だが謝罪すると、意外なほどあっけなく真島の顔から怒りが消えた。
それどころかチビチビお酒を飲んでいる私を見て、彼はふっと笑みをこぼす。
「別に良い、自分だって時々馬鹿らしくなる」
「でも毎回、こういうのやるの?」
「その方が女が良く喘ぐ」
相変わらず身も蓋もないが、無駄なロマンチストよりこういう即物的な方が好感が持てるのは確かだ。
「このカクテルも、実は媚薬入りとか?」
「そんな物を使わなくても、テクでどうにか出来る。ただ、シチュエーションに寄ってくれた方が後腐れが無くて良いからな」
「そういうもんなの?」
「死んだ女も生きてる女も、一夜限りの相手だ。ムードを出せば、無駄に自分のことを喋らなくても警戒を解いてくれるし、そう言う奴としか俺はやらない」
となると、私は彼の首尾範囲外なんだろう。そう思うと、申し訳ない気もちになる。
ここは少し大人になろう。いや、女になろう。好きでもない女を抱くなんて苦行を強いるのだから、それくらいはするべきだ。
だから私は残りの酒をあおると、覚悟を決め、来ていたTシャツを一気に脱いだ。
死んでも服って脱げるんだと、今更のようにちょっと驚いた。そしてそんな私に真島も驚いていた。
「何かやる気出てきた、私頑張るね!」
「いや、むしろ俺が……」
「ううん、私が頑張るの。だって頑張れなくて、それで失敗して未練になったんだもん。ここでやらなきゃきっと成仏できないし」
だから少しでも真島好みの女になろうと私は決める。
色々下手ではあるが、一応見てくれは良い方なのだ。
むしろ見てくれがそこそこ良いわりに、経験がついてこないので逆に失敗していたくらいである。
容姿が良いとそれなりの男が寄ってくるが、それなりの男は皆経験豊かすぎて私のレベルには合わせてくれなかった。
なにせ私はマグロ以下の女で、結局服を脱ぐ前に「バイバイさよなら」と言われる不器用レベルである。
でも今日は絶対にちゃんと脱ぐのだ。裸になってすることをするのだ。
だから私は覚悟を決め、Tシャツに続き、勢いよくズボンを降ろそうとした。
だがいくらやる気になっても、今まで1回も成功しなかった私の不器用さは伊達ではない。
死んでいるのに、今更緊張することはないのにやっぱり腕は震え、そしてなんと、下げようとしたデニムのチャックが咬んだ。
「ごっごめん……いきなり失敗した……」
こんな事ってあり得るのか。だってこれ、本物のズボンじゃないんだろうと内心慌てていると、今度は真島が噴き出す番だった。
一応笑みをこらえようと試みたようだが、ベッドに顔を押しつけていても笑い声がだだ漏れである。
笑うなと怒りたいところだが、それよりまずはこの状況を打破せねばと私はさらにチャックをいじる。
しかし無駄にオシャレな真島の寝室は、間接照明しかないので無駄に暗い。手元もよく見えず、必然的に私は自分の股間をのぞき込むという非常におかしな体勢になる。
そしてそこで、またしても事件は起きた。
男受けを狙って伸ばし続けていた髪が、あろう事かチャックに絡んだのである。
痛いと叫んで、やっぱり幽霊にも痛みがあるんじゃないかと訳もわからない怒りを口にすれば、笑いながら真島が私の側に来た。
きてくれたは良いが、正直こんなおかしな格好をしている私を見られたくない。
けれど動けば動くだけ髪は絡まり、情けなさと痛みは増すばかりだ。
「動くな、じっとしろ」
耳元で囁かれた言葉にうっかりドキドキしてしまった私を、真島はベッドに座らせる。
結局、私は股間をのぞき込むという珍妙な体勢のままでいろと命令され、チャックに絡んだ髪は真島が丁寧に外してくれた。
「……もう死にたい」
「安心しろ、もう死んでる」
「っていうか、今なら成仏できる気がする。すぐにこの場から消えてしまいたいし」
むしろ消えないかなと、私は自分の両の手を見た。
しかし消えない。どんだけセックスがしたいんだと、自分の下らない未練にこの時ばかりは呆れた。
「まあ、こんだけ恥かけばもう失敗はしないだろう」
「これ以上恥かいたら天国のお婆ちゃんに合わせる顔がないよ」
「じゃあ、こっからは本気だ」
どういう意味かと訪ねる間もなく手を取られ、そのままストンとベッドに倒された。
先ほどの事件のせいで緊張は増してしまったが、そんな私に真島はちゃんと気付いていた。
彼は私を安心させるように頭をやさしく撫で、ついばむような軽いキスを唇に落とす。
でもやっぱり緊張のほぐしかたがわからず、5回もキスしてくれたのに、フレンチキスのきっかけさえつかめかった。
けれどごめんと謝るより早く、真島がふっと笑う。
「そう言えば、君の名前を聞いてなかったな」
「凄く普通の名前だよ、清明とは釣り合わない感じの」
「言っておくが、俺も本名は田中啓治だ」
マジかと呟いたそのとき、遠ざかっていたはずの唇が私の唇に重なる。
中途半端に明いていた私の口に、彼の舌が差し入れられたのはすぐのことだった。
互いの舌を絡ませるなんて絶対無理だと延々悩んできたのに、彼はその悩みを一瞬で吹き飛ばす。
やろうとしてやるのではなく、その状況になるとそれは勝手に始まるのだ。
私の舌はまるで別の生き物のように真島の舌に絡まり、そこから息が止まるほど長いキスが始まる。
いや、だいぶ前にもう息は止まっているんだけど、でも何故だか最後は、真島より私の方が先に息苦しさを感じて唇を放してしまった。
「出来たじゃないか」
そういって微笑まれたが、息を整えるのに必死で、そしてその微笑みがあまりに素敵すぎて、彼の言葉に応えられない。
そうこうしているうちに、気がつけば真島は私の服と下着を綺麗に取り去ってしまった。
さすがイケメン陰陽師、女の霊の扱い方は超一流である。
「いくら喘いでも君の声は俺にしか聞こえない。だから好きなだけ乱れて良いぞ」
「乱れたことがないので乱れ方がわからないんだけど」
「我慢しなけりゃ自然と乱れる」
と言うなり、始まった愛撫に真島の言葉の意味を知った。
先ほどのキスと同じように、全ては自分の意志とは関係なく勝手に始まってしまう物なのだ。
だから、昔友達と興味本位で見た18禁ビデオそっくりなあえぎ声が部屋に響いているにも関わらず、それが自分の口からこぼれていると気付くのに少し時間がかかった。だって私の口からそんな物が出るとは思わなかったのだ。
ジェットコースターに乗っても、痴漢にあっても、階段でこけても「うぼぁっ」とか「あべっ」とか「あだだっ」等の珍妙な悲鳴しか上げられなかった私である。
可愛らしい悲鳴など、一生縁がないと思っていた。いやむしろ一生縁がなかった私である。
それが、イケメンに太ももを嘗められているだけで吐息とも嬌声ともつかない声を上げているのだ。
「死ぬって……すごい……」
思わずこぼすと、私を抱きしめていた真島が笑った。
「死んで良かったか?」
良いとは言いたくないが、そうしなければ彼に会うことが出来なかったことを思うと、否定は出来ない。
「真島さん……」
いや田中さんか、まあどっちでも良いかと思いつつ、私は生まれて初めて、自分から男の人にキスをした。
「ありがとう」
心の底からの感謝を込めて、私はそう言った。
今度こそちゃんと成仏できるようにがんばるねと、もう一度、私は彼にキスをする。
やっぱり緊張したし、照れたように笑ってしまったけど、自分的には上出来だと思った。
だがそのとき、先ほどまであんなに激しかった彼の愛撫が、唐突に止まった。
また何かいらんことを言ったのだろうかと慌てて彼を伺うと、わかりやすく動揺した顔がそこにはある。
「真島…さん?」
「……啓治だ」
「じゃあ、啓治さん?」
私が名前を呼んだ瞬間、真島、いや啓治の顔から動揺が消えた。
ついでに言えば色気と甘さも消えた。
「やめた」
そして放たれた言葉がそれである。
「やっ、やめた?」
「ああ、やめた。と言うかやめる」
言うと、啓治は私の体をシーツでくるみ、さっさとパンツとズボンをはいてしまう。
意味がわからない、理由がわからない、どうしていいかわからない。
その三重苦に苦しめられながらも、私は何とか言葉を探す。
「まっ待ってよ! さすがに寸止めで成仏しろって言われても無理!」
むしろ未練がたまりすぎて現世に居座っちゃうよと主張するが、啓治はこちらに背を向けたままだ。
「それでいい」
「いやいやいや、嫌だってば! だって私霊力が強いんでしょ! 放っておけば悪い霊に食べられちゃうんでしょ!」
「安心しろ、俺が守ってやる」
そんなカッコイイ台詞を言われても、と私はもちろん食い下がった。
すると啓治は、自分で脱がせた下着と服を私の方に放る。
「お前だって言ってただろう。好きな男とやりたいって」
「言ったけど、無理だから啓治さんで手を打とうとしたんでしょ! っていうか自分で手を打て的な事言って、部屋に連れ込んだのはそっちでしょう!」
だから責任をとれと、私は啓治の背中に縋り付いた。
オシャレBGMまでかけて、カクテルを飲ませた責任を取れと詰め寄った。
だが未だ返事をしない彼をじっと伺っていると、私はあることに気がついた。
それまで啓治は、私が何をしても笑うばかりで動揺はしなかった。甘い声音や表情はしても、それにすら余裕が見て取れた。
にもかかわらず、私が縋り付いた途端、彼は肩をびくりと弾ませたのだ。その上よく見ると、彼の頬と耳は驚くほど真っ赤に染まっていたのだ。
それが気になり、ふとしたイタズラ心で背中を指でなぞれば、彼は妙なうめき声を漏らす。
「啓治さん」
「離れろ」
「啓治さん」
「良いから離れろ」
「ねえ啓治さん」
「ともかく離れろ!」
「自分で言うのも恥ずかしいけど、もしかして私、啓治さんのストライクゾーンだったりする?」
途端に自慢のプライベートバーまで一目散に逃げ出した彼を見て、私は確信した。
セックスまでは行けなかったが、恋は人並みにしてきたのだ。多少なりとも感情の機微はわかる。
シーツを引きずりながら彼を追えば、プライベートバーのカウンターに彼は突っ伏していた。
耳を澄ませれば「なんでこんなブスに」とか「チャックに髪を絡めるような女だぞ」と失礼極まりない台詞が聞こえてくる。
だが悪い気がしないのは、そうする彼が無性に可愛らしく見えてしまったからだ。
正直プライベートバー持ちのイケメンなんていけ好かないし、女を使い捨てにするような男、こんな状況とテクがなければ抱かれたいとは思わなかった。
けれどこうして、悶々としている彼を見て気づいたのだ。
彼にも、人並みの恋心があるのだと。
まあそれを幽霊である自分に発動させるのはどうかとも思うが。
「カクテル作ってあげようか?」
言いつつ横に座れば、啓治はこちらをにらみつける。
「それはもう良い」
「でも中途半端にされるとこっちも困るんだけど」
そこでようやく啓治は僅かにだが表情を和らげた。それから大きなため息を一つこぼし、私の手をとる。
「つい数時間前までは成仏もせずゴロゴロしてたんだ。それが多少長くなっても問題はないだろう」
「でも」
「それに気付いたんだ。君みたいな幽霊ホイホイがあれば俺の仕事も楽になるって」
こいつ、自分の気持ちを認めないきかと思わずムッとしたが、どうやらその怒りに彼も気付いたようだ。
そこで慌てたように彼が私から目を背ける。
「あと実は、その、正直女にカクテル作るのはウンザリしてたんだ」
「洒落たBGMにも?」
「レコードなんてホントは好きじゃない。場所取るし」
だから、どっちにも無関心な女が、むしろ笑い飛ばすくらいの女が欲しかったんだと、上目遣いに私を見つめる眼差しは甘かった。
これだからイケメンはと思わず唸りつつ、彼の表情に目を離せなくなっている自分が憎い。
「さっきも言ったが、俺ならお前を守ってやれる。それにせっかくなら、セックスだけじゃなくていい男とデートもしたいだろう?」
「自分でいい男っていうんだ」
「俺は嘘は言ってない」
「じゃあ、自分の気持ちにも嘘つかないで」
私をどうしたいんですかと尋ねると、彼は私の体をじっと見つめる。
「1回したくらいじゃ満足できない体にしたい」
思わず頭をはたいたら、少しの間ののち「成仏されたら嫌だから」とようやく本音が漏れた。
「私も、出来ることなら好きな人としたいかな」
「俺は嫌いか?」
「人の体にお札を貼りまくったことをお忘れか」
「確かに悪かったと思ってる。今後はしないから許して欲しい」
別にそこまで気にしてはいないが、ここに来てようやくこちらのペースに彼を巻き込めるようになったのだ。
ここで素直に折れてしまうのは、ちょっと悔しい。
「許して欲しいなら、ちゃんと恋人として扱ってくれないと」
幽霊でもよければだけど付け加えた次の瞬間、啓治は私の体を抱き寄せた。
「問題ない。成仏さえしなきゃ、今すぐさっきの続きをしたいくらいだ」
でもちゃんと好きにさせるまではおあずけだと呟いて、啓治は次の作戦を考えると私に微笑みかけた――――。
遅刻しすぎのロマンチック【END】