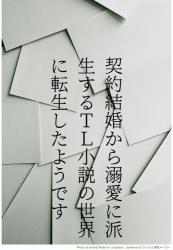***
――彼、真島清明とはじめて出会ったのは、テレビ番組だった。
正確には会ったというより、見たというべきか。
彼はゴールデンタイムに放送していた心霊番組のゲストとして呼ばれ、『現代に現れた凄腕イケメン陰陽師』という何とも陳腐な肩書きで紹介されていた。
しかし凄腕でイケメンと言う肩書きはどうやら飾りではないらしく、彼は周りのタレントが心霊写真やらビデオやらに脅える中、最後まで美しい顔を崩すことなく、的確なコメントを連発していた。
その後もテレビでちょくちょく見かけるようになり、「やっぱりタレントも陰陽師もイケメンに限るんだな」とぼんやり思っていたものの、まさか彼と実際に会うとは思っていなかった。
少なくとも生きているときは、そう思っていた。
いやむしろ、死んだあとも正直会うとは思っていなかった。
だって未練は残してはいたものの、私は品行方正で礼儀正しい幽霊だったのだ。
けれどどうやら、そう思っていたのは私だけらしい。
私が風呂場で足を滑らせうっかり死んでからと言う物、このアパートでは怪奇現象が続いていたのだ。
3号室では毎晩のように小島さんが白い腕の女に首を絞められ、4号室では真美ちゃんは鬼のような恐ろしい男を鏡越しに見るようになり、13号室の南野さんは部屋のあちこちから子供の声が聞こえるようになったと叫んでいた。
しかしそれもまた他人事だと思っていた。私の部屋は相変わらず空き部屋だったので、フラフラしていても誰にも迷惑をかけないし、外に出るときも極力人目を避けるように、常に電柱の影やダンボールの中に潜みつつ移動をしていたほどだ。
だからある日、除霊のためにと真島が来たときも、「やったーイケメンが見れるー」くらいの感想しかなかった。
そもそも彼が本物の陰陽師だとも思っていなかったし、正直陰陽師って何だよ、式神とか使う奴だろ、除霊とかより鬼退治とかが仕事だろ、と少々馬鹿にしていたのも否めない。
だが残念ながら、奴は本物だった。そして馬鹿にしていた罰まで当たった。
何と彼は、3号室でも4号室でも13号室でもなく、私の8号室にやってきたのである。
「原因はここです」
部屋の真ん中でゴロゴロしていた私を見下ろしながら、真島はそう言った。
唖然としている私と管理人の前で、彼は真剣な顔でそう言い放ったのだ。
「すぐに除霊をしますので」
勿論私に断りはなく、管理人を追い出すやいなや、真島は珍妙なお札を問答無用で私の頭にはり付けた。
生前はそれほど怒りっぽい性格ではなかったが、理由も無くお札をペタペタ貼られるなんて納得がいかない。あまりに理不尽である。
それに死んだことで少々大胆になっていたこともあり、私は額のお札を引きちぎると「私を責めるなんて間違いだ」と憤慨し、猛然と抗議した。
迷惑はかけていないこと、誰も怖がらせていないこと、それに死んだとはいえ女性の額にお札を張るなんて何て男だと私は散々まくし立てた。
そしてその結果、私は真島の口から最悪な言葉を聞くことになったのだ。
「君は大層口が悪いようだが、霊としてのたちも最悪なんだ。自覚はないようだが、君は俺の札を破るほどの凄まじい霊力がある。故にそれにつられ他の幽霊がここに集まったんだ。つまり君は悪霊吸引機、いるだけで人様に迷惑をかけているし、それだけで消える価値は十分だ」
その言葉に、私はショックを受けた。
だって幽霊とは言え「消える価値は十分」だなんてひどすぎる。
そして気がつけば、私は大泣きしていた。
真島の言葉にも傷ついたが、泣いてしまった一番の理由は死ぬ1週間くらい前に「お前と付き合うのはつかれる、もう消えてくれないか」と付き合っていた彼に言われたことを思い出してしまったからだ。
もちろん、人様に迷惑をかけて申し訳ないという気持ちもあったが、それでもやっぱり消えて当然なんて悲しすぎる。それに例え死んでも、失恋の悲しみと悔しさは消えないのだとわかり、それまた私の涙を誘った。
ちなみに真島は、私が泣いている間手持ちのお札を私の体に貼りまくっていた。変な水までかけられ呪文まで唱えられた。
しかし効果はなく、その上私が泣きやまないので、彼は憤慨した様子で最後は私にこう言った。
「泣いてても状況は良くならないし、負の感情を抱えれば抱えるだけ悪い霊が寄ってくるんだぞ!」
「霊が何よ、私も幽霊じゃない」
「霊の中には他の霊を取り込む物もいる。君のような無駄に霊力が多い癖に無能な幽霊は、そう言う奴の良い餌だ!」
「死んだ上にさらに食われるなんて聞いてない!」
「さっさと成仏しないが悪い!」
「私だって成仏したいわよ!」
でもできないからここにいるのだと主張すれば、真島は私をじっくりと観察した。
「さっきの泣き方から察するに、どうせ大した未練じゃないだろう!」
「私だって大した未練だとは思ってないけど、それでも成仏できないんだから仕方ないでしょ!」
「で、具体的にはなんだ」
「こき下ろしておきながら、言わせる気なの?」
「君を消すために俺は呼ばれたんだ。札や術が聞かない以上、正攻法を試すしかない」
「正攻法?」
「未練を消す」
そう言った途端思わず赤面したのは、私の未練がとんでもなく俗物的だったからだ。
「で、お前はどうしたいんだ?」
「言わなきゃ駄目?」
「どうせ死ぬ前にセックスしたいとかそう言うことだろう。君は処女っぽいしな」
「た、ただのセックスじゃなくてロマンチックなセックスがしたいの!」
同じだろうと一蹴されて、思わず凹んだ。
自分でも下らないのはわかっている。
でも好きな人と素敵な一夜を過ごすのが、ずっと夢だったのだ。
「じゃあ俺がサクッと寝てやるから成仏しろ」
「私は好きな人としたいの!」
「大丈夫だ。俺は今まで数え切れないほどの女をベッドでその気にしてきた」
あまりに自信満々すぎて、私はポカンとしてしまう。
「とりあえず、寝てやるから服を脱げ」
「そもそも、私死んでるけど」
「死人も含めて、女をその気にさせるのは得意だ」
「もしかして、以前も幽霊と……?」
「よくある。そしてどの幽霊も、俺の顔とテクに満足して消えていった」
全く崩れない自信には更に呆れたが、この顔で愛を囁かれたらその気になってしまうのもわからないではない。
「それでどうする、俺とやるか?」
「そういう身も蓋もないこと言わないで」
と言いつつ、結局超絶美形に私は負けた。
死んでも、やっぱりイケメンには叶わなかった。
――彼、真島清明とはじめて出会ったのは、テレビ番組だった。
正確には会ったというより、見たというべきか。
彼はゴールデンタイムに放送していた心霊番組のゲストとして呼ばれ、『現代に現れた凄腕イケメン陰陽師』という何とも陳腐な肩書きで紹介されていた。
しかし凄腕でイケメンと言う肩書きはどうやら飾りではないらしく、彼は周りのタレントが心霊写真やらビデオやらに脅える中、最後まで美しい顔を崩すことなく、的確なコメントを連発していた。
その後もテレビでちょくちょく見かけるようになり、「やっぱりタレントも陰陽師もイケメンに限るんだな」とぼんやり思っていたものの、まさか彼と実際に会うとは思っていなかった。
少なくとも生きているときは、そう思っていた。
いやむしろ、死んだあとも正直会うとは思っていなかった。
だって未練は残してはいたものの、私は品行方正で礼儀正しい幽霊だったのだ。
けれどどうやら、そう思っていたのは私だけらしい。
私が風呂場で足を滑らせうっかり死んでからと言う物、このアパートでは怪奇現象が続いていたのだ。
3号室では毎晩のように小島さんが白い腕の女に首を絞められ、4号室では真美ちゃんは鬼のような恐ろしい男を鏡越しに見るようになり、13号室の南野さんは部屋のあちこちから子供の声が聞こえるようになったと叫んでいた。
しかしそれもまた他人事だと思っていた。私の部屋は相変わらず空き部屋だったので、フラフラしていても誰にも迷惑をかけないし、外に出るときも極力人目を避けるように、常に電柱の影やダンボールの中に潜みつつ移動をしていたほどだ。
だからある日、除霊のためにと真島が来たときも、「やったーイケメンが見れるー」くらいの感想しかなかった。
そもそも彼が本物の陰陽師だとも思っていなかったし、正直陰陽師って何だよ、式神とか使う奴だろ、除霊とかより鬼退治とかが仕事だろ、と少々馬鹿にしていたのも否めない。
だが残念ながら、奴は本物だった。そして馬鹿にしていた罰まで当たった。
何と彼は、3号室でも4号室でも13号室でもなく、私の8号室にやってきたのである。
「原因はここです」
部屋の真ん中でゴロゴロしていた私を見下ろしながら、真島はそう言った。
唖然としている私と管理人の前で、彼は真剣な顔でそう言い放ったのだ。
「すぐに除霊をしますので」
勿論私に断りはなく、管理人を追い出すやいなや、真島は珍妙なお札を問答無用で私の頭にはり付けた。
生前はそれほど怒りっぽい性格ではなかったが、理由も無くお札をペタペタ貼られるなんて納得がいかない。あまりに理不尽である。
それに死んだことで少々大胆になっていたこともあり、私は額のお札を引きちぎると「私を責めるなんて間違いだ」と憤慨し、猛然と抗議した。
迷惑はかけていないこと、誰も怖がらせていないこと、それに死んだとはいえ女性の額にお札を張るなんて何て男だと私は散々まくし立てた。
そしてその結果、私は真島の口から最悪な言葉を聞くことになったのだ。
「君は大層口が悪いようだが、霊としてのたちも最悪なんだ。自覚はないようだが、君は俺の札を破るほどの凄まじい霊力がある。故にそれにつられ他の幽霊がここに集まったんだ。つまり君は悪霊吸引機、いるだけで人様に迷惑をかけているし、それだけで消える価値は十分だ」
その言葉に、私はショックを受けた。
だって幽霊とは言え「消える価値は十分」だなんてひどすぎる。
そして気がつけば、私は大泣きしていた。
真島の言葉にも傷ついたが、泣いてしまった一番の理由は死ぬ1週間くらい前に「お前と付き合うのはつかれる、もう消えてくれないか」と付き合っていた彼に言われたことを思い出してしまったからだ。
もちろん、人様に迷惑をかけて申し訳ないという気持ちもあったが、それでもやっぱり消えて当然なんて悲しすぎる。それに例え死んでも、失恋の悲しみと悔しさは消えないのだとわかり、それまた私の涙を誘った。
ちなみに真島は、私が泣いている間手持ちのお札を私の体に貼りまくっていた。変な水までかけられ呪文まで唱えられた。
しかし効果はなく、その上私が泣きやまないので、彼は憤慨した様子で最後は私にこう言った。
「泣いてても状況は良くならないし、負の感情を抱えれば抱えるだけ悪い霊が寄ってくるんだぞ!」
「霊が何よ、私も幽霊じゃない」
「霊の中には他の霊を取り込む物もいる。君のような無駄に霊力が多い癖に無能な幽霊は、そう言う奴の良い餌だ!」
「死んだ上にさらに食われるなんて聞いてない!」
「さっさと成仏しないが悪い!」
「私だって成仏したいわよ!」
でもできないからここにいるのだと主張すれば、真島は私をじっくりと観察した。
「さっきの泣き方から察するに、どうせ大した未練じゃないだろう!」
「私だって大した未練だとは思ってないけど、それでも成仏できないんだから仕方ないでしょ!」
「で、具体的にはなんだ」
「こき下ろしておきながら、言わせる気なの?」
「君を消すために俺は呼ばれたんだ。札や術が聞かない以上、正攻法を試すしかない」
「正攻法?」
「未練を消す」
そう言った途端思わず赤面したのは、私の未練がとんでもなく俗物的だったからだ。
「で、お前はどうしたいんだ?」
「言わなきゃ駄目?」
「どうせ死ぬ前にセックスしたいとかそう言うことだろう。君は処女っぽいしな」
「た、ただのセックスじゃなくてロマンチックなセックスがしたいの!」
同じだろうと一蹴されて、思わず凹んだ。
自分でも下らないのはわかっている。
でも好きな人と素敵な一夜を過ごすのが、ずっと夢だったのだ。
「じゃあ俺がサクッと寝てやるから成仏しろ」
「私は好きな人としたいの!」
「大丈夫だ。俺は今まで数え切れないほどの女をベッドでその気にしてきた」
あまりに自信満々すぎて、私はポカンとしてしまう。
「とりあえず、寝てやるから服を脱げ」
「そもそも、私死んでるけど」
「死人も含めて、女をその気にさせるのは得意だ」
「もしかして、以前も幽霊と……?」
「よくある。そしてどの幽霊も、俺の顔とテクに満足して消えていった」
全く崩れない自信には更に呆れたが、この顔で愛を囁かれたらその気になってしまうのもわからないではない。
「それでどうする、俺とやるか?」
「そういう身も蓋もないこと言わないで」
と言いつつ、結局超絶美形に私は負けた。
死んでも、やっぱりイケメンには叶わなかった。