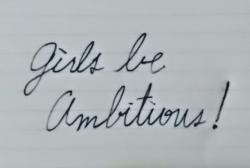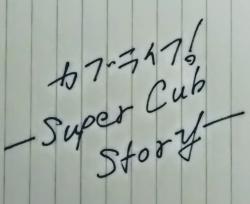優海は薫を諭すように、
「だからね、もし薫ちゃんがダンスに不安を感じたら、違うものを身につければいい。一つのことに人生を賭けるのもスゴイことだけど、見切りをつけて違う道へ踏み出すのも悪いことではないから、そういう考えがあると違うと思うなぁ」
そういうと、
「激励会なんて開いてもらえてうらやましいな。確か藤子ちゃんの捻挫のときはなかったハズだから」
と優海は麦茶の残りを飲み干して、さり気なく椅子を立った。
そのあとの激励会にも優海が顔を出して、澪やののか、藤子がいた時代のアイドル部の話題をしたりして、その日は離れた。