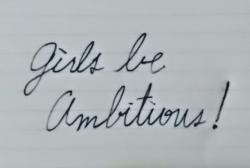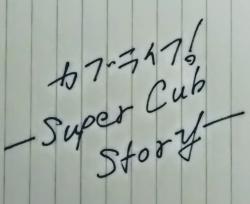藤子は執筆で行き詰まると、住んでいた西陣の町をぶらぶらと歩いた。
仕舞屋格子や糸屋格子のならぶ家並みは札幌にはない光景で、藤子にすればこれだけでも旅をしているような気分になって、戻ってから再びペンを取ると、前より良い物語が書けたようで、それが支えになっている面もあった。
賞が全てではなく、書いていることがただただ楽しかったらしい。
それでも、アイドル部時代の話はいつか書かなければならないであろう…という、自分に自分で決算をつけなければならない思いはあったようで、それが藤子に『夢と知りせば』を書かせた動機であったのかも分からない。
夕方、電話が鳴った。
「長内藤子先生ですか?」
聞けば新聞社で、大賞発表の瞬間を取材させてほしい、という。
「今日は別件がありますので」
藤子は小さな嘘をついて断わった。