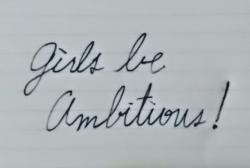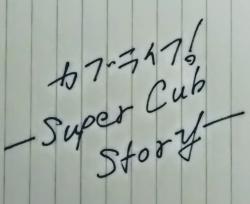十二月の国立競技場ライブが近づいた十月、来年度から顧問が内定した澪への引き継ぎ作業が始まった。
「この時期からやらんと、入試とかで間に合わんくなる」
頭の痛いところではある。
この数年間、教科担任は持っていたがクラス担任はほとんど持たず、ほぼアイドル部につきっきりに近い形で過ごしてきた。
「茉莉江を旅行に連れてってあげることも中々出来んくて」
清正は澪にだけもらした。
「先生、恐らくだけど茉莉江は、普通の人が経験できない世界を裏側から見ることが出来て、もしかしたら案外楽しかったりするんじゃないですか」
確かにツアーも同行してもらい、音楽番組の際には夫婦でテレビ局の入構証を作って入ったまでは良かったが、廊下で迷子になったことすらあった。
「そんなもんなんかなぁ…」
「きっと、ですけどね」
澪は部長の頃と変わらない笑顔を見せた。
その頃、新しく加わった萌々香はボイストレーニングの甲斐もあって、リードボーカルのレパートリーを少しづつ増やし始めてきていた。
「ひまりちゃん、ライブ立ちたかっただろうなぁ…」
たまに翔子は、ひまりの顔が浮かんで泣きそうになる日がある。
「まぁ迷惑はかけたかも知れないけど、ひまりちゃんは普通にしあわせになりたかったのかなぁ」
最初の頃は萌々香のようにおとなしく、しかも声が小さかった。
「ほら、ちゃんと声張って!」
そうやって、すみれに叱られていたことを思い出していた。
「そのすみれ先輩のレッスンを受け継ぐまでになったんだから、ひまりちゃんってスゴかったんだよ」
連絡を取り合うるなによると、近々定期検診があるらしい。
「お腹の子は女の子らしいって」
「大きくなったらアイドルになるのかな」
それだけは、誰にも分からないままであった。