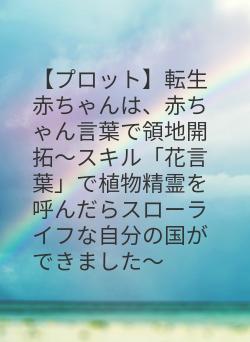あつあつの初めて食べるケーキを、火傷しないように慎重に舌に載せる。するとたちまち、焦がしバターの豊潤な香りとアーモンドの香ばしさが、口の中でほのかな甘さと柔らかに溶け合う。
香り高いふわふわとした生地は、まるで春の淡雪のように、舌の上であっという間に溶けてしまう。
そのことを残念に思いながらも日だまりにいるような幸福感に、恍惚として息をつくと、今まで自分は息を詰めて食べていたのだと初めて気づく。
こんな美味しい物がこの世にあるなんて、信じられない──
「若、いえ、ウィル様。これは何というお菓子ですか?」
「うん?フィナンシェだよ」
「フィナンシェ」
女は何度も小声で菓子の名を繰り返した。もう2度とこの先の人生でこの菓子を口にする事はないだろう。
だからせめてこの味とこの幸せを覚えていたい。
せめて名前だけでも。
何とか一生涯忘れずにいられるいい方法はないだろうか?
文字を書けない事を悔やみながらも女はパッと顔を輝かす。これ以上ないという程の名案が浮かんだのだ。
香り高いふわふわとした生地は、まるで春の淡雪のように、舌の上であっという間に溶けてしまう。
そのことを残念に思いながらも日だまりにいるような幸福感に、恍惚として息をつくと、今まで自分は息を詰めて食べていたのだと初めて気づく。
こんな美味しい物がこの世にあるなんて、信じられない──
「若、いえ、ウィル様。これは何というお菓子ですか?」
「うん?フィナンシェだよ」
「フィナンシェ」
女は何度も小声で菓子の名を繰り返した。もう2度とこの先の人生でこの菓子を口にする事はないだろう。
だからせめてこの味とこの幸せを覚えていたい。
せめて名前だけでも。
何とか一生涯忘れずにいられるいい方法はないだろうか?
文字を書けない事を悔やみながらも女はパッと顔を輝かす。これ以上ないという程の名案が浮かんだのだ。