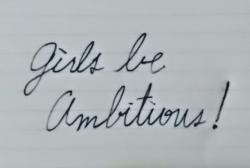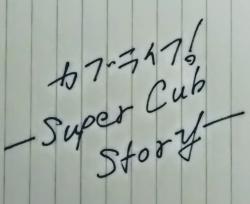合宿も終わりに差し掛かった七夕──北海道は八月七日である──の夜、ミーティングが終わると、
「あの、…ちょっといいかな?」
藤子が手を挙げた。
「どうしたの?」
基本的に藤子は積極的な発言はしない。
人から訊かれれば的確に答えるが、かといって余計なことは言わない。
その藤子が、自分から発言するのは椿事であろう。
「私ね…マネージャーになろうかと思うんだ」
「…マネージャー?」
爆弾発言に一瞬、理解ができなかった。
が。
普段おっとりした雪穂が即座に反応した。
「藤子ちゃん、正気?」
「うん」
冷静に藤子はうなずいた。
ずっと考えていたことらしかった。
「私ね、合宿で気づいたんだけど…タイムキーパーとか事務とかやって、こっちが向いてる気がしたの。それに私、ダンスちょっと駄目になってきてるし」
例の捻挫のあと、藤子は左の足首に違和感を抱えるようになっていたらしい。
「だけどみんなのことが大好きだから、それならマネージャーになろうって」
藤子の言葉の端々には、固い決心が漂っていた。
実のところ藤子には、言い出したら引かない面があって、達観と言えるほどまで俯瞰できるだけに、決めたら動かない頑固さすらある。