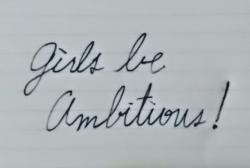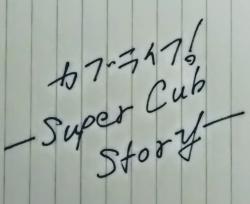次の日から、美波が部室に来なくなった。
「やっぱり藤子ちゃんの言う通り、辞めちゃうのかなぁ?」
すみれが小さく、ひとりごちた。
同好会の頃から見てきた、謂わば初期メンバーのようなものであり、また根っからのファンのようなものでもある。
屈辱まではいかないまでも、耐え難いところはあったのかも分からない。
「無理なら仕方ないって…美波さんだっていろいろあるんだろうし」
言葉を拾ったのは優海である。
「でもね、みんなそれぞれ、このチームに対して深い愛情を抱いてるってのは分かった」
私たち幸せなチームにいるのかも知れないね──優海は言った。
「そういう意味では、藤子ちゃんの意見通り誰も欠けたらダメな訳だし…難しいなぁ」
優海は腕をこまぬいた。